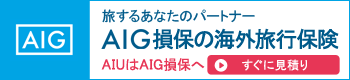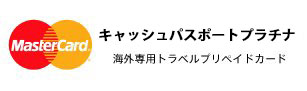★2/19・ 17:30-【☆パリ国際音楽アカデミー☆】現地講習会担当者がプログラムについて解説致します!★
パリ国際音楽アカデミー
Information Session
~パリ国際音楽アカデミーオンライン説明会~
参加費無料・完全予約制・オンラインでの参加も可能です
ゲストスピーカー:講習会講師 ユーグ・ルクレール先生
日時:2月19日(水)17:30-18:00
場所:≪アンドビジョン・東京オフィス≫
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-8 神田駿河台ビル2階
JR御茶ノ水駅御茶ノ水口から徒歩7分、東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩5分程度
♪参加ご希望の方は、こちらからオンライン予約フォームを送信して下さい。
※説明会予約を選択→その他ご要望等に“パリ国際音楽アカデミー”とご記入下さい。
お電話・FAX・メールでのご予約も承っております♪
電話:03-5577-4500 FAX:03-4496-4903 メール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
チリ共和国
| 気候 チリの気候は南北に長い国土の形状により、非常に大きく分かれる。北部は砂漠気候で、朝晩の気温の差が激しい。海岸沿いの主張都市は温帯気候で比較的過ごしやすい。南部の森林地帯は寒冷地帯で雨が多く平均気温も15度ぐらいにしかならない。火山が多いため地震も多い。 |
|
| 現在の天気 | |
| ビザ | 3カ月以内の観光目的の滞在なら不要。ビザについてはこちら。 |
| パスポート | 残存有効期間が滞在日数以上あることが条件 |
| 大使館などの在日政府機関 | |
| チリ共和国大使館 | Embassy of the Republic of Chile in Japan 〒105-0014 港区芝3丁目1-14 日本生命赤羽橋ビル8階 Tel: 03-3452-7561/2、7585 |
| 在東京チリ共和国総領事館 | Consulate‐General of the Republic of Chile in Tokyo 〒105-0014 港区芝3丁目1-14 日本生命赤羽橋ビル8階 Tel: 03-3452-7561 |
| 在大阪チリ共和国名誉領事館 | Honorary Consulate of the Republic of Chile in Osaka 〒530-0013 大阪市北区茶屋町17-1 毎日放送内 Tel: 06-6359-1123 |
| 在札幌チリ共和国名誉領事館 | Honorary Consulate of the Republic of Chile in Sapporo 〒060-0004 札幌市中央区北四条西4丁目1 加森ビル3 Tel: 011-232-0639 |
| 在長崎チリ共和国名誉領事館 | Honorary Consulate of the Republic of Chile in Nagasaki 〒857-2494 長崎県西杵郡大島町1605-1(株)大島造船所内 Tel: 0959-34-2711 |
| 現地日本大使館 | |
| 在チリ大使館 | Chile Embajada del Japon Av. Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile (Casilla 124, Correo 35, Santiago, Chile) Tel: (56-2) 232-1807 Fax: (56-2) 232-1812 |
渡辺泰人さん/ピアニスト/ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニスト/オーストリア・ウィーン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニストでご活躍中の渡辺泰人(わたなべやすひと)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年8月)
ー渡辺泰人さんプロフィールー

日本大学芸術学部音楽学科ピアノ専攻及び同大学院修士課程修了。芸術学部長賞を受賞し、読売新人演奏会に出演。同大学院在学中、日本大学大学院海外派遣奨学生として渡欧、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科第一ディプロマ課程修了。その後ミュンヘン国立音楽大学研究課程を経て、ザルツブルグ・モーツァルテウム国立音楽大学ピアノ演奏科に在籍。第6回モルコーネ市国際ピアノコンクール(イタリア)第2位入賞をはじめ、これまでに国内外の数多くのコンクール、及びオーディションにて入賞。現在はウィーンに在住し、ソロのみならず、ピアノ三重奏団“ヴェルトハイムシュタイン・トリオ・ウィーン”、及び“サロンオーケストラ・アルト・ウィーン”のピアニストとして演奏活動を行っている。現在、ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニスト及びウィーン市民学校ピアノ講座講師。
-では、最初に、渡辺さんのご経歴をお願いします。
渡辺 日本大学芸術学部の音楽学科ピアノ専攻を経て、同大学院の修士課程まで、日本で勉強しました。そして、大学院に在学中に、日本大学大学院の海外派遣奨学生制度に選ばれ、前からあこがれていたオーストリアに渡った後、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科(今と制度が多少変わっている)に入学しました。ここで第一ディプロマを取得した後、ドイツのミュンヘン国立音楽大学の研究過程に進学しました。研究過程終了後、再びオーストリアに戻り、ザルツブルグのモーツァルテウム国立音楽大学に入学しました。その後、仕事を始め、現在に至っています。
-ピアノを始められたきっかけは?
渡辺 両親の影響が大きかったです。父が、ジャズピアノがとにかく大好きでして。生まれた子どもには、絶対にピアノをやらせたい、という夢があったらしいです。そして、僕が思いっきりターゲットになりました(笑)。
-お父様もピアノを弾かれるのですか?
渡辺 いえ、楽器はやりませんが、すごくたくさんのCDやレコードを持っていて、いつもいつも音楽を聴いていました。
-では、小さな頃から家中にジャズが流れていたんですね。
渡辺 他にももちろん、モーツァルトやショパンなどのクラシックも流れていて、幼稚園や小学校時代を振り返ると、家には、常に音楽が流れていたように思います。父の影響が大きかったのですが、母親がバレエの先生をやっていたということも影響していると思います。でも、生まれた僕の背格好や体型などを見て、「この子にはバレエは向かないな」と、初めから、その道に進ませようとはしなかったみたいです(笑)。
-ピアノを始めたのは何歳くらいですか?
渡辺 たぶん3歳半くらいだったと思います。まだ幼稚園に行っていた頃でした。
-音楽系の大学に進まれる方は、音楽家を志す方が多いと思いますが、音楽の道で生きていこうと意識されたのは、いつくらいでしたか?
渡辺 今考えると、かなり小さい頃からですね。漠然とではありましたが、ピアノを教える先生になりたいって考えていました。ピアノと一緒に生きていくというか、どこかでピアノに関わっていたいっていう気持ちは、昔からありましたね。
-お父様から、ジャズをやれとは言われなかったのですか?
渡辺 いえ、言われませんでした。まずはクラシックを勉強して、気が向いたらやればいい、という感じでした。とにかく、与えられた練習を頑張ってやりなさい、という態度で僕に接していました。
-日本の大学で修士課程まで6年間学ばれていて、派遣制度で留学が決まったということですが、それまで全く留学を考えたことはなかったんですか?
渡辺 憧れはありました。大学4年の頃に、松浦豊明先生が東京芸術大学から日本大学大学院へ赴任されて来たんです。僕は、まだ学部生でしたが、ちょっと早めに先生の門下に入れていただきました。松浦先生は、芸大の教授だったときには大変お忙しい先生で有名でしたが、僕が教わった頃は、受け持ちの生徒が少なかったこともあり、とても気さくに接してくださいました。気が向くと電話をくださって、「週末、お茶飲みに来ない?」などと誘っていただくことも多かったんですよ。先生の奥様がケーキを焼いてくださったりして、僕たち門下生はみんな、先生のお宅に月に一回は伺っていました。そのときに、先生が収集されている古い音源のレコードを聴かせてくださったり、昔ドイツに留学されていた頃の品々を見せてくださったんです。当時のコンサートのプログラムや楽譜などを。それから、先生の奥様も、同時期にドイツに留学されていたということもあって、お茶のお菓子も、当時のドイツで教わったレシピで作ってくださったんです。なので、東京にいながらにしてヨーロッパの雰囲気が先生のお宅には漂っていて、その頃から、そんな様子にとても憧れていたんです。「絶対にドイツ語圏に行きたい!」と気持ちは強かったですね。ですから、派遣奨学生として選ばれたときは、夢が現実のものになったという感じでした。

-この留学前は、ヨーロッパに短期留学などで行かれたご経験はあったのですか?
渡辺 実は、派遣奨学生に応募した前後で、受かるかどうかは分からないけれど、下見をする必要はあるなと思っていたんです。そこで、ドイツ・オーストリア周辺を南から北にかけて見て回ったんです。初めに憧れのウィーンから入りました。旅行といえば旅行なのですが、僕の中では完全に「下見」でした。
-いろいろ巡った中でも、やっぱりウィーンがいいな、と思われたんですか?
渡辺 初めから憧れはあったんですが、実際に自分の目で見てそう思いました。他の街と比べても、やはり、ウィーンに着いた瞬間の直感が違いました。今振り返ってみても、「ああ、僕はここで勉強するんだ!」っていう強い印象がありましたから。もう、確信といってもいいくらいでした。そして、派遣奨学生として選ばれた時、留学先は、迷わずウィーンに決めました。
-派遣奨学生のシステムとして、留学先で師事する先生は、大学院側が選んでくれるのですか?
渡辺 いえ、この制度は、留学先の学校や先生を、自分で決めなければいけないんです。応募時点で、コンタクトを取らなければいけなかったので、そのコンタクト取りも兼ねて下見したんですよ。ウィーンで師事することになった先生は、知っている教授や先生方を頼って、皆さんから紹介された中のお一人でした。
-では、コンタクトを取った先生は、他にもいらっしゃったんですか?
渡辺 ええ。でも、やはり、ウィーンで勉強するんだという気持ちが強くて、ウィーン国立音大の先生にしました。

-渡航前に、ご自身が抱いていたウィーンのイメージと、実際行かれてからの印象の違いはありましたか?
渡辺 やはり、渡航前のウィーンのイメージは、TVなどで見る「華やかな音楽の街」という表面的なものでした。実際に行ってみると、治安の良し悪しや、街自体が抱えている問題が分かってきたりして、華やかな部分だけではないんだということが分かりました。ショックではあったのですが、それゆえにもっとウィーンを知りたい、という気持ちにもつながりました。
-ちなみにショックだったこととは、どういったことですか?
渡辺 まずは、移民の多さですね。オーストリアは、今でこそ小さな国ですが、大戦前は非常に大きな国で、戦争に負けた代償で、多くの労働力を受け入れた背景があります。主にトルコや旧ユーゴスラビア系など東側の人々なのですが、初めは、「ここはトルコなのか!?」と思うほどで(笑)、僕にとってはすごくショックでしたね。まあ、最終的にはそれもすべてひっくるめて、ウィーンなんだと思えるようにはなったんですけど。
-確かに、日本人はウィーンに対して、そういうイメージって持ってないですよね。
渡辺 ないですよね。それこそ、ニューイヤーコンサートの映像で見るような、華やかなホールや、ドレスで着飾った紳士淑女ばかりがいるイメージですよね。でも実際、そういう方々は、ほんの一部であって・・・。
-実際、ウィーンで学んでみて、日本での勉強仕方との違いなどで、ショックを受けられたことはありましたか?
渡辺 ウィーンで勉強し始めてショックだったことは、結局は「表現すること」を勉強するんだな、ということでした。ヨーロッパ系の学生たちの、「自らの語り口で、どこまでその作品を表現し切れるか」という、彼らの突き詰めていく姿勢に衝撃を受けました。日本だと、楽譜から音楽を読み取っていく理論的な作業や、技術的なことを学ぶのが中心だったんです。でも、ウィーンでは、「ここはもっとこういう音色で弾かなければ」とか「もっとこういうイメージで」などと、何より自発的なファンタジーを持った勉強が大事だったので、そういう部分では、少し戸惑いましたね。

-生活面ではどうでしょうか、カルチャーショックはありましたか?
渡辺 土日にほとんどの店が閉まるので、すごくゆったりした生活だなと思いました。東京だと人も多くて、慌ただしい中でピアノを勉強していたのですが、突然、大きな空間にポンと置かれたような感覚でした。それが虚無感だったというのではなくて、居心地よい感覚でしたが。
-ウィーン国立音大は、ご自分で受験されたのですか?
渡辺 実は、海外派遣奨学生の制度は、一年間のみという制度だったんです。大学院からの派遣の留学生とはいえ、正規の学生ではありませんから、師事した先生に頼る形で、ウィーン国立音大に出入りさせてもらっていたんです。なので、レッスンや授業を見学したりしか出来ませんでした。そこで、先生から、「これから先もウィーンにいたいのであれば、正式に受験してみてはどうか?」と言われたんです。日本大学にもすぐに確認を取り、休学中であるということで、ウィーン国立音大を受験することは問題ないとのことでしたので、実は、派遣留学生の期間中に受験したんです(笑)。
-え!? 大丈夫だったんですか?
渡辺 はい。休学中ということと、修了演奏試験や修士論文もすべて済ませ、卒業式に出席するだけの状態で渡航していましたから、問題ありませんでした。というわけで、派遣されてから3ヵ月後に受験したんです。ただ、授業が本格的に始まったのは、さらにその3ヵ月後でした。なので、最初の半年間は、レッスンや授業を聴講したりして過ごし、半年後から正式な学生として勉強を始めた、ということなんです。
-ちなみに、ドイツ語は、日本で勉強されていたんですか?
渡辺 派遣奨学生に決まってから、とりあえず1ヶ月間だけ東京のドイツ語学校に通って勉強しました。ですが、修士論文や渡航の準備などでバタバタしていたので、それ以外は参考書をパラパラめくる程度でした。
-となると、本格的に勉強し始めたのは、現地に行ってからですか?
渡辺 はい。一応、日本の大学でも2年間ドイツ語の授業はあったのですが、それは1ヶ月間行った東京のドイツ語学校くらいの内容で。本格的には、ウィーンに行ってから勉強を始めた、という感じです。今思えば、日本でのドイツ語の勉強内容は、ウィーンでの1週間分くらいにしかならなかったな、と(笑)。
-そうなんですか! それでは、けっこうご苦労されたのではないですか?
渡辺 はい。留学したての頃、街行く人々の会話は、宇宙語にしか思えませんでした(笑)。
-レッスンは、もちろんドイツ語ですよね。
渡辺 そうです。僕がウィーンで師事していたヴァッツィンガー先生は、語学に関しては厳しくて、「出来るだけ早くドイツ語をマスターしなさい」という方針でした。ですので、ドイツ語が全く分からない生徒に対しても、英語で話すことは全くありませんでした。でも、音楽は、用語がイタリア語だったり、隣で先生が見本を見せてくれたりするので、理解できてしまうんですよ。ですので、レッスンに関しては、あまり困らなかったというのが正直なところです。

-結局、ウィーン国立音大には何年いらしたんですか?
渡辺 3年です。
-ご卒業されてから、ミュンヘンに行かれたんですよね。
渡辺 ウィーン国立音大では、実は、先の課程に進学し始める状況だったんですけれど、1年の留学のつもりが、この時点で3年になっていましたから、「この先そんなに長くない。それならば、別の環境で別の先生に会ってみたい。」という気持ちが強くなりました。なので、受験をしなおして、ミュンヘン国立音大に入学しました。結局、その後のモーツァルテウム国立音大へも、同じ気持ちで移ったんですけれども。
-ミュンヘンを選ばれたきっかけは何だったんですか?
渡辺 同じドイツ語圏の中でも、他の国であるドイツに興味があったというのと、ドイツの中でも南にあるので、オーストリアに近いことが一番の理由でした。その距離感のお陰で、ウィーン国立音大の卒業前から、ミュンヘンにレッスンを聴講しに行ったりしていました。
-先生を決められてから、ミュンヘンへ行かれたのですか?
渡辺 ヴァッツィンガー先生も本当にいろいろ力を貸してくださったんです。ミュンヘン音大の先生を推薦してくださったのも、ヴァッツィンガー先生でした。
-ドイツとオーストリアでは、音楽性の違いはありましたか?
渡辺 やはり、国民性に影響していると思うんですけれど、ドイツのほうが、構築性を重んじるスタイルですね。オーストリアは、前にも言ったように、表現することや、自分という媒体を通して自分らしく奏でる、ということに重点を置いていましたので、その違いはありました。
-住みやすさの違いはありましたか?
渡辺 物価の面では、それぞれ高いものと安いものが違うという感じで、トータルとして大差なかったのですが、決定的に違ったのは住宅環境でした。
-税金が高いそうですね。
渡辺 ミュンヘンは、アパートの家賃が高くて、探すのが大変でした。平均的に、ウィーンでミュンヘン分の家賃を払えば、ミュンヘンの部屋の2倍も3倍も広い部屋に住めるという状況でした。住環境においては、ウィーンのほうが断然良かったです。
-寮には入られてなかったんですか?
渡辺 いえ、どの街でも、ずっとアパートに住んでいました。
-ドイツとオーストリアでは、コミュニケーションの取り方の違いはありましたか?
渡辺 ドイツ人のほうが、初めは距離を置く感じなんですけれど、一度打ち解けると、それからは温かく、人間と人間の付き合いが出来る感じはあります。オーストリアは、それよりもっとラフという気がしますね。
-オーストリアのほうがラテン系に感じますが・・・?
渡辺 国がイタリアに接していますからね。簡単に言うと、ドイツ人とイタリア人をたして2で割ったのが、オーストリア人の気質なのかも知れません。
-なるほど! さて、ミュンヘンでの生活を経て、再びオーストリアに戻られ、モーツァルテウム国立音大に入学されるわけですよね。「オーストリアに戻ろう、ザルツブルグに行こう」と思われたきっかけは何だったんですか?
渡辺 本当に不思議だったのですが、始めにウィーンで感じた気持ちが、ミュンヘンに行った後も、ずっと気持ちの中にあったんです。この先、まだ勉強できるのであれば、オーストリアで勉強したいと。また、ドイツよりもオーストリアで勉強するほうが、自分に合っているような確信があったので、オーストリアに戻ろうと決意しました。
- 一度、日本に帰ろうとは思われなかったのですか?
渡辺 はい、思いました。実は、この頃から、職探しを視野に入れながら勉強を続けていたんですけれど、これといった決定打がなかったので、勉強を続けるという形を取っていました。

-ウィーンとザルツブルグで、大きく違うことはありましたか?
渡辺 決定的に違ったのは、ザルツブルグでは、シーズン中の音楽会が少ないということです。有名なザルツブルグ音楽祭はあるのですが、夏だけのものですし。ウィーンのように大きなオペラ座がないし、楽友協会のような大きなホールもないので、なかなか演奏会に足を運べるチャンスがなかった、というのが大きかったです。
-それは大きいですね。やはり、本場の音楽を観るという意味ではウィーンが一番ということですか?
渡辺 ええ。でもミュンヘンもすごく良かったですよ。バイエルン州立歌劇場やガスタイクのホールなどで、連日たくさんの演目がありましたし。
-それで、モーツァルテウムをご卒業されて・・・?
渡辺 実は、モーツァルテウム国立音大を卒業する前に、仕事のことが見え始めたので、ディプロマを取らずにそのまま出てしまいました。
-お仕事というのは?
渡辺 初めは、日本に帰って引き続き仕事を探すか、お声掛けをいただいた、ウィーンでの小さな仕事に就くか迷っていました。それで、日本で一度、区切りをつけるために、数ヶ月間、コンサートをしながら過ごしたんです。結局、この数ヶ月の間に、やはりウィーンでお話をいただいた仕事をやってみようと決心しました。
-ウィーンで仕事をしようと決意した、決定的な理由を教えてください。
渡辺 モーツァルテウム国立音大に行った時点で、留学期間がだいぶ長くなっていたので、ひょっとしたら自分は慣れ親しんだオーストリアで、充実した仕事をやっていけるのではないか、と漠然と感じていました。その気持ちに正直に頑張ってみようと、思い切って決断しました。
- 一番最初のお仕事とは、どんなお仕事だったんですか?
渡辺 最初は、現地の普通高校の音楽の先生だったんです。ピアノの個人レッスンもあったのですが、カトリック系の学校だったので、ミサが毎週ありますから、ピアノと同じウェイトで合唱のレッスンがあったんです。これに立ち会合って、指導するというのが僕の任務でした。
-このお仕事は、どのようにして見つけたんですか?
渡辺 学生時代、この高校のミサで、何度も演奏をさせていただいていたんです。当時、チャペルのパイプオルガンが壊れていたので、キーボードでオルガン部分を弾かせていただいていました(笑)。そういったつながりで、欠員が出たときに、「やってみないか?」と声をかけてもらったんです。このオファーが魅力的で、日本でコンサートをしていた数ヶ月の間に、オーストリアに戻ろうと決意したんです。
-実際に、学生さんに音楽を教えるというのはどんな感じでしたか?
渡辺 初めは、僕で勤まるのだろうか、という不安がありました。それに、僕は、カトリックの人間ではないので、ミサの流れとか、基本的なことから勉強する必要があったんです。でも、相手が高校生だったので、あの年代特有の人懐っこさで接してくれて、すぐに不安はなくなり、楽しんで出来るようになりました。

-このお仕事は、何年くらいされていたのですか?
渡辺 実は、後に得た仕事との関係で、1年足らずで辞めざるを得なくなってしまいました。音楽の授業だけでは、仕事として本当に少なかったので。大きな仕事を探さなければいけないと考え始めて、在職中からいろいろなところに履歴書を送ったり、オーディションに応募したりしていました。それこそ200~300という数です。ピアノに関わる仕事なら何でも片っ端から応募する、という感じでしたね。空いている時間に作業していました。
-現地で日本人が仕事を得るというのは、やはり難しいことなんですか?
渡辺 はい。大学以外のほとんどの音楽学校は、採用試験の規準に、「オーストリア国籍、もしくはEUの国籍を持つ者」と記載されてます。たとえば、現地の方と結婚された日本人などであれば、それでも相当大変ですが、かろうじて潜り込めるかもしれませんけど・・・。日本人というだけで、最初の採用規準にひっかかってしまうので、非常に難しかったです。友人に、自分からどんどん履歴書を送ったほうがいい、とアドバイスされていたので、そうしていました。
-そんな中で、なんとか次の職を得られたんですよね。
渡辺 はい、でも、簡単ではなかったです。地方のコンセルバトワールの採用試験を受けたときも、最終選考までパスしていたのですが、試験官から「あなたは、ウィーンに住んでいるけれど、このくらいの少ない時間枠の仕事だったら、あなたが住んでいる場所には合わないんじゃないの?」と言われて、僕の次の成績を取っていた人が採用されたこともありました。この人は、その街に住んでいるオーストリア人だったんです。こういう悲しい思いとか悔しい思いを何度もして、だんだん分かってきたことが、「明日からでもすぐ仕事が出来る」という距離感のほうが見つかりやすい、ということでした。たとえば、ドイツの大学や劇場にも応募したんですけれど、「あなたはウィーンに住んでいるようだけれど、こちらに引っ越してくる気はあるのか?」という返事を何度も受けたりしましたから。やっぱり自分は、ウィーンとその周辺で一生懸命探さなければいけないんだな、と思い始めた矢先、ある日突然、街中で携帯が鳴ったんです。それが、なんと、夢のまた夢だと思っていた、ウィーン国立歌劇場からだったんです! 「あなたの履歴書を見たのですが、明日、バレエ学校の伴奏の試験をやるので、午後来てください」と。採用試験にエントリーしていたのですが、その連絡でした。

-急な電話ですね!
渡辺 日本じゃありえないですよね(笑)。僕としては、母がバレエの先生だし、妹も踊っていることもあって、バレエには親しみがあるというだけで、ダメもとで応募していたんですよ。だから、一瞬躊躇したんです。受けても無理だろう、と思っていましたから。でも、「行けません、なんて言っちゃだめだ!」と自分を奮い立たせて、試験を受けに行きました。その採用試験を経て、今に至っているというわけです。
-すごいですね! 採用試験はどんな内容だったんですか?
渡辺 バレエのトレーニングのクラス90分を、ピアノ伴奏してくださいと言われ、その場で弾きました。バレエの伴奏に関しては、音楽大学では教えてもらえるものではないし、ほとんどのピアニストは、どうやるのか知らないと思うんです。たまたま僕は、家族がバレエをやっていて、伴奏の経験もあったというのが功を奏したのでしょうね。それまでは、母や妹とは全然違う分野で活動しているんだっていう気持ちがありましたけど、この育った環境のおかげで、なんとか90分やり遂げられたんだと思います。
-他の応募者の方と一緒だったんですか?
渡辺 僕が受験した日は、僕だけだったのですが、別の日にも試験は行われていたみたいです。定年退職される方がいたので、欠員を埋めるための採用試験だったんです。
-試験は、一度弾いただけで、特に担当官との面接などはなかったのですか?
渡辺 ディレクターと面接がありました。後から知ったのですが、試験の最中、オペラ座の関係者やバレエ学校のトレーナー、他のピアニストなどが、代わる代わる僕の演奏を審査していたようです。そして、ディレクターから、「他のピアニストが病欠のときなどにやってみないか?」と言われたんです。
-もう、その場で話があったということですか!?
渡辺 はい。その場で言っていただきました。ウィーン国立歌劇場のバレエ学校のディレクターだったんですが、その場で仕事に関する細かいことも話し始めたので、これはポジティブに取っていいんだな、と。
-それは本当にすごいことですね! 日本人の方が、そういうお仕事に就かれるということは、なかなかないですものね。
渡辺 いえいえ。運やタイミングも大きいなって、本当に思うんです。
-その後、どのくらい経ってから、そのお仕事を始められたのですか?
渡辺 すぐに、しょっちゅう電話がかかってくるようになったんですよ。バレエ学校のピアニストに病欠が出るたびに、連絡が来るようになったんです。でも、ふたを開けてみたら、定年退職されるはずだった方が、その後2年近くも在職されていたので、その期間は非常勤という形でした。正式に常勤のピアニストになったのは、去年の9月からです。
-そうなんですか。ちなみに就労ビザは問題なく下りたのですか?
渡辺 はい、幸い、勤務先がウィーン国立歌劇場ですので、非常勤でやっているときから、国立オペラ座が、労働許可書など必要な書類を発行してくださったんです。逆に、労働許可書を出さずに外国人を雇っていると、雇用者側に問題が出て来るんですよ。なので、非常勤を始めて1ヶ月くらいで、すぐ郵送されてきました。実際「こんなに早く!?」って驚きましたね。その点に関しては、本当に幸せでした。そして、これらの書類を提出したら、ビザはすぐに下りました。

-週に何回くらいのペースでお仕事していたんですか?
渡辺 非常勤のときは、まちまちでしたね。仕事のない週もあれば、病欠が出たときは一気に10日間とかもありました。いろいろな演目のリハーサルや、バレエ学校側の都合で時間割が変わったときなどに、常勤ピアニストの都合がつかなかったような場合も、電話がかかってきました。
-今は、どういう形ですか?
渡辺 今は、クラスを持たせていただいているので、毎週月曜日から金曜日までです。時々週末も入りますが。
-ソロではなく、伴奏者として弾くことに関して、何か気をつけていることはありますか
渡辺 伴奏に関しては、日本にいた頃から声楽や器楽の伴奏など、好きだったのですすんで勉強させてもらっていました。ただ、バレエの伴奏は特殊なので・・・。 気をつけることは、テンポ感とかリズムの抑揚ですね。たとえば、ジャンプのときにずっしり弾いてしまうと、重くなって飛べなくなってしまったりしますし、体の大きさには個人差があるので、回転も人によって速さが違ったりします。だから重さや軽さ、どこにアクセントをつけてどこをなめらかに、どこを歯切れ良く・・・など、拍子とか拍とかに関する部分は気をつけています。
-細かいお仕事なんですね。この仕事のやりがいは、どんなところに感じますか?
渡辺 結局、バレエピアニストという職業は、ジュークボックスのような存在にならなければいけないんですよ。「こういう動きに合わせて、何か弾いて」と言われたら、そのように弾かなければいけないですし。でも、踊り手さんたちが、自分のピアノに合わせて、楽しそうにレッスンを受けている姿を見ると、「ああ、自分の音楽で、こんなに楽しんでくれているんだ」と嬉しくなりますね。そういうことに、やりがいを感じます。
-渡辺さんのように、外国で仕事をしたいという日本人の方がたくさんいると思いますが、仕事を見つけるコツはありますか?
渡辺 「自分には、これくらいしかできないだろうな」と、自分で思っている判断よりも、もっと大きな夢を持って、そこに近づいていくエネルギーを失わないように、自分の楽器を演奏し続けていくことなのかな、と思います。
-最後に、一番難しい質問を(笑)。渡辺さんにとって、クラシックとは、そして音楽とはどういう存在でしょうか。
渡辺 ・・・・・・(笑)。やはり、僕という人間は僕なんですけれど、音楽を通して、いろいろな人間になれることでしょうか。威張った人間、悲しんでいる人間、ロマンチックな人間、コミカルな人間・・・。音楽の表現を通して、自分がいろんな役者になれるというか、そういうことがやはり魅力ですね。
-今後、海外で活躍したいという方に、「これはやっておいたほうがいいよ」など、何かアドバイスがあれば、教えてください。
渡辺 海外で働く人は、皆さん開口一番におっしゃると思うんですけれど、言葉が一番大切ではないかと。言葉の次に大切なものがあるとすれば、コミュニケーションを取ることですかね。努力をしてコミュニケーションの力をつける、というのはおかしいですけれど、音楽の世界でも、結局人と人とのつながりなので、言葉の壁を越えた、コミュニケーションの努力は必要かなと。

-日本人は、引っ込みがちですもんね。積極的になれないというか。
渡辺 日本人として活かせる長所って、たくさんあると思うんです。それを生かしつつ、自分をもっと周りに溶け込ませるようにできればいいのかな、と。全部楽しんでやってしまえたらベストですけれど。
-日本人として活かせる長所というのは、具体的にどんなこところでしょうか?
渡辺 きちんとしているところとか・・・。僕が言うのもなんですけれど(笑)。日本人は、きちんとしているというイメージを持たれています。約束に関することだったり、礼儀正しさなどは長所ですよね。そういうのを活かしつつ、自分たちが日本にいるときより、ちょっとだけ積極的に話しかけてみたりだとか、挨拶したりとか。ちょっとした心遣いでコミュニケーションは膨らむので、そこは努力すればいいのかな、と、。
-最後になりますが、渡辺さんの音楽家としての夢、目標を教えてください。
渡辺 当面は、今の状況をもっと自分が楽しめるように、バレエのピアニストとして経験を積んでいきたいです。と、同時に、今まで積み上げてきた、ソロのピアノの勉強や室内楽、その他のアンサンブルなども、並行してレパートリーを広げていけたらいいなと思っています。
-ご活躍をお祈りしています。今日は、お忙しいところ、本当にありがとうございました!
コピー 植山けいさん/チェンバロ奏者/フランス・パリ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回、パリでご活躍中の植山けいさんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2012年1月)
 ―植山けいさんプロフィール―
―植山けいさんプロフィール―
ロンドン生まれ、東京育ち。2004年Paolo Bernaldiチェンバロコンクール第2位(イタリア)。第19回国際古楽コンクール<山梨>チェンバロ部門第3位(日本)。
桐朋学園大学ピアノ科、アムステルダム音楽院チェンバロ科(オランダ)、ロンジー音楽院チェンバロ修士課程(アメリカ)、ブリュッセル王立音楽院フォルテピアノ科修士課程終了(ベルギー)。現在パリと東京を中心にチェンバロ奏者、通奏低音奏者として活躍中。
2010年、レ・シエクルとプロメテウス21(フランス)によるバッハのチェンバロ協奏曲及び、ブランデンブルク協奏曲全曲演奏ツアーにソリストとして出演。その時の演奏が、フランス国内でラジオ・テレビ放映され、好評を博す。また、オランダやアメリカで開催したコンサートでの演奏を地元メディアに取り 上げられ、高く評価された。ボストン古楽音楽祭(アメリカ)、モーツァルト音楽祭(ユネスコ世界遺産ヴュルツブルグ宮殿、ドイツ)に出演。サル・プレイエル(フランス)、シャペル・ロワイヤル(ヴェルサイユ宮殿、フランス)、ブリュッセル王立楽器博物館(ベルギー)などでも演奏会を行う。2001年には、 ボストン(アメリカ)ならびに東京において、バッハ・ゴルトベルク変奏曲を演奏し、チェンバロ奏者としてデビューを飾る。2012年、デュポールのチェロ ソナタ全曲を、チェリストであるラファエル・ピドゥーと世界初録音し、スイス・ノイシャテル博物館所蔵J.ルッカースチェンバロでバッハ:ゴルトベルク変 奏曲のソロ録音がリリースされる。(2枚ともIntegral Classicより発売)
これまでピアノを小島準子、ヴィクター・ローゼンバウム、フォルテピアノをピート・クイケン、ボヤン・ボティニチャロフに、チェンバロをピーター・サイクス、メノ・ファン・デルフト、クリストフ・ルセ、ユゲット・ドレイフュスの各氏に師事。G.レオンハルト氏のマスタークラスに参加。
- まずは、植山さんの簡単なご経歴を教えて下さい。
植山 小学校1年生から中学校3年まで9年間桐朋学園の音楽教室でピアノを習い、その後桐朋女子高等学校音楽家、桐朋学園大学大学のピアノ科へ行きました。卒業半年後にアメリカ・ボストンのロンジー音楽院に2年の予定で留学しま。けれども、フォルテピアノやチェンバロにも興味を持っていたのでピアノレッスンと同時に古楽器を習い始め、ピアノのデイプロマを取得後にチェンバロ科の修士課程を2年しました。その後古楽の盛んなヨーロッパできちんと17-18世紀のスタイルを学びたいと思いアムステルダム音楽院に2年行き、フランスのバロック音楽を理解するにはフランスへ住まないと無理だと思い、その後パリへ行き6年間過ごしました。気が付いたら3カ国で13年を過ごし本帰国したばかりです(笑)。
- チェンバロに初めて触られたのは?
 植山 高校の時、有田正弘先生の古楽実習という授業を受けました。その最後の授業で、先生のお宅を訪問する機会があり、博物館みたいに色々な楽器が置いてあり、初めて18世紀のアンテイ―クのチェンバロを弾かせて頂きました。まだ全然チェンバロの構造など分からなく、バッハ時代の鍵盤って言う程度の知識でしたが、今まで聴いたことのない音色で、ピアノ教育で受けた音楽観念をくつがえされるようなショッキングな出来事でした。有田先生の授業では、例えば、メヌエット、サラバンドという舞曲のスタイルや、ヨーロッパの17-18世紀の政治や風習などピアノのレッスンで聞いたことのない内容を初めて聞き、目から鱗でした。バッハのイギリス組曲なのに、その中にはフランス式やイタリア式で書かれたクーラントがあり、どうやって見分けるか、弾き分けるか、どの様なダンスだからテンポ感はこうとか。
植山 高校の時、有田正弘先生の古楽実習という授業を受けました。その最後の授業で、先生のお宅を訪問する機会があり、博物館みたいに色々な楽器が置いてあり、初めて18世紀のアンテイ―クのチェンバロを弾かせて頂きました。まだ全然チェンバロの構造など分からなく、バッハ時代の鍵盤って言う程度の知識でしたが、今まで聴いたことのない音色で、ピアノ教育で受けた音楽観念をくつがえされるようなショッキングな出来事でした。有田先生の授業では、例えば、メヌエット、サラバンドという舞曲のスタイルや、ヨーロッパの17-18世紀の政治や風習などピアノのレッスンで聞いたことのない内容を初めて聞き、目から鱗でした。バッハのイギリス組曲なのに、その中にはフランス式やイタリア式で書かれたクーラントがあり、どうやって見分けるか、弾き分けるか、どの様なダンスだからテンポ感はこうとか。
みんな毎日8時間真面目に練習をして、怒られながらも耐えて、とにかく上手になることだけを考えて必死に頑張っていたと思いますが、初めて音楽とヨーロッパの文化のつながりを、有田先生に教えて頂き、【宮廷音楽家や作曲家は雇われて、王様のために作曲していたんだよ】とか、そういう基本的な事も全く知らないし!(笑)そもそもバッハが本当に生きていたのか・・・とすごく疑問でした(笑)。
そういう意味で、楽譜上の音符をただ綺麗に早く上手に弾いてコンクールで賞を取るようになるということよりも、もっと本質的にどう音楽がヨーロッパで生まれ、親しまれ、発展して、ヨーロッパ文化の中に浸透してきたのかということに興味を持ち始めました。バッハの音楽などは素晴らしいから300年経った今も残って、日本も含め世界中で弾かれているっていうことを、日本のピアノ教育の中では理解しきれなかったんですよね。
- なるほど。それを有田先生が教えてくださったと。
植山 新しいドアを有田先生が開けてくださったというか…。
だから私の周りの今バロック音楽を弾いている友達は皆、日本や本場のヨーロッパで一流の団員として世界ツアーをして活躍していますけれど、みんな元々モダンバイオリンやモダンピアノを頑張ってきた子が、よりその作曲家に近づきたいっていう思いで、バロックに目覚めてしまった(笑)という感じです。
私は小さい頃から、「モーツアルトは真珠がころころと転がるイメージで弾いてね」とみんな言うけど、一体誰が決めたんだろう(笑)?って子供ながらにすごく不思議でした。ドイツという国にも行ったことないし。
【モーツアルトが天才、天才と言うけど、本当に生きていた人なのかな?】とか疑問でしたが、ウイーンのモーツァルトハウスに行って、実際に作曲していた天井に天使が描かれている綺麗なお部屋なんですけれど、そこを観て初めて生きてたんだなあって思いました。モーツァルトが実際に使っていたフォルテピアノやベートーベン、ハイドン、メンデルスゾーン、リストの家が博物館になっている所へ実際に行って、どういうフォルテピアノを使っていたかによって、今現存するほぼ同じモデルのフォルテピアノを弾かせてもらい、作曲家がイメージしていた【音の世界】を知ることができるんですね。すると、スタンウェイを弾いた時も、それぞれの作曲家がどんな音色のピアノを弾いて作曲をしていたか、随分イメージがはっきりして、より作曲家の音の世界を近くに感じれる様になりました。アメリカやヨーロッパの旅行の先々で弾ける楽器博物館や個人のコレクションは出来るだけ訪ねて行って弾きました。そういう意味では、高校の頃から、古楽器に興味を持ち始めました。
- 日本にいる間はピアノを専攻してらしたのですよね?
 植山 はい。小さいころから練習したピアノから、例えばチェンバロに替わる、フォルテピアノに替わるって、多分日本では、替われる勇気がでないんですね。先生も猛反対するだろうし、親は勿論、周りもそんなこと許されない雰囲気。アメリカは、【何歳になっても勉強し続ければいいよ】という、学びたい事や年齢に関係なく、みんな好きなことを自分の人生でやっていくという、すごく自由な雰囲気なので、私のピアノの先生はバロックが嫌いにもかかわらず(笑)、【人生一回だからお好きなことやりなさい】って言って下さって…。本当に感謝していますね。
植山 はい。小さいころから練習したピアノから、例えばチェンバロに替わる、フォルテピアノに替わるって、多分日本では、替われる勇気がでないんですね。先生も猛反対するだろうし、親は勿論、周りもそんなこと許されない雰囲気。アメリカは、【何歳になっても勉強し続ければいいよ】という、学びたい事や年齢に関係なく、みんな好きなことを自分の人生でやっていくという、すごく自由な雰囲気なので、私のピアノの先生はバロックが嫌いにもかかわらず(笑)、【人生一回だからお好きなことやりなさい】って言って下さって…。本当に感謝していますね。
- いくらアメリカとはいえ、専攻を替えようと思った時には勇気が必要ですよね。
植山 ええ、半年間毎日悩みましたね。今までのピアノ―チェンバロに転科したのはアメリカで2年ピアノを勉強した後だったんですけれど―それが24歳の時で、ほぼ20年勉強してきたピアノを捨てるのか、ピアノの蓋を閉めるってことなのかという恐怖感があって…。
果たしてチェンバロが自分に合っているかも全く分からないし、誰にも訊けないし、他に例がなかったので(笑)。
- 専攻を替える方も少ないと思いますが、その中でもチェンバロは少ないですよね?
植山 桐朋の卒業生はモダンピアノでロンドンとかドイツで留学して、イタリアとか、ジュリアーノ、インディアナとかみんなモダンピアノですね。
- チェンバロに替わると活躍の場面も、またピアノとは違ってくると思うんですけれど。
植山 全く違いますね。
- チェンバロのリサイタルなどは、数は少なくともある?
植山 勿論あります。チェンバロやバロック音楽を日本へ紹介していく意味で切り開いていった方などいらっしゃいます。ピアノ人口が100人いるとしたら、チェンバロ人口は3人くらいだと思いますが。
- チェンバロですと、まず楽器がどうやって保存できるのかとか、お家で大丈夫なのかなとか心配になってくるのですけれど。
植山 そうですよね、色々分からないことが多いですよね。まず私の感覚でいうと、チェンバロのタッチはピアノの鍵盤の3分の1位の軽さなんですよ。なので、ピアニストがいきなりチェンバロ弾くと叩きすぎちゃって壊れてしまったりします!
ピアノとの決定的な構造の違いはピアノがハンマーで音を出しているのに対して、チェンバロは小さな爪の様なもので弦をはじいているので、どちらかと言うと、ハープに鍵盤が付いているようなイメージです。チェンバロの弦をはじく部分は、17-18世紀は鳥の羽を削った1mmくらいの爪みたいな物だったんです。上手いチェンバリストとほど、殆ど動かないんですね、指が何にもしてないように見える。例えばバイオリンのピチカートを、より大ホールで響かせたいと思ったら、浅くはじいてしまうと全く響かないのと同じで、より張力を感じて最後にぷちんって弾く方が響きますね。
- はい、そうですね、分かります。
植山 あれをチェンバリストは指でやっているんです。
- なるほど。
植山 叩くと逆に音は潰れて汚い音しか出ません。鍵盤のほんの2、3ミリを触った時に、鳥の羽(今はプラスチックの爪のような部分)が、弦に触れてはじくまでをいかに感じられるかっていう、ミリ単位の指先の感覚が必要なんです。チェンバロに替えた時には、体にモダンピアノの20年の癖が入っていたので、叩くし、腕は回す、肘がなぜか歌ってるというか勝手に動く!(笑)肩も体も前後に揺れるという癖を一切止めて指だけをミリ単位で鍛えるというピアノの癖を抜く所から始めました。
- 大変そうですね…。
植山 練習する時に、自分の動きが大きすぎるなって思った時は、背中を固定するために、ものさしがなかったので(笑)、傘を背中に差して練習しました(笑)。いかに自分が無駄な動きをしているかが分かります。とにかく指は脱力して力は一切必要ないので、ピアノの筋肉は全部落ちましたね。
- では今はピアノを弾くとなると大変?
 植山 今、ピアノを弾くと筋トレみたいですよ(笑)。モーツアルト時代のフォルテピアノは、まだチェンバロが存在した時代に発明された初期のピアノなので鍵盤も軽く、チェンバロのテクニックで弾けます。フォルテピアノが発明されて楽器の構造が変わり、強弱が出せるようになり、モーツァルトは最新の楽器に大喜びしてピアノソナタを作って…それは本当に感動的なことだと思うんですね。だから、私は(最新技術であるピアノから)チェンバロに戻りましたけれども、あれだけの進化を遂げた、ピアノにしかない魅力は素晴らしいと思います。ブラームスの曲を聞いたりすると、赤い絨毯を歩いているような重厚さを感じますし、それはバロック音楽とは違う魅力ですね。
植山 今、ピアノを弾くと筋トレみたいですよ(笑)。モーツアルト時代のフォルテピアノは、まだチェンバロが存在した時代に発明された初期のピアノなので鍵盤も軽く、チェンバロのテクニックで弾けます。フォルテピアノが発明されて楽器の構造が変わり、強弱が出せるようになり、モーツァルトは最新の楽器に大喜びしてピアノソナタを作って…それは本当に感動的なことだと思うんですね。だから、私は(最新技術であるピアノから)チェンバロに戻りましたけれども、あれだけの進化を遂げた、ピアノにしかない魅力は素晴らしいと思います。ブラームスの曲を聞いたりすると、赤い絨毯を歩いているような重厚さを感じますし、それはバロック音楽とは違う魅力ですね。
チェンバロをアメリカ、アムステルダム、パリで専念した7年後くらいに、フォルテピアノを学ぶ最後のチャンスだと思い、パリに住みながらベルギーのブリュッセル音楽院のフォルテピアノ科に入り、2年間通いました。月1回パリから新幹線みたいなタリス高速列車に乗って通いました。パリから1時間20分で行けるので、千葉から東京に行く感覚で(笑)通っている生徒さんが沢山いましたよ。パリのオーケストラでチェンバロの仕事をしていたので、さすがに4ヶ国目に引っ越して一からやり直すのは無理だと思い、2年間ハイドンのフォルテピアノ初期時代からフランクのロマン派の時代の曲まで違うフォルテピアノ、構造に対してどの様に弾きわけるかという事を勉強しました。チェンバロから今のモダンピアノまでへの発展を学んですごく良かったですね、そういうことは日本でなかなか学べないので。
今パリではモダンとバロックの両方を弾きこなせるという事がオーケストラなどの仕事でも需要が増えています。例えば、パリオペラ座のオーケストラの団員で、仕事もキャリアも安定しているのに、再びバロックヴァイオリン科に入って学ぶ方等いらっしゃいます。モダンだけじゃなくて、バロックも弾けるっていうのが、今流行っているというか、アラモードになっていて、バロックの弓に持ち替えて弾けるようになりたいって人たちも結構多いですよ。
まだ日本では、モダンはモダン、バロックはなんか古臭い、なんであんな異色な!っていう感じで観られますよね(笑)
- 日本では確かに住み分けというか、全く別のものになっている感じがありますね。最近フランスへ留学したいと言う学生さんが増えているように思うのですが、幅広く自然に勉強できるからっていう理由があるのでしょうか?
植山 うーん、個別の楽器のことは詳しく分かりませんけれど、木管金管系は確かにすごく上手ですよね。
- 元々ヨーロッパで始まった楽器ですしね。本場にいくってことがそれだけで勉強になりますよね。
植山 ピアノは例えばアメリカ、中でもニューヨーク、いわゆるジュリアード系のピカピカの明るい音でばりばり弾くと、聴衆も喜んでくれる。だけれど、そういう演奏をヨーロッパですると、良く弾けるけど、スタイルが分かっていないのでは?内容が浅い・・・と言われたりすることがあります。
アメリカ、またはヨーロッパに留学するかで全然違うし、ヨーロッパの中でもイタリア・フランス・イギリス・ドイツではそれぞれ違うと思います。自分がフランス音楽をやりたいのか、ベートーベンを極めたいのか、先生との出会いにもよりますし。ロシア人でも素晴らしいバッハを弾くか方もいますし。
逆にロンドンに12年ピアノ留学・お仕事をしている友達は、イギリスはフランスにもドイツにも属していないから、自由で割と個人を尊重してくれると言いますね。でもイギリスはヨーロッパだから伝統的なスタイルから外れたことは好まないと思います。アメリカはスタイルをとっぱらって、彼女の弾き方は素晴らしいと、人間性をそのまま受け入れてくれる人たちなので。同じ自由でもアメリカとヨーロッパでは、その雰囲気や趣味が異なると思います。
- 最初ご留学されたのがアメリカなのはなぜだったのでしょう?
植山 高校3年生の時にローゼンバウムという先生が、ボストンの音楽院の学長兼ピアニストをしていて、学校で公開レッスンを受けました。毎年、日本で公開レッスンをされていたので、高校3年生から4年間、毎年参加していました。初めてショパンのバラード1番のレッスンを受けた時に、「この先生と何か通じるな」とピンと来たので翌年、大学生になって夏期講習をボストンへ受けに行きました。ご縁ですね。
大学の時はフランス語を始めて、とてもフランスに惹かれていたので旅行へ行き、3、4年生時には講習会を受けに行ったり、フレーヌ音楽祭に行ってレッスンを受けたりしましたが、そうぴたっときたわけでなくて(笑)。特にフランスの先生は個性が強いので(笑)。自分に合うか合わないかは、レッスンを受けて確かめる以外にないと思うんですよ。
- 人から聞いても違うこともあると。
植山 ええ、実際友達に薦められて受けたけれども、全然私にはぴんとこなかった事もありました。アメリカ人はとてもオープンでコミュニケーションがしやすいのですが、フランス人はコミュニケーションがすごく特殊なんで(笑)。オープンというより、プライベートな感じを好む方が多いと思います。フランスが個人主義の保守的な人たちが多い国だと思います。それは、伝統や歴史があるので重んじるという所からも来ていると思います。
例えばアメリカ人だと、ハロー!ハワユー (How are you?) って誰にでも笑顔だし、みんな気持ち良く接してくれて、ちょっと弾けばブラボー!!!という感じで、若い頃に行くと伸びると思います。褒めて褒めて伸ばす方針。
フランスは本当に良い時にはトレビアン!と言うけれど、【悪くない=パマル】という表現を聞くことが多いです。例えば日本語で、演奏後に【悪くなかったね】と言われたら、褒め言葉でないですよね。だけど、フランス人は皮肉屋さんなので、割と気に入っている場合もパマルと言うんですよ(笑)。パマルはどうやら褒め言葉らしい?ということが、2~3年後にフランス人の友達に聞いて分かったり!国によって認め方も違うんだなって(笑)。
パリに住み始めた最初は2年間本当に何も起こらなくて、落胆しました、本当に厳しい…。パリって華やかな、人生薔薇色みたいなイメージがあるのに、実際に住んだら灰色みたいな(笑)、ギャップがあれだけ大きい街は他にはないのではと3ヶ国住んでみて思いました。一番苦労もしたけれども、6年間とても貴重で素晴らしい体験をさせて貰えたと思います。どの分野の音楽でも一流がいらっしゃいますし。
- そうですね。やっぱり留学先にもよるんでしょうか。
植山 人により国との相性はありますね。でもどこに行くにも、勉強する先生によって大きく印象も充実感も変わると思います。先生が素晴らしい演奏家でも、初めて外国暮らしで、家の借り方も分からないし話せない。だけれど先生はほったらかし、ツアーで忙しくて不在で月に数日集中レッスンのみという場合もあります。行ってみて現状が分かることが多いので、留学前に1度どういう場所か、町や音楽院の雰囲気、何よりも先生と信頼感があるのか実際に行って確認するのは良いと思います。
- なるほど。
植山 私も最初は本当に数え切れないほど失敗をして、パスポートを盗まれたり…。アメリカからヨーロッパに大陸を変える引越しは結構大変でしたね。
- アムスではどうやって師事する先生を見つけられたのですか?
 植山 オランダは、チェンバロやフォルテピアノでいうメッカ・聖地なんですね。先日亡くなられた高名なグスタフ・レオンハルト、ピアノでいえば、リヒテルみたいな方が生きていらしたのと、彼のメソッドがやはり主流でオランダに10年以上留学していたフォルテピアニストの先輩に聞いて、重い荷物をガラガラがらがら引いてレッスン受けに行って。
植山 オランダは、チェンバロやフォルテピアノでいうメッカ・聖地なんですね。先日亡くなられた高名なグスタフ・レオンハルト、ピアノでいえば、リヒテルみたいな方が生きていらしたのと、彼のメソッドがやはり主流でオランダに10年以上留学していたフォルテピアニストの先輩に聞いて、重い荷物をガラガラがらがら引いてレッスン受けに行って。
アムステルダムの先生は、1回しかレッスンを受けなかったんですけれども、とても充実していました。時間きっちりで、連絡メールもすぐ返信があり、イギリス組曲を2時間びっちり丁寧に教えて下さって。ボストンの初めてチェンバロを教えて頂いた先生は本当に面倒見の良い、大らかな先生で、彼以上に素晴らしい先生はいないと思っていました。けれど、5年間、一からチェンバロを教わり、元々ヨーロッパで生まれたチェンバロを、アメリカ人だけに習うのはどうかと思い、文化的背景を学ぶ為にも発祥の地、ヨーロッパへ行こうと思いました。
ボストンの先生はヨーロッパのコネクションがなかったので、自分で行くしかないと思い、スイス・フランス・ベルギー、オランダを強行突破の様に先生探しの旅をしました。実際、アムステルダムの先生と勉強し始めたら、井の中のかわずで、知らないことがこんなに沢山あるんだと、また一からやり直しいう感じでしたね。
- なるほど。フランスに行かれた時はすでに演奏家として?
 植山 いえ、まだアムステルダム音楽院を卒業したばかりでした。22歳でアメリカに行き、27歳でアムステルダムへ行った時先生に「もう27歳?僕は32の時には子供が3人居たよ」って言われました(笑)。でも、ベルサイユ宮殿で盛んだったフランスのバロック音楽は、ドビュッシー、ラベルに通じる、フランス人にしかないエスプリや雰囲気があり、実際フランス語で話して、暮らしてみないと絶対理解できないだろうなあと思っていました。特に、チェンバロの練習曲や教則本は17世紀の古フランス語で書かれているので原語で読んで理解しないと、演奏法がわからない。すでに29歳で、コンヴァト(コンセンヴァトワール)国立申し込みが30歳までなので、ぎりぎりだったんですけれど、さすがに学生こんなにやったから、うんざりしていたので、何にもプランなしで(汗)、ただフランスに行く!行くぞと(笑)。
植山 いえ、まだアムステルダム音楽院を卒業したばかりでした。22歳でアメリカに行き、27歳でアムステルダムへ行った時先生に「もう27歳?僕は32の時には子供が3人居たよ」って言われました(笑)。でも、ベルサイユ宮殿で盛んだったフランスのバロック音楽は、ドビュッシー、ラベルに通じる、フランス人にしかないエスプリや雰囲気があり、実際フランス語で話して、暮らしてみないと絶対理解できないだろうなあと思っていました。特に、チェンバロの練習曲や教則本は17世紀の古フランス語で書かれているので原語で読んで理解しないと、演奏法がわからない。すでに29歳で、コンヴァト(コンセンヴァトワール)国立申し込みが30歳までなので、ぎりぎりだったんですけれど、さすがに学生こんなにやったから、うんざりしていたので、何にもプランなしで(汗)、ただフランスに行く!行くぞと(笑)。
- 勇気がありますね!
植山 なぜかフランスに行かずして日本に帰れないと思っていました。
- ビザとか大丈夫だったんでしょうか?
植山 ブローニュ(パリ郊外)にお家が見つかり、歩いてすぐの所にブローニュ地方音楽院があり、そこに素晴らしいチェンバロの通奏低音科の先生がいるといことで、2年間修士課程を勉強しました。
そうこうしてるうちに、仕事につながって行きました。
- 仕事を得るきっかけはあったのでしょうか?
植山 友達からの1本の電話のみです!チェンバロの場合は、自分で履歴書をどこかに送るなどの機会がないんですよね。大概のオケってチェンバロ奏者は1人いれば十分なんですよね。
それでも、バロックオケは日本の10倍以上あります。それだけ仕事もコンサートもあるし、著名なオケの場合は2~3年先まで演目が決まっているので、いつチェンバリストが必要と随分前から分かります。団員の人が弾けなかったら、友達の誰でもいいから、弾ける人を探すとなります。友達に、「来月ヒマ?」と聞かれて、「あいてるよ」と答えて、そこからですね。
私はそれまでオケと一緒に弾く機会がほとんどなかったので、失敗ばかりでした!全然違うところで、一人だけ入っちゃったり(笑)、私のせいでもう一回振り直しなんてこともありました。みんなこっちを振り向いて冷たく見られたり…ただでさえアジア人で浮いているのに(笑)。最初は挨拶もしてくれないし。ようは弾けてなんぼってことです。弾けたら何となく…良いとも言わずに何回かコンサートに呼ばれて、続けて電話がかかってくれば、前回は大丈夫だったらしいと(笑)。そんな感じで未知の世界が一杯でした!
そこから輪も広がり、別のメンバーが、自分の地元で音楽祭をやりたいから弾いてと言われて行く、そこに行って別の人に出会い、なんか一緒に弾こうよと言われ、アンサンブルのメンバーに知らぬ間になっていて(笑)・・・とか。
アンサンブルのメンバーに誘ってくれた友達の旦那さんは実は有名なピアノトリオのチェリストだったのですが、私1人だけ何も知らなかったんです(笑)。
アンサンブルのブランデンブルグ協奏曲の初合わせに行ったら、「バイオリンの方も上手だけど、全然バロック分かってない、ブラームス弾くみたいにバッハを弾いてる、この人何者なんだろう?!」って思ってました(笑)。チェリストの旦那さんは、コンセンヴァトワールでモダンとバロックチェロを勉強して両方に精通している方で、一生懸命バイオリニストさんに教えてあげているんですよ。かたや奥さんの彼女はバロック専門、なのに一言も言わないので「なんでガーガー弾くあの人に、教えてあげないの?」とリハーサル後に聞いたら、「彼、誰だか知らないの?タワーレコードにCDが20枚はある人だよ」と。誰?!私だけ知らなかったの!?その人に「君のチェンバロ音が小さすぎて僕聴こえないよっ」って言われて、「すみませんけれど、あなたの音量が大きすぎて、あなたのせいでですよ」って答えてしまいました(笑)!!彼女は、あの有名なチェリストの奥さんと見られることが多く、それが嫌だったので自分からは言わないことにしてたみたいなんですね。それでも有名だから大概の方は気付くのでしょうけれど、私は外国人だし、知らないし、分からなくて(笑)
- 奥様はきっと楽しかったですよね。
植山 そうですね。相当ボケたキャラクターに思われたみたいです。それがご縁で、旦那様とも3年間一緒に弾かせて頂き、ブランデンブルグのヨーロッパツアーなどをその後ご一緒して、パリコンサートのライブ録音はクラシックのラジオ番組で放送されたりしました。私は2011年2月に本帰国した後に、そのご夫婦から6月~11月に「この日とこの日は空いている?」聞かれ、「ベートーベンとも交流のあったデュポールという作曲家の世界でまだ誰も弾いていないソナタ全集を世界で初めて録音しないか?」ということで、日本ではなかなかできない企画だったので、もう1度フランスに5カ帰りました。その間に、ゴルトベルク変奏曲を380年前のマリーアントワネットが所蔵していたというスイスの博物館にあるチェンバロで録音もしたので、3月に2枚のCDがパリと日本を含む15ヶ国で発売されます。
元を辿れば、友達からかかってきた電話1本からここまで繋がって、みんなに本当に感謝です。
- 人との繋がりが基本というか、大切なんですね。
植山 とても大事だと思います。急いで音楽家を探している場合、信頼する音楽家に電話して、「君が無理ならば、君が信頼している他の音楽家を紹介して」という運びになるので、そのコネクションの中にいるかいないかというので仕事量が変わってくるみたいですね。
努力している子は何かとコンサートやリハーサル、カフェやご飯にも顔を出し、パリの音楽家の中に浸透していましたね。留学中は学校で勉強してコンクール等で頭一杯だと思いますけれど、その土地で音楽を仕事として生きていきたいならば、言葉が話せないと勿論無理ですし、積極的に自分でこういう事をやっていきたい、アンサンブルをしたいん、こういうコンサートをしたいので場所やオーガナイズできる方を紹介して欲しいと自分ではっきり主張しなければ動いていきませんね。
- 日本人は、自主性や積極性が、ヨーロッパに比べて、大人しいとよく言われますが。
植山 自主性や積極性は大事なんですけれど、ヨーロッパの人に比べて、日本人は自己主張をするように育てられていないから…。譲り合って、相手のことを考えるのが美徳ですからね。でも、徐々に慣れていくと思いますし、はっきり自分の意見を伝えるというのは、音楽家としても必要な事だと思います。
- 今後の音楽的な夢は?
 植山 チェンバロという楽器がまだ広く知られていないので、少しでも多くの方に知って頂けたら嬉しいです。
植山 チェンバロという楽器がまだ広く知られていないので、少しでも多くの方に知って頂けたら嬉しいです。
バッハをピアノで演奏していた時に、装飾音に悩んだり、分からない事が沢山あったのですが、ピアニストの方にもチェンバロでバッハを元々どのように弾いていたか知って頂けたら、ピアノでバッハを弾く時に良いヒントになるかと思います。パリで日本人のピアノの先生を教えていましたが、「チェンバロはこんなに新鮮なんですね」ってすごく喜んでいらっしゃいました。そういう意味で世界を広げるというか、魅力を体験してもらいたいなと思っています。
- これから留学したい海外で活躍をしたい音楽家にアドバイスありますか?
植山 日本人の真面目さ、勤勉さやテクニックでは世界で高く評価されているし、外国人の先生の間でも礼儀正しい事も含め定評があります。でも、外国には「テクニックはあまりなくても、なぜか魅力的なんだよね、あの人の演奏って…」という演奏が多いですが、そんな音楽的な魅力が日本人に加わったら良いのではないでしょうか。
- 外国人はどうしてそういう方が多いのでしょうか?
植山 私も、それはどうして?どこから?と考えてきました。
向こうの人は、真面目に練習するだけでなく、コンサートや美術館や文化的な一流のものに日常の生活で自然に接し、感性を高めていると思います。また、テクニックがなくても自分がどの様に表現したいかというイメージやアイデアがはっきりしていると、やはり音楽を通して訴える力が強くなるのではないでしょうか。
日本人の私たちは、きちんと弾くという所をまずクリアしてから表現力という感じですが、外国人は表現する為にこういうテクニック必要・・・まず表現力を重要視していると思います。
例えば、自分が今現在弾いているドビュッシーの音楽を、家に行くこともできるし、博物館にあるドビュッシーが弾いて作曲していたエラールのピアノを誰でも弾かせて貰えます。現地でしかできない経験を沢山していく事が宝だと思います。失敗を恐れないで下さい。私は数々の失敗をして学んできたタイプですが、恥ずかしいと言っている場合でなく、何でも経験して、分からなければ教えて貰えば良いと思っていつも周りに聞いてました(笑)。恥ずかしいから話かけられないとか、あの先生に観て貰いたいけれど自信がないから今度にしよう、と思っていたら外国へ行ってしまったとか、本当に目の前にあるチャンスは、自分で掴んでいく、アンテナ張っていくしかない。
- そういうチャンスに気付けることが大切ですね、ぼんやりしていたら気付けない。
植山 私も最初友達に言われたのですが、温室育ちで音楽しか知らない人生でした。でも、留学は生活半分音楽半分というのが現状で、生活が上手く回らないと音楽にも集中できなくなってしまうんですね。ビザでトラブルがあって書類が取れないとか、それだけで移民扱いされちゃいますから(笑)。外国人警察署、移民当局へ行って、半日並ばされてやっと1年分更新して。「私は犯罪者か?」って気が滅入ることもあります。それでも、自分が何をしに来たのか目的意識をはっきり持つ事は大事ですし、自分が何かピピッと感じたら迷わずに積極的に行動することが次に繋がったり、コンサートで弾いてという話に通じる場合もあります。自分の留学生活、自分の人生だから、自分のために頑張ってほしいですね。みんな笑ったり、泣いたりと色々な時期があり全て含めて、やっぱり留学して良かったと思うと思います。そんな色々な経験が知らないまに音楽に深みを与えるのではないかと思います。自分では分からない場合もありますが、ドイツへ留学したピアノの旧友の演奏を聴いてガラッと変わっていました。より深みが出て素晴らしかったです。
- やはり日本という独特の環境もありますでしょうか。
植山 日本ほど安心して住めるところではないので、最初は大変だと思います。日本より平和は国はないです!エスカレーターが話したり、トイレが話したり、あれはフランス人衝撃ですよ(笑)!まさに、至れり尽くせりの国ですから。日本でどんなにエリートでコンクール歴がある方でも、留学して「もっと自由に弾いて」と先生に言われて、自分の心を開放するということが分からなくなることがあると聞きます。みんな悩んで、どん底に落ちて、1回自分を壊して、生まれ変わると、本人は気が付かなくても、先生のおっしゃることを信じて新しい方向で音楽を見つめたら、数年後には更にスケールの大きい音楽家になっていたということもありますので、恐れないでほしいですね。みんな知らない事や知らない場所へ身を置くのに不安なのは一緒。それでも、自分を信じて進めばいつか忘れた頃に良い結果が出たり、自分で自分の成長に気が付くかもしれませんね。
- 大変貴重なお話をありがとうございます。これから留学をする皆さんも参考にしてくれると思います。
植山 チェンバロという分野が留学生の方が多くはないと思いますので、お役に立てれば嬉しいのですけれど。
- チェンバロを目指す方だけでなく、広くみなさんに興味を持っていただける面白いエピソードをいただいたと思います。本日は本当にありがとうございました!
-----------------------------------------------------------------------------------------
*お知らせ*
ラファエル・ピドウー氏(チェロ)と共演のCDが4月末に発売となります!
----------------------------------------------------------------------------------------
ダンス留学アンドビジョン【最新情報 vol.10. 2015-11-11 05:00:00】
≪火曜21時にお引越し♪≫パリ特集!国内情報も!AndVision音楽留学メールマガジン
N.S.さん/ウィーン冬期音楽講習会
★2/14・ 9:00-【☆バークリー音楽大学ソングライティングワークショップ☆】現地講習会担当者がプログラムについて解説致します!★
バークリー音楽大学ソングライティングワークショップ
Information Session
~バークリー音楽大学ソングライティングワークショップオンライン説明会~
参加費無料・完全予約制・オンラインでの参加も可能です
ゲストスピーカー:バークリー音楽大学ソングライティングワークショップ プログラムディレクター バレリー・オース先生 (バークリー音楽大学准教授)
日時:2月14日(金)9:00-9:30
場所:≪アンドビジョン・東京オフィス≫
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-8 神田駿河台ビル2階
JR御茶ノ水駅御茶ノ水口から徒歩7分、東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩5分程度
♪参加ご希望の方は、こちらからオンライン予約フォームを送信して下さい。
※説明会予約を選択→その他ご要望等に“バークリー・ソングライティング”とご記入下さい。
お電話・FAX・メールでのご予約も承っております♪
電話:03-5577-4500 FAX:03-4496-4903 メール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。