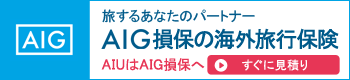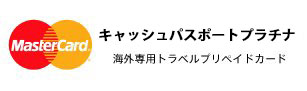中嶋彰子さん/声楽/オーストリア・ウィーン
 15歳でオーストラリアに渡り、シドニーで音楽教育を受ける。1990年の全豪オペラ・コンクール優勝を機に、シドニーとメルボルンのオペラハウスにてデビュー。1999年、ウィーン・フォルクスオーパーと専属歌手契約を結び、その卓越した歌唱力と演技力、華やかな存在感で圧倒的な人気を獲得。一躍劇場のトップスターに。イタリア・ベルカント・オペラからモーツァルト、シュトラウス、ヴェルディ、そしてフィリップ・グラスなどの現代作品まで、幅広いレパートリーも魅力のひとつ。
15歳でオーストラリアに渡り、シドニーで音楽教育を受ける。1990年の全豪オペラ・コンクール優勝を機に、シドニーとメルボルンのオペラハウスにてデビュー。1999年、ウィーン・フォルクスオーパーと専属歌手契約を結び、その卓越した歌唱力と演技力、華やかな存在感で圧倒的な人気を獲得。一躍劇場のトップスターに。イタリア・ベルカント・オペラからモーツァルト、シュトラウス、ヴェルディ、そしてフィリップ・グラスなどの現代作品まで、幅広いレパートリーも魅力のひとつ。
ダンス留学アンドビジョン【最新情報vol.10. 2015-09-29 07:00:00】
佐藤佑樹さん/モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミー&アレグロ・ヴィーヴォ室内楽マスタークラス
★2/17・ 18:00-【☆ウィーン国際夏期ピアノ講習会☆】現地講習会担当者がプログラムについて解説致します!★
ウィーン国際夏期ピアノ講習会
Information Session
~ウィーン国際夏期ピアノ講習会オンライン説明会~
参加費無料・完全予約制・オンラインでの参加も可能です
ゲストスピーカー:講習会講師 ステファン モラー先生
日時:2月17日(月)18:00-18:30
場所:≪アンドビジョン・東京オフィス≫
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-8 神田駿河台ビル2階
JR御茶ノ水駅御茶ノ水口から徒歩7分、東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩5分程度
♪参加ご希望の方は、こちらからオンライン予約フォームを送信して下さい。
※説明会予約を選択→その他ご要望等に“ウィーン国際夏期ピアノ講習会”とご記入下さい。
お電話・FAX・メールでのご予約も承っております♪
電話:03-5577-4500 FAX:03-4496-4903 メール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
キューバ共和国
| 気候 キューバの気候は亜熱帯性海洋気候で、乾季と雨季がある。乾期は11月から4月、雨期は7月から10月年間を通して平均気温25.5度と暖かいが、貿易風の影響で夏の暑さも意外に過ごしやすい。ハリケーンが9,10月は多いので、計画をきちんと立てよう。 |
|
| 現在の天気 | |
| ビザ | 観光目的で30日以内の滞在ならビザは必要ないが、かわりに「ツーリスト・カード」が必要。学生ビザについてはこちら。 |
| パスポート | 残存有効期間が滞在日数以上あること |
| 大使館などの在日政府機関 | |
| キューバ共和国大使館 | Embassy of the Republic of Cuba in Japan 〒106‐0044 港区東麻布1丁目28-4 Tel:03-5570‐3182 開館時間:9:30〜17:30 (木・金は 17:00 まで) 領事部開館時間:9:30-12:00 ビザの取得について 電話番号:03-5570-4481 FAX番号:03-5570-4483 |
| 現地日本大使館 | |
| 在キューバ大使館 | Cuba Embajada del Japon Centro de Negocios Miramar, Edi, 1-5 to. Piso, Ave. 3ra, Esq, a 80, Miramar, Playa, Habana, Cuba (Apartado No. 752) Tel: (53-7) 204-3355 Fax: (53-7) 204-8902 |
|基本情報 | 物価 | 気候・現在の天気 | ビザ・パスポート |
| 大使館などの在日政府機関 | 現地日本大使館 |
千々岩英一さん/ヴァイオリン/パリ管弦楽団副コンサートマスター/フランス・パリ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回はフランスでパリ管弦楽団副コンサートマスターとして、パリ地方音楽院およびパリ市立音楽院教授としてご活躍中の千々岩英一(チヂイワエイイチ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年3月)
ー千々岩英一さんプロフィールー

東京芸術大学音楽学部附属音楽高校を経て同大学を卒業後、フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院に学び、審査員全員一致の一等賞を得て卒業。田中千香士、数住岸子、ピエール・ドゥカン、オリヴィエ・シャルリエ、フィリップ・ヒルシュホルン、ワルター・レヴィンの各氏に師事。1998年よりパリ管弦楽団で副コンサートマスター。パリ国立地方音楽院およびパリ市立音楽院(パリ13区モーリス・ラヴェル音楽院)教授。ソリストとしてドナウエッシンゲン音楽祭(ツァグロセク指揮フランス国立管弦楽団)、パリ・シャトレ座のパリ管弦楽団定期演奏会、東京シティフィルハーモニック管弦楽団の定期演奏会などに出演した他、室内楽奏者としてベルリン芸術週間、「パリの秋」音楽祭、ルーヴル、オルセー美術館室内楽シリーズ、イギリス・オールドバラ音楽祭など多数演奏。CDはスカルコッタス作品集 (Bis) 、ノーノ、ラッヘンマンの弦楽四重奏曲(仏Assai)、マルク・アンドレ・ダルバヴィの協奏曲(エッシェンバッハ指揮パリ管、仏Naive)などが出ている。
-初めに簡単にご経歴をお願いします。
千々岩 1969年に東京に生まれ、5歳からバイオリンとピアノを始めました。10歳からバイオリンに専念するようになり、東京芸大の付属高校、東京芸大と進み、その後、パリ国立高等音楽院に留学しました。音楽院在籍中にパリ管弦楽団の副コンサートマスターになって、今年で11年目です。
-バイオリンを始められたきっかけは何ですか?
千々岩 はじめにピアノを習った先生のお姉さんが、芸大をオーボエ専攻で出た方だったんですが、バイオリンも教えておられていたんです。それで、せっかくだから両方習ったらいいのではないか、ということで、始めました。僕は、習い始めてすぐに、「自分はピアニストになる」と決めていたんですが、8 歳くらいのときに、ピアノの先生から、「ピアノで食べていくのは難しいから、バイオリンに専念したほうがいいのでは」と言われて、バイオリニストの先生(小林久子氏)について仕方なくバイオリンに集中するようになりました。
-そんなに早くからプロになる道を考えていたんですね!
千々岩 音楽家の家系ではないのですが、父親も母親もとても熱心でした。音楽に憧れがありつつも自分ではできなかったという想いがあったのだと思います。僕自身、バイオリン、ピアノに関わらず、小さい頃から音楽がとても好きだったので、「これを職業にしたい!」と思ったのも、だいぶ早かったですね。
-それでは、8歳のときに先生から「ピアノでは食べていけないわ」と言われたときは、ショックでしたか?
千々岩 先生(平尾はるな氏)はパリ音楽院で勉強されて、プロの世界をよく知っている方でした。先生からしたら、男がピアノでコンサーティストをやっていくには、よっぽどの飛び抜けた才能がないと難しいと感じたのではないでしょうか。その点、バイオリニストなら、オーケストラでも弾く機会があるので可能性があるのではないか、という話だったんです。もっともそのころはオーケストラなんて、TVで見るくらいで生で聴いたこともないし、興味ありませんでしたが。
-そこからは、もうバイオリンを中心に学んでいかれたのですか?
千々岩 そうですね、10歳からはバイオリン一本でした。ピアノは高校の副科で再開するまでは先生には付かず、自己流で弾いていた程度でしたが、今でも、本当はピアニストになりたかったという恨みは残っています。やはりレパートリー的には魅力的な楽器ですから。ピアノをあきらめたときは悲しくて激しく泣いたことをいまだに覚えています。
-パリにご留学されたのは何歳のときですか?
千々岩 大学の四年生のときです。卒業するまで待つとパリ国立高等音楽院の年齢制限に合わなくなるので四年の秋に入試を受け、その時には芸大の必修単位は卒業試験以外ほぼ取り終わっていたので、半年間のうちに数回パリと東京を往復して芸大も卒業しました。
-ご留学を考えるようになったのは何歳のときですか?
千々岩 国際コンクールを受けるために、18歳のときに初めてヨーロッパに渡ったときにヨーロッパの文化に初めて接し、その空気の中で生活したいという気持ちを強く持ったんです。それから、講習会などに参加するようになり、留学を具体的に考えるようになりました。
-初めからフランスへの留学を希望されていたんですか?
千々岩 最初はロシアへの留学を考えていて、大学時代はロシア語も学んだりもしていました。ところが、当時のロシアでは、留学の学生ビザが下りなかったんです。他の可能性を考えたときに、初めて教わったピアノの先生や大学でのバイオリンの先生(田中千香士氏)がパリに留学されていたこともあってフランスには親近感を覚えていたので、ロシア以外だったらフランスを留学先として自然に考えるようになりました。
-どのように師事する先生を探されたんですか?
千々岩 国内の講習会で、ピエール・ドゥカンというパリ国立高等音楽院の教授と知り合いまして、留学を大学3年と4年の間の春休みに決めました。パリのオペラ座のコンサートマスターを長く勤められた方で、講習会で接した演奏も素晴らしく、留学が決まったときはとても嬉しかったです。東京では壁にぶちあたっていたので、心機一転、いちからやり直す気でした。
 -パリ国立高等音楽院というとトップレベルの学校ですが、入試はどんなものでしたか?
-パリ国立高等音楽院というとトップレベルの学校ですが、入試はどんなものでしたか?
千々岩 年齢制限があって、バイオリンの受験資格は22歳までだったんです。僕は、当時2か月ほど22歳を超えていたので本来なら資格がなかったのですが、先生が音楽院と交渉してくださったんです。その結果、特別に許していただいて入試を受けることができました。フランスの場合、なにか規則に引っかかって実現が無理なように見えても、交渉次第でなんとかなることがよくありますね。入試は、そんな事情もあったので他の受験生がだいぶ若く見えました。
-留学前にフランス語の勉強はされていたんですか?
千々岩 大学の第一外国語をフランス語でとっていました。学校で学ぶフランス語は文法中心で、会話のテクニックはほとんどこちらに来てから覚えたという感じです。
-そうすると、入学後に語学の面で少し苦労されましたか?
千々岩 フランス語はなかなか発音が難しくて、自分では文法的にきちんと話しているつもりでも、通じていないことがあったり(笑)。いまではパリ音楽院の入学資格の条件のひとつにフランス語能力もあるようですし、当時の音楽院のカリキュラムでは、フランス語を習う時間というのはまったくなかったので、友だちと会話する中で、実地で学んでいったという感じです。
-ご留学後、日本の音楽とフランスの音楽で感じた違いは何でしたか?
千々岩 日本だと、合奏をしてもまず縦の線を常に意識するところがあると思うんです。パリ音楽院の選択授業でグレゴリオ聖歌を一年間やったときに、横に流れていく音楽を実感しました。そのとき特にフランスでは、縦の動きよりも横の動きへの志向が強いのかもしれないということを肌で感じました。
-フランスの音楽というのは、色彩的できらきらしているイメージがありますものね。
千々岩 そうですね、それはドビュッシーやラヴェルが活躍した時期が、印象派絵画の最盛期だったのでそれらが短絡的に結びついて、フランス音楽イコール印象派という先入観をあたえるからかもしれないですね。僕はとくにフランスものだけが色彩感が豊かというわけではないと思います。
-なるほど。パリ国立高等音楽院は何年間、在籍されていたんですか?
千々岩 いわゆる普通の大学のコースだと当時のカリキュラムとしては卒業のために最低3年、最高5年かかりました。そのあとに日本語に直訳すると完成科という課程がありました。その課程を直接受験することも考えたのですが、そこは大学院というよりもむしろディプロマコースのような感じで、バイオリンだけに専念するコースだったのであまり興味がわかなくて、まずは本科で3年間学びました。専門楽器のレッスン以外に楽曲分析、室内楽、オーケストラ、合唱(混声合唱、またはグレゴリオ聖歌)が必修、在学中にシステムが変わってオプションで指揮や即興、エクリチュール(書法)など興味に応じて単位を取ることができるようになりました。バイオリン科を卒業した後、バイオリンの完成科に2年いて、その後、カルテットで室内楽の完成科に2年いました。
-計7年の間、在籍されたのですね。
千々岩 日本を発つときから、将来はいずれフランスで仕事を見つけて食べて行こうと思っていたので、様子を見るためにもなるべく学校には長く在籍した方がいいなと思っていたんです。やはり、すぐに食べられるようになるわけではないし、学生をしながら少しずつ演奏活動をして、仕事に繋げていこうと思っていたんです。さいわい両親も協力的で、フランス政府の給費が三年で終わった後も援助を続けてくれました。結局、6年目にオーケストラに入って、音楽で食べて行けるかどうかとても心配していた両親を安心させることができたことが、何よりも嬉しかったです。
 -一番最初からパリ管弦楽団ですか?
-一番最初からパリ管弦楽団ですか?
千々岩 はい。最初から今のポストで入団しました。
-すごいですね。フランスでオーケストラに入団したいと希望する方は多いと思いますが、履歴書を送って推薦状をもらってテストを受けられるという感じですか?
千々岩 ドイツなどはそうだと思いますが、フランスの場合は割ともっとオープンで、誰でも受けられるんですよ。例えば、オランダなど他のヨーロッパの国では、ヨーロッパの市民権を持っていないと受けられなかったりもしますが、フランスではそんなことはなくて、外国人でも誰でも受けることはできます。例えば、日本に住んでいて紹介状がなくても受けられます。要は楽器さえ弾ければ入ることができるんですよ。
-募集の情報は、どういったかたちで手に入れることができますか? 大々的に公表していますか?
千々岩 音楽雑誌に掲載されていたり、音楽院に行くと募集のポスターが掲示されています。あとは、今はインターネットで見ることができるようになっていますね。どのオーケストラのウェブサイトにも求人のコーナーがあります。
-千々岩さんが受けたオーディションはどのような様子でしたか?
千々岩 僕が受けたのは、ソリスト(首席)のオーディションだったので、受験者自体がそれほど多くありませんでした。一次でイザイの無伴奏ソナタ、課題のオーケストラスタディを弾いて、二次はブラームスのコンチェルト、さまざまなスタイルのオーケストラのソロ、三次試験でバッハの無伴奏ソナタとオーケストラスタディ、ソロを弾きました。パリ管で既にトゥッティで在籍しているひとが10人くらい一次免除で二次試験から加わったと覚えています。
-そもそもパリ管弦楽団のオーディションを受けたきっかけは何ですか?
千々岩 どうしてもパリ管に入りたかったというわけではなく、あと1年しか学校に籍を置けないことがわかっていたので、その
間にとにかく空いている席を受けないと、フランスを去らなければいけなかったんです。ですので、切羽詰まって仕方なく、ですかね(笑)。
-では、当時、他のオーケストラのオーディションも受けられていたんですか?
千々岩 オペラ座のオーケストラの第一コンサートマスターの席も受けました。そのときはうまく弾けなくて、途中で落ちてしまいました。そのちょうど2か月後が、まったく違うプログラムでのパリ管の試験でした。二回の試験の間にアパートで部屋の模様替えをしたときにギックリ腰になって一週間くらい動けなくて辛かったことを覚えています。オーケストラの募集について言えば、自分が受けたいときに自分に適した席が空いているかどうかわかりませんし、せっぱつまれば火事場の馬鹿力も出てくるし、運の善し悪しがかなりあると思います。
-ドイツではオーディションのときにカーテンがあるという話を聞きますが、パリ管ではいかがでしたか?
千々岩 ないですね。他のオーケストラでもあったりなかったりだと思います。そのあたりは、毎回変わると思います。
 -例えば、日本人が有利な面や不利な面はありますか?
-例えば、日本人が有利な面や不利な面はありますか?
千々岩 試験官の立場で審査するときに、とくに人種差別があると意識したことはありません。ただ、先入観は働くでしょうね。日本人の場合、クリーンに弾ける以上に何かないと難しいとは思います。
-そうなんですね。
千々岩 受かっても、その後半年から一年の間、試用期間があるのですが、その間にアウトになる人もけっこういるんです。外国人だとコミュニケーションの問題がある場合が多いんですよね。
-なるほど。そういう意味で、演奏以外のパーソナリティも重要視されるんですね。
千々岩 そうですね。パーソナリティと言われても、何をしていいか分からないから、本人は結構きついです。フランス人の場合、初めにエキストラで弾いて、ある程度オーケストラ独自の雰囲気が分かってから試験を受けて入ることが多いと思うんです。エキストラに呼ばれるためには一度入団試験を受けて好成績を残したり、先生からの紹介などが必要になります。僕の場合は、オーケストラの中に一人も知っている人がいなかったので、心細い感じはありました。ただ、その前にフランスの現代音楽のアンサンブルで仕事をしていたので、そこでの経験がオーケストラに入ったときに役に立ちましたね。それがなかったら、多分、中に入っていくのが難しかったのではないかなあと思います。
-今では、パリ管弦楽団の仕事の他に、パリ地方音楽院、パリ市立音楽院でも指導されているんですよね?
千々岩 はい、パリ地方音楽院(CNR改めCRR)は3年前にパリ管の首席コンサートマスターのドガレイユさんのポストを引き継ぎました。また、パリ市の音楽院でも教えています。パリ市には20区まであって各区に音楽院があるのですが、13区で指導しています。ここはパリのなかでは規模、レヴェルともに一二を争う学校のようです。
-いろいろな国の生徒さんに教えてらっしゃるのですか?
千々岩 日本人の生徒さんもいます。CRRは初めたときは6人生徒がいたのですが、そのうち3人が日本人で、あとはフランス人が2人、アメリカ人が1人でした。市立音楽院ではフランス人4人。
-アメリカ人の生徒さんに教える場合は、授業は英語ですか?
千々岩 いえ、フランス語です。英語は以前にくらべて話せなくなってしまいましたね。話してもフランスなまりの英語になってしまいます(笑)。
-今でも日本人の生徒さんは多いのですか?
千々岩 どこかの音楽院に登録して滞在許可をもらっている学生が、プライベートで僕のところにもレッスンを受けにくるという感じです。最近は、日本人に限らずオーケストラの入団試験の準備に来る人も多いです。
-なるほど、なるほど。
千々岩 せっかくフランスに来るのですから、フランス人の先生にフランス語で習うというのは、妥当なことだと思います。フランス人の先生とフランス語で話すというのは大切なことなんですよ。フランスに来てレッスンだけの学校に入ると、グループレッスンでもないかぎり音楽の話をフランス語でする機会というのが極端に少なくなってしまうんです。フランス人は、わりと排他的で、外国人の友だちを積極的に作りたいと思っている人はあまりいません。こちら側から積極的に話しかけていかないと、なかなか向こうからは仲間に入れてくれません。
-千々岩さんはどうされていたのですか?
千々岩 僕の場合は、室内楽をフランス人と演奏することで、だんだんと人の輪が広がっていった、という感じです。
 -千々岩さんにとって、音楽とは何でしょうか?
-千々岩さんにとって、音楽とは何でしょうか?
千々岩 僕にとって音楽はコミュニケーション・ツールです。フランスに来たばかりで、言葉が出来ない頃でも、音楽を通してだったらコミュニケーションがとれているという実感はずっとありました。ですので、音楽も言葉の一つという意識が強いです。
-長い間、パリで活躍してこられたわけですが、これから先の目標があれば教えてください。
千々岩 実は、自分がやりたかったことは、もうほとんど実現してしまったんです。現代音楽をすることもできたし、カルテットをする夢もかないました。それから、コンチェルトを弾くという目標も果たすことができました。これまでに自分が積極的にしてこなかったことで言えば、録音を残したいなと思っています。自分の企画でアルバムを残したいですね。これが、外面的な目標です。もっと内面的なことで言えば、演奏の際に音楽とよりいっそう一体化できるように、深めていきたいと思います。
-最後に、留学を考えている方にアドバイスをお願いいたします。
千々岩 自分で求めることがあれば、環境が整えば得ることができます。でも、何がやりたい、と具体的に求めることがないと、どうにもなりません。それは日本でも同じだと思います。とりあえず行けばなんとかなる、ということはありません。
-具体的にやりたいことを定めてから留学をしたほうがいいということですね。
千々岩 言葉が通じないなど、外国に来ると壁が立ちはだかることもあるかと思いますので、そこで味わう辛さにくじけない強さが必要になってくると思います。今は、情報がかなりあふれている時代で、留学生のブログなどを目にすることもあるかと思います。そこに書かれているのを読むと、おいしいもの食べて、コンサート聴きに行って楽しそうだな、なんて思うんですが、負の部分は、なかなか目にすることができないのではないかと思います。また、留学をしたからといって、それでいきなり自分がグレードアップされるわけではないということも、肝に銘じておかなければなりません。
-千々岩さんご自身は、そういった留学後の言葉が通じない辛さはどうやって乗り越えられましたか?
千々岩 僕は、逆に日本にいる頃、居場所がない感覚を感じていたんです。だから、居場所をどうしても見つけなきゃいけないという思いで日本を出たので、言葉が通じないという状況に対して、あまり辛いとは感じませんでしたね。試練の一つと思っていました。ただ、振り返ってみると、僕は友だちに恵まれていたんです。外国人の友達、そして日本人の友達。よく「言葉を覚えるために、わざと日本人とは関わらないように努力する」なんて話も耳にしますが、僕は、日本人の友達もすごく大事だと思います。やはり苦労を共にする同志ですから。無理して排除するのは、気張っていて大変だなぁ(笑)と思います。
-偏らないのが大事ですね。
千々岩 本当にそうですね。若い生徒たちを見ていると、初めは友だちもいなくて、暗い顔をしているんですが、みんな伸び伸びとやっていますよ。それぞれ交流ができて、だんだん明るくなってくる、パリがだんだん自分の庭になってくる、それが目に見えて分かるんですよ。
-そういった精神的な成長とともに音楽も変わってきますよね。
千々岩 うん、それはあると思います。僕は日々を生きるうちに感じること、見聞きすることのひとつひとつすべてがフィルターになって音に表れると思います。個性というのは、無理矢理見つけなくても自分の中から滲み出てくるものだと思います。だから、普通に自然体でやっていくのがいいと思います。
-今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
注)パリ国立高等音楽院を目指す方は最新の情報を必ずご確認ください。2008年に改革がありカリキュラムが大きく変わっています。
コピー 葉玉洋子さん/サンタチェチリア音楽院声楽教授/イタリア・ローマ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回、で声楽の教授としてご活躍中の葉玉洋子(ハダマヨウコ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2012年5月)  ―葉玉洋子さんプロフィール―
―葉玉洋子さんプロフィール―
福岡県出身、広島大学高等教育学部音楽科卒業、大阪音大専攻科終了。大阪芸術大学音楽課声楽科講師。イタリア、ローマサンタチェチリア音楽院、サンタチェチリア アカデミーで学び、ローマを中心にイタリアの重要な国立歌劇場で数多くのオペラを歌う。パルマ国立音楽院、ボローニャ国立音楽院声楽科教授を歴任後、現在ローマ・サンタチェチリア国立音楽院声楽科専任教授としてイタリアベルカント唱法、イタリア、フランスドイツオペラを教えている。 -まずは、葉玉様の簡単なご経歴を教えていただけますか。
葉玉 イタリアに35年住んでいます。福岡県の出身です。広島大学を卒業したあと、大阪音大の専攻科に行きまして、そのあと大阪芸術大学の声楽科で2年間教えました。その後ローマに留学してローマ・サンタチェチリア音楽院に入りました。在学中に国際コンクールで第1位になり、すぐにイタリアの国立歌劇場で歌い始めました。成功の一番の要因は、ペーザロで開催される非常に重要なフェスティバル、第1回ロッシーニ・オペラ・フェスティバルの主役に抜擢されたことが大きいですね。そのことが、イタリア中の新聞に書かれたところから始まりました。
-プロの歌手としてご活躍されるようになったきっかけはありますか?
葉玉 国際コンクールで1位になって声がかかるようになり、最初はロッシーニのオペラばっかり歌っていたところ、ペーザロの主役に抜擢されたわけです。その後は、イタリア中の国立オペラ座から呼ばれて、たくさんのオペラ座で歌うことができました。ヴァチカンで、ローマ法王御前演奏、ヨーロッパ青少年オーケストラと競演したり、イタリア各地を回ったりもしました。コンサート、主にオペラを歌っていました。
そのあとに、国立音楽院の声楽の教授になる国家試験を受け、通りまして、パルマ、ボローニャ、そして今はローマのサンタチェチリア音楽院声楽課選任教授として教えています。
-出身の音楽院ですね。最初のローマへの留学のきっかけはあったのでしょうか?
葉玉 友達が留学先のローマから帰ってきて、色々なローマでの音楽文化の世界を話してくれて、それを聞いたら、行きたいなあと思って。最初からローマに行きたいと思いました。
-最初に音楽の世界に入られたのはいつからでしょう?音楽に興味をもたれたきっかけはありますか?
葉玉 両親がクラシックをとても愛していまして、小さな頃から、親しんでおりました。母がピアノを、おばがバイオリンを弾いておりました。
-音楽一家だったのですね!
葉玉 そうですね。小さな頃から、色々な楽器を習いました。ピアノ、バイオリン、フルート、歌も大好きで、機会があれば色々なところで歌っていたんです。小さいときから、音楽家になることは、わたくしにとって普通のことだったわけです。
-たくさんの楽器の中から声楽をえらばれたのはなぜ?
 葉玉 歌が大好きだったんですね、楽しくて。バイオリンは毎日6~7時間は勉強しないと、プロにはなれません。遊ぶ時間がなくなるので、バイオリンではプロにはなれないと思っていました。遊びたかったんですね(笑)。とにかくビバーチェ、活発な少女でした。スポーツもやりましたし、家の近くで蝶々取りや、木を登ることが大好きでした。オペラを歌うのには体の動きが重要ですので、スポーツ・体操のニュアンスも非常に大切です。日常生活での体の動きは小さなものだと思うのですが、オペラでは大きく動くことが大切です。
葉玉 歌が大好きだったんですね、楽しくて。バイオリンは毎日6~7時間は勉強しないと、プロにはなれません。遊ぶ時間がなくなるので、バイオリンではプロにはなれないと思っていました。遊びたかったんですね(笑)。とにかくビバーチェ、活発な少女でした。スポーツもやりましたし、家の近くで蝶々取りや、木を登ることが大好きでした。オペラを歌うのには体の動きが重要ですので、スポーツ・体操のニュアンスも非常に大切です。日常生活での体の動きは小さなものだと思うのですが、オペラでは大きく動くことが大切です。
声楽というのは、高校に入るころ、15~16歳くらいでは、まだ早いんですよね、高校の3年生から正式に声楽の勉強を始めました。幼少時は、小さかったから声楽を勉強する歳になってなかったので、楽器を習ったということです。バイオリンやフルートは、レガートを勉強するのに非常に良かったです。イタリアでは、カンターレ・エ・レガーレ(Cantare è legare)と言うのですが、歌うのはレガートすることだ、と特に重要視します。のちに声楽を勉強しはじめたときに、感覚がもうすでに体の中に入っていたので、とても助かりました。
-昔やっていたことが全部つながって役に立っているんですね。
葉玉 呼吸法は、フルートが同じなんです。横隔膜を使う、長い、長い呼吸法ですね。色々な面で、楽器を経験していたのは有利だったと思います。
-声楽を勉強するにあたってイタリアに渡られました、イタリアのよい点は?
葉玉 イタリアは、全ての音楽の形式が生まれた国なんです、オーケストラ、シンフォニー、コンサート、様々な楽器…ここから生まれているんですね。イタリアで生活していると言葉自身が非常に歌にあった言葉だと分かりますし、歌を勉強する人は一度は勉強にいらしたほうがいいと思います。言葉そのものが音楽ですので。
弦楽器も全てここから始まっています。レガートを大切にする文化、声楽でも楽器でも音楽にはレガートがないといけませんし、楽器を弾いている先生たちもすごくレガートを大切にしますので、その勉強にはイタリアが一番だと思います。テクニックはアメリカなどが非常にありますけれども、楽器を歌わせることに関しては、イタリアが一番だと思いますね。アメリカはテクニックを非常に大切にする国ですね、イタリアでは、例えばリズムがちょっとおかしくても、(楽器が)すごく歌っていればそれを認めますので、レガートをすることが一番なんですね。とにかくまずはレガートを学ぶことが基本ですね。その上で、他の国をまわることも非常に有意義だと思います。
歌の場合は、大半のオペラはイタリア語ですので、イタリアで生活していないと、ニュアンスが出ないんです。言葉に沿って作曲家は作曲していますので。違った言語の人がオペラを歌うと、どうしても変になる。歌を勉強する方たちは一度はどうしてもイタリアで生活しないと、と思います。
-イタリアでも他の国の歌曲なども勉強されるんですよね?
葉玉 もちろん私もドイツの歌曲、フランス歌曲も教えます。こちらではフランス歌曲はとても重要視されています。でも、ドイツ歌曲ではメロディが一番大切になる。ドイツと比べますと、歌う方法が違う。ベルカントの唱法で息の上にのせる歌い方、というのがあります。呼吸、今はドイツもそれを取り入れていますが、20~30年前までは呼吸法が少し違っていました。ちょっと高い、支える場所がちょっと高くて、そのために声がちょっと硬くなるわけです。支える位置が低いほど、声が柔らかくなる。全ての共鳴腔を使いますのでね、柔らかくなるわけです。今はドイツでも、ヘルマン・プライ以降は、発声がすごく柔らかくなったと思います。
-イタリアの悪い点は何かありますか?
葉玉 イタリアの悪いところは、政治が援助をしない点ですね。私が来た当初は、オペラ座はたくさん開いていてシーズンがあったんですけれど、今は本当に少なくなりました。オーケストラの数も少なくなりました。それは本当に良くないと思います。伝統的な文化にお金をかけないのは非常に良くないですね。国にお金がなくて、政治家には賄賂の問題がすごくあります。本来ならば、文化にお金を投資すると、旅行者などによってもお金が還元されると思うのですが、目先のことにのみ気をとられているというか、長い視野に基づいたプログラムができない国民なんです。
-どこもにたりよったりのところがあると思います。古い劇場のとりこわしに対しての署名運動など、日本も同じですよ。
 葉玉 本当に残念です。
葉玉 本当に残念です。
-イタリアを留学先として選ぶ場合、特に声楽の場合は選ばれる方が多いと思うのですが、準備などで重要なことはありますか?
葉玉 第一番としては、語学を勉強してきてください。イタリアの歌を歌うためには非常に重要です。語学が分かっていないと、イタリアの歌にはならないので。
加えて、映画でもテレビでも良いのですが、ヨーロッパ人の体の使い方を良く観て、研究して来てください。日本人とは全く違いますね。日常生活でも大分違います。何とかして真似るようにできると、本当に役に立つと思います。日本人は動作が小さいのですね。体を大きく開けて。そして絶対にしゃがまないように。例えば、何か物を落としたときに、日本人はしゃがんで取りますよね、それはこちらではサマにならないので、絶対にやらないようにしてください(笑)。腰を下ろさないで。足を曲げても良いですけれど、いつも背筋をまっすぐにして、おしりをぐーっと下に下ろさないこと。日本から来た若い子を見ていると、何か書くときになど、すぐにしゃがんじゃうんですね(笑)。
それとやはり、体づくり。何かひとつ、体操、スポーツなどをして、横隔膜を強くしてこちらに来ると、ベルカント唱法が楽に自分のものになるはずです。
-そもそも、会話をするときの声の大きさなども違うイメージがありますが?
葉玉 イタリア人は、横隔膜を使ってしゃべりますね。イタリア語自身が顔の前面にあたるようになっているんです。ずっと共鳴腔を使いますので、それが大きな声という感じがするってことなんです。響かせるってことです。日本語の通常の感覚では、横隔膜を使わずに、喉だけで発音するようになってしまうんです。横隔膜を使って話すことがとても難しい。日本語はすべての音に母音がある点は良いのですが、普段は母音を使わない発声なんですね。「もー」と言うとき、「もおー」とお腹を使うようには言わないと思うんです。日本語とは子音も違いますし。
必要なことは、言葉の準備、体の準備―横隔膜を鍛えることですね。
-イタリアに来るにあたって、気持ちの面で覚悟してきたほうが良いことはありますか?
葉玉 日本人は、正直さに慣れているんです。イタリア人は正直ではありません、ウソはあたりまえ、悪いことだとは思っていないんです(笑)。その点に本当に気をつけていただかないと、国民性が違いますのでね。日本人は正直でまじめでしょう?イタリアはそうじゃないんです(笑)、反対なんです(笑)。それを頭の中に入れて来てください、それでも皆だまされています、まあ些細なことですが、平気でだますのでね(笑)。たとえば、何か小さいものをお買い物に行きますでしょう、イタリア人は、おつりを少し少なく渡してきます、お勘定を確認するとおつりが足りない、それを言うと、おー間違えてしまいました~すみません、と当たり前のように言います(笑)。気がつかなければそのままですね。だから、ちょっと疲れますね(笑)。
-なるほど(笑)。イタリアでお仕事をされていますが、働くにあたって日本人が有利な点・不利な点はありますか?
葉玉 歌手の場合は、日本人はマダムバタフライ・蝶々夫人を必ず自分のレパートリーとしてください。日本人じゃないと歌えないので、非常に有利です。必ず日本人を見ると、マダムバタフライが歌えるか?と訊かれます。プロの歌手として成功するには、体の動きをヨーロッパ人のようにできるようにならないと貧弱に見えます、動きを大きくしないといけません。カリスマ性、人の目をずっと自分に惹きつけておく力、それは生まれつきが多いので、教えようと思ってもなかなか難しいものですが、元々その力がある方は表現の方面にはお勧めですね。
-カリスマ性というのは、後天的にも培うことができるものでしょうか?
葉玉 そうですね。育った環境も影響しますね。たとえば、学生の中でもひとりだけ何か違って目がいってしまう、事務所の中のある一人の人にどうしても目がいってしまう、ついその人を見てしまう、などの例があると思うのですが、生まれつきそういったカリスマ性を備えている方がいます。生まれつきではなくても、環境の影響や、本当にひとつの勉強に集中、それだけを愛して勉強しているとカリスマ性が出てきます。突然変わっていく歌手も沢山見てきました。常に、前進しよう、良くなろう良くなろう、と思っているとカリスマ性が出ますね、自信も必要ですね、最初はなかったけれど、だんだん自信がついてくると、カリスマ性が大きくなります。その点は人種や出身は関係ないですね。
あらゆる場所で、日本人でプロとして働いている人たちの真面目さ、正確さは、素晴らしいと思います。日本人は国民性が素晴らしい(イタリア語で●)と言います、まじめで正直で、評価されますね。イタリア人も真面目で正直であることは良いことだと思っているんですよ(笑)、でもイタリア人はちょっとごまかせるチャンスがあると、すぐやっちゃうわけです(笑)。日本人のような性質は素晴らしいと思うけれども、そうはできないと(笑)。各ジャンルで働いて成功している日本人の方は非常に尊敬されているんです。イタリア人も、どの点が素晴らしいのか分かっているはずなんですね。
-日本人がステージに立つ上で、何か不利な点はありますか?
 葉玉 動きが小さいこと。そして、言葉が伝わらない限りは、どうしても舞台で歌っても伝わらず、観衆は受けてくれないんです。聴いていて言葉の意味が判らないと、表現として伝わらない。
葉玉 動きが小さいこと。そして、言葉が伝わらない限りは、どうしても舞台で歌っても伝わらず、観衆は受けてくれないんです。聴いていて言葉の意味が判らないと、表現として伝わらない。
-先生として活躍されるにあたっては、日本人であることはどのように影響していますか?
葉玉 イタリアの国立音楽院における、日本人の声楽の選任教授はわたくしだけです。声楽は言葉が土台になっているでしょう?イタリア人の歌手たちは、声楽は自分たちにしか理解できないという、自負があります。日本人が、どうしてベルカントを教えるのか?という壁は非常に大きかったです。他の人より10倍くらいは勉強しないといけなかったですね。言葉のニュアンスなど全てが分かっていないとオペラを歌えないのにという考え、それそのものは正しいと思うのですけれど、外国人がどうしてイタリア人に教えるのか、と。その壁を乗り越えるまでに非常に色々な障害がありました。大半の生徒さんはイタリア人なので、最初にわたくしと接触する際には、日本人がどうやって教えるのか?という訝しげな態度であることも多いのですが、教えていくうちに、私の中にどれだけの豊かなものがあるのか、ということが分かってくる、そうすると今度は反って、葉玉先生じゃないといやだと言ってくれるようになります。どうして?と最初は言われますね。
-でも教授しているうちに信頼を寄せられるのは素敵ですね!入学時から葉玉先生をご指名される生徒さんもいらっしゃると伺っています。
葉玉 留学してくるときから、わたくしをご指名される方もいらっしゃいますよね。大学院では教授を選ぶことができるんです。たくさんのイタリア人の生徒さんがわたくしを選択してくれます。それは本当に嬉しいです。やった!という感じです(笑)。クラスは全部で15人くらいですが、日本人の生徒さんも3人います。イタリア、ルーマニア、フィンランド、ブラジル、中国、アルジェンチンなど世界中から生徒さんが集まります。男性のほうが少ないですね、歌を歌う人口が女性のほうが多いですからね。最後におこなったサマースクールでは、12カ国から来ていました。それぞれに国家を歌ってもらって(笑)。のちに全員、勉強させて、サンタチェチリア音楽院入学させました。大変国際色豊かです。学ぶ分野としては、サンタチェチリア音楽院ではオペラと歌曲、ドイツ歌曲、フランス歌曲、それが主ですね。
-日本人として不利な点は、自ら克服されたということですね。
葉玉 そうであることを祈っています(笑)。そうはいっても、やはり今でも日本人の癖は出ますし、舞台の上ではやらないように気をつけていますがね、日常生活では日本人だと思います。体の動きなどはもう克服していると思うのですが、メンタリティが。
-まじめで正直なところをキープされているんですね(笑)、それはもう鬼に金棒ですね!先生にとって声楽・歌はどんなものでしょうか?
葉玉 そうですね、声楽を深く勉強したことによって、他の分野にも視野が拡がりました。文学、科学そういったものでも本当に分かるというか、理解できるようになると思います。ひとつのジャンルですごく深く勉強すると、他のジャンルのこともだんだん分かってくると思います。最初は音楽だけで、他のことには興味がなかったんですが、今は全て、歴史、科学など、知りたいと自然に思いますし、解剖学などは非常に勉強しました。様々なジャンルについて分かってきたようなかんじがします。
-深く、そして広くなっていくということですね。
葉玉 深くだけやっていたつもりでも、いつのまにか拡がっていて。わたしにとってはそうですね。それぞれの人によっても違うとも思いますが、声楽が全部の根源になっているということですね。
-これからの音楽的な夢などございましたら教えていただけますか?
葉玉 大きなおおきな夢があります(笑)!イタリアの各地に非常に綺麗なオペラ劇場があるのですが、かなりの数が閉まっているわけですね。1700年代、1800年代に作られた美しい劇場、大中小たくさんありますので、その中の1つを使ってオペラシーズンをやりたいんです。使わないのはもったいないです!1つの劇場を開けて、わたくしのオペラシーズンを行いたいなあ、というのがわたくしの夢です。そして、そこで毎年、新人の歌手がデビューできるようになる…大きな夢ですね。実は既にスポンサーを探したのですけれど、現在は経済危機がひどく、皆さんお金がないんです(笑)。タイミングを待っているかんじですね。
-生徒さんがデビューして、活躍して…
 葉玉 大勢の様々な評論家やマネージャー、エージェントを招待して、たくさんの歌声を聴いていただいて、その中の誰かを世界中にデビューさせたいという夢ですね。
葉玉 大勢の様々な評論家やマネージャー、エージェントを招待して、たくさんの歌声を聴いていただいて、その中の誰かを世界中にデビューさせたいという夢ですね。
わたくし自身は、舞台からは引退しています。
わたくしは、教えることと歌手であることは両立できません。歌手は自分のことだけ考えないといけないので。歌手活動と教授活動を同時におこなった時期が最初の1年か2年あるのですが、そこでできないとわかりました。
歌手として、どういうことに気をつけるか、どういう表現をするか、どういうことを観客に提示できるか、それを勉強するには24時間でも少なすぎるぐらいなのです、自分のことだけを大切にしないと成り立ちません。
でもその状態では、生徒に何かをあげるという姿勢が全く生まれない。それだとお給料を貰うためだけに教えに行っているという感じです。教師というのは、自分の経験、持っているものを全てあげるんです。ですので、わたくしは完全に止めました、歌うのを。自分の持っている経験・豊かになったものをあげる、全てをあげないと良い教師ではないわけです。
私にとっては全く両立できることではないですね。勉強は常にしています、新しい曲にあたったりすると勉強しますが、あくまでも生徒にあげるためにです。わたくし自身が舞台で歌うためではありません。
今現在、生徒さんがいっぱいついてきて下さっている。先生のように、たくさんのものを、経験をあげたい、全部をあげたい、という先生には今まで会ったことがないと言われます。全てを、自分の持っているものを全て生徒にあげたいです。
-生徒さんにとっては非常に貴重な存在ですね!色々なところで、先生と歌手と両立されている方をお見かけいたしますので、それはスタンダードなことかと思っていたのですが、先生のお話を伺って、目からウロコでした。
葉玉 わたくしにとっては、ふたつを両立できる方は不思議ですね。完全に仕事の性格が違いますのでね。
先生として、シーズンを行うことが夢ですね、大きな夢です(笑)。もし実現できたらご招待いたします!
-ありがとうございます!イタリアで教師として活躍する秘訣というのはありますか?
葉玉 語学が完全に自分のものになっていること。そうでなければ、生徒たちと交流できませんのでね。そして、ヨーロッパ人の10倍くらいの豊かさを持っていないとたちうちできません。彼らは文化の素養を自然に体の中に持っているのでね、私たちにとって、それは外から入ってきたものですからね、やはり勉強はいつもしていないとだめだと思います。勉強とは、文化を感じることを含めてですね。たくさんの展覧会に行くことや、演劇を観に行ったりすることは、大切な勉強ですね。歴史を調べたり、解剖学などを学んだりする家の中で行なう勉強もさることながら、ファッションの歴史的な違いを観に博物館に出かけることなども全て勉強の中に入っています。日常生活全てですね。
常に生徒に何を教えようかと考えています(笑)。日本の文化では、特に哲学、禅や柔道・剣道は、集中力を育てるのに大変助けになります。わたくしはイタリアに来てから始めたのですが、日本には集中力を強くするための色々な哲学、体系がありますね。
-イタリアに限らず、海外に出て勉強しようと思っている人達にアドバイスがありましたら、ぜひお願いいたします。
葉玉 第一番に留学先の語学を勉強すること、そして良い先生をみつけること。先生の選び方を間違うと成長しないんです。
-先生の選び方というのはどのようなものがありますか?
葉玉 歌の場合は、50分や1時間のワンレッスンのあと、喉が疲れていないかどうかで分かります。喉が疲れない、体の気持ちがいい、それは良い先生です。悪い先生ですと、1時間歌わせると、声が出なくなったり、喉が痛くなったり、体が疲れちゃったり。それは、テクニックの問題、発声法の問題ですね。それは人によって違うということはありません。息を吸って吐く、それが正しく行なわれていれば絶対に疲れません。それと、もうひとつ、どこに行っても、必ず国立の音楽院に入るようにしてください。競争者が沢山いる、人に会う機会がたくさんある、歌だけでなく器楽もある、音楽史、音楽学も勉強しなければならない、色々な刺激が受けられますでしょう、人間が豊かになるんです。国立の学校ですと、教授陣が非常に良く吟味されている、長いキャリアを持って教えていらっしゃる先生が大半ですのでね、やはりレベルが高いと思うんです。それと、もし留学したいという希望があるならば、なるべく早く出発して下さい。若いほど筋肉も、頭も柔らかいのでたくさんの吸収力があります。できるだけ早いほうがいいですね。どうしても大学を終えてから、という場合では、22歳ではぎりぎりですのでね、大急ぎでいらしてください。
-年齢におけるハンディはありますか?
葉玉 もし、上手になれたとして、良いマネージャーについてもらうには、若いほうが有利ということはあります。やはり、年齢によって、例えば30歳だと歌手でお金を儲けることができる時間が少ししかない、とマネージャーが判断するかもしれない、常にマネーの問題はついてきますからね(笑)。若いとそれだけ活動期間が長いですからね、マネージャーはより若いかたをみつけようとするのは現実的です。
-なるほど(笑)。ローマという街は日本人の学生は多いですか?
葉玉 ミラノのほうが多いですね、ミラノはローマの約5倍くらいいるのではないのでしょうか?ですがベルディ国立音楽院は入るのが大変難しい。ローマサンタチェチェリア音楽院も入学試験が難しいですので学生の大半は個人レッスンだけで過ごしていると思いますが、もったいないですね。
-ビザの関係からだと、個人レッスンだけでは非常に厳しいですよね。
葉玉 その通りです。やはりできれば私立の音楽院に入って、ビザを貰って…ということですね。できることならば、国立に入って簡単にビザを貰うほうがいいですが、入学試験を受けることができるレベルになるには、準備として最低5ヶ月くらいはかかります。語学の試験もありますのでね、試験の前に現地に来て、入りたい音楽院のレベルまで何とかして届くように上げて、なんとか入学にこぎつける、そのためにはやはり事前に5ヶ月は必要です。どこの国に行っても同様に大変だと思います。
-先生は留学先を決めるにあたって、イタリア・ローマだけがみえていたのですよね。
葉玉 そうですね。イタリアオペラを聴いていると気持ちが良くて、オペラを歌いたいと思っていましたので(笑)。ミラノは気候が悪くて…寒いのと湿気が多いのと、空気が悪いんです(笑)。ローマは交通量も多いのですが、海の近くなので、空気をふぁーっと、海風が綺麗にしてくれるんですね、日光もたくさん差しますし(笑)。ミラノの音楽院もすごく良いですが。
-大変楽しくお話を伺わせていただきました。本日はお忙しいところ本当にありがとうございました!