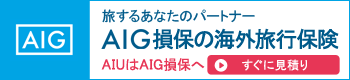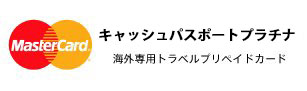ブラジル連邦共和国
![]()
|
気候 ブラジルの気候は広大な国土ゆえ、熱帯性気候、亜熱帯性気候、半砂漠型乾燥気候、高地の亜熱帯性気候、温帯性気候とさまざまに分かれる。国土の90%は熱帯地域に属するが、人口の多い都市部などはだいたい高原地帯にあり、温暖な気候ですごせる。一日の中で温度差があるので、服装には注意を。 |
|
| 現在の天気 | |
| ビザ | ビザが必要。ビザについては管轄の領事館に確認してください。 |
| パスポート | 残存有効期間が有効期限が6カ月以上であること。 |
| 大使館などの在日政府機関 | |
| ブラジル連邦共和国大使館 |
Embassy of the Federative Republic of Brazil in Japan 〒107-8633 港区北青山2丁目11-12 Tel: 03-3404‐5211 |
| 在東京ブラジル連邦共和国総領事館 |
Consulate‐General of Brazil in Tokyo 〒141-0022 品川区東五反田1丁目13-12 五反田富士ビル2階 Tel: 03-5488-5451 管轄区域: 北海道、東北、関東、山梨、新潟、長野 ビザ申請時間:月・水・金曜日:8:30 〜 12:00 受領時間(窓口1番にて):月曜日から金曜日8:30 〜 14:30 |
| 在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館 |
Consulate‐General of Brazil in Nagoya 〒460‐0002 名古屋市中区丸の内1丁目10‐29 白川第8ビル2階 Tel: 052‐222‐1077/8 管轄区域: 中部(山梨、新潟、長野を除く)、近畿、 中国、四国、九州、沖縄 |
| 在京都ブラジル連邦共和国名誉領事館 |
Honorary Consulate of Brazil in Kyoto 〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所内 Tel: 075-823-1145 |
| 在神戸ブラジル連邦共和国名誉領事館 |
Honorary Consulate of Brazil in Kobe 〒650-0021 神戸市中央区三宮1-4-9 株式会社上島コーヒーフーズ内 Tel: 078-392-2971 |
| 在鳥栖ブラジル連邦共和国名誉領事館 |
Honorary Consulate of Brazil in Tosu 〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大宮町408 久光製薬株式会社内 Tel: 0942-81-1501 |
| 在那覇ブラジル連邦共和国名誉領事館 |
Honorary Consulate of Brazil in Naha 〒900-0015 沖縄県那覇市泉崎1-15-5山里ビル1階 沖縄インターオーシャンサービス内 Tel: 098-867-3304 |
| ブラジル観光局 | ホームページによる案内(英語) |
| 現地日本大使館 | |
| 在ブラジル大使館 |
Brasil Embaixada do Japao Avenida das Nacoes, Lote 39, 70425, Brasilia, D. Federal, Brasil (Caixa Postal 07-391) Tel: (55-61) 442-4200 Fax: (55-61) 443-9685, 242-0738 |
| 在クリチバ総領事館 |
Curitiba Consulado Geral do Japao Rua Marechal Deodoro, 630 Edificio CCI, 18 andar, 80010-912 Curitiba Parana, Brasil (Caixa Postal 2028) Tel: (55-41) 3322-4919 Fax: (55-41) 3222-0499 |
| 在サンパウロ総領事館 |
Sao Paulo Consulado Geral do Japao Avenida Paulista 854, 3-andar, CEP 01310-913, Sao Paulo, Brasil Tel: (55-11) 3254-0100 Fax: (55-11) 3254-0110 |
| 在べレン総領事館 |
Belem Consulado Geral do Japao Avenida Magalhaes Barata, 651, Edificio Belem Office Center, 7 andar 66063-240, Belem, Para, Brasil (Caixa Postal 912) Tel: (55-91) 3249-3344 Fax: (55-91) 3249-3655 |
| 在ポルトアレグレ総領事館 |
Porto Alegre Consulado Geral do Japao Av. Joao Obino, 467 Petropolis, 90470-150, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Brasil (Caixa Postal 1022) Tel: (55-51) 3334-1299, 3334-1135 Fax: (55-51) 3334-1742 |
| 在マナウス総領事館 |
Manaus Consulado Geral do Japao Rua Fortaleza, 416-Bairro Adrianopolis, CEP:F69057-080, Manaus, Amazonas, Brasil (Caixa Postal 4188) Tel: (55-92) 232-2000 Fax: (55-92) 232-6073 |
| 在リオデジャネイロ総領事館 |
Rio de Janeiro Consulado Geral do Japao Praia do Flamengo, 200-10 andar, 22209-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Tel: (55-21) 3461-9595 Fax: (55-21) 3235-2241 |
| 在レシフェ総領事館 |
Recife Consulado Geral do Japao Rua Padre Carapuceiro, 733, 14 andar, Edf., Empresarial Center I, Boa Viagem, 51020-280, Recife Pernambuco, Brasil (Caixa Postal 502) Tel: (55-81) 3465-9115 Fax: (55-81) 3465-9140 |
石橋幸子さん/ヴァイオリン/チュ-リヒ・ト-ンハレ管弦楽団/スイス・チューリッヒ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回スイス・チュ-リヒ・ト-ンハレ管弦楽団でご活躍中の石橋幸子(いしばしゆきこ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年8月)
ー石橋幸子さんプロフィールー

大阪府出身。桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコ-ス首席卒業。1997年リュ-ベック音楽大学に留学し、ザハ-ル・ブ口ン氏に師事。1999年よりチュ-リヒ音楽大学大学院にて ジョルジュ・パウク氏に師事。仙台国際音楽コンクール、クライスラ−国際コンクール入賞他、ドットバイラー国際コンクール、モーツァルト音楽コンクール、キバニス国際室内楽コンクールで共に第1位受賞。青山財団より「青山音楽賞大賞」受賞。現在、ディビット・ジンマン率いるスイス・チュ-リヒ・ト-ンハレ管弦楽団に在籍し、08/09シーズンは第2コンサートマスターとして活躍中。
-まずは、簡単なご経歴を教えてください。
石橋 5歳からバイオリンを始め、桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋学園大学ソリストディプロマコースを卒業しました。その後、リューベック音楽大学に留学したのち、チューリヒ音楽大学院を卒業しました。現在は、スイスのチューリヒ・トーンハレ管弦楽団に在籍し、ヨーロッパでの活動を中心としながら、日本国内でも、定期的に演奏しています。
-バイオリンを始めたきっかけは?
石橋 母が声楽家でしたので、子供達にも音楽を学ばせたい、という気持ちがあったようです。私には1歳年上の、現在はビオラ奏者として活躍している姉がおりまして(石橋直子氏)、私が物心つく頃には、すでに彼女がバイオリンを弾いていました。それを見て、私もやりたいと言って始めました。
-ご自分で、バイオリンを選ばれたんですか?
石橋 そうらしいです。姉が練習している姿を見て、自分も弾きたいと言ったようですが、全く覚えていません(笑)。小さい頃って、よく子供達は何でも真似から入りますよね。私もそこから始まったのだと思います。

-では、ご家族の影響が大きかったのですね。小さい頃から、クラシックに親しまれていたんですか?
石橋 そうですね。母はオペラ歌手として沢山のコンサートに出演していましたし、父親もクラシックが大好きで、自分でレコードを聴きながら指揮をしていました。父の車の中では、いつもビバルディの「四季」の音楽が流れていて、私たち姉妹はそのような環境から、すんなりとクラシック音楽を受け入れていましたね。
-高校から、桐朋の音楽科に進まれたということですが、ご自身で進路は決められたのですか?
石橋 はい。私は小学6年生から中学2年生の頃まで、東京と大阪を往復して、東京芸術大学の(故)田中千香士先生に月1回レッスンを受けていたんです。日曜日は始発で東京へ、という生活をしていたので、大阪から離れることにも抵抗がなく、自分が行きたい学校へ行こうと思っていました。
-では、この頃からすでに、将来は音楽家の道に進もうと思われていたのですか?
石橋 目標を持ち出したのは、高校に入ってからです。周りのレベルがすごく高くて、自分もこの中の一人なんだと自覚したとき、このままではいけないと痛感しました。視聴覚室にこもっては、いろいろな方の演奏を聴いて参考にしたり、興味のあるコンサートには出来るだけ行きましたし、自分の練習を怠ることは出来ないので、朝5時の始発に乗ってよく通学していました。今思えば、高校生の時が一番練習をしてましたね。すべてを吸収したいという気持ちで、努力を惜しまずに取り組んでいましたから。・・・若さですね(笑)。
-その頃は、一日にどのくらい練習されてたんですか?
石橋 週末は、8時間練習をしてました。平日は、だいたい5時間くらいだったでしょうか。
-8時間! 周りの学生さんも同じくらい練習されていたのですか?
石橋 具体的には覚えてませんが、みんな頑張ってましたね。
-そのまま大学に進まれて、卒業後に、リューベック音楽大学に留学されましたね?
石橋 はい。桐朋で私が専攻したソリストディプロマコースというのは、特殊なコースなのです。バイオリンの実技試験で、決められた一定の得点以上を何回も持続できれば、最短3年で卒業できるというコースなのです。ソリストを育成する場所でしたから、学科はある程度免除されましたが、とにかくバイオリンの演奏に秀でていないと卒業できない、という学部でして。幸運にも私の場合も、3年で卒業できて、その年に21歳でドイツに留学しました。
-素晴らしいですね!では、ずっと良い成績をキープされてたということですね?
石橋 決して簡単ではなかったんですよ。高校時代からの6年間、良い成績というよりも、思うような演奏が出来ずに、たくさん挫折もしました。大事な場面で緊張しすぎたり、自分の力が出せなくなってしまった時期もありました。だから、とにかくたくさん練習して、常に自分の弱い部分を克服出来る様、格闘していくしかなかったんです。ですから、表面的には、高校もソリストディプロマコースも首席で卒業しましたが、そこに辿り着くまでは決して楽な道ではなかったんです。
-厳しい努力のたまものだったのですね。
石橋 そうですね。実際先生から、「キミは、精神的に弱い部分があるから、少し修行をするとか、座禅を組めば!」と言われたこともあるんですよ(笑)。その言葉で、これではいけない、何とかせねば!と思いましたね。それ以来、練習以外にも書物を沢山読んだり、周りの友人や先生からも助言をいただいた、とにかくトンネルの中を必死でさまよいながら、光を探していた感じです。ですので、当時を振り返れば、全く順風満帆ではなかったんですよ(笑)
-練習を重ねたり、書物を読んだりすることで、緊張や精神面の弱さを克服できたということですか?
石橋 はい、少しは!(笑) でも、今だに格闘してますよ!一つの事がクリア−出来たら、また新たな壁が見つかるので‥(笑) それに、コンサートでは毎回新しい課題が出てきます。ですので自分をどの様な状況に持っていくと、一番ベストな演奏が出来るかというのを、毎回のコンサートで見つけ出している感じです。経験を積みながら、少しずつ成長していければ嬉しいですね。
-さて、留学に関してですが、具体的に留学を意識し始めたのは、いつごろですか?
石橋 ソリストディプロマに入って2年目のとき、ロシア人のブロン先生に出会いました。当時先生は、たびたび来日されていて、私も何度かレッスンを受けていました。そしてそのレッスン内容がとても素晴らしかったので、1年以上かけて、「卒業後は、ぜひ先生のもとで勉強したい」という強い気持ちを、お伝えし続けたんです。そして、先生が受け入れて下さることになりまして、出会って2年後に留学という形になりました。
-留学するに当たっては、先生としっかり意思疎通をとっておくことも大切なんですね。
石橋 ええ。私のところに、留学の質問をしに来る方もいますが、私が言えることは、習いたい先生がいるのであれば、その先生ときちんとコンタクトを取っておくべきだ、ということです。その先生のところで学びたい、という自分の意思をしっかり伝え、先生にも、育てたいという気持ちがあるかどうか、きちんと確認をとっておくべきだということです。そして、その時点で、クラスでの順番待ちの人がいる場合もありますから、空いている枠があるかどうかも確認しておかなければいけません。渡航したは良いけれど、習いたい先生に習えなかったり、やりたいことができずに、宙ぶらりんになってしまう人も多いですから。
-それは、非常に重要なことなんですね。
石橋 はい。と言いつつ、私の場合、ブロン先生のところには数ヶ月しか勉強出来なかったんです。実は、肘を壊してしまって・・・。腱鞘炎にかかり、全く弾けない状態になり、休学することを余儀なくされました。そして、日本に戻って数ヶ月治療に専念しました。
-そうだったんですか。弾けないという状況は、お辛かったでしょうね・・・。
石橋 そうですね。それまで、挫折はたくさん経験しましたが、あの状態まで弾けなくなったことはなかったので、本当に厳しくて大きな試練でした。

-それでも、海外で勉強することを諦めずに、再挑戦されたんですよね。
石橋 やっぱり、音楽の基本は、ヨーロッパだと思っています。これは、ヨーロッパに住んで約10年経った今でもそう感じます。日本にいて、本や資料で勉強したり、口で説明を受けても、やはり肌で触れてみないと分からないことが多々あると思うんです。たとえば、バロック音楽にしても「なぜ教会で、なぜあの奏法で弾かなければいけなかったか」というのが、その教会に立って空間を感じるだけで理解できることもありますから。ですので、ヨーロッパに身を置いて、自分自身で体感したいと思ったんです。実際、休学してから1年間は、先生を探しにヨーロッパを周り、そして肌で音楽を吸収することに専念しました。オーケストラのコンサートを聴きに行ったり、バイオリンに限らず、いろいろなレッスンも聴講したり、音楽家が住んでた場所を訪ねる旅もしました。
-強いお気持ちがあったのですね。では、次のパウク先生とは、どのように出会われたのですか?
石橋 実はパウク先生との出会いは16歳の時でした。パウク先生が、桐朋でのマスタークラスを聴きに来られた時、「もし海外で勉強したいのであれば、是非僕のところに来なさい!」と声をかけて下さっていたんです。しかし、すぐに先生のところへ飛び込んだわけではありません。まず、先生の講習会に参加して、「本当にこの先生に習いたい!」という確信をもってから、パウク先生に私を生徒にしていただけるかお尋ねをしました。腱鞘炎の事も含めて、今までの事情や自分の強い気持ちをお伝えして、先生のお話やレッスン内容の素晴らしいさを体験した上で、この先生となら絶対信頼関係を築けると思えた時点で、チューリッヒに移る事を決意しました。
-やはり、留学する上で、良い先生との出会いというのは、本当に大事なんですね。
石橋 その通りです!留学には、良い先生を探すことと、強い意志と目標を持つことが、とても大事なんです。これがなければ、海外で生きていくことは難しいですよ。実際、挫折して帰国する人も、たくさん見てきました。事前に先生と連絡を取り合って、きちんと受け入れ先を見つけることと、ある程度の語学は身につけてから渡航する、ということも大切です。また、私の経験からいっても、奨学金制度があるのであれば、出来るだけチャレンジしたほうが良いと思います。
-ちなみに、ドイツ語はいつごろから勉強をされていたのですか?
石橋 留学の1年前から勉強を始めましたが、結局まったく通じませんでした。それで、後々かなり苦労しましたね。最初の頃は英語でコミュニケーションを取っていたんですが、やはり、だんだんドイツ語を話す必要性が出てきました。そこで、ドイツ語の集中講義を受けたのですが、コンクール前など、とにかく練習したい時期に、講義に時間を取られたりして、非常に辛かったです。留学1年前に始めても遅かったくらいですから、この先、留学を考えているのであれば、語学の勉強を始めるのは、早いに越したことはありません。
-リューベックやチューリッヒに入学されたときは、語学力を問われたりはしなかったのですか
石橋 リューベックのときは、勉強をしたという証明書が必要でしたね。チューリッヒは、ドイツで勉強していたという経歴があったからか、免除されました。
-やはり、言葉は出来るに越したことはないですね。
石橋 本当にそうです。10年経った今でも、まだまだ苦労していますので!早ければ早いほうがいいです。そして、英語も少しは理解出来ると役立ちますよ。

-では、チューリッヒに行かれてみて、ドイツとスイスで、音楽の勉強の仕方に違いはありましたか?
石橋 国による違いというより、習った先生の違いでもあるんですが・・・。ブロン先生からは、ピエロ的な要素を学びました。誰もが想像のつかないような、ニュアンスの取り方や、間の取り方などです。パウク先生からは、音楽性の導き方や演奏技法、曲の様式観を学びました。どのようにしたら、自分の味や音楽性を活かして表現ができるのか、ということも多く学びました。それぞれの先生から、違った部分を学べて、本当に幸せでしたね。
-素晴らしい先生方に出会われたんですね。
石橋 はい。留学して、まず大切なのは「音楽」だ、ということを学びました。流れを感じ、自分の心からあふれ出てくる歌を信じて、そのまま弾けばいいということです。テクニック的なことは、あとで補っていけるものですから、小さいことを気にせず、まず弾いてみる。パウク先生の生徒は、みんな違ったカラーを持っていて、私も私自身の個性をのばしていただきました。そして自分の味を活かしつつ、のびのびと演奏ができるようになりました。
-どれくらいの期間、パウク先生に師事されたのですか?
石橋 1999年から2003年までです。
-そのあとに、管弦楽団に入団されたんですね。これはどういったきっかけですか?
石橋 やはり、最終過程を卒業すると、日本に完全帰国するか、現地で働く場所を探すか、という選択をせまられます。私はまだまだヨーロッパで学びたかったので、もしオーケストラに入れば、また新たな発見があるのではないかと思いまして・・・・。最初は、とりあえず試用期間の1年間だけやってみよう、と思って入団しました。でもそこで素晴らしい方に出会ってしまい、スイスに残る事を決意しました(笑)
-採用試験は、募集広告が出ていたんですか?
石橋 はい。トーンハレは毎回応募人数が多いのですが、その時も200人くらい応募があったようです。そこからまず書類選考で人数を絞り、私の受けた時は1次試験に37人参加し、2次試験で5人になり、3次試験では3人だけが残りました。最終試験では、オーケストラの曲以外に初見もありました。その結果、運良く受かることが出来ました。
-審査員は何人いらっしゃるんですか?
石橋 オーケストラメンバーは約100人いるんですけど、その中のだいたい30~40人は審査に入ってます。1次試験は、誰が審査しているのか見えない形式なのですが、2次審査からは、ずらりとならんだ審査員の前で弾くことになります。かなり緊張する場所でしたね(笑)
-30人もいたら緊張しますよね。
石橋 はい。しかも、全員しかめっ面で、ジーっと見てますからね(笑)
-日本人が認められて、採用されると言うのは難しいと思うんですが、いかがでしょう?
石橋 たとえば日本人とドイツ人が同等の力を持っていたら、絶対ドイツ人が採用されると思うんです。ですのでそこで勝つには、個性が必要なのだと思います。私の場合は、自分の良さを伝える表現方法の一つとして「歌心」が自分にはあると思っています。ですのでいつも演奏する時、「皆さん、今日はこの場所で私の演奏を聴いてくれてどうもありがとう!」と、常に感謝しながら演奏しているんです。ちょっとでも、自分の良さというか、自分自身の個性を信じた演奏し、それが相手に伝われば、どんぐりの背比べの中でも、ピカッと光れる思います。
-技術以外で何かコツはありますか?たとえばコミュニケーション能力や語学力とか。
石橋 入団する際は、全く必要ありません。
-完全に実技の力だけを評価されるということなんですね。
石橋 はい。でも入団後は、1年もしくは2年、試用期間があるのですが、この間にドイツ語が出来ない人には、ドイツ語学校に通うように指示をいただきます。しかし最近はどこのオーケストラもインターナショナルになっていて、最低限の会話が出来れば、それほど厳しくその国の言葉を要求されることはなくなってきたと思います。

-試用期間後、続けられない方もいるわけですよね?その際の審査の基準は?
石橋 まずは実技が中心ですから、その1年間は常にベストを尽くし、よく準備をして本番に備える、というのが最低ラインです。あとは、人間性も必要になってくるのでしょうね。私がいつも心がけているのは、どこの国のどんな国民性をした方でも、誠意を持って接しようということです。たとえば、ドイツやスイスでは、自己主張のハッキリしている方が多いので、そういう場では、私も言いたいことをきちんと主張します。日本人らしく、ニコニコと大人しく話しを聞いているだけだと、「何を考えているかわからない」と言われて終わりです。言葉が流暢でなくても、きちんと誠意を持って対応することを心がけるようにすれば、自分の人間性を理解してもらえるのではないか、と思います。
-ところで石橋さんは、音楽的な問題にぶつかったときの解決は、ご自身で解決されますか?それとも誰かにアドバイスを求めますか?
石橋 まずは自分で解決法を見つけます。それでも何も見えてこなかったら、周りの人に聞きます。学生時代は、自分で考えた上で、「先生だったら、どのような解釈をされますか?」っと質問していました。そして、違った方向から光が見えてくる時もありました。
-新しい曲に取りかかる時もそうですか?
実は大学生の頃、桐朋の大先輩の指揮者の小澤征爾先生にお会いしたときにお話を伺ったんです。「先生は新しい曲を始めるとき、どうやって勉強されるんですか」って。先生がおっしゃるには、「まず自分でスコアを読んで勉強する」ということでした。「他の方のCDとかは聴いたりしないんですか?」と伺いましたら、「もちろん、聴かない。自分でまず勉強しておかないと、周りの音楽から影響されてしまって、他人の音楽になってしまうから。」と教えていただいたんです。これを聴いた瞬間、目からウロコが落ちました。その頃の私は、まずいろんな方のCDを聴くことから始めていたんです。でも、そのお話を伺ってからは、まず自分で楽譜を読んで、考えるようになりました。もちろん、3倍も4倍も時間はかかります。道が開けないようなときでも、何ヶ月も時間をかけて、迷いながらも自力で仕上げてみるんです。その後で、先生に意見を求めたり、他の演奏を聴いたりと、アドバイス要素を入れるんです。そうすると、根の部分は自分の音楽で固められているわけですから、ぶれることはありません。
-なるほど。先入観をもってしまうと、自分の音楽が作りにくくなるでしょうからね。では、海外留学をして、オーケストラに入りたいという方にアドバイスをいただけますか。
石橋 常に自分がどうありたいか、強い志を持って楽器に触れることですね。努力をし続ける強い精神力と、覚悟を持って始めてください。

-やはり信念を持たないといけないですよね。
石橋 はい。強い信念を持っていれば、一度は海外に住んでみるのも悪くありませんから!しかし永久に住むとなると色々と大変ですけども(笑)。未だに私の場合、日本に着いた瞬間、ほっとして心からリラックスしているのが分かるんです。ヨーロッパにもう10年も住み、既に慣れたとはいえ、やはり異国は異国なんですね。ずっとこちらでは私達は外国人なんです。ですので本人の希望があるのであれば、ヨーロッパ留学は本当にお勧めしますが、しっかりと心の準備をしてきてほしいです。
-石橋さんご自身は、信念が揺らいだことはありましたか?また、そのときはどうやって克服しましたか?
石橋 先ほどお話したように、一度腕を壊して帰国したのですが、その時はそのショックとホームシックもあり、一度自分を守ってあげられる場所に体を戻すことで、「怪我しちゃったけど、でも良く頑張ったね」と言い聞かせ、精神的にも落ち着け、肉体的にも解放できる環境を自分で作りました。その上で、改めてしっかりと自分の気持ちに向き合いました。そして、やはりもう一度勉強したいと強く思いましたので、再びヨーロッパに戻ったんです。でも、実際は留学というのは学びに行くことですから、先生との関係がとても大事です。先生との信頼関係がしっかりできていれば、相談も出来るし、アドバイスもいただける。乗り越えられる部分は大きいですよ。
-それでは、石橋さんにとってクラシック音楽とは、何でしょうか?
石橋 ええっ!それは難しい(笑)。 ・・・結局、やっぱり「私自身」なのかな。楽器を使って「心」を伝わる、自分からのメッセージなのでしょうか。
-これからも、スイスと日本を拠点に活動されていくかと思いますが、音楽家として今後の夢はありますか?

石橋 これまでの音楽人生で、沢山の事を学び、体験でき、とても幸せでした。それを今度は、私が色々な方々に伝えいく番だと思っています。
バイオリンを通じて今後も、感謝の気持ちや喜び、そして悲しみ、いろいろな表情の「心からの音楽」を皆さまにお伝えていきたいです。
-これから留学を考えているみなさんにとって、すごく貴重なお話でした。今日はお忙しいところ、本当にありがとうございました!
-------------------------------
石橋幸子さんの今後の活動は下記のホームページでご覧になれます。
http://www.yukikoishibashi.com
コンサート情報
2013年10月7日 京都 カフェ モンタージュ 20時開演 (問い合わせ先 075-744-1070)
弦楽三重奏コンサート
ドホナーニ 弦楽三重奏
ヘンデル(ヘルバーソン編曲)パッサカリア (vl&va)
ベートーベン 弦楽三重奏 0p、9-1
石橋幸子 ヴァイオリン
石橋直子 ビオラ
五味敬子 チェロ
2013年10月10日 名古屋 花山音楽プラザ 1F ロビーコンサート 18時30分開演 入場無料
石橋姉妹による弦楽三重奏コンサート
シューベルト 弦楽三重奏 D.471
ヘンデル(ヘルバーソン編曲)パッサカリア (vl&va)
ドホナーニ 弦楽三重奏
モーツァルト ビオラとチェロの為のソナタ K292
ベートーベン 弦楽三重奏 0p、9-1
石橋幸子 ヴァイオリン
石橋直子 ビオラ
五味敬子 チェロ
2013年10月13日 名古屋 電気文化ホール 14時開演 入場料3000円
(問い合わせ先 Jプロジェクト 090-5439-8821)
石橋直子トリオコンサート
シューベルト 弦楽三重奏 D.471
ヘンデル(ヘルバーソン編曲)パッサカリア (vl&va)
ドホナーニ 弦楽三重奏
モーツァルト ビオラとチェロの為のソナタ K292
ベートーベン 弦楽三重奏 0p、9-1
石橋幸子 ヴァイオリン
石橋直子 ビオラ
五味敬子 チェロ
2013年10月14日 豊中 フェリーチェホール 14時開演
石橋姉妹による弦楽三重奏コンサート
問い合わせ先 090-9888-1017
シューベルト 弦楽三重奏 D.471
ヘンデル(ヘルバーソン編曲)パッサカリア (vl&va)
ドホナーニ 弦楽三重奏
モーツァルト ビオラとチェロの為のソナタ K292
ベートーベン 弦楽三重奏 0p、9-1
石橋幸子 ヴァイオリン
石橋直子 ビオラ
五味敬子 チェロ
玄玲奈さん/ダンサー・振付家・講師/オーストリア・グラーツなど
ダンス留学アンドビジョン【ダンス新着情報 vol.10. 2015-12-08 07:00:00】
≪お得な情報をお届け!≫ボストン特集&国内情報♪AndVision音楽留学メールマガジン
Y.M.さん/ウィーン冬期音楽講習会
★2/19・ 18:00-【☆ムジカルタ春期音楽講習会☆】現地講習会担当者がプログラムについて解説致します!★
ムジカルタ春期音楽講習会
Information Session
~ムジカルタ春期音楽講習会オンライン説明会~
参加費無料・完全予約制・オンラインでの参加も可能です
ゲストスピーカー:講習会ディレクター Florence Labさん
日時:2月19日(水)18:00-18:30
場所:≪アンドビジョン・東京オフィス≫
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-8 神田駿河台ビル2階
JR御茶ノ水駅御茶ノ水口から徒歩7分、東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩5分程度
♪参加ご希望の方は、こちらからオンライン予約フォームを送信して下さい。
※説明会予約を選択→その他ご要望等に“ムジカルタ春期音楽講習会”とご記入下さい。
お電話・FAX・メールでのご予約も承っております♪
電話:03-5577-4500 FAX:03-4496-4903 メール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
ペルー共和国
| 気候 ペルーの気候は、南回帰線の内側にあるため、熱帯圏となるが、地域によってさまざまな地理的影響を受け、異なった気候となっている。乾燥した海岸砂漠から氷河の迫り出した雪山、熱帯ジャングルのアマゾンまで存在する国。熱帯雨林、山岳地域、海岸地帯それぞれの特徴があるので、自分の滞在する土地の気候は事前に調べておこう。 |
|
| 現在の天気 | |
| ビザ | 観光目的で90日以内なら不要。ビザについては大使館にご確認ください。 |
| パスポート | 残存有効期間が帰国時まであること。 |
| 現地日本大使館 | |
| 在ペルー大使館 | Peru Embajada del Japon Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima, Peru (Apartado No. 3708) Tel: (51-1) 218-1130 Fax: (51-1) 463-0302 |
| 在リマ総領事館 | Lima Consulado General del Jap熔 事務所は、在ペルー大使館と同じ。 |
布施菜実子さん/ヴァイオリン/ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団/ドイツ・ミュンヘン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回ドイツ・ミュンヘンフィルでご活躍中の布施菜実子(ふせなみこ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年8月)
ー布施菜実子さんプロフィールー

東京生まれ。4歳よりヴァイオリンを始める。桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学を1998年に卒業。在学中には仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演したほか、東京文化会館小ホールにて新人音楽家デビューコンサートなどに出演。またカール・ライスター弾き振りのオーケストラにてコンミスを務めるなど多数の学内オーケストラにてコンミス、首席を経験。卒業後すぐに渡独。ミュンヘン音楽大学ではマイスタークラスに入学し、2000年にマイスタークラスディプロムを取得、卒業。Münchener Kammerorchesterの契約団員を経て、2000年のマイスタークラス卒業と同時にミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団に入団。現在オーケストラ以外に、室内楽などを中心に演奏活動を行っている。これまでにヴァイオリンを故鈴木共子、朱貴珠、クルト・グントナーの各氏に、室内楽を店村眞積、堀了介、村上弦一郎、バルトーク・カルテット、アルバンベルグ・カルテット、アマデウス・カルテットなどに師事。
-では、最初に、布施さんのご経歴を教えてください。
布施 4歳からバイオリンを始め、6歳で桐朋学園大学付属「子どものための音楽教室」に通い始めました。桐朋学園女子高校音楽科を経て、桐朋学園大学を卒業し、ミュンヘン音楽大学マイスタークラス(大学院)に2年間在籍しました。卒業後、すぐにミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団に入団し、現在に至っています。
-素晴らしいご経歴ですね!
布施 いえいえ。私はコンクールなどはほとんど受けていませんので、コンクール歴はないんですよ。
-それは意外です。では、音楽に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
布施 実は、それほど、音楽やクラシックに興味はなかったんです。バイオリンも、自分からやりたいと言って始めたわけではありませんでした。母親が、自分がバイオリンをやりたかったから、ということで、私に始めさせたんです。桐朋学園の高校に入るまでは、他のお友だちと同じように、普通にポップスなども聴いていました。その頃は、プロの音楽家になるなんて、全然考えてもいませんでしたね。
-それでは、クラシックに興味を持ち始めたのは、高校に入学してからなんですか?
布施 そうですね。音楽高校だったので、素晴らしい経歴を持つ子たちがたくさんいたんです。コンクールで全国一位とか、地方から出てきている人もいましたし。そんな中にいたら、かなり刺激を受けまして。やっと目覚めたというか、初めて、自分の意思で練習するようになったんです。
-大きな刺激だったのでしょうね。
布施 はい。そして、高校三年生の頃、ザルツブルグ夏期講習会・モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミーに参加したんです。そこで初めて、ヨーロッパの音楽を聴いたんです。先生だけじゃなく、参加している講習生の演奏も聴いているうちに、「ヨーロッパの音楽って、クラシックって素晴らしい!」って、感動したんです。その頃からですね、留学を考え始めたのは。

-ザルツブルクの講習会が、留学するひとつのきっかけになったのですか?
布施 はい。きっかけのひとつではありました。でも、師事していた先生に相談しましたら、「高校を卒業してすぐというのは、少し早いのではないか。」とアドバイスをいただきまして、大学で勉強してから、ということにしました。実は、大学2、3年の頃には、大学の先生から、「そろそろ留学してもいい時期ではないか。」と言わてはいたんです。でも、休学するよりは、やはり卒業してから留学したいと思いまして・・・。そして、4年生になってから、これがもうひとつの大きなきっかけになるのですが、スイスのレンクで行われた講習会に参加したんです。
-ザルツブルグだけでなく、スイスでも講習会に参加されたんですね。
布施 はい。そして、そこで、すごく素晴らしい先生に出会ったんです。ミュンヘンで教えてらっしゃる、とても有名な先生でした。「どうしても、この先生に習いたい!」と思った私は、講習会が終わってから、先生に直接、先生のもとで勉強させてほしいと話しに行ったんです。しかし、先生のクラスは、すでに入る順番を待っている方が大勢いたので、来年入るのは無理、とのお返事でした。でも、私は、そこで諦めなかったんです(笑)。今となっては、無謀だと思うのですが、日本に帰ってからも、先生に何度かご連絡したんです。もちろんお返事をいただくことはありませんでしたが・・・。そういう状況なのに、単純に、行ったらなんとかなるだろうと思ってたんですね。大学を卒業してすぐ、4月にはミュンヘンに渡ったんです。
-すごい勇気と行動力ですね!
布施 無謀ですよ(笑)。そして、渡航してからすぐ、先生にお電話したのですが、やはり、「今年は、定員が一杯だから、突然来られても無理だ。」と言われました。当たり前ですよね(笑)。ただ、一度聴いてもらったら、「マイスターのレベルには達しているから、試験には合格するだろう」と、ミュンヘン音大のマイスターコース受験を勧められ、大学の先生も紹介していただいたんです。そして、マイスターコースに合格しまして、その先生のクラスに入ることになったんですが、いろいろな事情がありまして、さらに別の先生に教えていただくことになったんです。正直、その先生のことは、全く知らなかったのですが、レッスンに行ってみたら、この方が、素晴らしい先生で・・・! 私が今いるミュンヘンフィルで、以前、コンサートマスターをやられてた方でしたので、オーケストラスタディもよく見てもらいました。人間的にも素晴らしい方で、今思えば、偶然に偶然が重なって、結果的に私にとって、とてもラッキーな出会いとなりました。
-そういう出会いって、本当、分からないものですね。
布施 ええ、あれだけ講習会で出会った先生に習いたい!って思っていたのに・・・。結果的には、すべて無駄ではなかったですね。
-元をたどれば、講習会だったわけですからね。
布施 はい。やっぱり夏期講習っていうのは、大きなきっかけになりますから、留学したいと考えている人であれば、ぜひ、積極的に参加してほしいですね。

-では、留学に関することをお伺いしますが、クラシックを勉強するに当たって、ドイツの良い点、悪い点があったら教えてください。
布施 ドイツに限らず、ヨーロッパの街では、大小関わらず、毎日どこかでコンサートをやってます。安い値段で、気軽に良い音楽を聴くことができるんです。それがすごく良いことですね。日本だと、何ヶ月も前から予約して、頑張って予定を空けて行くって感じですけど。そんな堅苦しいイメージはなくて、「買い物のついでに行ってみよう」っていう感じで、それこそ、ジーンズを穿いてても行けてしまうんです。学生時代には、学割を使って、たくさんオペラを見ました。今思えば、それが私にとって、大きな収穫でしたね。
-日本だと、そうは簡単に行けませんものね。
布施 大ごとになりますもんね。それに、こちらでは、コンサートに行かなくても、あちこちに教会がありますから、ちょっとのぞいてみたり、街の雰囲気を味わっているだけでも、大きな価値があると思います。
-そういうことも、音楽に影響するでしょうからね。
布施 はい。音楽は、やはり人間の内面を映し出すものですから。たとえば、日本の音大生のように、部屋にこもって練習ばかりしているよりは、街に出て一息入れるのも必要だと思います。外に出て、ドイツ人の生活を直接肌で感じたり、何か感動したりすることによって、それが音楽に生きてくるのじゃないのかな、と思います。
-では、何かドイツの悪い点はありますか?
布施 あまり感じたことはないですね。自分から来たくて来たので。自分にとっては、すべてが新しくて、プラスになることばかりでした。いつもポジティブに物事を考えていないと、外国で暮らしてるというだけで、気が滅入ったりすることもあるでしょうし。
-そうですね。ホームシックで、マイナス思考になったりすることもありますからね。
布施 単純なことで言うと、食事なども全然違いますから、そこでホームシックになってしまう方も多いですよね。たぶん、自分の気持ちの持ちようではあると思うんですけど。自分が、そこで何をしたいのかっていう目的があって、楽しみになる部分が多ければ、ホームシックになっても頑張れるのではないかと思うんですけど。
-まさに、その通りですね。さて、ドイツ留学するにあたって、一番重要なことは何だと思いますか?
布施 もちろん、語学は大切だとは思います。留学前に、少なくとも簡単な会話程度はできたほうがいいと思います。ただ、渡航してからでも、コミュニケーションを通して、語学は上達しますから、一番大事なことだとは思わないんです。それ以上に、現地に知り合いがいれば、事前に、なるべく多く情報をもらうことが大事だと思います。特にドイツは、ビザを取得したり、事務的なことがとても大変です。最近は、インターネットでたくさん情報は得られると思うのですが、学校や街によって、少しずつ事情が異なることも多いですからね。
-留学前の情報収集がキーなのですね。
布施 はい。私は、来たばかりの頃、練習するより、事務的なことをする時間のほうが多かったんですよ。学校の入学手続きもそうですし、滞在ビザも、たくさん書類上の手続きを踏まなければいけなくて。だから、これらの事務手続きや書類作りは、日本で準備しておいたほうが絶対にいいです。こっちに来てから、「あの書類が一つ足りない。親に送ってもらわなくては。」などというのは、本当に時間の無駄でしたから。

-では、今、お仕事をされていて、日本人で有利な点、不利な点はありますか?
布施 最近では、日本人だから、というような人種差別的なことは、ほとんどないと思います。ミュンヘンは保守的な街って言われてますけど・・・。オーケストラも、外国人はなるべく入れたくないらしいって話も聞いていたんですけどね。でも、いざ入ってみたら、とてもインターナショナルなオーケストラでしたから、あまり人種的なことは気にしなくていいと思います。ただ、ドイツで、オーディションを受けるときには、招待状が必要なんですよ。ドイツの音大で勉強しました、というだけでは、なかなか招待状は来ません。そういう意味では、受けようと思ったときが、アジア人全般、たぶん不利だとは思います。ただ、オーケストラアカデミーやプラクティカント(研修生)を受験する場合には、招待状は必要ありません。そういうところで経験を積めば、ドイツのオーケストラで弾いていたという経歴を示すことが出来ます。私の考えではありますが、相手にそれ印象付けると、招待状をもらえる確率は高くなると思うんです。そこまで来れば、人種は関係ないです。
-布施さんは、招待状をもらったんですか?
布施 私の場合も、学校と並行して、ミュンヘンフィルの契約団員として、弾かせてもらっていたんです。そのオーディションは、誰でも受けられましたから。そこで採用されて、契約団員として活動を始めてから2ヵ月後に、正式オーディションを受けられたんです。最近は、日本人の方もオーケストラアカデミーやプラクティカントで、たくさん見かけるようになりましたから、皆さんもそうやって始められているのでしょうね。
-少しでも、ドイツで経験を積んでおくということが大切なんですね。
布施 はい。学校と並行してできると思うので、卒業してからと考えずに、在学中から、少しずつ始めたらいいと思います。特にドイツの場合は。
-では、続いて、難しい質問です。布施さんにとって、音楽はどういう存在ですか?
布施 私にとっての音楽は・・・、大きな「喜び」でしょうか。家で練習してても、コンサートで演奏してても、聴衆として聴いていても、曲の素晴らしさや、それによって作曲家の偉大さに感動するようになったんです。この感動は、言葉にするのは難しいのですが、本当に、喜びというか幸せというか…。その空間にいる、何千人という人々と、一つの音楽を共有できるって、なんて幸せなことなのだろう、と思うようになりました。でも、こういう風に感動できるようになったのは、こちらに来てからです。日本にいた頃は、ただ、がむしゃらに練習していましたから。試験に向かって頑張っていた、という感じで。こちらに来てから、音楽が「身の周りにある普通のもの」と感じられるようになりました。リラックスできるようになったというか、頑張りすぎなくなったというか・・・。そうしたら、突然、音楽が、自分にとって喜びに変わってきたんです。
-違った国の音楽に触れるというのは、そういう利点もあるのですね。
布施 ええ。たぶん、自分の視点が変わったと思うんです。気張らなくなったんですね。ですから、レッスンというものを、楽しんで出来るようになったんです。そして、新しいレパートリーを増やすことに専念するのではなく、今まで日本で練習した曲を、自分の新しい感覚で、もう一度弾いてみたいという欲求も出てきました。だから、レパートリーは、そんなに増えませんでしたけど(笑)。
-日本の音大生は、皆さん「テストが・・・」って、よくおっしゃってますものね。
布施 ですよね。私もその一人でしたから、すごく分かります。年に2回、試験があったんですけど、その試験に向かって曲を練習していました。試験の点数ばかり考えていて、楽しむという余裕なんか、全くありませんでした。音楽大学に限らず、学生にとって、試験の点数は常に気になるものですけどね(笑)
-プロの音楽家として活躍するコツや、成功する条件などを教えてください。
布施 成功する条件というのは、必ずしもないと思うのですが・・・。ひとつ言えることは、日本人は、謙遜する傾向にありますけど、ドイツで、それはしないほうが良いと思います。ドイツ人は、図々しいところがあるので、それに対抗できるくらいでないと、せっかくのチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。たとえば、仕事がもらえそうなときに、謙遜して「自分で勤まるのでしょうか」などと言ってしまうと、そのまま不安として受け取られてしまいます。謙遜や社交辞令は、まったく通用しない国なので、ダイレクトに自己主張するのが大切ですね。
-自己主張は、日本人のニガテ分野のひとつですものね。
布施 ええ。日本人だと、相手のことを考えて「こういったら失礼かな?」などと考えて、自分の思っていることも言えなかったりしますよね。ドイツ人は、失礼だと思えば失礼だとハッキリ言いますから、まずは、思ったことをきちんと言うことが大事です。これは、勉強している学生でもそうだと思います。まして、ドイツ人の中で仕事をしようとしているのであれば、なおさら大切なことです。
-日本人にとっては難しいことかもしれませんが、大切なことですね。
布施 あと、よく聞くのが、こういう話です。すごく上手な方が、オーケストラのオーディションを受けて、自分でも良く弾けたと思っていたのに、不採用だったと。それは、その人の出来、不出来ではなく、オーケストラとの相性の話だと思うんです。「すごく上手だけれど、うちのオーケストラには、多分合わないな。」とか、そういうこともあるんです。受けている側にしたら、自分のレベルが低かったのか、などとショックを受けると思うのですが、プロになりたかったら、「ここと縁がなかった」って割り切って、次に向けて切り替えることも大事です。
-落ち込んでしまうでしょうけどね・・・。
布施 これに関しては、どの国の方でも同じです。どうしても入りたかったオーケストラで不採用になったら、やっぱり落ち込みますよ。でも、そこは頭を切り替えないと。

-最後になりますが、海外で勉強したいと考えている方々に、布施さんからアドバイスをお願いします。
布施 まず、自分が、海外で何を学びたいかを、明確にしておくことが大切だと思います。勉強できる時間は限られていますから、目的はハッキリ設定しておいたほうがいいです。たとえば、オーケストラに入りたかったら、学校は、オーケストラに入るための準備期間にする、という考え方もできます。また、留学後に日本に帰りたい、と考えているのであれば、ソロ活動に専念できるような勉強をするとか、やりたいことによって、勉強の仕方も変わってきますから。もちろん、現地に行ってから、自分の気持ちが変わることはあり得ることですが、ある程度は、しっかり目的を持っていくべきだと思います。
-目的を持って勉強するということですね。多くの学生さんにとって、とてもためになるお話だと思います!
布施 そう言っていただけると、嬉しいです。
-今日は、たくさん興味深いお話を聞かせていただいて、本当にありがとうございました!