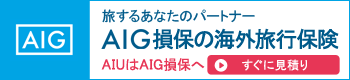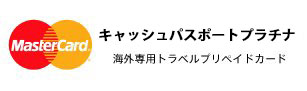布施あづささん/ジャズピアノ/ピート・マリンベルニ教授・アンドビジョン特別プログラム/アメリカ・ニューヨーク
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

布施あづささんプロフィール
フェリス女学院音楽学部卒業。レナートバイリンガル(語学学校)とピート・マリンベルニ先生のジャズピアノレッスンを受講。
-はじめに自己紹介をお願いします。
布施 フェリス女学院の音楽学部を3月に卒業しました。ジャズピアノを4年間勉強していました。ピアノは3歳から始めて、高校まではクラッシックピアノを習っていました。
-クラッシックからジャズに変わったきっかけは何かあったんですか?
布施 高校の3年間、音楽科に通っていて、クラッシックだけをびっちりやっていたので、もっと他の世界に飛び込んでいきたいという気持ちがあって、ジャズを始めました。
-これまでに講習会に参加したり、海外の先生のレッスンを受けたことはありましたか?
布施 一度もないです。
-海外に旅行されたことはありましたか?
布施 はい、ハワイなどに行く機会がありました。
-今回、語学レッスンと音楽レッスンがセットになったご留学をされたわけですが、受講しようと思ったきっかけは?
布施 大学生活の集大成として、ジャズピアノの本場であるニューヨークで勉強したかったということと、自分の語学レベルを少しだけでも上げたいと思ったことです。
-語学レベルを上げたいと思ったのは、将来的に何か目的があるのですか?
布施 将来、また留学したいと考えているんです。そのためにも会話ができるようになりたいと思っていて、今回は、下見もかねてニューヨークに行きました。
-下見はできましたか?
布施 街の雰囲気などはばっちり下見してきました!(笑)しかし、会話はなかなか難しいと感じました。文法がわかっていても、自分の考えていることを会話にして発するというのは、すごく難しいんだな、と感じました。
-頭ではこういうことを言いたいな、と思っても、なかなか言葉にできない感じですか?
布施 そうですね。言えない悔しさともどかしさをすごく感じました。

-それぞれのレッスンの感想をうかがいたいのですが、まず語学レッスンはいかがでしたか?
布施 レナート(語学学校)は7〜8人の少人数にレベル分けされたクラスで、ほとんどが会話の授業でした。
-日本人は何人かいましたか?
布施 私の他に1人だけいました。スペイン人が多くて、他に、メキシコ、ブラジル、フランスの方がいました。
-他の受講生とは仲良くなりましたか?
布施 はい。友だちになることができました。現地では、一緒にご飯に行きましたし、帰国後もメールを交わしています。
-では、学校以外でも英語を交わす機会があったのですね。
布施 そうですね。なかなか難しかったですが……(笑)。
-ジェスチャーを交えて……といった感じですか?
布施 そうですね。ジェスチャーや指差しをたくさん使って、コミュニケーションをとっていました。こちらが一生懸命に伝えたい、と思って話すと、たいてい向こうも分かってくれますね。「あ! 分かる、分かる!」って感じでした。
-では、音楽のレッスンはいかがでしたか? 今回は、語学学校が紹介してくれた音楽レッスンと、弊社が紹介したピート・マリンベルニ先生のレッスンを受講されたんですよね。
布施 2人の先生に共通していたのは、感性から入っていく、ということでした。具体的に言うと「とにかくまず、好きなように弾いてみて」といった感じで、そこが日本とは違うなと感じました。やはり日本は、形から入るというか……、わりと自由がきかなくて「こう教えたらこう弾いてね」という感じなんですが、ニューヨークでは「自由に弾いてみて」というところから入って、ちょっとでも弾けたらすごく褒めてくれるので、本当に楽しく弾けました。
-それぞれの先生にはどんなことを教わったのですか?
布施 レナードで紹介してもらったフォーノ先生はラテンジャズが専門の方なのでボサ・ノヴァを教えてもらい、マリンベルニ先生からはスタンダード・ジャズを教えてもらいました。
-マリンベルニ先生のレッスンはどのように進んだのですか?
布施 スタンダード・ジャズの本に載っている曲を自分でアレンジして流して弾いて、先生にコメントをいただく、といった感じでした。
-難しそうですね。
布施 けっこう大変でした(笑)。あとは、先生と一緒に弾いたりもしました。
-レッスン中はピアノを弾いていることが多かったですか?
布施 そうですね。もうずーっと弾いていました。私が弾いていると、先生が入ってきて、音で会話をしている感じでした(笑)。なので、本当に楽しいレッスンでした。
-マリンベルニ先生はどんな方でしたか?
布施 まず、すごくハンサムでした(笑)。すごく優しくて、穏やかでおもしろい方でした。それがレッスンにも表れていました。
-1回のレッスンはどのくらいでしたか?
布施 1時間です。そのときの雰囲気でちょっと延びることもありました。
-今回のレッスンで新しく学んだのはどういうことですか?
布施 いろんな人のピアノの奏法をもっと聴かなければいけないと感じました。聴いて、コピーして、そこから自分の音をつくっていく、ということをレッスンを通して学びました。アドリブに関しても、今までは好き勝手に弾いていいと思っていたんですが、「話すように弾いて」と言われて、実は言葉のフレーズのように音を繋げていくものなんだ、ということを学びました。
-それは、新しい発見でしたね。
布施 そうですね。ですので、帰国したこれからも具体的にどういった練習をしていけばよいのか分かったのも大きな収穫です。先生からも具体的に練習法のアドバイスをいただきました。
-他に何か印象的なことはありましたか?
布施 マリンベルニ先生はいろいろと喩え話をしてくださいました。「いろんな生き方があって、みんな理想に向かって頑張るんだけれども、それはピアノにも共通していて、自分の理想とする音を奏でるために毎日練習しなきゃいけないんだ。でも、忘れてはいけないのは、必ず楽しむということだよ」と言ってくださって、その言葉が深くて、ズキンときました。
-なるほど。そういえば、レッスンのときに通訳さんはつけていなかったと思いますが、特に問題はありませんでしたか?
布施 意外となんとかなりました。先生も1対1だとゆっくり話してくださったり、なんとか伝えようとしてくださるので、理解することができました。
-向こうでピアノの練習はどうされていましたか?
布施 ホームステイ先のお家でしていました。玄関を入ってすぐの廊下にピアノがあって、それをお借りしていました。学校から帰って夕方までの間しか弾けなかったので、その時間で練習していました。だいたい毎日1時間くらいです。
-レッスンでやった曲を復習で弾くような感じでしたか?
布施 はい、そうですね。次のレッスンで前に習って練習した曲を聴いていただくこともありました。

-レッスンや練習、語学学校以外の時間は何をされていましたか?
布施 買い物に行ったり、ジャズ・バーに行ったり、バレエを鑑賞しました。ニューヨークでしか味わえないことを実感したかったので、いろんなところに出かけました。
-それは一人で行かれたんですか?
布施 いえ、語学学校でニューヨーク在住の日本人の女性の方と知り合って、その方と一緒に出かけていたので、本当に心強かったです。38歳と年上の方だったので、頼れるお姉さんという感じでした。
-バレエは何を観に行かれたんですか?
布施 ニューヨークシティバレエ団です。毎週月曜日に90ドルのチケットが25ドルになるので、わざわざ並んで観に行きました。
-ジャズ・バーというと、行かれたのは夜ですよね?
布施 いえ、ブルーノートのブランチ・ライブというものに行きました。日曜日のお昼にやっていて、値段も少しリーズナブルなんです。ジュリアードの学生の演奏を観に行ったのですが、同じくらいの年とは思えないくらいレベルが高くって、感動しました。
-ニューヨークに住んでいる人など街の様子はどうでしたか?
布施 みんなすごく忙しそうで、いろんな言語が飛び交っていて、「ここはどこ!?」って感じでした。
-ニューヨーク以外のところに観光はされましたか?
布施 他にもボストンやワシントン、ニュー・ジャージーなど、行きたいと思っていたのですが、行かずじまいで惜しかったなぁ……と思います。
-ホームステイ先はいかがでしたか?
布施 お部屋は本当にキレイでした。ベッドも「今まで、こんなベッドに寝たことない」っていうくらいフカフカで、サイズもキングサイズでした(笑)。ホテルの一室のようで、本当にラッキーでした。家族も優しくて、ホストマザーが一度、イタリアンのレストランに連れていってくれました。かわいがってくれて、私が若いからか「ベイビー」と呼ばれていたんです(笑)。最後も「また来てね」と言ってくれてうれしかったです。
-ホームステイ先と学校までは、どうやって移動されていたんですか?
布施 地下鉄を利用していました。乗り換えも、同じホームで向かいに来る電車に乗り換える感じだったので、わりと迷わずに利用できました。看板を見れば分かるようになっているので、大丈夫だと思います。
-道に迷ったりはしませんでしたか?
布施 もう初日から迷ってしまって大変でした。人に聞いて無事にたどり着けたんですが、そういうことがあったので、毎日家を授業の2時間前に出るようにしていました。
-えー! 大変ですね。
布施 それを1週間続けて、道を完璧に覚えてから、1時間くらい遅く出るようにしました。
-お食事はどうされていましたか?
布施 ランチは学校帰りにお店に寄って、夜はデリを利用したり、ホストマザーが作ってくれたものをいただいていました。
-外食のときの値段はいくらくらいでしたか?
布施 ランチは10ドルくらいでした。夜はデリで6ドルくらい使っていました。向こうは量が多いので、6ドルでもけっこうお腹いっぱいになりましたね。
-向こうでは、語学学校やレッスンなど海外の方とお話する機会が多かったと思いますが、そういった方とうまく付き合っていくコツは何かありますか?
布施 シャイにならないことだと思います。思ったことをはっきり言う人たちなので、自分もそうしないとその会話に入っていけないんです。
-最初から自分の意見を言うことはできましたか?
布施 いえ、出来ませんでした。徐々に徐々に……という感じです。何気ない会話でも授業でも、自分の意見を求められることが多いと感じました。積極的にいくのが本当に大事だと思います。
-留学中に困ったことはありましたか?
布施 やはり、道に迷ったことですね。あとは、ドライヤーがなくて、大変な思いをしました。それから、日常品に不便を感じることが多かったです。例えば、ティッシュを買ってもゴワゴワしていたり……、といった細かいことに不便を感じて、向こうに行って、日本の環境って本当に恵まれているなと感じました。
-ご留学されてよかったなと思ったのはどういう瞬間ですか?
布施 考え方が変わりました。今まで自分が正しいと思ってきたことを、また別の視点から見ることができました。こういう考え方もあるんだ、と視野が広がりましたね。あとは、日本を離れて日本の良さを知ることができたと思います。
-日本に帰って来て、成長したと思うことがあれば教えてください。
布施 今までは友だちを羨んだりすることが多かったのですが、それがなくなって、自分は自分なんだと思えるようになりました。たった3週間しか滞在していないのですが、向こうは、自分は自分で突き進む人が多いので、私も私で自分をちゃんと持ってしっかっりしていかなきゃいけない、と感じたんだと思います。

-日本と留学先でどんなところに違いを感じましたか?
布施 生活面で言えば、まったく干渉がないことです。多分日本だと、ホームステイに来ていても、かまってしまうと思うんです。でも、向こうでは、プライベートがきちんとあると感じました。私は干渉されない方がいいので、すごく楽でした。音楽面では、向こうの人たちは生まれたときからノリがある、と感じました。本当に音楽を楽しんでいるっていう感じでしたね。
-留学する前にしっかりやっておいたほうがよいことを教えてください。
布施 きちんと下調べをしておいたほうがいいと思います。さっきお話したティッシュとか……(笑)、本当に小さいことなんですけど、そういうことがすごく気になってくるんです。ハンドブックにもそういうことは書いていないので、留学をした人に話を聞いてみるのがいいと思います。
-今後は、どういう音楽活動をされていくんですか?
布施 4月からは社会人になって、音楽とはまったく関係のない仕事をしますが、早く蓄えて、また留学したいと思っています。今度は、ピアノだけで、もう少し長く留学したいと思っています。
-今日は本当にありがとうございました。
堀江夕子さん/ピアノ/アルベルト・フランツ先生・アンドビジョン特別プログラム/オーストリア・ウィーン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

堀江夕子さんプロフィール
1970年生まれ。ヤマハ音楽教室講師を経て、現在堀江音楽教室主宰。音楽教室・英語教室・クライミング教室・設計事務所を併せ持つクライミングジムロック・ジム ほりえ 代表。ウィーンでアルベルト・フランツ先生のピアノレッスンを受講。
-はじめに、簡単な自己紹介をお願いします。
堀江 5歳からピアノを習い始めました。高校2年生で進路を考えたときに、何をするか迷いまして、結局、音楽系には進まずにピアノも一度辞めてしまいました。そのあと、大学3年生の頃になんとなく指が寂しくなって、また弾き始めたんです。その頃、ちょうど就職をどうしようか考えていた時期でもあって、そしたら、当時のピアノの先生がヤマハの人だったんですが、「ヤマハを受けてみない?」って誘ってくれたんです。それがきっかけで試験を受けたら合格したので、ヤマハ音楽教室に入りました。
-それからずっとヤマハとの関係は続いているんですか?
堀江 いえ。25歳で結婚するときに、辞めました。主人の実家に引っ越しをして、そのあとは、クライミングを一生懸命したかったので、ピアノは、結婚式の教会で時々、弾くくらいでした。
-今回、ご留学されようと思ったきっかけは何かあったんですか?
堀江 子育ても一段落して、音楽教室の経営も安定したんです。そしたら、引き出しが空っぽになってしまったような感じがして、何かしたいな、と思ったんです。それで、ウェブサイトで探していたら、アンドビジョンさんのサイトを見つけて、資料を取り寄せたんです。
-それは8月の頃でしたよね? それまでは留学も考えていませんでしたか?
堀江 そうですね。クライミングをしながら、知り合った方たちに「ピアノをしていたの」って話をしたら、そこでだんだん輪が広がって、今は音楽教室の生徒も60人くらいいるんです。そういうのもあって、2年前くらいからちゃんと弾こうと思うようになりました。それで、自分自身、先生にもついていたんですね。先生はたくさんいらっしゃるので、弾ける先生にも来ていただいたりしていました。そういうふうに、ピアノへの思いはだんだん募っていて、今回、留学をしてみようと思ったんです。
-そうだったんですね。アルベルト・フラン先生を選ばれた決め手は何だったんですか?
堀江 ホームページでも最初の方に紹介されていたので、お勧めの先生なんだろう、と思ったことと、初心者でも大丈夫といったことが書かれていたので、フランツ先生にお願いしたいと思いました。
-レッスン場所がウィーンでしたが、惹かれる部分はありましたか?
堀江 そうですね。オーストリアというのは、クライミングの世界ではトップレベルなんです。覇者がオーストリアからたくさん出ていますし、情報もたくさん入ってくるんです。それで、オーストリアにどんなバックボーンがあるのだろう?と気になっていました。それだけではなく、やはりウィーンは音楽の街ですし、行きたいと思いました。
-そうすると、初心者でも大丈夫なフランツ先生だったこと、クライミングにも関係があること、音楽の街であること、と三拍子そろっていたわけですね。
堀江 そうですね。それから、音楽留学というとすごく志が高い人が行くのかな、という不安もあったのですが、同じくらいのレベルの方の体験談も見せて頂いたので、安心して申し込みました。
-それから、留学までにドイツ語を勉強されたりしましたか?
堀江 いえ。急なことだったので……。“指差しオーストリア語の本”を買ったくらいです。指を差してなんとか伝わるかな、と思ったんです。
-その本に載っていたことで、何か役に立ったフレーズはありましたか?
堀江 向こうでその本を開くこと自体、ほとんどありませんでした。英語が通じる国なので簡単な英語と“ダンケ”と“ブレス・ゴット”の2つで大丈夫でした。
-生活する上でも英語が話せれば問題ありませんでしたか?
堀江 はい、大丈夫でした。

-フランツ先生のレッスンは全部で3回でしたよね。いかがでしたか?
堀江 まず最初にモーツアルトの時代のブラピーアの話から始まりました。あとは、クライミングをしていて指が痛かったので、最後の頃は、弾くときの姿勢や手が痛いときの弾き方、指の動かし方、力の抜き方のストレッチなどを教えてくださいました。
-ただ単にピアノを弾く、ということだけではなかったんですね。
堀江 そうですね。私もいくつか聞きたいことがあったので、質問をいくつか用意して行ったんです。それに対して、先生がひとつずつ丁寧に答えてくださいました。あとは、第一次世界大戦前後で教則本が変わったことから、弾き方の違いで今は故障者が多いのだけれど、姿勢に気をつけることで君の痛みはとれるよ、と教えてくださいました。日本に帰って来てから実際にその弾き方にしたら、まだ違和感はあるんですが、確かに痛みは出ないんです。本当にびっくりしました。
-その弾き方が堀江さんに合っているのかもしれないですね。
堀江 肩を後ろにして、ひじを開きすぎない弾き方なんです。すごく恰幅のいいおじさんが弾いているような感じになるので、主人はそれを見て笑っているんですが(笑)……。
-でも、痛みが取れてよかったですね。フランツ先生のレッスンの中で一番大きな発見はそのことでしょうか?
堀江 そうですね!
-日本のレッスンだとあまり姿勢については言われないですよね?
堀江 そうですね。ひじや指の形については指摘されることがありますが、私の場合は、姿勢が悪く肩が出ていたようなんです。それをフランツ先生が見つけてくれて、肩が出ているから、ひじも出てしまうんだ、と気づくことが出来ました。
-実際のレッスンの流れはどういうものだったのですか?
堀江 最初にモーツアルトの話から始まって、弾いてみて下さいと言われて、弾いて、直されて、という普通のレッスンの流れでした。途中から「あれ、指が転ぶね」ということで話が始まり、いろいろとアドバイスをしてくださいました。私が何か質問をすると、その質問はおもしろい、と言ってメモをとったり、先生が何かを言ったりしたときの私の反応が珍しかったようで、それもメモに取っていました(笑)。私は普通の反応をしたつもりだったのですが、先生には新鮮だったようです(笑)。
-おもしろい生徒さんだな、と思われたんですね。
堀江 あとから通訳さんに「君はおもしろい題材だ」と先生がおっしゃっていたと言われました(笑)。
-なんだか楽しそうなレッスンの様子がすごく伝わってくるエピソードですね。
堀江 はい、とても楽しかったです。
-通訳の仕方やフランツ先生とのやりとりはいかがでしたか?
堀江 先生が話し終えるとすぐにバラバラバラと通訳してくださって、私の言いたいこともきちんと伝えてくださいました。1時間半という限られた時間の中でやりとりをしなければいけないので、言葉のストレスを感じるのは嫌だったんです。先生と二人で楽譜を覗いて、顔を突き合わせて、どうします? とやるとすごく疲れると思うんです。そういう意味で、3回とも通訳の方に来ていただいて、よかったと思います。通訳の方もピアノが弾ける方だったのも、すごくよかったですね。先生が私の反応のメモをとっている間に、「通訳さんはどう弾きますか?」、「僕はこうかなー」なんてやりとりをしていました(笑)。
-今回は、どんな曲を見てもらったんですか?
堀江 フランツ先生はモーツアルトがご専門だと聞いていたので、モーツアルトのソナタを持って行きました。
-他には何か用意して行かれましたか?
堀江 簡単なもので、メンデルス・ゾーンを持って行きました。メンデルス・ゾーンの1番をもっと意味があるように弾いてみたいと思っていたんです。でも結局、メンデルス・ゾーンまで行かずに、ソナタも1曲で終わり、「はっ! もう時間だ!」という感じでした(笑)。
-その分、1曲を濃く教えてもらった感じでしょうか。フランツ先生のレッスンを受ける前と受けた後で、そのソナタを弾いて何か変化はありましたか?
堀江 帰ってきてから、日本の先生に見ていただいたのですが、「左手がきれいにまとまっていますね」と言われました。フランツ先生と左手の連打を練習するのに、バスケットボールのようにやろうということで、ピアノから降りてバスケットボールの練習をしたんです(笑)。それの効果があったのかもしれませんね。
-それも楽しそうですね。さきほどストレッチの話をされていましたが、どういうストレッチを教わったのですか?
堀江 力の抜き方のストレッチで、肩から腕を水平に上げて、ひじを90度曲げた状態から、糸がぷつんと切れたようにマリオネットのように落とすんです。その状態で、私は肩が前に出てしまうんですが、前に出ないようにと何度も注意されましたね。

-ウィーンでは、練習室を予約されていたかと思いますが、練習室はいかがでしたか?
堀江 アンドビジョンさんから送っていただいた用紙に部屋の番号まで書いてあったので、何の問題もなく部屋を使えました。部屋は7部屋くらいあって、ピアノも5台くらいあったと思います。
-けっこう練習時間を取られていましたよね。みっちり練習されたんですか?
堀江 1日目は一生懸命弾きましたね。着いた最初の日にレッスンがあったので、レッスンの後、4時間くらい練習しました。お水を飲んで、スーパーで買ったハムをかじりながら、練習しました(笑)。
-ハム、ですか?
堀江 はい。けっこうおいしいハムが売っていたので、それをそのままかじっていました(笑)。
-お食事はどうされていたんですか?
堀江 最初にスーパーで食材を買い込みました。それで、朝はトーストにトマトとチーズとハムのサンドイッチを作って食べていました。ラップにくるんで持って行って、お昼もそれで済ませることも多かったです。あとは、アンケルというサンドイッチのチェーン店で食べたり、ウィンナーシュニッツェル屋さんで食べたりしていました。
-ウィンナーシュニッツェルはおいしかったですか?
堀江 おいしんですけど……、すごく大きいんです。適当に頼んだら、自分の顔より大きなものが出てきました(笑)。薄くてペラペラなんですけど、それでも顔以上のサイズなのでボリュームはあって、ウィンナーシュニッツェルを食べた日は、それしか食べられませんでしたね。
-夕飯はどうされていましたか?
堀江 1日目は、普通の個人のお店で外食したんですが、ちょっと量が多くてびっくりしました。ヒドリという日本食のお店があったので、そこに入り、一度行ったらおいしかったので、あとは毎晩、通っていました(笑)。からあげや定食、焼き鳥、巻き寿司、などいろいろありました。日本人のスタッフさんばかりだったので、その方たちに現地のお話を聞いて、毎晩、楽しく過ごすことができました。
-やはり日本食が恋しくなりますか?
堀江 若い頃は、外国に来てまで日本食を食べる人の気がしれない、なんて思っていたんですが……(笑)。向こうの食事もおいしいんですけど、ウィンナーシュニッツェルやパンを食べていると、やはりお米が食べたいな、と思いますね。スーパーにもお米は売っていたのですが、朝ご飯やお昼ご飯は自分で作ることがほとんどだったので、夕飯くらいいいや、と外食していました。

-レッスンや練習以外の時間はどのように過ごされていましたか?
堀江 仕事に関することですが、クライミング・ジムの視察に行っていました。向こうの建物や規模を見て、肌で感じていました。それから、オペラを日本から予約して行ったので、「フィガロの結婚」を観ることができました。
-えー! いいですね。やはり、本場のものは違いますか?
堀江 はい。日本でもよく観るのですが、全然違いますね。建物が円形で上の方に席がある会場でした。1万4、5千の席がありましたが、それでもすごく臨場感があって、周りの人たちも口ずさんだり、鼻歌を歌ったり、知っている曲では歓声を上げたり……、そういう空気を体験できて、すごく良かったです。
-そういうのって、日本ではあまり体験できないですよね。
堀江 そうですね。日本ではそういう体験はしたことがありませんでした。
-他にも観光はされましたか?
堀江 小さいところに見所がギュギュっとつまっている街だったので、レッスン会場から練習室に行く間にも、観光名所がちょこちょこありました。あとは、ステファン寺院や旧市街のあたりを観光しました。でも、どこかに行かなくても、電車に乗っているだけで、すごい建物がたくさんあるので、それを見ているだけでも楽しめましたね。
-向こうでは日本人以外の現地の人や他の国籍の人と話す機会も多かったかと思いますが、何か話すコツなどはありますでしょうか?
堀江 しかめっ面はいけないと思っていたので、笑顔で“ダンケ”と“ブレス・ゴット”と言っていました。通りすがりの人でも、すれ違ったら挨拶をしていましたね。挨拶をすると、向こうの人も笑顔で返してくれました。

-今回はフラットにご滞在されていましたが、いかがでしたか?
堀江 すごくおもしろかったです。ホテルやキャンプではわからない、ウィーンの人の生活の実態が見られたのが良かったです。
-大家さんと話す機会はありましたか?
堀江 最初の日に鍵を渡すのに待っていてくれて、英語でわーっと、ガスや鍵の説明をしてくれました。どうやら日本びいきの大家さんだったようで、仏像がお部屋の角にありました(笑)。けっこう大きい仏像で、大人が座っているより少し大きいくらいのものだったので、すごくびっくりしました。あとはたぬきの置物もあって、おもしろいお家でした。
-部屋の広さはいかがでしたか?
堀江 ダブル・ベッドが2つもあって、家族で借りられるな、というくらい広かったです。主人は設計の仕事をしているので、現地でスケールを買って、いろいろと測っていましたね(笑)。そして、その広さや色使いに感心していました。そのセンスの良さは、他のお家も同じで、そのセンスというのは、街をきれいに保とうという精神から来ているのかな、と感じました。主人も日本に帰って来たら、「やっぱり信州の町並みって変だよね」とか言っていて、この前も「もうちょっと、もともとあるものでできることを、提案していく必要があるよね」なんて、お友達に話していました。
-今回、レッスンを受けて良かった瞬間があれば教えてください。
堀江 やはり、百聞は一見に如かず、だと思いました。これまで、書物や楽譜でいろいろな先生方に教えていただいたのですが、その場所に行かなければ分からない目に見えない空気や雰囲気、クラッシック音楽が培われて来た社会風土のようなものを感じることができたのが、良かったと思います。また、そういうのに触れて、日本に帰って来た今、視野が広がったと思いました。小さなところに詰まっていたものが外に出て、上から見られるようになった気がします。
-なるほど。
堀江 弾くこともすごく楽しくなって、ピアノの先生からも「堀江さん、楽しそうだね」と言われました。あとは、自分が教えるときも、行く前は、あまり弾けない子たちに対して、こんなんでいいのかなとブレがあったのですが、自分が留学したことで変わりましたね。音楽留学ってすごい人たちが行くんだろうなと思っていたのですが、そんなことはなくて、フランツ先生もその中で出来ることを教えて下さったんですね。そんな経験をして帰って来てからは、30分のレッスンの中で15分は歌って弾いてもいいかな、とか、その時間の中で曲のレパートリーを増やして、とか楽しいレッスンをしてあげようと思えるようになりました。
-堀江さんご自身は今後はどうされていきたいとお考えなんですか?
堀江 先生がモーツアルトを研究されているので、ウィーンなので、という理由から何となくモーツアルトを教わったのですが、これも何かのご縁なので、せっかくだからちゃんとモーツアルトのソナタを弾けるようになろうと思いました。

-またフランツ先生のレッスンを受けたいですか?
堀江 はい、そうですね。先生が嫌がらなければ(笑)。
-いえいえ、そんなことはないかと。きっと先生も覚えてらっしゃいますよ(笑)。最後になりますが、これから留学を考えている方にアドバイスをお願いします。
堀江 自分もそうだったのですが、まずは迷う前に失敗してもいいから、行きたいときに行くのがいいと思いました。いつか時間が出来たら、とか、お金が貯まったら、とかではなく、まず、出てみることが大事だと思いました。そうすれば、自然に次のことが浮かんでくると思います。そのときには、簡単な中学校レベルの英語を話せれば日常生活は十分だと思います。先生とのやり取りも長期滞在だと事情が違ってくるかもしれませんが、1週間くらいの短期の滞在でしたら、通訳さんをつけて、言葉のストレスをなくすことで、限られた時間を有効に使えると思いました。
-なるほど。今日は貴重な体験談を本当にありがとうございました。
佐藤暁彦さん/ジャズドラム/シエナジャズサマーコース/イタリア・シエナ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 佐藤暁彦さんプロフィール
佐藤暁彦さんプロフィール
中学時代に、吹奏楽部のパーカッションでドラムを始める。大学でジャズ研究会に入部し、ジャズドラムを開始。2007年、シエナジャズサマーコースに参加。講習会では、選抜のビックバンドのメンバーに選ばれる。2007年、横浜ジャズプロムナードにコンボバンドで参加。
― はじめに略歴を教えてください。
佐藤 中学生のとき、ドラムをやりたくて吹奏楽部に入り、高校でも引き続き、吹奏楽部でした。大学でコンボ主体のジャズ研究会に入部して、興味があったジャズをやり始めました。同時にポップスのバンドも結成し、大学卒業後も続けて、インディーズでCDを出したりもしたんです。一方、大学卒業後、ヤマハ音楽院で、ジャズに限らず、ポップス、ロックといろいろ学びました。卒業後は、ポップスの活動がメインだったのですが、だんだん、またジャズを本格的にやりたいなと思うようになって、ジャズクラブやライブハウスに行くようになったんです。
― 今もポップスは演奏されているんですか?
佐藤 頼まれたら演奏しますが、今は本格的にジャズに絞ってやろうと思っています。
― どこか決まったライブハウスで演奏されているんですか?
佐藤 地元の横浜や横須賀のライブハウスで演奏することが多いですね。横浜はかなりそういうお店が多いんです。
― 講習会に参加したのは何がきっかけですか?
佐藤 演奏の仕事があまりなかった時期に、何かしようと思い立って、以前から覗いていたこちらのサイトでこの講習会に興味を持ったんです。普通、イタリアにジャズしに行くヤツいないだろうと思って(笑)。
― アメリカとは迷わなかったですか?
佐藤 最初は、アメリカも考えたのですが、日本の人がジャズを勉強しようと思ったら、普通、アメリカに行くじゃないですか。だから、他の人と違うことをやってやろうと(笑)。
― それでイタリアに?
佐藤 もともとイタリアのジャズに興味は持っていたんです。講習会には、エンリコ・ラバというトランペットの先生もいたんですが、その方はイタリアジャズの中では、世界的に有名な人です。東京のブルー・ノートに来たときに観に行ったのですが、それもこの講習会に参加したきっかけになっています。そのときにイタリアのジャズをおもしろいと感じたんです。アメリカのジャズと比べても、泥くささがないというか…。ヨーロッパのジャズというのは、クラシックの影響が強いとよく言われています。やっぱりイタリアのジャズも、クラシックをジャズに昇華したような感じがしますよね。
 ― それでは、シエナジャズ講習会の全体の様子を教えてください。
― それでは、シエナジャズ講習会の全体の様子を教えてください。
佐藤 今回の講習会はシエナジャズという大きなイベントの一環でした。全体で200人くらいが参加していました。各パート30人くらいですね。楽器の他にも作曲のコースで来ている人が数人いました。
― レッスンはどのように進められたのですか?
佐藤 最初に選抜試験がありまして、それで2クラスに分かれて、クラス別に1人ずつ先生がつきました。
― 選抜試験というのはどのような試験だったのですか?
佐藤 基礎的なことができるかどうかをみる試験です。1人ずつ呼ばれて、「こんな感じのできる?」「これやってみて」という感じで行われました。
― レッスンはどんな内容でしたか?
佐藤 ドラムを2つ並べて、2人がセッションをするといった内容です。基本的には生徒2人がセッションをしましたが、場合によっては先生が叩くこともありました。例えば「早めのテンポで」とか「こういう拍子で」といったテーマが出されて、それにそって2人がセッションをします。それを先生が聞いていて、指導してくれます。
― ずっとグループレッスンだったんですか?
佐藤 そうですね。短期間の講習会なのでそういう形なんだと思います。
― 他の生徒の皆さんは上手でしたか?
佐藤 講習会を受けた人の中には、若い人もいたし、これからジャズやりますっていう人もいたんですが、ラッキーなことに僕は上級者のクラスに入ることができたので、皆さん、上手でしたね。音楽のレベルはとても高かったです。
― 講習会のスケジュールを教えてください。
佐藤 朝の9時から始まって、夕方の5時までのスケジュールですが、だいたい5時半くらいまででした。間に1時間くらいお昼の休憩がある程度で、あとはずっと講習です。実技のレッスンだけでなく講義もあったのですが、それも含めて本当にみっちりでした(笑)。
― 講義はどんな授業でしたか?
佐藤 音楽理論と聴音(ヒアリング)、ジャズの歴史、それから楽曲分析の授業がありました。理論の授業では、コードや音階のことを学びます。ドラムでもそういうことは知っておいた方がいいので、ためになりました。楽曲分析ではある曲を聞いて、その曲の構成、リズム、進行がどういうものかを分析していきます。
― 何語でやりとりされているんですか?
佐藤 基本的にはイタリア語ですが、実技のレッスンのときは僕が分からないと、先生が英語で言い直してくれました。理論の授業のときは、いちいち先生が言い直していると時間がかかってしまうので、英語が堪能な生徒さんを紹介してくれて、その人が英語で教えてくれました。僕はそんなに理論は詳しくないのですが、自分の持っている音楽のボキャボラリーで考えていけば、理解することができました。
― 参加を決めてから、事前に語学の勉強はされたんですか?
佐藤 英語はもちろん、イタリア語も音楽用語などはそれなりに勉強していきました。結果的にそれはすごく役に立ちました。おもしろいもので、耳が慣れてくると、音楽用語であれば、イタリア語でも大まかにわかるようになってくるんです。
― すると、言葉にはほとんど困らなかったですか?
佐藤 いや、困りましたね(笑)。勉強もしていたし、なんとかなるだろうと思っていたんですが、いざとなると、緊張してしまって聞き取れないこともありました。指示を間違えて受け止めて演奏してしまったこともありました。それから、受け身の姿勢ではなくて、「こう表現したいんだけどどう演奏したらいいのか」とか、もっとこちら側からアプローチできる語学力があればよかったなと思いました。
― では自分から質問されることはあまりなかったのですか?
佐藤 そうですね。そこが悔やまれますね。あとから冷静になれば、英語でこう言えばよかったな、とは思うのですが、なかなかその場では言葉が出てこなかったです(笑)。
― 日本人は参加していましたか?
佐藤 いえ、僕1人でした。ほとんどがイタリア人で、あとは何人か他のヨーロッパの国から来ていました。ある程度予想はしていたのですが、まさか本当に一人とは…(笑)。そういう意味では、すごく目立ちましたね。最初の説明会に行ったときも、視線を感じました(笑)。
― 講習会中は、個人練習はどのくらいされたのですか?
佐藤 実質、やる時間がなかったですね。ファイナルコンサートというのがあって、選抜のメンバーでビックバンドを結成したのですが、そのメンバーに選ばれたんです。それで、その練習が講習のあと、夜の7時くらいまであって、個人の練習をする時間はなかなか取れませんでした。
― 選抜メンバーに選ばれたんですね。すごいですね。
佐藤 クラス分けの選抜試験のときに同時に見ていたらしく、ラッキーなことに先生が推薦してくれたようです。
 ― 選抜メンバーとの練習はどうでしたか?
― 選抜メンバーとの練習はどうでしたか?
佐藤 最初の練習のときに1人ずつソロを回していって、最後に僕もドラムソロをしたんですが、ソロが終わったあとにみんなが「お前、いいじゃん」って拍手してくれたんです。それですごく楽になりましたね。これなら楽しくやっていけそうだなと思いました。
― そのバンドの練習も事前に個人練習はしなかったんですか?
佐藤 そうですね。譜面だけ見ておいて、あとは全体の練習のときにその場で演奏しました。ただ、昼休みを削って(笑)、生徒同士で他の楽器と組んでセッションしていました。
― セッションをする部屋は用意されていたのですか?
佐藤 昼休みなので、開いている部屋を使いました。あとは、もともと使われていない部屋も事前に予約すれば使うことができました。
― イタリアの事務局はどうでしたか?
佐藤 中には適当な人もいましたが(笑)、けっこう親切にしてもらったと思います。根本的なシステムが日本と違うので、戸惑うことも多かったんですが、優しく教えてくれました。
― 宿泊先はどうでしたか?
佐藤 シエナにある大学の寮に泊まりました。二人部屋でした。講習会に参加した人は、けっこうバラバラに振り分けられていたようで、大学の寮に限らず、中にはホテルの人もいました。
― 宿泊先と講習会の会場は近かったのですか?
佐藤 僕の宿泊先はけっこう距離があって、歩くと40分くらいかかるところでした。朝はバスがあるので利用していました。
― 帰りは歩いていたのですか?
佐藤 シエナジャズという大きなイベントなので、講習会の会場や特設ステージで、インストラクターの方やイタリアのプロミュージシャンたちがライブをしているんです。練習後にそれを見ていると、帰りが12時半位になってしまうんです(笑)。もちろん、バスは終わっているので、帰りは、歩いて帰っていました。せっかくなので、ライブも観ておきたかったんです。
― 治安はどうでしたか?
佐藤 よかったですね。周囲でも危険な目に遭ったというような話は聞きませんでした。宿泊先までも離れていたので人通りの少ないところもあったんですが、危険そうな感じはありませんでした。小さい街なので、治安はよいと思います。
― 食事はどうされていたのですか?
佐藤 お昼は近くにあったバールでパニーニをつまんで、夜はピザ屋さんで食べる、ということが多かったです。食事はどこのお店もおいしかったですね。
― 海外の人たちとうまくつきあうコツはありますか?
佐藤 イエス・ノーをはっきり言うことですかね。はじめのうちは日本人的な曖昧な返答をしていたのですが、それで相手を怒らせてしまいました。年下の16歳くらいの子に「日本人にはノーという言葉がないのか!」って言われました(笑)。向こうの人たちは、はっきりしていますね。でも、ノーと言っても、失礼にはならないのでイヤならイヤと伝えるのがいいと思います。あとは、こちらから話しかけてコミュニケーションをとっていくのがいいと思います。
― 講習会に参加して良かったと思える瞬間はありましたか?
佐藤 それはやっぱりファイナルコンサートに出られたことですね。シエナにすごく大きな聖堂があるんですが、その前の広場に大きなステージを組んで、そこで演奏したんです。メンバーとは、ずっと一緒に練習していたので、信頼関係ができて、向こうも自分のことを受け入れてくれて、それが伝わってきたんです。そういう瞬間はすごく良かったです。
― 留学して成長したなと感じる部分はありますか?
佐藤 演奏面では、向こうで友達に「もっと楽しもうよ」と言われて、あぁ、楽しむのが大事なんだな、と思いました。その友達は、僕が演奏すると苦しそうに見えるって言うんです。そういえば、日本にいるときから立ち向かうぞという気持ちでいて、楽しむということをあまり意識していなかったことに気づかされました。それから、留学する前はテクニックを身につけたもののどう表現すればいいのか、と行き詰まっていた部分があったのですが、レッスンの中で「どうしたら音楽的な対話ができるのか」という内容も多かったので、とても勉強になりました。「最初にどう表現したいかを考えなさい」と言われたのが印象に残っています。
 ― 音楽以外のところではいかがですか?
― 音楽以外のところではいかがですか?
佐藤 何でも自分でなんとかしないとどうにもならないんだということを痛感しました。 例えば、講習会中も、若い人でも自分で様々な手配をやっているわけです。日本だと、手取り足取りという感じですよね。
― そのあたりが日本とイタリアの違いでしょうか?
佐藤 そうですね。自己責任の部分が強いと思います。講習会をどう消化していけばいいのかという基本的な部分ですら教えてくれないんです。本来は講習会の中でいろいろなことが出来るはずなんですが、こちらから聞かないと分からないままです。例えば、資料を借りられるということは、聞いてみてはじめて、出来ると知りました。講習会を最大限に利用しようと思ったら、そういう自ら働きかけていく姿勢が大事になってくると思います。
― 留学前にしっかりと準備したほうがいいことを教えてください。
佐藤 語学です。語学を学んでおけば、理解の仕方がちがってくると思いますよ。確かに言葉がなくても通じ合える部分はあるのですが、やはり講習会なので、深く質問していこうと思ったら、語学を学んで行くことが必要です。
― 今後留学する人にアドバイスをお願いします。
佐藤 シエナに行きたい人は、イタリアに興味がある人だと思うんですが、今の時代、日本でもアメリカでもイタリアでも同じ情報はシェアできますよね。そんな中、どうしてイタリアまで行きたいのかをはっきりさせてから行った方がいいと思います。「どうしてイタリアまで来たの?」とイタリア人に言われるくらいですから(笑)。これは、他の国でもそうだと思うのですが、自分の意思をはっきり伝えれば、向こうも受け入れてくれると思います。
― 最後に今後の活動予定を教えてください。
佐藤 横浜・横須賀のジャズクラブを中心に、複数のグループでライブ活動しています。
― ビックバンドはもうやらないのですか?
佐藤 機会があれば、今回の経験を活かして、ビックバンドもやってみたいな、と思っています。
― 実現したらぜひ教えてください。楽しみにしています。ありがとうございました。
佐藤さんの近況は以下のホームページで!
http://www.geocities.jp/pacifico_sato/
香田亜以さん/ヴァイオリン/アンギャン夏期国際マスタークラス/ベルギー・アンギャン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 香田亜以さんプロフィール
香田亜以さんプロフィール
1989年札幌生まれ。北海道大学工学部2年在学中。現在、北海道大学交響楽団、その他アンサンブルに所属。
2009年ベルギー・アンギャン夏期国際マスタークラス受講
-まずは、香田さんの簡単なご経歴を教えてください。
香田 4歳からバイオリンを始め、プライベートレッスンで先生について習っています。音楽大学ではなく一般の大学に通っています。
-今回アンギャンに行かれたわけですが、それまでに海外に行かれたこと、レッスンを受けられたことはありましたか?
香田 いえ、ありません。初めてです。
-海外の講習会に参加して、音楽を勉強しようと思ったきっかけは?
香田 作曲家が生きた国や場所で、実際に曲を作った場所を見てみたいという思いや、その空気を感じながら弾いてみたいという思いがあったからです。
-ベルギーを選ばれた理由は?
香田 ブロン先生のレッスンを以前テレビで見たことがあって、一度生でレッスンを見てみたいな、と思っていたんです。
-では、以前からブロン先生にご興味があったのですね。
香田 はい。ブロン先生は、日本にもけっこういらっしゃっている方なので。
-今回、アンギャンの講習会はどれくらいの人数が参加されていましたか?
香田 最初の1週間は聴講生だったのですが、大体25人ほどでした。2週目は6人です。
-どの国の人が多かったですか?
香田 フランス人、ドイツ人はやはり多かったです。でも、ブラジルから来ていた方もいましたし、日本人もいました。国際色豊かでしたよ。
-レッスンは英語でしたか?
香田 はい、英語でした。
-1週間目はザハール・ブロン先生の聴講ということですが、毎日聴講には行かれましたか?
香田 毎日ではありません。一週目は人数が多かったので、一人あたりでは40分のレッスンでしたが、朝から晩まで行われていました。出入り自由なので、気軽に聴講しに行っていました。
-実際にレッスンを聴講した感想は?
香田 実際に外国人のレッスンを初めて見ましたが、ブロン先生は基本ドイツ語だったので先生の話していることが分からなくて…。でも、ブロン先生はお手本として弾いてみせていたので、それで理解できるという感じでした。フレーズとか入り方とか。受講生が上手な方ばっかりだったので、聴いているだけで表現の仕方など本当に勉強になりました。
-レッスンの雰囲気は、どんな感じですか?
香田 先生と自由に話せるような雰囲気でした。聴講している生徒や親もたまに先生と話したりもしていましたよ。
-2週目からのウルフ・ヴァーリン先生のレッスンはいかがでしたか?
香田 それが、先生が直前に病気になられて、講習会にいらっしゃらなかったんですよ。
-そうだったんですか!?
香田 急遽、ミッチェル先生という女性の方に代わったんです。最初、どういう方かも分からなかったので、不安でした。帰ってから調べてみたら、ソロ活動をされている先生のようで。ソロの方なので弾き方がやっぱりパワフルでした。見せるパフォーマンスを大事にされているというか。
-そんな方のレッスンを受けられて、逆に良かったかもしれないですね。
香田 はい。最初はびっくりしましたが、刺激的でした。
-ミッチェル先生のレッスンは、どのくらいのペースで行われましたか?
香田 一回1時間のレッスンを一週間に3回ですね。先生方のコンサートがあったので、その練習のために、レッスンの時間が変わって日数的には4日間やりましたが。
-レッスンの内容はどういった感じでしたか?
香田 フレーズの取り方や表現の仕方がメインだったと思います。聴講の時も感じましたが、もっともっと自分を出していかないといけないんだなって。自分がどんなに感情的に弾いたとしてもミッチェル先生はOKを出してくれませんでした。
-何曲くらい見ていただけたのですか?
香田 私は2曲持っていきました。皆さんは、3~4曲持って来ていたので、2曲は少なかったかなとも思ったんですけど、自分の気になった所を突き詰めて習えたので良かったです。
-2日で1曲見てもらった感じですか?
香田 いえ。無伴奏とコンチェルトを一曲ずつ持っていったのですが、弓を上手く使ったフレーズの取り方をもっと教えてもらいたくてコンチェルトを中心にレッスンを受けました。
-その中で、基礎的なことを教わったのですね。
香田 やはり体の動かし方とか、表現の仕方ですね。先生がお手本を見せてくださって。小柄な先生だったんですが、動きの大きな方でした。
-どんな人柄の先生でしたか?
香田 とても優しくて、いつもにこやかな方でしたね。演奏とのギャップがありました。
-レッスン以外の時間は何をしていたんですか?
香田 もちろん練習はしましたが、友達とご飯を食べに行ったり。何度かパーティーもありました。少し時間があったので、一人でブリュッセルの観光もしました。
-充実されていたようですね。練習は、どこでされましたか?
香田 近くの学校が夏休み期間でしたので、そこの教室を使って練習しました。
-ひとり何時間とか決められているのでしょうか?
香田 いえ、決まっていませんでした、朝10時から夜7時まで学校が空いているので、自由に使えました。十分練習できましたよ。
-海外の方とのコミュニケーションはいかがでしたか?
香田 雰囲気はすごく楽しかったですけど、やっぱり、もうちょっと英語が話せたら良かったな…と思いました。
-事前に英語は勉強されていたんですか?
香田 いえ、全然。(笑)行ってみて、頑張ろうという気になりました。
-文化の違いで驚いたことはありましたか?
香田 そうですね。よく言われることですが、本当に自分の意志をはっきり言いますね。ちゃんと自分の意見を持ってて、自信を持って言えるというか。外国に行って、私はもっと自分を出せる気がしました。周りがみんなそういう空気ですから自然と自分に自信も持てますね。海外では、やはり積極的にならないといけないですよね。
-日本人の感覚よりオーバーな感じでやったほうがいい感じなんでしょうかね
香田 はい。それでも、全然オーバーではないんですよね。むしろそれくらいしないと伝わらない。
-なるほど。街の様子はどんな感じですか?
香田 小さな町で、特に観光するところもないような田舎でした。でも、お城の中が本当にキレイでした。公園の中にお城があるのですが、歩いて回ると2~3時間くらいかかりましたよ。ゴルフ場もあってゆったりとした雰囲気で本当に落ち着く場所でした。
-ブリュッセル市内はどんな感じでしたか?
香田 多くの人でとても賑やかでしたよ。本当に親切な方ばかりで道に迷っても全く困りませんでした。
-治安はどうでしたか?
香田 問題ありませんでした。怖い思いもしませんでしたし、英語も通じましたから。
 -初めての海外という方にも、比較的安心な場所のようですね。今回、宿泊先は、どういったところでしたか?
-初めての海外という方にも、比較的安心な場所のようですね。今回、宿泊先は、どういったところでしたか?
香田 ホームステイでした。おじいちゃんとおばあちゃんの、すごく素敵な家庭でした。息子さんもブリュッセルに住んでいるので、週末に来たりしていました。その方が、日本の大学に行っていたようで、日本語がペラペラでした。色々お話してくれましたよ。
-海外のお宅に入るのは、不安があったと思うんですが。
香田 そうですね。でも、毎年日本人を受け入れているホームステイ先でしたので、日本人がそこに滞在したんです。なので、安心でした。凄く大きなお家なので、たくさん受け入れられるみたいです。本当にお城のようなお家でした。
-ひとりに一家庭ではないんですね。
香田 他の受講生はほとんどそうだったみたいですが、わたしが滞在したお家だけは、たくさん受け入れていました。他の参加者からは一番良いステイ先だと言われましたよ。
-それはラッキーでしたね! 滞在中の食事はどうされましたか?
香田 朝はステイ先で用意してくれるので、それを食べました。パン、ジャム、コーンフレーク、フルーツなどが並んでいて、自分の好きなものをそれぞれ取って食べるという感じです。夕食も用意してくれたのですが、講習会が終わるのが18時頃で、ステイ先までのシャトルバスの時間が21時でしたから、その空いた3時間で他の受講生たちと一緒に食べることが多かったです。
-レストランはあるのですか?
香田 はい、会場の近くにはありました。日本食レストランもあったのですが高そうだったので、中華料理屋さんによく行きましたね。結構美味しかったですよ。ステイ先ではほとんど毎日パンが出ました。あと、ソーセージも多かったですね。
-講習会場までは、どうやって移動していたんですか?
香田 シャトルバスが迎えに来てくれました。前の日に名前を書いて予約すると、家の前まで迎えに来てくれるんです。帰りも同じ要領でした。
-歩いては行けない距離だったんですか。
香田 ちょっと無理ですね。どこも行けないんです、田舎過ぎて(笑)。ホームステイ先があるところなどは、本当に何もなかったんです。学校の近くにはスーパーがあるので、学校のあとに寄って、その後バスで帰るという感じでした。
-今回、講習会に参加して一番良かったことは何ですか?
香田 バイオリンの技術についていえば、今後の課題が浮き彫りになって、これから練習していく上で大きな収穫となりました。日本人の演奏だけでなく、色々な方の演奏を聞いたことによって、表現の仕方の幅が広がったように思います。また、室内楽のレッスンもありました。私は今回ピアノ、チェロの方とトリオを演奏することができました。残念ながら私の聞いたことのない曲になったのですが、ピアノ、チェロの方と一緒に弾いているだけで、自分にどのような演奏、表現が求められているのかが感じ取れたのです。まるで魔法のようでした。今までで一番楽しく、衝撃的な室内楽のレッスンでした。ソロのレッスンより室内楽の方が楽しかったかもしれません(笑)
-今後の音楽活動に生かせそうですね。今後、海外留学をしてみたいという方にアドバイスをお願いします。
香田 やはり、ペラペラではなくてもいいので、英語は話せたほうがいいということですね。一生懸命話していれば、分かってくれる部分はあるのですが、話せるに越したことはありません。
-音楽家になりたいという目標はありますか?
香田 そうですね。今までは音楽は趣味だと思っていたんですが、今回参加してみて音楽の素晴らしさを改めて実感しましたし、もっと深く追求して将来的にそういう道に進めたらいいなとは思い始めています。
-今回の留学で可能性も更に増えたことと思いますので、今後も頑張ってください。今日はお忙しいなか本当にありがとうございました。
須山由梨さん/ピアノ/ウィーン国際音楽ゼミナール/オーストリア・ウィーン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 須山由梨さんプロフィール
須山由梨さんプロフィール
3歳よりヤマハ音楽教室に入会。幼児科~ジュニア専門コースで学ぶ。中学2年生で「第2回かやぶき音楽堂ピアノデュオ連弾コンクールD部門」第2位、中学3年生で「第6回若き獅子たちのジュニア音楽コンクール」県知事賞を受賞。兵庫県立西宮高校音楽科ピアノ専攻を経て神戸女学院大学音楽学部器楽(ピアノ)専攻入学。同時に半年毎に阪神間にて自主企画コンサートを実施(1~3回目はフェリーチェ音楽院、4回目以降は世良美術館)。3年生で「第54回朝日推薦演奏会」に出演、「第15回KOBE国際学生音楽コンクールピアノ部門」奨励賞を受賞。現在4年に在籍し「第16回オータムコンサート」に出演、ハンナ・ギューリック・スエヒロ賞を授与される。ボリス・ベクテレフ氏に師事。2009年夏、ウィーン国際音楽ゼミナール ジュゼッペ・マリオッティ先生のコースを受講。
-まずは、須山さんのご経歴からお願いいたします。
須山 兵庫県立西宮高等学校音楽科を卒業し、現在、神戸女学院大学音楽学部の4年生です。
-講習会に参加されたのは、今回が初めてなんですよね?
須山 はい、初めてです。海外旅行としては、小さい頃に行ったことはあるようなのですが、記憶にないんです。写真を見て、ああこんなところに行ったんだな、という感じで。
-今回、参加されたきっかけは、学校でそういう制度があったからということですが。
須山 そうですね。今年から制度が始まって、こういう講習会に参加しませんか、という掲示を見て存在を知りました。そこに書いてあった講師陣の中に、以前から気になっていた先生のお名前を見つけたのも、大きな理由です。その先生にも教えていただきたいし、海外で講習を受けられるなら、と思い応募しました。
-その制度には、学内で選考試験などはあったのですか?
須山 はい、一応選考は成績だったようです。3年生の後期の成績が評価されたようです。
-素晴らしいですね。さて、講習会ですが、参加者はどのくらいの人数がいましたか?
須山 50人くらいだったと思います。実際、全員集まるという機会がなかったのでよくわからないのですが・・・。担当の先生によって、行事への関わり方が違いまして。たとえば、オープニングイベントなどに、「いってらっしゃい」って送り出してくれる先生もいれば、「僕たちは僕たちでやりましょう」みたいな先生もいらしたので。
-参加者は、どんな国籍の方が多かったですか?
須山 私たちのときは、日本人が本当に多かったです。ちらほら他の国の方はいらしたんですけど。
-ウィーンは、日本人には人気の場所ですし、日本の大学生のお休みの時期でしたもんね。
須山 そうですね。夏休みが始まる頃だったので、皆さんも行きやすかったんでしょうね。私は、二期に参加しましたけど、フルートの友達が五期で行ったときには、外国の方が多かったって言っていましたので、時期によっても違うみたいです。
 -講習会のスケジュールは、先生ごとに個々で決まっていたんですか?
-講習会のスケジュールは、先生ごとに個々で決まっていたんですか?
須山 はい。私の場合は、土日を除いて毎日レッスンしていただきました。本当に先生によって、大分スケジュールも違っていたみたいです。
-たくさんレッスンを受けられて良かったですね。
須山 本当にありがたかったです。時間としても、1時間から1時間半くらいで、それが毎日でしたから。
-先生はどんな方でしたか?
須山 本当に穏やかで親切な、まさに紳士という方でしたね。細かいところにまで気を使ってくださって、すごく丁寧に教えていただきました。
-レッスンではどんなことを教わりましたか?
須山 ペダルの使い方をよく教えていただいたのが印象に残っています。先生曰く、ウィーンスタイルという奏法があるそうで。そういうことをいろいろ教えていただきました。
-レッスンはドイツ語ですか?
須山 基本は英語でした。ただ、いろんな言語がしゃべれる先生なので。日本でも徳島文理大学の音楽学部長をされている方で、時々日本語も混じりましたし(笑)。
-練習はどこでされていたんですか?
須山 学校とホテルの練習室ですね。どちらも、2時間を上限として、予約して使う形です。私は、学校の練習室もホテルの練習室もどちらも使いました。
-それぞれの練習室で違いはありましたか?
須山 学校の練習室は、アップライトのピアノだったんです。ホテルは3部屋中2部屋がグランドピアノでした。私は、そのうち1つの部屋が気に入ったので、主にその部屋で弾いていました。
-レッスン以外の時間は何をしていましたか?
須山 コンサートに行ったり、観光したりしていました。美術館へ行ったり、ショッピングなどもしましたね。
-美術館はどうでしたか?
須山 やっぱり素晴らしかったです。美術博物館に行ったんですけど、本当にいたるところに作品が並んでいて、歴史を感じられる作品がたくさんあって、感動しましたね。有名な絵などもありましたから。
-ウィーンは、そういう芸術面は充実してますからね。
須山 ただ、ちょうどオペラをやっていない時期だったので、それが残念でしたけど。
-それは残念でしたね。コンサートは何のコンサートに行かれたんですか?
須山 ひとつは、観光客向けの弦楽四重奏だったんですが、歌やバレエもついていました。こじんまりとした所だったんですけど、素晴らしかったですよ。あとは、ウィーン国立音楽大学の先生が指揮されている、管弦楽団のコンサートに、私のピアノの先生に招待していただいて行きました。とてもいい思い出になりました。
-宿泊先はホテルだったと思うんですが、対応はいかがでしたか?
須山 すごく皆さん親切でした。しいて言えば、シーツなどを整えてくださるハウスキーピングの方が、日によって、すごい早いときがあって、思いっきり寝ているときに来てしまったこともありましたね(笑)。「Don't Disturb 」の札とかなかったので・・・。困ったことはそのくらいで、とても過ごしやすかったですよ。
-宿泊先と講習会場は、どうやって移動していたんですか?
須山 トラムで移動しました。不安だったんですけど、最初、詳しい方が連れて行ってくださったんです。おかげで、すぐ自分で乗れるようになったので、毎日使ってました。
-助けてくださる方もいたんですね。
須山 はい、とてもありがたかったです。宿泊先にも日本人の方が多かったですし。学校の先輩と、向こうでばったりお会いしたりもして、それも心強かったですね。
-食事は外食が多かったんですか?
須山 そうですね、友達と一緒に行きました。けっこうイタリアンレストランが多くて、入りやすかったのでよく行っていました。あとはカフェとかですね。値段としては、平均、10から15ユーロくらいだったと思います。
-日本と比べると、やや高いですよね。
須山 そうですね、量も多いんですけど。ただ、私の場合は、すごくお腹がすいていたので、たっぷり食べてましたから(笑)。レッスンだけでもお腹が空きますからね。
-皆さんも、疲れてたくさん食べるって聞きますよ。カフェではお菓子も食べられたんですか?
須山 はい。お昼とおやつを食べたり、夕飯とデザートを食べたり。それこそ、ザッハトルテとか、ケーキとか、思う存分食べてきました(笑)。あとは、ウィーンの郷土料理の、ヴィーナシュニッツェルも食べました。
-それはどういう料理なんですか?
須山 牛や豚のカツレツです。シュニッツェルセンターというのがホテルの近くにあって、そこにも通いました。ヴィーナシュニッツェルのファーストフードみたいなものなんですけど。
-どんなソースなんですか?
須山 ソースはかかってないですね。塩コショウで、すごくシンプルなんです。
 -今後行かれる方にはぜひ食べてもらいたいですね。さて、日本人の方が多かったということですが、海外の人と交流することは少なかったんですか?
-今後行かれる方にはぜひ食べてもらいたいですね。さて、日本人の方が多かったということですが、海外の人と交流することは少なかったんですか?
須山 お店の方とはお話しする程度でしたね。
-そのときに上手くコミュニケーションするコツはありますか?
須山 笑顔と挨拶ですね。ガイドブックにも書いてあったのですが、お店に入るときも、挨拶をするように心がけました。そうすると皆さんも笑顔で返してくれるので。
-特に困ったことやトラブルはありましたか?
須山 大きなトラブルは特になかったんです。ひとつ挙げれば、前日に大学の下見に行ったんですね。そのときは地下鉄を使ったんですけど、地下鉄からホテルに帰れなくなって・・・(笑)。友達も一緒だったんですが、どうしても分からなくなってしまって、近くの方に聞いて教えてもらったりして、なんとか無事にたどり着いたということがありました。
-現地の人も親切だったんですね。
須山 本当に親切でしたよ。片言の英語で話しかけたんですけど、すぐに英語で答えてくれましたし。
-英語は皆さん話せるんですね。
須山 はい。お店の方も英語で対応してくださいました。
-ドイツ語が話せるほうがベストだけれど、英語でも困らないんですね。
須山 はい、お店での会話ならそれでも。観光客の方も多いので、お店の方々は、日ごろから英語を話してらっしゃるんでしょうね。
-今回講習会に参加して良かったことは何ですか?
須山 もちろん、ウィーンの文化に触れることが出来たのも嬉しかったんですけど、講習会の中で、 ベーゼンドルファーザールで演奏する機会があるっていうのが、しおりに書いてあったので、そういう機会があったらいいなって思っていたんです。そうしたら運良く、そこで弾けることになりまして。私はベーゼンドルファーが好きなので、夢のような場所で演奏できて、とても感激しました。
-素晴らしいですね!今後の自信にもなりますね。では、日本とウィーンとで大きく違う点は何ですか?
須山 日が暮れるのが遅かったですね。9時くらいにやっと暗くなる感じで。日本でいるときの感覚からしたら、「あれ?もうこんな時間?」っていうのことがありました。
-電車などの交通が遅れたりとかはしなかったんですか?
須山 トラムは、バスみたいな感じで、少し遅れることはありましたけど、大幅な遅れはなかったですね。あとは、また食べ物の話ですが(笑)、料理を注文してから来るまでの時間が長かったです。日本だとクレームがつくくらいでしょうか、平均で30分は待ってましたね。ですから、コンサートに行く前などは、余裕を持ってご飯を食べに行ったほうがいいと思います。
 -今後留学する人へ、何かアドバイスはありますか?
-今後留学する人へ、何かアドバイスはありますか?
須山 私の場合は、西洋音楽の歴史がすごく遠いものだったんです。それが、作曲家のゆかりの地などを訪ねたりして、「こういう所からこういう音楽が生まれたんだな」って実感できて、身近に感じられるようになりました。想像以上のものを感じられたので、ぜひ、皆さんにも、実際足を運んでみてほしいなと思います。
-では、留学前にしっかりやっておいたほうがいいことはありますか?
須山 私の場合は、語学をもうちょっとやっておいたほうがよかったと思いました。片言の英語でも通じるのですが、ドイツ語も少しはやっておいたほうがいいと思います。メニューを見るときや、標識を読むときなども苦労しましたので。通りの名前も細かく書いてありますし、地図も見やすいので、最低限それが読める程度の語学力があればいいと思います。
-留学を経て、今後の進路は?
須山 今、大学4年生で、大学院に進学を希望しているのですが、試験が1ヵ月後なのでまだ分かりません。神戸女学院の大学院があるので。そのまま進めたらいいなと思っています。
-試験では何曲弾かれるんですか?
須山 4曲です。40分程度のプログラムを組まなくてはいけないんですよ。
-いつかまたウィーンにも行ってみたいですか?
須山 はい! すぐにでも行きたいです!
-今度は研究として留学されるのでしょうか、演奏家としてなのでしょうか。
須山 演奏家としてでしたら嬉しいですね。
-今後の活躍を期待しております。本日はありがとうございました。
簾田勝俊さん/フルート/ミステルバッハ国際夏期音楽マスタークラス/オーストリア・ミステルバッハ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 簾田勝俊さんプロフィール
簾田勝俊さんプロフィール
プロフィール追加
2009年夏、ミステルバッハ国際夏期音楽マスタークラス において、カーリン・レーダ教授のコースを受講。
-まずは、現在までのご経歴を教えてください。
簾田 高校1年生のときにブラスバンドに入り、フルートを始めました。でも、進学校でしたから1年で辞めたんですけど。
-では、フルートは、ご趣味として練習を重ねてきたんですか?
簾田 いえ、それからずっと遠ざかっていまして。2年半前、57歳の時ですが、キヤノンという会社を辞めて独立し、会社を興したんです。それで、自由時間が出来たものですから、数十年ぶりに再開したというわけです。レッスンにも2年半前から通っています。
-では、講習会に参加されるのは全く初めてだったんですね?
簾田 はい。日本では、新日本フィルの方のレッスンなどを受けたりしたこともありましたが、海外は始めてです。
-これまでに海外に行かれたご経験は?
簾田 はい、仕事を含めてしょっちゅう行っています。
-どこが一番思い出深かったですか?
簾田 世界中ですからね(笑)。個人的には、北欧が好きですね。写真展でも北欧の写真が多いですよ。
-今回、このミステルバッハの講習会に行きたいと思った理由は何だったんですか?
簾田 仕事もあるので、スケジュールが合ったというのが一番の理由ですね。ニューヨークで写真展があったりしましたから、しょっちゅう行ったり来たりは出来ませんし。実は、モーツァルテウムも気になったのですが、オーディションがあるということだったので諦めました。落ちたらやだなと思って(笑)。ミステルバッハはオーディションがないですし、誰でもコンサートに出られるというところが魅力でしたね。
 -講習会の参加者はどのくらいでしたか?
-講習会の参加者はどのくらいでしたか?
簾田 フルートだけで15人くらいです。
-どんな人が参加されていましたか?
簾田 ほとんど学生でしたね。一番若い子は、13歳でした。コンクールで優勝して、そのご褒美として参加していたみたいですけど、かなり上手かったですね(笑)。オーストリア人がほとんどでした。僕以外は、生徒も先生も顔見知りのようでしたね。先生が普段も教えている生徒もいたみたいです。僕は、世界各地から集まってくると思っていたので 、そこは予想と少し違っていました。それはそれで良かったですけど。
-アジアの方はいらっしゃらなかったんですか?
簾田 台湾の子が二人いましたけど、その子たちもオーストリアに留学している子たちでしたね。
-スケジュールはどんな感じでしたか?
簾田 8日間の中で、1時間のレッスンが5回くらいありました。夜はアンサンブルの練習をしましたし、かなり充実していましたね。先生たちのコンサートも含めて、コンサートは3日間ありました。
-先生はどんな方でしたか?
簾田 3人いたんですが、まずカーリン・レーダー先生というウィーンの音楽院の教授がメインで教えてくれました。そして、イタリアの大学で教えてらっしゃる方、もう一人はイスラエル出身のオーストリアの大学の先生でした。それぞれ個性的で面白かったですよ。
-皆さんフレンドリーでしたか?
簾田 そうですね、とてもフレンドリーでしたよ。僕が写真を撮るのを分かっていて、写真を撮ってほしい先生とかもいましたし。いい写真をたくさん撮れたのも良かったですよ。とても美しい生徒もいたから(笑)、レッスン中なんて、ものすごくいい絵になりますし。写真家としても、なかなかそういう機会には恵まれないですからね。
-ぜひ拝見したいです!
簾田 日本でも写真展やると思いますから、見てください。
-レッスンではどんなことを教わりましたか?
簾田 今やっている教わりたい曲を中心に教えてもらうのと、コンサート用のレッスンです。コンサートにおける心構えや姿勢、気持ちのもっていき方とかを教えてもらって、非常に勉強になりました。音楽は人に聴かせるものだっていう考え方とか、やはり違うなって思いました。日本では、練習することが重要なんだっていう考え方ですからね。国民性の違いもあるでしょうが、やはり音楽の国だなと思いましたね。僕も、もともと人前で演奏するのが好きだし、人に楽しんでほしいなという思いを持っていたので、合っていましたよ。日本のレッスンでは、オーケストラに所属している子や音大を卒業した子などもいますが、積極的に前に出て行くということは、あまりしませんからね。
-日本人の国民性でしょうかね。
簾田 「オーケストラに入っていても首席はやりたくない」とか言う人もいますよ。何でだろう?みたいな(笑)。僕は、下手でも首席やらせてくれないと面白くないって思うタイプだし、コンチェルトでも「ソロやらせてくれないかな」とか(笑)。今回の講習会でも再確認しましたが、音楽っていうのは、人を気持ち良くさせるというか、そういうのも重要な要素ですので、そのために練習するのが大事なんですね。
-良い勉強になったんですね。日本の曲を演奏されたそうですが、反応はいかがでしたか?
簾田 「春の海」ね。受けましたよ。コンサート後に、この譜面くれないかって言う先生もいました。日本にも聴かせる曲があるんだ、ということを見せられたのは非常に良かったです。「来年は、絶対モーツァルトのコンチェルトをやる」って言って帰ってきたんですけど(笑)。オーストリアですから、やはりモーツァルトもやりたかったんですよ。僕は、かぶれているわけじゃないですけど、ヨーロッパは美術や芸術の面で素晴らしいものがあると思っていますので、もっと知りたかったんですよね。
 -やはり、聴かせる音楽という点では、日本とは違いましたか?
-やはり、聴かせる音楽という点では、日本とは違いましたか?
簾田 練習を聴いていても、日本とは根本的に違うなって思いました。あそこの雰囲気で聴くのもまた違いますしね。初日に、先生が弾いたのを聴いた時、ああやっぱり先生は違うなって思いましたけど、その後、生徒の音を聞いても、やっぱり音の流れが違うなって感じましたね。非常に心地良いんです。そういう心地良さが音楽の原点になっているのかなって思いました。音楽ではないですけど、僕の写真もそういうものが多いんですよ、静けさを感じるような心地良いものが。
-レッスンは、基本的にドイツ語だったんですか?
簾田 僕の個人レッスンは、ほとんど英語でしたね。他の生徒はドイツ語が多かったですけど。イタリアの先生は、英語のほうが得意だったので英語でしたが、基本的に二人の先生はドイツ語でしたね。
-言葉のほうは大丈夫だったんですね。
簾田 ええ、英語は。普段使っていますから。
-練習はどこででされていたんですか?
簾田 練習室は特になかったんです。自分の部屋がかなり広いのでそこでやったり、先生のレッスン室でやったりました。夏休みの間のドミトリーのような所でしたので、どこで吹いてもOKだったんです。
-自由で良かったですね。どのくらい練習しましたか?
簾田 僕はそんな長くないです、2時間くらいでしょうか。他の子は、朝から晩までやっていましたね。朝8時っていうと音が聞えてきましたから。
-レッスンや練習の時間以外は、何をされていましたか?
簾田 レッスン以外は、写真を撮っていました。僕は、オーストリアやドイツの田舎の風景が好きなので。非常にいい写真がたくさん撮れましたよ。歴史的な建築物がたくさんありますからね。
-街の様子はいかがでしたか?治安は良いほうですか?
簾田 オーストリアやドイツは、いろんなところに何十回と行っていますが、怖いことはないですね。ただ、若い女の子たちは分かりませんけど。ナイロビなんかに比べたら安全ですよ(笑)。オーストリアは夜9時にもなれば、レストランなども閉まってしまいますから。イタリアやギリシャは夜2時くらいまでは大騒ぎしてますけど。
-街の人の様子はどんな感じですか?
簾田 オーストリアやドイツは、基本的には真面目な人が多いですよ。日本みたいに繁華街が乱れているとかそういうのはないですね。そして、特にミステルバッハは田舎なので、夜にはほとんど人がいませんよ。スーパーなども6時には閉まってしまうような所ですから。ほとんど音楽しかやることがないっていう感じですね。
-音楽を集中して勉強したい人にはピッタリですね。
簾田 みんな音楽が好きですよね。参加者は小さい頃から音楽をやっている子ばっかりだから。僕くらいですよ(笑)。でも、行ってよかったと思います。まあ、海外にあまり行ったことのないような男性だったら、少しキツイかもしれませんが。孤独になっちゃうかもしれないから(笑)。僕は、音楽が好きな人なら、もっと来たらいいのにって思いますけど。
-どこかに遊びに行かれたりはしなかったんですか?
簾田 行きませんでしたね。その1週間くらいは音楽漬けでいたいと思ってましたから、良かったですよ。
-宿泊先は、寮だったんですね。
簾田 寮みたいな感じですね。いろいろな合宿の人も使うのでしょうか、ほとんど誰もいなかったです。ご飯も、簡単な朝食が出るくらいですから。
-管理人さんはいらっしゃらなかったんですか?
簾田 いなかったです。カーリン・レーダー先生と、彼女のご主人が中心になって面倒を見てくれたので、非常にこじんまりとした感じでしたよ。
-カーリンレーダー先生の対応はいかがでしたか?
簾田 非常に良かったですよ。ご主人も素晴らしい方でしたね。クラリネットとサックスの間みたいな楽器でアンサンブルに参加してくれたり。演出が好きな方で、野外コンサートのときのライティングなどは、素晴らしかったですよ。僕が持っていった写真データを使って、日本の曲のときは日本の写真を壁に投影したりして。観客はワインを飲みながら、それを聴くっていう雰囲気を作ってくれたりしました。夫妻が住んでいるところが車で10分くらいのところらしく、いろいろ世話を焼いてくれて楽しかったですよ。
-宿泊先から講習会場へは、どうやって移動していたんですか?
簾田 一緒の場所だったんです。コンサートだけがシティホールだったんですよ。
-ご飯は、どうされていたんですか?
簾田 朝はパンとハムとチーズ、あとは果物がちょっとある程度です。昼は、みんなでピザを取ってつまんだりという感じでした。夜は、アンサンブルの練習を毎晩6時から10時くらいまでやっていますから、その後みんなで飲みに行ったりしました。食べるものはソーセージくらいしかないんですけどね。質素そのものです。
-外食でも安く上がるんですね。
簾田 ええ。ミステルバッハには、日本のように何千円も何万円もするような食事をする場所はないですからね。まあ、千円も出せば腹いっぱいですよ。
-今回は、オーストリアの参加者が多かったということですが、海外の人と上手く付き合うコツはありますか?
簾田 僕は、写真の話がありますからね。相手も聞きたがりますし、僕はあまり苦労はしないですね。
-簾田さんは、積極的に話されるほうですか?
簾田 そうでもないですよ。向こうから必要なことを話しかけてきて、そこから話題になっていくという感じですかね。イタリア男みたいに、女の子に声を掛けまくるようなことはしないですよ(笑)。若い学生ばかりでしたが、ひとり中年の女性もいらして、その方も良く話しかけてきましたね。
-趣味的なものがあると、話しやすいんでしょうね。
簾田 そうですね。日本の中高年の男性で、留学される方はあまりいらっしゃらないでしょうけど。
-それがけっこういらっしゃるんですよ! ジャズピアノとかが割と多いですね。クラシックではバイオリンの方とかいらっしゃいますよ。
簾田 そうなんですか。フルートは全体的に女の子が多いですけどね。
-さて、留学中に何か困ったことはありましたか?
簾田 全然、何もなかったです。僕は何十回と行っていますが、ドイツ、オーストリア、フランスなどでは、今まで怖い思いをしたことは全くありません。今回も、ローマから飛行機が1時間半くらい遅れたんですけど、ドライバーが待っててくれましたし。真面目なお国柄だなと思いましたよ。
 -今回講習会に参加して、良かったと思う点は何ですか?
-今回講習会に参加して、良かったと思う点は何ですか?
簾田 それはもう、最後のコンサートですね。若い子たちが、みんなで親指を突き上げて、日本語で「良かった!良かった!」って言ってくれたことです。日本人ピアニストの渡辺さんから教わった言葉らしいんですけどね。アンコールではないのですが、演奏後、もう一回舞台に立って拍手を浴びたのが嬉しかったですね。
-それは素晴らしいですね!日本人が日本の曲を演奏したのも良かったのでしょうかね。
簾田 一番感激してくれたのは、オーストリアの大学から来ていた先生ですね。カーリン・レーダー先生が忙しくて来れない時、舞台のリハを見てくれたんですが、演奏後にハグをしてくれたりして。確かに、「春の海」をフルートで演奏するのとても良かったですよ。日本の誇る名曲だなって思います。
-現地の方は、日本の曲を聴く機会もなかなかないでしょうからね。
簾田 カーリン・レーダー先生が、「絶対受けるから、この曲を演奏しなさい」っておっしゃって。でも、日本の曲とはいえ、勉強になりましたよ。やはり人に聴かせる音楽としての教え方ですよね、楽譜どおりに弾きなさいというのではなく。そういう教わり方をしたことはなかったので、勉強になりました。
-教え方も国によって違うんですね。
簾田 やはり、あれだけのものを作り出す国ですものね。僕は、クラシックの専門家ではないですが、クラシック音楽って良く出来ているなって思いますよ。僕はずっと技術屋として、もの作りをしてきましたから、音楽も「どうしてこんなものが作れるんだろう」って、もの作りの観点からも感動してしまったんですよね。そういう面でも、行って感じられて良かったと思います。僕は、やはり感動から物事が始まるって思っていますから。
-ブログを拝見しても、良い経験をされたというのが伝わってきました。では、留学に参加してみて、自分が変わったなって思うことはありますか?
簾田 この年だから簡単には変わりませんが(笑)、先ほども言ったように、音楽に対する見方は変わりました。本質に近いものを感じられて良かったです。その環境にいないと聴こえない音っていうのもありますから。それと、音楽や絵画、写真でもそうですが、人に感動を与えることが大事だなって、今まで以上に感じました。ヨーロッパでは、どんな小さい街でも、コンサートをやっていますから、そういう感動に触れる機会が非常に多いでしょう。日本ではなかなかないですからね。
-音楽に対する姿勢は、日本とは違いますか?
簾田 ヨーロッパでは、音楽そのものを学ぶことが大事だっていうか、本質的なものを勉強する考え方ですが、日本は、ロビー活動が重要視されるような感じが、少なからずありますからね。
-では、今後留学する人へアドバイスをお願いします。
簾田 積極的に行ったほうがいいと思います。
-「行きたいけど行けない」って言っている人ほど、行ったほうがいいですよね。
簾田 僕は、長年小さいオーケストラに入っていますが、向こうのアンサンブルの指導を受けてみて、やはり全然違うなって思いましたからね。カーリン・レーダー先生のご主人を見てても思いました。アンサンブルのとらえ方や、体の使い方までも違いますから。今回、垣間見ただけですが、本気でやるんだったら、海外で勉強することはいいことだと思いますよ。
 -では、簾田さんの今後の音楽活動について教えてください。
-では、簾田さんの今後の音楽活動について教えてください。
簾田 音楽でメシを食おうとは思っていませんけど(笑)、機会を作ってできるだけ演奏したいです。すぐ近くに信州国際音楽村っていうのがあって、そこの屋外の木の舞台に上がって、一人で演奏したりとかするんですが、観客が一人二人で手を叩いてくれるだけでも嬉しいですからね 。この前も外で吹いてたら、「おじさんすごいね、フルート吹いているの?」って声かけられたりして。田舎ですから、普段あまり聞く機会がないと思うんですよ。なので、ここで小さい子どもたちにフルートを教えたりもしたいとも思いますね。本当は、犬がいなければ、2年や3年ヨーロッパに行ってみたいんですけど。スロバキアの大学一年で卒業できるとかいうプランもあるようなので、そういうのいいかなって思うんですよ。1年くらいは音楽の専門の勉強をしたいなって思います。でも、犬がかわいそうですからね(笑)。
-せっかく見せる音楽を学ばれたので、演奏する機会がたくさんあるといいですね。
簾田 若い子たちは一生懸命音楽をやっていますけど、もっともっと人前で演奏するということをやったらいいと思いますよ。 ・・・あなたは音楽をやっていたんですか?
-私は中学、高校とピアノを専門で学んでいましたが、才能がなくって・・・。
簾田 そうですか。でも、若いときに、自分の才能の限界は決めちゃいけないって思いますよ。僕も昔は、才能が必要だと思っていたんですが、今は、目標意識を高く持つことだなって、そういう気がします。僕の場合は音楽専門でやってきたわけではないからかもしれませんが、「音楽も出来る」っていうのが、とても嬉しいんですよ。少しでもやっていて良かったなって思いますから。才能のある人っていうのは、必ずいるんでしょうけど、音楽って一生懸命やれば、誰でも人に感動を伝えられると思いますよ。
-なんだか、とても励まされました!今日は本当にありがとうございました。
海瀬京子さん/ピアノ/ベルリン芸術大学/ドイツ・ベルリン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 海瀬京子さんプロフィール
海瀬京子さんプロフィール
静岡県出身。西島淑恵、高原節子、塩谷安圭美、播本枝未子、倉沢仁子、エレーナ・ラピツカヤの各氏に師事。東京音楽大学付属高校、同大学を経て同大学院修了。2004年第28回ピティナピアノコンペティション特級準金賞および聴衆賞、併せてロイズ賞、三井ホーム賞、王子賞を受賞。2005年第74回日本音楽コンクールピアノ部門第1位。併せて野村賞、井口賞、河合賞を受賞。2010年第17回アルトゥール・シュナーベルコンクール第1位。これまでに東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、セントラル愛知交響楽団、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団、群馬交響楽団、東京音楽大学シンフォニーオーケストラ等と共演。また、NHK交響楽団首席奏者メンバーと室内楽を共演。2007~2010年度(財)ローム・ミュージックファンデーション奨学生。現在ベルリン芸術大学に在籍中。
-まずは、簡単なご経歴をお願いします。
海瀬 5歳からピアノを始めまして、東京音大の付属高校に入学しました。そして、そのまま東京音大と同大学院を修了しまして、現在ベルリン芸術大学に留学中です。
-ずっと長く音楽をやっていらっしゃるんですね。最初に始めたのは、近所のピアノ教室ですか?
海瀬 はい。ただ、その前に始めは近所の音楽教室に入って、みんなとわいわい音楽を楽しんでいました。母が元音楽講師だったのでグランドピアノが家にあったりして、音楽が身近にある環境で育ちました。
 -本格的にピアノを学ぼうと思ったきっかけは?
-本格的にピアノを学ぼうと思ったきっかけは?
海瀬 ピアノを始めた頃から、なんとなく音楽家になりたいとは思っていたんです。具体的には、中学校くらいの頃から、早く本格的な教育を受けたいと思うようになりました。のちに教わることになる高校・大学時代の教授に教わりたいなって思ったとこから、本格的に音高受験を準備し始めたという感じですね。
-留学を決意されたきっかけは?
海瀬 実は、元々はあんまり留学のことは考えていなかったんですよ。運良く奨学金がいただけることになったので、留学を決意しました。
-奨学金はどの団体のものですか?
海瀬 ローム・ミュージックファンデーションです。大学院2年の時にいただいたんですが、その奨学金は、国内の学校でも海外の学校でも、最長4年もらえると言うものだったんですよ。なので、日本の大学院で残りの1年間分を使って、今のベルリン芸大が3年のプログラムなので、ちょうどいいなということで。
-ベルリン芸大を選ばれたということですが、決めるまでのいきさつは?
海瀬 日本の先生が、この先生がいいんじゃないかとおっしゃったんです。実際、受験する前に、現在の先生の前で演奏したところ、先生も気に入ってくださいまして。あと、都会に行きたいという思いもあったんです。いろいろな講習会を受けたりして悩んでいたんですが、ベルリンに来た時、しっくりきたんですよね。それで、やっぱりここにしようと思いました。
-どういった講習会に参加されたんですか?
海瀬 ザルツブルグとか、浜松でやってる浜松国際ピアノアカデミーなどです。
-今師事されている先生は、どんな方なんですか?
海瀬 エレーナ・ラビツカヤ先生と言うロシア人女性です。
-ベルリン芸大を志望されている方は非常に多いのですが、受験の内容や出願書類などについて教えてください。
海瀬 私の課程の試験は実技のみです。曲も、バッハ、古典のソナタ一曲と自由曲ですね。でも、とにかく受験者が多いので、試験は1次試験と2次試験にわかれて行われます。1次試験では2~3分しか弾かせてもらえなかったです。2次試験になると、もうちょっと長く弾けるんですが、それでも全部は弾かせてもらえなかったですね。その短時間で、とにかく結果を出さなきゃいけないので、それは大変でしたね。出願書類は、そんなに覚えていませんが、特に多くなかったと思います。願書と写真、成績証明書、卒業証明書、それと語学の修了証明書などです。
-結果はその場で分かるんですか?
海瀬 その日のうちにだいたいの結果は出ますが、会議を経て正式に決まるので、書類を待たなくてはいけません。人によっては、先生からの情報では合格だったのに、会議後書類が送られてきて不合格だった、なんて人もいました。
-志望動機書などはなかったんですか?
海瀬 そういうのはありませんでした。
 -試験の時の思い出を教えてください。
-試験の時の思い出を教えてください。
海瀬 すごく短くしか弾かせてもらえないと聞いていたので、私は、山を張ったというか、大体ここが出るだろうと予想して、そこだけ練習していたんです。でも、受験の直前に先生に聞いていただいた時、先生に「あなた、なんでここは弾かないの?」と指摘されたんですよ、あまり準備してなかったところを。「ここも出されるかもしれないから弾きなさい。」と言われたんです。それが、試験の4~5日前だったんですけど、急遽それを練習しましたら、実際、そこが試験に出たんですよ! やっぱり、ちゃんとやっておかないとだめなんだと思いましたね(笑)。
-レッスンしてもらって良かったですね!留学に関しての手続きは、ほぼご自分でされたんですか?
海瀬 ドイツ語が全然出来なかったので、ドイツ語の詳しい方に助けていただきました。もちろん全部ではなく、最初自分で書いて、最終チェックをお願いしました。
-では、手続きに関しては、そこまで苦労はされなかったんですね。
海瀬 はい。私は周りの方に恵まれていまして。こちらの先生とのやり取りも、大変素晴らしい先輩が親切にお世話をして下さいました。とてもありがたかったですね。
-そういう方がいると心強いですね。ちなみに留学準備はどのくらいから始めましたか?
海瀬 今の学校に決めてからとなると、半年ほど前からでしょうか。
-それまでドイツ語は勉強されてましたか?
海瀬 はい。ベルリン芸大は語学が厳しい学校でして、入学してから1年以内に、中級レベルの試験をパスしないと退学になってしまうんですよ。私は、大学でドイツ語を専攻してなかったので、慌てて1年前くらいから学校に通いました。けれど、実際はこっちに来てからはなかなか活かせなかったですね。最初はすごく辛かったです。
-ドイツに渡ってから、語学学校には行ってたんですか?
海瀬 はい、もちろん。毎日通っていました。最初の一年は、いったい何をしに来たんだろう?というくらい、語学ばっかりやっていました。そうしないと、試験にパスできないので。
-じゃあ最初の1年は語学学校に行きつつ、音楽はレッスンのみという感じですか?
海瀬 そうですね。今は語学の試験もパスしたので、レッスンのみです。そういうコースなので。ベルリン芸大は、とにかく自由な時間が多いんですよ。日本での成績証明書を見ながら、どの授業を取ったらいいか照らし合わせていくんですが、私の場合、たいていは日本で終えてきていたんですね。なので、室内楽とレッスンのみ取っています。室内楽は日本でもたくさん勉強していたのですが、なぜか取らないといけないことになりました(笑)室内楽というのも授業があるわけじゃなくて、3回本番をやればいいというものですし、レッスンも週に1回です。本番がある時は、追加でレッスンしてくださいますけど。
 -噂なんですが、先生の推薦があると、語学の成績に関して厳しくないというのは本当ですか?
-噂なんですが、先生の推薦があると、語学の成績に関して厳しくないというのは本当ですか?
海瀬 それはいわゆる力のある先生のみ、でしょうね。でも、そのような先生に師事していても語学試験は取らないといけないでしょうし、あくまで噂程度、ととらえていた方が良いと思いますよ。
-そんなに甘くないですよね。
海瀬 でも、たいていの方はクリアしてますので、それほど恐れる必要はないかもしれませんが、一生懸命やらないといけないのは確かです。
-学校の雰囲気はどんな感じなんですか?
海瀬 ベルリン芸大は大きいので、校舎も何個かに分かれていますから、みんなばらばらでよく分からないんですよね。特徴は・・・、自由に使える時間がたくさんあるということでしょうか。自分の時間がたくさんあると思います。だから、いかようにも頑張れるし、怠けようと思ったらいくらでも怠けられる。それはどこでも同じかもしれませんけど。
-ドイツの学校は、厳しいのかなというイメージがあったのですが。
海瀬 自己管理がきちんと出来ていないといけないと思います。中間試験などもないので、3年間で唯一の試験は、卒業試験ということもありえますから。日本の学校みたいに、一年に一回試験があるわけではないで、時間の使い方は、その人にゆだねられています。自由なようで、それはある意味では厳しいことだと思います。
-そうなんですね。学生さんは、みなさん一生懸命練習されているんですか?日本の学生ほど、みんな練習しないと聞いたのですが。
海瀬 私も本番前など以外はそれほどはしてない方だと思いますけど。日本人の中でも、人それぞれですかね。でも基本的にきちんと練習しているんじゃないでしょうか。あと、こっちの人は、休むときは休むってはっきりしていますね。日曜とかは、学校も空いているみたいですね。
-日本人留学生の方はけっこういるんですか?
海瀬 はい。ピアノだけで、10人以上いるんじゃないでしょうか。ベルリンには、もう一つ音大がありますので、そちらも合わせると、かなり多いと思いますよ。
-日本とドイツで大きく違うことは?
海瀬 重複しますが、時間の使い方が自由に出来るので、自分自身にかかっているということでしょうか。
-授業やレッスンは日本と違いますか?
海瀬 特に違いはないと思います。日本か海外かではなく、それは担当の先生によって違うものでしょうね。私が日本で師事していた教授は長くドイツにいらした先生だったので、その影響か日本にいた時からその時々の状況によってレッスン内容が全く違いました。私の出来によってはレッスンが成立せずに終わってしまう、なんてこともありました。海外だともっとルーズ、のようなイメージを持っているかもしれませんが、逆に今の先生の方が時間に合わせて進行されているので、それぞれ先生方によって違いますね。
-熱心な先生なんですか?
海瀬 そうですね。細かく見てくださいます。段階を踏んで教えてくださるというか。
-レッスンは、時間通りに始まりますか?
海瀬 はい。私が日本で師事していた先生は大変お忙しい方でしたので、3~4時間待つこともしばしばでしたが、こっちに来てからのほうが時間通りですね。生徒数も日本の比にならないほど少ないですから。遅刻しても、それもその生徒の責任って感じで、咎められたりしないんです。心の中ではむっとしているかもしれませんが(笑)。
 -学費は、奨学金でまかなえているんですよね。
-学費は、奨学金でまかなえているんですよね。
海瀬 はい。
-日本でしっかり勉強しておいた方がいいことはありますか?
海瀬 勉強の仕方というのか、音楽に向かう姿勢をきちんと確立しておいたほうがいいと思います。自分で作り上げる能力を持っておかないといけないですね。それがないと、軸がどんどんぶれていってしまうので。
-日本だと、先生主体で音楽を作っていくというイメージが強いですが、それはないんですね。
海瀬 ないですね。日本、海外に関係なく基本は自分で作り上げるものだと思います。ですから自分で作り上げる力を培っておかないといけないのではないでしょうか。やはり、先生によっては癖みたいなものもありますから。「これは先生の癖だ」と判断できるようになっていないといけないというか。
-いろんな先生に見ていただくというのはいかがでしょうか。
海瀬 それはいいことだと思います。先生によってはそれを嫌う方もいらっしゃいますけど。でも私は、いろんな見方を教えていただける貴重な機会だと思います。
-あと、やっぱりドイツ語は勉強しておいた方がいいですよね。
海瀬 それは100%そうですね。そうでないと、ストレスだらけになってしまいますから。私も未だに出来ないですけど、最初の頃は、外に出るのもイヤでしたから。
-ベルリンは、ドイツ語だけなんですか?英語もOKなんですか?
海瀬 ドイツ語ですね。私の先生はロシアの方ですが、英語は一切話せないので、ドイツ語かロシア語のみですね。ぜひ日本で勉強しておいたほうがいいと思います。
-日ごろの練習はどのくらいされていますか?
海瀬 家でやったり学校でやったりするんですけど、本番前になって、ようやく弾き始める感じなので・・・(笑)。2~4時間とかでしょうか。
-休みの日は、どこかに行かれたりすることが多いですか?
海瀬 特にはどこにも出かけてもいないんですけど、こっちに来てから、思いきってピアノから離れてみるということもしてみています。
-不安にならないですか?
海瀬 それはないですね。周りののんびりした雰囲気を見ていると、そういった時間を過ごしてみるのもいいのかもしれないと思って。そういった日常的な「余裕」を作ることによって、自分の音楽にも何か良い影響があるかもしれない、と思います。それと音楽マンションのような、防音の部屋ではないので、周りの方の生活を考えなくてはいけないですし。
-フラットで一人暮らしですか?
海瀬 はい。ピアノをレンタルして、家で練習しています。
-弾いてはいけない時間帯とかがあるんですか?
海瀬 一応、日曜の午前中は弾かないようにしているとか、夜も8時くらいまでにしてます。私のところは周りの方も理解のある方々なので。そこらへんはフレキシブルにやっていますね。
-いい家が見つかって良かったですね。
海瀬 そうですね。みなさん住宅事情で苦労されていますからね。学校では、2時間くらいしか練習出来ないので。日本と違って、普通のレッスン室で練習するので、先生がレッスンをしていると部屋の数が減ってしまうんですよね。
-2時間でも足りないのに、大変ですよね。
海瀬 そうですよね。だから、ピアノの人は、たいてい自分の家にピアノを入れています。
 -学外でのセッションやコンサートの機会は多いんですか?
-学外でのセッションやコンサートの機会は多いんですか?
海瀬 それもやはり、コネクションでしょうか。力のある先生のところですと、そのつながりで声がかかってくるみたいですが、私の先生はそういう方ではないので、自力で頑張って機会を作っていかないとなかなか無いです。なので、学外での演奏の機会はあまりないですね。
-何かに出演されたりしましたか?
海瀬 友達と室内楽をやったり、学内で行われたコンクールに出場しました。知人の方からリサイタルの話を紹介していただいたり、来年はコンクールの副賞でベルリンでもリサイタルの予定があります。
-やっぱりコネクションって大事ですね。現地の音楽の業界のツテは出来るのもですか?
海瀬 それもやっぱり先生によるかもしれませんが、基本的にはコンクール受けたり、自分でチャンスをつかむことが大事だと思います。
-留学生の皆さんは、コンクールとか受けてるんですか?
海瀬 はい。ドイツ国内外に限らず、受けてると思います。
-そういうところからプロへの道を開拓されているんですね。海瀬さんの一日のスケジュールはどんな感じなんですか?
海瀬 家にいる場合は、練習してご飯食べて練習して、っていう感じですね。出かける時は出かけますけど。特別なことはしていないです(笑)。
-お友達は、現地の方が多いんですか?
海瀬 どうしても日本人の方が多いですね。外国人のお友達は少ないです。少しだけ韓国の友達がいますけど。
-韓国の人だと、ドイツ語を練習し合えますしね。
海瀬 はい。お互い同じようなテンポなので(笑)。
-ベルリン芸大は、留学生も多いんですか?
海瀬 すごく多いです。私の周りで、ドイツ人ってあまりいないんじゃないでしょうか。アジア人がたくさんいます。特に日本人と韓国人。学校全体でもそうだと思います。
-海瀬さんのところの門下では、どんな比率ですか?
海瀬 日本、韓国、ロシア、アイルランド人などですかね。西洋人が3~4人くらい、5~6人がアジア人という感じです。
-でもドイツ語が必要なんですよね。
海瀬 守衛さんや事務局の人は全員ドイツ人なので。そういう方々とのやりとりも必要ですからね。
 -日本人以外の国の人とうまく付き合うコツはありますか?
-日本人以外の国の人とうまく付き合うコツはありますか?
海瀬 私は、外国人の知り合いが少ないので・・・。積極的に話しかけたり、輪に加わっていくというのは大事なんじゃないでしょうか。
-そうですよね。やはり話題は音楽のことですか?
海瀬 他愛もない話ですね、芸能ニュースやサッカーの話など、共通の話題を見つけて話しています。
-住む場所も、自分で探されたんですか?
海瀬 たまたま先輩が同じところに住んでいらして、そこが空いているよと紹介していただいたんです。
-ラッキーでしたね。
海瀬 そうですね。その先輩は、前から知り合いだったのではないんですが、受験前に先生に会いに行ったとき、レッスンの時間が、たまたま前後してたんです。そのとき、「あ、この人日本人だ!」と思って、レッスンが終わるのを待ち構えて話を聞いたんです。そしたら、同じアパートの部屋が空いていると言うことで、大家さんにお話してもらうようにお願いしたんです。
-自分から話しかけたことによって見つけられたんですね。
海瀬 気になることがあったらどんどん聞いて、スパッと決めていかないと。特に住宅は、みんながいい所を探していますからね。
-悩んでいる暇があったら行動しないとって感じですね。大変な部分もあるかと思いますが、留学して良かったと思う瞬間はどんな時ですか?
海瀬 言葉が分からなくてストレス感じたり、レッスンで自分にない部分を指摘されて悔しく思う時こそ、留学している醍醐味を感じますね。ベルリンには世界でも超一流のオーケストラやオペラがあります。そこに良く足を運ぶのですが、そういった一流のものに間近で触れられた時なども、留学して良かったと思う瞬間ですね。
-そこで自分が変わったなとか、成長したなって思うのでしょうか?
海瀬 自分ではまだよく分からないですけど・・・。でも、日本に帰ったとき、先生に久々に聞いていただいたりして、「変わったね」とか「良くなったね」みたいに言ってもらえると嬉しいですね。
-こんなこと知らなかった、とかいう発見はありますか?
海瀬 ありますね。私はとにかく音色の種類を増やしたいと思って来たので、そういう面で、先生も細かく指摘してくださいますから、新しい発見はたくさんあります。
 -それをどんどん習得している最中なんですね。
-それをどんどん習得している最中なんですね。
海瀬 毎回毎回、同じようなことを言われてしまうので、成長してないなってがっかりするときも多いですけどね。くじけそうになりますけど、ここで諦めるわけにはいかないっていう気持ちで頑張っています。
-前向きに考えられて素晴らしいです。ベルリン芸大なんてなかなか入れない学校ですし。海瀬さんが受けられたときは、どのくらい受験者がいてどのくらい合格されたんですか?
海瀬 130人くらい受験して、5~6人ですね。前に受験していて、入学時期をずらしてくる人もいるんですけど、その人たちを入れても10人くらいでしたから。
-試験官はどのくらいいらしたんですか?
海瀬 1次試験は午前午後に分かれていて、それぞれに分かれて先生がいるんですけど、2次試験は全教授が来ていましたね。
-それは緊張しますね!
海瀬 でも、フレンドリーな感じでしたよ。それよりも、ベルリン芸大の試験は、すごく大きなホールであったのですが、響きがかなりないところなんです。だから慣れていないと大変ですね。先生方は和やかでしたけど、ホールに対して緊張しました。
-今は2年生ということですが、卒業されてからの進路はどうお考えですか。
海瀬 私は最終的に日本に帰って、日本で音楽活動をしていきたいと考えています。
-プロのピアニストを目指されるんですね。
海瀬 なれるかなれないかは別ですけど。あとは、教えたりして音楽で生きていけたらと思います。
-音楽教授を目指したいとかはありますか?
海瀬 もし、そういったチャンスがあれば、ですね。
 -最後に、これから留学する人にむけてのアドバイスを。
-最後に、これから留学する人にむけてのアドバイスを。
海瀬 今は、ある程度のお金さえあれば、音楽的なレベルに関係なく比較的誰でもが留学しやすくなり、インターネットで簡単にどこでもつながれる時代だと思います。飛行機で簡単に日本と行き来も出来ます。街中には日本人もたくさんいて、日本のものも簡単に手に入ります。一昔前の先輩方が留学していた時の苦労を思うと全く状況は違うと思うので、なぜ自分は留学するのかということを、心に決めてから来た方がいいと思います。まずは「行ってみたい、見てみたい」という好奇心があることが大前提だと思うのですが、今の時代でしたら、何かしら自覚を持っていかないとブレてしまうと思うんです。ある程度、留学に対する大きな目標を持つというか、自分は最終的にどうなっていたいのか、というのを考えてくるのも大事だと思いますね。人によってはとりあえず来てから考える、というのも良いのでは、という方もいらっしゃいますが。現在はどこに行っても留学生もたくさんいて、私の周りで、とりあえず来たけど、語学も出来ずにどうしていいか分からないという人もいて、そういう人はトラブルに巻き込まれたりしています。ですから、自分の中に一本考えを持ってきたほうがいいと私は思います。
-しっかりした意思を持っていないと、せっかくの留学を活かせないということですね。
今日は、参考になるお話をたくさんお聞かせ下さって、本当にありがとうございました!
--------------
海瀬京子ピアノリサイタル
開演: 2010年10月8日(金) 19時...(18時30分開場)
入場料金: 3,500円
会場: トッパンホール 112-8531 文京区水道1-3-3 tel:03-5840-2200
主催・お問い合わせ: カノン工房 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
広瀬ゆう子さん/ヴァイオリン/ウィーン国際音楽ゼミナール/オーストリア・ウィーン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。
 広瀬ゆう子さんプロフィール
広瀬ゆう子さんプロフィール
二歳からバイオリンを始める。慶應義塾大学中退。ウィーン国際音楽ゼミナール参加。
— 現在までの略歴を教えて下さい。
広瀬 二歳の頃からバイオリンを始めて、はじめは鈴木メソッドに通っていました。本当にバイオリンが好きで、「バイオリンを続けるか、幼稚園に行くかどちらにする?」と両親に聞かれて、「バイオリン!」と答えたほどでした。途中体調を崩した事もあって、自宅近くのバイオリン教室に変わりました。ドイツから帰国されたばかりの有名な先生だったのですが、そうと知らずに入りました。中学生の時にジュニアオーケストラに入団したんですが、経営難で潰れてしまって‥それでシニアオーケストラに入りました。高校に進み、その後音楽大学へ進学したい気持ちもあったのですが、「堅実な人生を歩んでほしい」という両親の希望で慶応大学に入学し、その際ユースオーケストラに移りました。大学では室内楽のサークルで活動していました。
— 今までバイオリンを中断したことはないのですか?
広瀬 じつは高校の吹奏楽部の時に少しだけあまりやっていない時期があります。シニアオーケストラでドヴォルザークの『新世界』を演奏した時に、管楽器が素晴らしいと思ったんです。それで私も木管楽器をやってみたいと、浮気心がでちゃいました(笑)。中学校では少人数の合唱部に所属していたので、大所帯の部に属してみたかった、というのもあって、高校の吹奏楽部に入りました。でも実際に入部してみると、木管楽器はとても人気があって、経験者が優先されたので、チューバの担当になっちゃいました(笑)。今はもうチューバは演奏していませんし、マウスピースも高校に置いてきました。その間は部活動が忙しくて、バイオリンは週に一度程度しか弾けませんでした。それも親から決められて一時間だけだったんですが、まったく弾かない時期はないですね。
— いつ頃から留学したいと考えていましたか?
広瀬 高校時代からドイツにバイオリン留学したいという思いがありました。海外のディプロマコースの存在を知って、社会人になった後で、働いて貯めたお金で留学することができる、いつかは音楽で夢を叶えたいと思っていました。
— 何がきっかけですか?
広瀬 大学2年生の時に体調を崩して退学せざるを得なくなってしまい、それからは派遣社員として社会に出ました。その頃、よく悪夢にうなされていて‥。夢にバイオリンの先生が出てきたんですよ。音楽をやれと私に言っているようでした。それで音楽を志すことに決めました。そうしたら、たまたま友人がドイツ留学すると言うんです。私が前からドイツに行きたかったのに、「先にドイツに行くなんてずるい!私も行く!」と(笑)。バイオリンの先生がハンブルグ交響楽団の客演コンサートミストレスだったこともあって、ドイツには前々から興味がありました。ノイシュバンシュタイン城(シンデレラ城のモデルとなったミュンヘン近くの城)が大好きで、ドイツ語も好きだったんです。
— 実際にはオーストリアのウィーン国際音楽ゼミナールに参加されていますが?
広瀬 最初はドイツに行きたかったんです。ですが、ドイツのコースはオーディションで聴講生と受講生に分かれるような、レベルの高い講習会だったので、まずはウィーンを検討することにしました。いずれは長期留学をしたいのですが、これまで海外に行ったことがないので、まずは短期から、と考えて、アンドビジョンのスタッフの方に薦めていただいたウィーン国際音楽ゼミナールにしました。よく考えてみると、私は英語しか話せないので、ドイツだと田舎に行ってしまったら言葉が通じなくなるおそれがあるけど、ウィーンだと都市だから英語が通じて安心だな、と思ったんです。それに、ウィーンからだとミュンヘンも近いので、帰国する際にドイツに寄ることもできるかと。ゼミナール終了後、本当にミュンヘンやノイシュバンシュタイン城にも寄って帰って来ることができたんですよ。
 — 準備期間はどのくらいでしたか?
— 準備期間はどのくらいでしたか?
広瀬 3ヶ月ほどでした。あっという間でした。
— 学費はどのように捻出されたのですか?
広瀬 派遣社員として働いていたお金と、子供の頃からのお年玉や入学祝などの貯金に、祖母からもらった成人祝いを足しました。
— ウィーンでは実際に英語が通じましたか?
広瀬 そうですね。ホテルや大きいお店、チケット売り場などでは普通に通じました。観光客が行くような場所では大概通じたと思います。ですが、バーなどに行くと、マスターは話せても、その奥さんは話せなかったり、常連さんが話せなくて通訳してもらったりしました。私自身、父親の薦めで英語は小さい頃からやっていて、これまでも読み書きはできました。ただ、英会話のチャンスが日本ではなかなかないので、ウィーンに行ってからコツを掴むまではたどたどしいものでしたが、2週間ほどでそれもスムーズにできるようになりました。
— ドイツ語(オーストリアの公用語)は特別に勉強して行ったのですか?
広瀬 もともと語学が好きなので、独学で少しかじってはいたのですが、留学が決まってからは仕事もしていたので、なかなか時間がとれなくて‥。でも英語が通じるということだったので、語学の勉強をするよりは楽器を弾いた方がいいかな、と、特に勉強はしませんでしたが、挨拶程度はドイツ語で会話することができました。
— ツィエンコフスキー先生のコースを選ばれたのはどうしてですか?
 広瀬 ゼミナールのブロックⅡはポーランド人のツィエンコフスキー先生とロシア人のアレンコフ先生お二人の講師で、どちらに教えていただくか迷っていました。以前ツィエンコフスキー先生にレッスンを受けられた方が「ツィエンコフスキー先生はとてもよかったよ」と言われていたのと、バイオリンの先生に相談したら、どちらもお名前をご存知だったんですが、「ロシア人は厳しいらしいわよ」と言われたので、ポーランド人のツィエンコフスキー先生にしました(笑)。
広瀬 ゼミナールのブロックⅡはポーランド人のツィエンコフスキー先生とロシア人のアレンコフ先生お二人の講師で、どちらに教えていただくか迷っていました。以前ツィエンコフスキー先生にレッスンを受けられた方が「ツィエンコフスキー先生はとてもよかったよ」と言われていたのと、バイオリンの先生に相談したら、どちらもお名前をご存知だったんですが、「ロシア人は厳しいらしいわよ」と言われたので、ポーランド人のツィエンコフスキー先生にしました(笑)。
— ツィエンコフスキー先生にレッスンを受けてみて、いかがでしたか?
広瀬 大変気さくな方で、レッスン中はもちろん真剣に教えてくださるんですが、普段はフレンドリーに接してくださいました。今まで習った日本人の先生達と違っていたのは、本場ヨーロッパ、ウィーンの、最先端の演奏を教えてくれたことです。たとえば、「チャイコフスキーの第2楽章はコンソルディーノ(ミュートを付けて)と楽譜には書いてあるけれども、作曲した当時は規模が小さい所で演奏していたからで、現在は大きなホールで弾くから基本的にはミュートは付けずに弾くんだよ」と。それが今回の留学で一番感動したことです。弓順も、カール・フレッシュ版よりも、ペーター版よりも、オイストラフ版の楽譜がいいよ、と教えていただきました。それに、私のレベルに合わせて、具体的に私のテクニックの悪いところを指摘してくれて、とにかく真剣に教えてくださいました。自分のレベルとはちょっと違うな、ということは一度もありませんでしたね。他の生徒さんにも一人一人のレベルに合った指導をされていました。
— それでは一時間はあっという間でした?
広瀬 はい、あっという間でした(笑)。
— レッスンは何人で行われるんですか?その中に日本人はどのくらいいました?
広瀬 十三人ほどで、日本人は三分の一くらいかな?韓国人と足したら半分くらいだったと思います。なかにはウィーン国立音大に合格して、ツィエンコフスキー先生の門下生としてこの後入学する、というポーランドの男の子もいましたが、アジアの方が多かったですね。音大生の方や音大浪人の方が多かったのですが、日本人で、音大卒業後に自分でお教室をされているという方も参加されていました。
 — レッスンはどんな形で進められましたか?
— レッスンはどんな形で進められましたか?
広瀬 最初はコースごとにみんなで集合して、レッスン日と時間を決めました。ツィエンコフスキー先生の場合はその後すぐレッスンだったんですが、なかにはバイオリンを持って来ていない生徒もいました。時間は朝の9時から遅くても夕方の4時くらいには終わる感じです。自分の弾きたい曲を希望して教えてもらって、基本的にはレッスン一回に一曲、私は全部で五曲教えてもらいました。毎日レッスンを受けていた方は結構大変だったと思います。私の場合、途中体調を崩して入院してしまったので五曲でした。入院前後はアンドビジョンや講習会のスタッフの方がちゃんと連絡をとってくれて、意向を酌んで体調が回復した後半にレッスンを集中していれてくださり、臨機応変に対応してもらうことができました。
— 周囲の人の学習態度は日本とは違いましたか?
広瀬 そうですね、何分日本人が多かったのですが(笑)。それでも、韓国人の方などは先生がいらっしゃる前からピアノと合わせていたりして、レッスンに参加されている時点で意欲的な方が多いな、とは感じました。
— 現地でのレッスン以外の練習はどうされていましたか?
広瀬 ホテルの自分の部屋で練習していました。時間が決められていて、9時から12時と、14時から20時まででした。
— レッスン以外の時間はどうされていました?
広瀬 そうですね、練習以外の時間は観光を楽しみました。シェーンブルン宮殿からハイリゲンシュタット(ベートーベンゆかりの地)まで、くまなく周りました。駅の近くに、行きつけのバーまでできて、地元の方との交流を楽しみました。他のレッスン生も、どこにも観光に行かなかった、という人はいなくて、シェーンブルン宮殿だけには行ったとか言っていました。ちなみに、シェーンブルン宮殿よりも、私は王宮宝物館の方がお薦めです(笑)。
— どうやって現地の方と交流したんですか?
広瀬 高校の英語の先生から、「日本の5円玉は穴が開いていて、貨幣としてとても珍しいから、海外に行く時は持って行くといいよ」と聞いていたので、留学が決まってから一所懸命5円玉を貯めていました。でもホテルでは「これ、コインランドリーで見つけた」とか言われてあまり‥(笑)。
それから、千代紙を1セット持って行きました。電車の中とかで鶴を折っていると、周りの人が珍しそうにジーッと珍しそうに見てくるんで、差し上げるととても喜んでもらえました。日本のこと知っている方には「オリガミー!」って言われて(笑)。知り合った5歳くらいのイタリア人の女の子には作り方を教えてあげました。その子のお母さんが手伝って、お父さんがビデオまで撮って。そしたら、その女の子がお礼にと、左右の頬に唇を寄せる挨拶、あれをしてくれたんです。すごく嬉しかったです!折鶴はきっかけとしてとてもよかったですね。ホテルでチップを置くときに一緒に添えておくと、一緒に持って行ってくれていました。
— 宿泊先のホテルはどうでしたか?
 広瀬 とてもよかったです。スタッフのみなさんとても親切で、ほかのレッスン生から聞いた話にだと、朝食が7時からと決まっていたんですが、それよりも早く出なければいけない時があって、フロントに相談すると、早い時間に合わせてお弁当を作ってくれたそうです。宿泊とセットになっている朝食がとても美味しかったです。ハムが何種類もあって、ズッキーニがシャキーンとしていて。蜂蜜やヘーセルナッツバターや、ジャムがたくさんありました。ジュースも何種類も用意されていたし。ホテルには共同ですがキッチンも使えますので、自炊できます。近くにはスーパーがありますし、部屋も、とびきり新しい、というわけではないんですが、ちゃんと綺麗に掃除されていて、広くて。ちなみに2人部屋より1人部屋の方がバスルーム広いです(笑)。
広瀬 とてもよかったです。スタッフのみなさんとても親切で、ほかのレッスン生から聞いた話にだと、朝食が7時からと決まっていたんですが、それよりも早く出なければいけない時があって、フロントに相談すると、早い時間に合わせてお弁当を作ってくれたそうです。宿泊とセットになっている朝食がとても美味しかったです。ハムが何種類もあって、ズッキーニがシャキーンとしていて。蜂蜜やヘーセルナッツバターや、ジャムがたくさんありました。ジュースも何種類も用意されていたし。ホテルには共同ですがキッチンも使えますので、自炊できます。近くにはスーパーがありますし、部屋も、とびきり新しい、というわけではないんですが、ちゃんと綺麗に掃除されていて、広くて。ちなみに2人部屋より1人部屋の方がバスルーム広いです(笑)。
— バスタブ付きですか?
広瀬 バスタブはさすがにないです。
 — ドライヤーはありますか?
— ドライヤーはありますか?
広瀬 部屋には付いてないんですが、フロントに言えば貸してもらえました。
— 生活費はどのくらいかかりましたか?
広瀬 そうですね‥。食費の金額で変わってくると思うんですが、高級なレストランや日本食店は、それはもちろん高いです。でも、駅前とかにおっきなピザが2ユーロくらいで売ってるんですよ。焼いてすぐ切ってくれます。シュニッツェル(ウィーン風カツレツ)は3ユーロで売っています。ちなみにマヨネーズとケチャップは別売りです(笑)。ウィーンにはねぎるという習慣はないんですが、たぶん、食費は抑えようと思えばいくらでも抑えることができると思います。朝食は宿泊費とセット料金なので、朝たくさん食べるようにしてタンパク質をそこで摂って、あとはパンとジャムで生活するとか(笑)。交通費はとても安いです。1回券は1.7ユーロですが、一週間フリーパス券があって、それが10.50ユーロなんですよ。それをよく利用していました。切符はクレジットカードでも買えます。今ユーロが円に対して高くなっていますけれど、もともと物価が安い国らしくて、私はそんなに高くは感じませんでした。
 — 何か不便なことはありましたか?
— 何か不便なことはありましたか?
広瀬 特別ありませんでした。レッスン生の中には英語やドイツ語があまりできなくてちょっと困っている子もいたようです。本はドイツ語のものしか売ってないので、よく分からない。それくらいですね。
— ホテルから学校まではどのくらいの時間かかりましたか?
広瀬 そうですね、30分かからなかったと思います。ホテルからシュネルバーン(郊外電車)の駅まで3分かからないくらいだったし、電車の本数は頻繁にありましたから。駅を出て大学まではすぐなので、20分くらいかな?
— 電車の中の治安はどうでしたか?
広瀬 よかったですよ。たまに、本当にたまにヘンな人はいましたが。
 — 留学する際に持っていった方がいいと思うものがあったら教えてください。
— 留学する際に持っていった方がいいと思うものがあったら教えてください。
広瀬 音楽面では、とにかく曲は多めに用意しておくことです。多いにこしたことはありません。生徒が少ない時とか、予定している曲数よりも多く教えてもらえることがあります。バイオリンの方はピアノ伴奏譜も持っていかれるといいと思います。ピアノ伴奏有りか無しかを選ぶことはできるんですが。楽譜に関することで言うと、もし同じ曲を日本でも習っていたら新しく楽譜を買っていかれると、書き込みが混ざらずにいいと思います。生活面では、ホテルのキッチンにはグラスや鍋やフライパンなどの調理器具は揃ってるんですが、お皿や食器がないんですよ。お皿1枚とスプーン1本、持っていくと便利だと思います。あと、ヨーロッパはシャンプーとコンディショナーに分かれていないので、気にされる方はご自分がお使いのものを用意されるといいと思います。それから、日本に電話やメールをする機会もあると思うんですが、日本の時刻が分かるように、世界時計とか、なければ腕時計を2つ持っていくと便利だと思います。
— 日本とウィーンでの違いは感じましたか?
広瀬 そうですね、音楽的なことで言えば、日本では譜面は暗記して弾くのが当たり前だという風潮がありますよね。実際私もプロなら覚えるのが当たり前だと思っていたんです。ソナタに関して言えば、ウィーンでは譜面を見ない方が逆に悪いイメージを持たれるそうなんです。ソナタはピアノと2人だけど室内楽だから、見るのが当たり前だと言われました。私が暗譜で弾いたらびっくりされました(笑)。そういった日本では知らない常識みたいなものがウィーンにはきっといっぱいあるんでしょうね。まぁ、私が特に音大に入ってないから余計それが多かったかもしれないんですけど。あとは、音の鳴り方が全然違うと思いました。空気が違うと感じましたね。文化面では、向こうではすれ違う人と必ず挨拶するんですよ。日本では絶対ないことですよね。みんなフレンドリーで、親切で。荷物を棚に上げるところとか必ず手伝ってくれるし。そんなウィーンの文化が好きでした。道路の幅ひとつにしてもすごく居心地よかったですね。生活面では、虫をね、あまり気にしない文化らしくて‥網戸が付いてない家がほとんどなんですよ。それでハエや小バエが入ってきたりはします。一度、ホテルに持ち込んだサワークリームに蟻がたかって大変だったことがありました。硬いんですよ、ウィーンの蟻って(笑)。日本でやるみたいにプチって指で潰そうとしても潰れないんで、ハウスキーパーの人に来てもらって取ってもらいました。都市部では人を刺すような蚊はいませんでしたね。たぶん山の方に行かないといないと思います。
 — 留学して良かったと感じる瞬間はどんな時でしたか?
— 留学して良かったと感じる瞬間はどんな時でしたか?
広瀬 今付いているバイオリンの先生も素晴らしい方ですし、日本でも十分音楽の勉強はできると留学する前は思っていました。まぁ、多少は違うのかな、とは思っていましたが。でも、留学してみると「全然違うな」と思いました。やはり、日本は狭いと感じました。さきほどお話したように、チャイコフスキーのコンチェルトにしても、最新の弾き方があるということが分かりました。ほかにもたくさんヨーロッパの新しい技術を教えていただいたので、もっと練習して自分のものにしていきたいと思います。音楽面以外では、ウィーンにはコソボから来て働いている人がたくさんいるんです。紛争で家族を亡くした方とも話をしました。自分がいかに井の中の蛙だったか思い知らされました。オーストリアという広い所に行ったおかげでそういう自分に気付くことができた時に、留学してよかったと思いました。お金を貯めてまたどこかに留学したいです。
— 留学をして、自分が成長したな、と思うところはありますか?
広瀬 私、お金を貯めてまた留学したいと思っているんです。最初はウィーンに行って、広い世界を見て、世界を知った気になったんですけど、よく考えてみると、ウィーンって世界的な観光地なので、そこで観光したり、住んでいる人達って『世界が100人の村だったら』風に考えると、世界のほんの一部のお金持ちの人達なんですよね。だから、これからは東南アジアとか、貧しい国の人達のこともちゃんと見なければいけないと思ったんです。それで、本などでいろいろと勉強するようになりました。そういうところに目を向けることができたところは成長したと思いますね。もともと私、僻地に学校を建てるのが夢なんです。それが一層強まりました。
 — 今後の進路について聞かせてください。
— 今後の進路について聞かせてください。
広瀬 ウィーン国立音楽大学への入学を当面の目標に、私立の音楽院を踏み台にしても行きたいなと思います。将来的な目標としては、これは中学生くらいからの夢なんですが‥。葉加瀬太郎さんや、高嶋ちさ子さんみたいに、クラシックを身近に聞いてもらえる音楽家になりたいです。「ジュピター」のようにクラシック音楽が流行したように、ざっくばらんに一般の方にもクラシックを楽しんでもらえたら、と思います。ヨーロッパに移住したいという希望もあります。帰国したら、たとえ他の仕事をしながらでも、ファミリーコンサートみたいな、一般的な方が知っている曲だけを集めたコンサートがしたいな、と思っています。「これ好きだけど、題名が分からない」って曲、みなさんきっと多いと思うんですよ。そういう曲を集めて、青島広志さんみたいに自分でMCもしながらコンサートしたいんです。一人でも多くの人に、クラシック音楽に親しみを持ってもらえたらな、と思っています。いくらこれから技術を磨くと言っても、今からテクニカルな演奏家になるのは無理だと自分でも分かっているので、そちらの方面で活動できたらな、と思っています。教えるよりは、自分が弾きたい方なので、普段は教えながらでも、楽器を弾く友達はいっぱいいるので、そういうコンサートをやっていけたらと思います。
— これから留学する人に、心しておかなければいけないことを教えてあげてください。
広瀬 レッスンを受ける際は、曖昧な返事はなるべくしない方がいいと思います。先生もたぶん困っちゃうので。生活面では、いくら英語が通じるといっても、挨拶程度のドイツ語は覚えて行った方がいいと思います。「こんにちは」「ありがとう」くらいでいいと思いますが。それから、クレジットカードがレストランでもスーパーでも使えますし、切符とか小さい金額のものでも何でも買えて、領収書が一緒に出てきます。その領収書にクレジット番号や有効期限がきちんと書いてあるんです。それがあるとインターネットショッピングが出来てしまうので、万が一その領収書が他人の手に渡ると、クレジットカードが悪用される可能性があります。だからくれぐれも失くさないように注意してください。それからこれは女性限定ですが、ナンパ注意です(笑)。面倒くさいです。英語が分からないフリしていればいいと思います。他には、先ほどウィーンは治安が良いと言いましたけれども、いくら治安が良いとは言っても、日本より治安が良い国はまずないです。大学の教授から教えてもらったことですが、パスポートは首から提げるタイプよりも、お腹に巻くタイプとかの方が良いと。私はずっとスカートかズボンだったので、パスポート、額が大きいお金、電車のパスなどの貴重品は袋に入れてウェストに挟んでました。ウィーンで一度、私が駅のインフォメーションを探していたら、おばあさんが駆け込んできて、「バッグ盗まれました」って言ってるのを見たことがあります。だから置き引きにも十分注意してください。ウィーンはある程度英語が通じるといっても、それは日常会話程度のことなんですね。何があるかわかないので、私は医学用語を入れた電子辞書を持って行って、入院した時に医学用語をドイツ語で表示したりしてとても役に立ちました。あとは、常備薬は必ず携帯するとか、国際電話のかけ方は何があるか分からないのでマスターしておくとか、海外保険は入るとか‥。どこに留学するにしろ、「留学する際の注意点」ガイドはアンドビジョンでもいただけるので、必ず読んだ方がいいと思います。
— 今回の留学は入院されて大変でしたね。
広瀬 ちょうど行きの飛行機の中で『300』という映画を見たんですよ。ゲルマン民族の話なんですけど、救急車をホテルの方が呼んでくださったら、体格が良いドイツ人が2人来て怖かったです(笑)。ちなみに救急車は451ユーロでした‥(留学生保険でカバーされます)。
 — 最後に一言、これから留学される方にどうぞ。
— 最後に一言、これから留学される方にどうぞ。
広瀬 ウィーンは世界的に有名な観光地で、いろんな国からいろんな人達が集まってくる所です。特に夏期講習の時期は観光の季節でもあるので、いろんな方と触れ合うことで、本当にこれからの人生を変えるだけの衝撃を受ける可能性は十分にあると思います。
— ありがとうございました。
霧生貴之さん/トランペット/イタリアフィルハーモニー管弦楽団/イタリア・ピアチェンツァ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回はイタリア・スイスでご活躍中のクラシックトランペット奏者・霧生貴之(キリュウタカユキ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「イタリアでクラシックトランペットプレーヤーとして活躍するには?」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います(インタビュー:2005年8月)。
ー霧生貴之さんプロフィールー

桐朋学園大学トランペット科卒業。G.二コリーニ国立音楽院卒業。チューリッヒ国立高等音楽院卒業。桐朋学園大学在学中から国内のオーケストラにエキストラとして出演。第5回カザルツァ・リグレ国際コンクール管楽器部門及び独奏部門総合1位、第10回リヴィエラ デッラ ヴェルシリア国内コンクール2位。イタリア音楽院在学中からピアチェンツァのイタリアフィルハーモニー管弦楽団で演奏するようになる。現在はミラノ・ジュゼッペ・ベルディ交響楽団、パルマ市立歌劇場オーケストラ、チューリッヒ交響楽団などのオーケストラで演奏する一方、ソロやアンサンブルなどでもイタリア・スイスを中心にヨーロッパで活躍中。今秋(2005年)より北イタリアを代表する金管五重奏団Golliwogg Brass Quintettoメンバー。現在最も有望なクラシックトランペット奏者である。
ー 音楽に興味をもったきっかけは?
家は音楽家の家庭で、母がピアニストで父もトランペット奏者だったものですから、僕の場合は母がトランペットをやらせたかったというのがありますね。僕も周りの環境で音楽家になるんだと小さい頃から自然に思うようになりました。だからすごく必死にやるとかそういうのはなかったですけど、英才教育で天才少年とかいうのでも全然なかったんですけど、小さい頃からなんとなく、いずれ音楽家になるんだろうな、と思いながら育っていましたね。僕は一番最初にトランペットという楽器を手に持って試したって言う記憶がないんです。気がついたら楽器が家に転がっていて、気がついたら吹いていたという感じですよね。だから最初吹くのが大変とかそういう記憶もないんです。
ー 最初からクラシックだったんですか?
父親がクラシックのトランペットプレーヤーだったので、ジャズなどは個人的には好きですけど、僕は一度もそちらの方に関心を持ったり、プロフェッショナルとして興味を持ったことはないですね。ピアノなんかもわりと小さい頃から始めましたけど、それはもう音楽大学に入るためにピアノをやっておかないといけないからという事でやっていたような感じでした。あんまりまじめにやってませんでしたけど(笑)。
ー 日本の大学にいかれたんですか?
最初日本の音楽高校、桐朋学園に入って、大学まで卒業しました。その後、大学の先生がドイツで勉強をしていたので、その影響を受けて留学するつもりでドイツのほうに行きました。でもコネクションがなかったので、僕の興味のあった人が、来日したときに楽屋に駆けつけてあなたの元で勉強したいんですけど、と言ったら、じゃあとにかく住所を渡すから、演奏のテープを送ってくださいと言われてました。それで、演奏テープを送った後に連絡を取り合っていたんですけど、ドイツのカールスルーエというところで、入学試験を受けたんですけど、受からなかったんです(笑)。
ー なにか受かりやすいとかあるんですか?
今言いますと、そのドイツのカールスルーエというのは多分ドイツの中でも一番入るのが難しいと思うんですよ、トランペットのクラスになると。本当にドイツで一番有名な学校で、僕はそのときまだそこまで難しいものだというのは理解していなかったんですけど、まあ、自分が好きだというのの一心で行ったんです。その人に師事したかったので。その後、日本に帰ってきたんですけど、親と喧嘩をして僕は家を出ることになったんです。大学在学中からフリーランスで日本のプロフェッショナルのオーケストラのエキストラの仕事や、他の仕事はあったので、一人暮らしをしながら生活を続けていたんです。ただ僕にとっては留学というのは僕にとっては必要なことで、親とは喧嘩はしましたけど、親も僕もその点については意見は同じだったので、1年半ぐらいたって、親が「そろそろもし留学をしたいんだったら、もう一回チャンスをやろう」という話になりました。それで、もう一度何とか勉強できるところを探そうということになりました。
ー すでにプロでやっているのに再度留学したいと思ったのはなぜですか?
僕の場合、トランペットを吹くという点で根本的に問題があって、それがどうしても日本では解決できなかったんですね。音を出すということに問題があったんです。日本では、いままで勉強したやり方で何とか仕事はこなしてましたけど、そのやり方では何年も伸びてなくて、限界があったんですよ。トランペットの奏法って言うのはいろんな方法があるわけです。簡単に言えば正しい吹き方をしていれば伸びますけど、どこかに問題あるわけですよ。それを修正するためには一度やりなおさないといけない。仕事をしながらというのは難しいですね。仕事での失敗は許されませんから、必然的に今までやった奏法のほうが安全なわけです、リミットがあったとしても。仕事をするためにはある程度吹ければ良いですけど、自分の音楽性をもっと伸ばそうとしたらそれ以上のものを要求しますので、そこの壁にあたっていたのですね。
ー 仕事では挑戦ができないということですよね。
そうですね。いい奏法に挑戦するというコンディションは日本で仕事をしながら作れなかったわけです。それが一つの理由であるのと、母親が音楽家でやっぱり留学をしていましたから、ヨーロッパに来ることが、音楽家として勉強にもなるし、欠かせないのでは、と言うことでした。
ー 実際留学しようとしたときはどこに決められたんですか?
そのときはまだちゃんと決めていなくて、まずは先生探しの旅行をしました。旅行にあたって、何人かの人を訪ねて、ドイツのトロッシンゲンの音楽大学の先生とコンタクトが取れて、そこに夏に来てもいいよということになったんですね。その後に人生を大きく変える出来事がありまして、母親が教えている音楽学校がイタリアのピアチェンツァという町の音楽学校と交流を結んだのです。母親がその音楽学校の校長先生がいらしたときに会食をする機会がありまして、ある日突然母親から「イタリアのコンサルバトーリオ(音楽院)に校長先生を知っているんだけど、イタリアというのはどうなの?行ってみたらどう?」といわれたんですね。その時点で僕にとって留学のスポンサーは母親です。ここで「いや、でもイタリアっていうのは知らないし、いいよ」と言って、機嫌を損ねるとまたこの話がおじゃんになるかも、というのが頭を掠めたんですよ。そこで「うん、わかった。じゃあとりあえず行ってみようか」と思わず言ってしまったんです(笑)。そういうことってないですか(笑)?子供は子供でプロジェクトを立ててるけど、でも、そういうときに限って親が全然違うプロジェクトを持ってくる。日常でもたくさんあると思うんです。それで、ドイツに行く前にイタリアに行くということになったんです。ここでもすごく不思議なケースだと思うんですけど、その校長先生に連絡をとって、音楽院にいい先生はいらっしゃいますか?と聞いたら一人先生を紹介してくれたんですね。その先生にコンタクトとったら、その先生というのが自分で金管アンサンブル(トランペット、トロンボーン、ホルンとチューバ)を自分で持っていて、自分で演奏会を企画したりして、すごくアクティブに活動している方だったんですね。それで、何月に来るんだといことで、8月の何日と何日、9月の何日と10月にはベルギーで演奏旅行があるので、今トランペットが足りない状況だから、是非それに出て欲しいと突然いわれたんですね。一回プロフィールみたいなのは送りましたけど、僕はそれまで演奏テープを出してもいなかったので当然驚きます。ただイタリアなので、どこまで本当か分からないけど、行ってみる価値はあるんじゃないかと。あんまりひどいようだったら、イタリアに絶対いなきゃいけないわけではないし、ピザでも食べて、オペラでもみて、また移動すればいいだけの話だ、ぐらいに思っていたんです。
ー 実際に行かれたんですよね?

ええ。そうしたら、逆にとても興味深くて、最初のうちは演奏会とかありましたけど、やっぱり時間がとても自由でリフレッシュする時間がすごくありましたね。イタリアはある意味何もないので、頭の中を真っ白にして、もう一回立て直すというか、僕にとってもそういう時間がとても必要だったんですね。
ー イタリアは良かったんですか?
そうですね。とりあえず僕にとっては良かったですね。この状況を続けることは悪いことではないな、と。すごく将来のことが見えていたわけではないんですけど、今のコンディションがすごくいいので、続けることは悪いことではないなと。その間にいい友人にたくさん出会ったりしましたし、イタリア人の友人と出会って、すごく助けていただきました。僕の先生にあたる人が、面倒見てくれよということで少し英語の話せる人を何人か紹介して頂いたんです。今の一番親しい友人になっていますけど。
ー 最初にかなり多くの人に助けていただいたんですね。
日本人の方は全く知り合いがいなくて、一人イタリアに長く住んでらっしゃる方がいて、コンタクトを取るときにいくつか手伝っていただいた程度で、後はほとんどイタリア人の方に助けて頂きました。ピアチェンツァの街には日本人がほとんどいなかったので、周りのイタリア人たちも初めての経験なわけですよ、外国人を助けるというのは。
ー 珍しかったんですか?
そうですね。しかもトランペットというのは僕もイタリアに長く留学していますけど、まず聞きませんから。
ー 通常トランペットというのはドイツが多いのですか?
間単に言いますと、オーストリア、ドイツ、フランス、アメリカですね。いろんな派があって、メソッドがありますので、日本でどんな先生についていたかとか、どういう影響を受けたかによっても変わってきます。だからイタリアというのは非常に珍しいですね。イタリアのコンサルバトーリオは4月に入学願書を出して、試験が6-7月ないし9月にあるんです。僕は8月に来ているので当然入学願書も出してないし、入れなかったので、一年待つことになったんです。ただそこで、校長先生が許可を出してくれました。聴講生システムというのはイタリアのコンサルバトーリオではありえないんですけど、校長先生の許可というレベルで、授業やレッスン、その他の全てのものに参加する許可を出してくれたんです。次の年に入学するという条件の下に。ただ。ここでちょっとしたハプニングがありました。一年間待って準備した入学試験の日にその頃仕事をしていたウディネフィルハーモニー管弦楽団の仕事と重なってしまったんです。ウディネはピアチェンツァから400キロ以上離れています。それを先生に話したら“しょうがないな、何とかしてみるよ”と言ってくださってなんと無試験で入学させていただきました。(笑)
ー 結構とんとん拍子に進んでいますね?
そうですね。ただ警察のことで大変だったりしました。僕はツーリストビザでイタリアに入国していたので、滞在していい期間が3ヶ月なんです。それで警察にもう3ヶ月イタリア人からの招待があったので、伸ばしたいという事を申告しようと思ったんです。それをやるのに、ピアチェンツァから朝4時半の電車に乗って、6時から8時半に警察の門の前に並んで中で再び並び終わるのが12時、イタリア語もほとんどわからない状況で、それを3回やる羽目になったんです(笑)。蓋をあけてみると、やらなくても良かったんじゃないかという気もしますが、あの時点で不法滞在になる可能性を考えるとやるしかなかったんですよね。
ー その後音楽院に入られて、どのくらい通われていたんですか?
イタリアの音楽学校というのは科目によって通う年数が違ってくるんです。イタリアの音楽学校は音楽大学ではなくて、音楽院なので、ピアノだったら10年、ヴァイオリンだったっら8年という年月を勉強しないといけないんですが、飛び級ができるんですね。トランペットに関しては5年ですね。歌は6年かな。でもそれはどういうことかというと、学校入学時に楽器が演奏できる状態じゃない人も入るわけです。逆に言えば5年でトランペットが吹けるようになって、卒業しないといけないんですね。
ー 最初に演奏できない方も来ているてわけですね?
イタリアのシステムでそこに問題があることもありますが、そこで天才的に伸びる人も中にはいますよね。
ー 人によって、年数は違うということですね。
そういうことですね。僕は結局長くいたいということで、3年で卒業したのかな。(トランペットのコースは)5年のところを3年で卒業しましたね。
ー その後卒業されてオーケストラに入ろうということだったんでしょうか?
98年の11月から今のオーケストラの仕事をいただくようになりました。ドイツなど場合は、システムがイタリアに比べてすごくしっかりしているんですね。どんな街にもオーケストラがあって、まあ就職先ということになると思うのですが、給料がもらえて、そこに就職したら、生活ができるということになります。でも、イタリアはそういうシステムがほとんどないに等しいんですよ。ピアチェンツァのオーケストラに所属してますが、毎月の給料としてはもらえないんですね。要するに歩合制ということです。もちろんオーケストラのメンバーなので、何か用事があって演奏ができないときは自分がこの日はいけませんと事務局に言いに行かなくてはいけなんです。すごく簡単にいうとフリーランスに近いので学生でも実力があれば可能なんですね。
ー オーケストラの仕事を取るためにどういうアクションを起こしたんですか?
団長というか、一番偉い人が、ピアチェンツァのファゴット科の教授をしていました。彼はオーケストラの中ではもう演奏はしていないんですけど、オ−ガナイズをしていて、彼のコンセプトの中にでピアチェンツァ出身の人で集めるオーケストラというのがあって、ピアチェンツァのコンサルバトーリオの中でめぼしい人がいると、必ずチャンスを与えてくれるんですね。たまたますぐにチャンスがあったわけではなかったので、あなたのオーケストラで仕事をしたいのですがオーディションの機会はないですか、と自分からインフォメーションをしました。彼はオーディションはないけれど君がいることは知っているから、電話番号を残してくれれば、もしかしたら機会があるかもしれないと言われたんです。しばらくそのままだったんですけど、チャンスがあったとき話を下さったんです。
ー 実際に日本とか他の国のオーケストラでの仕事を考えたりはしますか?
もちろん世の中何があるか分からないですから日本の事は常には考えていますが、現実的に日本に今すぐ帰るかというと難しいですね。実際今ピアチェンツァのオーケストラで仕事をしていますけど、他のもたくさんのオーケストラで仕事をしてるんです。有名なオーケストラだとミラノ・ジュゼッペ・ベルディ交響楽団からよく仕事を頂きますね。この間お辞めになったのですが、リカルド・シャイーが指揮をしていた楽団です。97年の11月に新国立歌劇場のこけら落としで、ワーグナーのローエングリーというオペラをやったときに1ヶ月エキストラでオーケストラに戻ったんですが、それを機に日本に帰らなくなってしまいました。97年から今まで(2005年8月)、唯一帰ったのは2003年10月にベルディ交響楽団日本ツアーがあったときに連れて行ってもらっただけですね。
ー 日本よりイタリアの方がやりやすいというのがあるんですか?
良く分からないですが、仕事でもコンクールでも自分で取るものではないと思うんです。コンクールに勝つ、と言いますが、頑張ったから勝ったわけではないと思うんです。自分の意思ではなくて他の人があなたが勝ったんだよ、って言うわけですよね。仕事だって、あなたに仕事頼みますよ、って他の人が言うわけです。結局普通に生活している状態で、もちろんただ家で練習していたら、電話がかかってくるという単純な問題ではないですけど、そういう部分があると思うのです。結果として僕にはイタリアにいれば仕事は確実にありますから、今日本に帰るよりも確実にイタリアにいるほうが仕事があるわけですね。
ー イタリアのオーケストラに外国人はかなりいるのしょうか?
イタリアの場合、外国人の多いオーケストラと、イタリア人ばかりのオーケストラとに分かれます。外国人がオーガナイズしているオーケストラもあるわけです。これは変り種なんですが、ある時期ミラノにたくさんのロシア人の人が来る時期がありました。そういう人たちが地元に根をつけていくと、ロシア人で演奏会を企画するようになって、彼らの所に直接仕事が来るようになります。僕がそのようなオーケストラに行った時はイタリア人の優秀なバイオリン奏者が一番後ろの方にいて、コンサートマスターとか、チェロのトップの人などの主要な人は全員ロシア人で、練習中もみんなロシア語という感じでした(笑)。イタリア人もここは一体どこなんだという感じで、その中ではおとなしくしているしかないですよね(笑)。
ー そういう風にいろんな国の人と演奏してきてイタリア人に一番影響を受けたことはどのようなことですか?

一番大事なことは、どのようなスタイルで演奏するかという事です。キャラクターが演奏する作品にあっているかどうかということが彼ら(イタリアのオーケストラ)にとって一番最初にくることなんです。一番最初に来るのが、音程でもリズムでもないのです。僕たちがやっているのは音楽です。ということは、どういう音楽を演奏するかというところから始まるわけです。楽譜に書いてあることを正しく演奏するというところから入るのではなくて、どういうキャラクターの音楽をこれから演奏するのかというところから入るんです。
ー 日本の場合はどうでしたか?
日本は楽譜に書いてあるとおり正確にという感じですね。正確というのはメトロノームがいくつ、シャープがいくつ、十六分音符があったらそのとおりの音をとります。でもそうじゃなくて、どういう音楽だからこの十六分音符を詰まらせなきゃいけないとか、そういうところから判断するわけです。
ー みんなでディスカッションするのですか?
まあ、それをまとめるために指揮者がいるのですが。でも、そのオーケストラの癖もありますし、ベルディはみんながうるさくなります。特に僕の住んでいる所からベルディが生まれた所が近いのということもあると思います。パルマでの仕事もありますが、パルマはほんとにベルディにうるさいですね。パルマのベルディは、ウィーンでいうウィンナワルツみたいなものですから。
ー 日本にいる時とイタリアにいる時と大きく違うのは気持ちの部分から入るということですか?
基本的にいろんなことが違いますけが、仕事をしていて一番違うなと思うのは、日本のオーケストラは練習の1回目の時がものすごく良いんです。そのあとに指揮者がいろいろ言い出すとだんだん悪くなっていく(笑)。要するにみんなが集中して完璧を目指した時が一番良くできるわけです。それが何回も繰り返していくうちにだんだん新鮮味がなくなっていくというのでしょうか。イタリア人は初日の演奏は本当にひどいですよ。1回目にうまくいかなかった人が2回目も同じように悪かったりしますから。音を間違えてメージャーの和音のところを1回目にモールで吹いて、2回目もまたモールで間違えることもあります。その代わり 1日目から2日目へ行くときに全然良くなりますし本番の時に一番良くなるようにみんなもって行きます。
ー やっぱりそこを目指して山が上がっていくという感じですか?
それは意識的なものではないと思います。彼らがそこまで意識的に考えているとはとても考えられません(笑)。やっぱり音楽を演奏するというのはとてもエネルギーのいる作業です。それは本番で出すもので、練習のときはあまり出さないものなのでしょうね。自分が演奏するという段階と練習しているという段階との意識の違いだと思います。
ー 音楽活動をしていく上でこだわりを持っていることはどのような事ですか?
一番大事なのは、音楽に対してどういうコンセプトを持ってやっているかということが自分の頭の中でクリアかどうかだと思います。バロックをやるときはバロック、ロマンティックをやるときはロマンティック、モダン音楽の時はモダン音楽のようにそれぞれどういうものが必要かということです。例えば、ウィーンの音楽をウィーン風にウィーンの人たちが納得するように演奏することができるかどうか分からないのですが、そういうことではなく自分の中でウィーンの音楽はこういうコンセプトなんじゃないかということが自分の頭の中にそれがあることが重要ではないかと思います。 霧生貴之さんトランペット奏者
ー 音楽活動しているときに最も興奮することがどういうことでしょうか?
オペラが好きなのでいい歌手と演奏しているときで、特にイタリアオペラの盛り上がるときは興奮しますね。オーケストラの中でトランペットを演奏しない時間もたくさんあるので、そんなときはピットの中にいならがものすごい興奮してますね(笑)。聞き入っています(笑)。
ー お客さんの拍手はそんなに影響はないですか?
オペラなどのピットにいる状態というのは、あまり影響はないですね。
音楽家として僕はこういうふうに考えているんです。オーケストラももちろんやっているのですが、トランペットとオルガンや金管五重奏などのソロや室内楽の活動を行うときが結構あります。音楽家としての演奏活動というのはそういう所でやる音楽なんです。オーケストラというのは、プロフェッショナルなものだと思うんです。仕事なわけです。オーケストラで演奏する事に対して思い入れがありすぎると、破綻がくることがたくさんあるんです。例えば、指揮者の要求と自分の好みがあわなかったり、同僚がよく吹けなかったり、いろんな場合があります。自分の調子が悪いとか、そんな場合に破綻がくるんです。
ー オーケストラの場合は一人でやるものではないですからね。
そうですね。オーケストラというのは本当に会社と一緒だと思います。役割があってそれをいかにちゃんとこなせるかということです。一番重要なのはオーケストラでは他の人達と同じ感じ方が出来ているかということだと思います。自分がうまく演奏できたかどうかというはそんなに重要ではないんです。全体的なものなのでそれがうまくはまっているかどうかということだと思うんです。全員が同じように感じれなかったらオーケストラはうまく機能しないと思います。
ー やっていて面白いのは、オーケストラというものはないんですね?
やはり留学などをして何を勉強しているかというのは、オーケストラではなくてソロのレパートリーに対しての音楽的解釈を高めるとか自分の新しいレパートリーを広げていくとか、新しいジャンルの新しいスタイルを身につけるとか、そういうことを僕はやりたかったんですね。ソロやグループの時は音楽的なディスカッションができるんです。オーケストラというのは時間も限られているし、人数もたくさんいますからそう簡単に自分の意見を言うべき場所でもないと思うんです。そういうことをまとめるのが指揮者の仕事ですから。もちろんパートをまとめるに当たって言わなければならないこともたくさんありますけど。
ー 霧生さんにとってクラシックや音楽とは何でしょうか?
トランペットを演奏して音楽を感じて音楽を楽しめるということは、自分の人生の中で「生きる」ということの一つだと思います。「生きる」というエネルギーの中に含まれる一つのパーツだと思います。これが全てではないですけれどもね。
ー 将来の夢というのを聞かせていただけますか?
夢というのは難しいですよね。僕はあまり夢というふうには考えたことないんです。どうしてかというとまず最初はここ半年、数年やらなくてはいけないプロジェクトがありますよね。そういうことを考えるという事が僕が夢を考えるという事と繋がります。夢というのは動かないものではないわけです。ある場所にいるときに、その方向で一番遠くにいけるのはどこかなって考えるのです。そして一番のびそうなところを伸ばしていきます。だからその場その場によって変わってくるわけです。そこに行った時にどうするかということが大切だと思うのですね。僕にとって一つの所を目指してそこに行くというのはかえって進むのが難しいことになるんじゃないかと思います。夢というものは物事を固定してしまうのでは、そのような固定するという観念が僕にはなんじゃないかと思うんです。
ー なるほど。遠くに何かを持って進むというのではなく、今この場で一番遠くに飛べる場所をたえず選んでいるということなんですね?
そうですね。それが僕にとって音楽活動をするにあたって現実的なことなんです。自分にとって自分が満足できることが夢の最終的なコンセプトではないのかなと思います。夢はなんのために持つのかというと夢に到達できたら幸せになれるとることや満足できるということなわけですよね。ということは何が夢かということではなくて、自分がその活動によって満足できるかということだと思うんです。
ー 海外でミュージシャンとして活躍する成功する条件というのは何かあるとお考えですか?
海外かどうかは分からないんですが、音楽家というのは人間的に成熟していない方が多いのではと思うのです。僕が言いたいのは、音楽家も社会人じゃないですか。音楽家だろうが画家だろうが警察官だろうがペンキ塗りだろうが社会人なわけです。ペンキ塗りだから社会性がなくていいというわけではないわけです。社会人であれるということがやはり仕事に繋がると思います。音楽家は、すごい欠けてるわけではもちろんないのですが、いろんな小さな所でどこかが抜けているということはあると思います。それぞれ抜け加減が違うのです(笑)。演奏活動をするということですが、音楽的演奏の追求とは全く違います。演奏会というのは企画しないといけないわけです。エージェンシーが常時ついてくれるわけでもなければ自分がそこに行って演奏だけすればいいわけではないんです。そうなったときに他の仕事の事も自分でできないと仕方ないです。誰もやってくれませんから。例えば伴奏する方を探して呼ばなくてはいけません。それでどういう人がいいかという時に、いい演奏家でもその日にくるかどうか分からない人を呼ぶんだったらきちんと来てくれる人を呼びたいわけです(笑)。来ない人と言ってしまうと語弊がありますけど。まあ、実際には、来ない人もいると思いますけど、本当に来ない人というのはあんまりいないですよね。仕事に関するディスカッションにしても自分が思ったことをいつも正直に言うということも都合が悪い場合がたくさんあるわけです。自分が思っていることを言ってはいけないという意味ではなくその時に必要な事をみつけてきちんと言えなくてはいけないと思います。仕事をとるために、仕事をくださいとあちこちで言えとは全然思わないのですが、自分に仕事を下さったときにその仕事はできますよという回答ができて、この人に仕事を頼んだらこの人は仕事ができそうだな、と相手に思わせることが必要だと思います。やはり人と人とはコミュニケーション、話すということでしますからね。ヨーロッパは特にそういう社会人であるということは厳しいのではないかと思います。イタリアで学校を卒業したあとスイスのチューリッヒにある高等音楽院に3年間勉強しに行ったんですね。現在もスイスにも仕事でよく行きます。その時に思うことは、イタリアとスイスはどちらも社会のルールが違います。そういうのを敏感に感じるとれるということは非常に大事だと思います。
ー 海外で留学したいという方にアドバイスはありますか?
留学した人をたくさん見ましたけれど、留学すること自体は大いに結構だと思います。しかし、勉強するのは自分ということを忘れないで欲しいと思います。それは、どんなにいい先生でも、どんなに悪い先生でも結局やるのは自分なんです。先生達がうまくしてくれるのではなく、先生達はよくなるアイディアはくれるかもしれないですが、自分がどうやってやるかということをまず見つけることが大切だと思います。それが分からなければどこにいても何をやっても空回りしてしまうと思います。大事なのは自分がみつかっていればその先はどんどん見えてくるのではないかなと思います。留学ということに関しても留学をしないということを選択した時でもそうじゃないかなと思います。
ー 単純に音楽は留学したほうがいいとお考えですか?
それは非常に難しいです。日本で何をやっているのかもありますしね。ただ僕が一つ言えるのはせっかく生きているのですから、地球があるのだったら、地球のいろんな場所に行ってみることは人生経験として悪いことではないんじゃないかなと思います。もちろん人生経験が豊かでなくていいという人がいるかもしれませんが(笑)、いろんな所にいくのは簡単で非常にいろんな経験ができることではないかなと思います、単純に。
ー 今後の演奏活動を聞かせてください。
8月はバカンスになるのですが、8月の後半から演奏会がクレモナの教会であります。金管五重奏もあります。9月・10月はオペレッタの演奏がスイスであります。その間に室内楽の演奏会がいくつか入っていますね。イタリアはスケジュールが入ってくるのが遅いので、今の段階だとまだ早いのです(注:インタビューは2005年8月1日に行われました)。オペレッタはスイスの仕事だから早いのですけどね(笑)。例えば、4月に友達から電話のメール(SMS)が来ました。11月30日と12月3日と5日空いていないか、教えて欲しいと言われたんですね。ああ、メッセージが来たなと思っていたら15分後に、またメールが来て、できれば今すぐ知りたいんだけど、と言われましたよ(笑)。
ー 本当にお国柄ってありますね(笑)。イタリアはそんなことないでしょうね(笑)。
そうですね。イタリアのスケジュールはまだだからよく分からないんです(笑)
坪井悠佳さん/ヴァイオリン/チューリッヒ国立高等音楽院ザハール・ブロンアシスタント/スイス・チューリッヒ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回はスイス、チューリッヒ国立高等音楽院で世界的名教師ザハール・ブロンのアシスタント兼講師/演奏家としてご活躍中のバイオリニスト坪井悠佳(ツボイユカ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「ヨーロッパで学ぶバイオリン」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2005年9月)
ー坪井悠佳さんプロフィールー

東京生まれ。4歳よりヴァイオリンを始める。14才でイギリスのユフディ・メニューイン・スクールに留学。メニューインに認められメニューイン指揮フィルハーモニア・ハンガリカとモーツァルト協奏曲第三番を共演。メニューインの80歳記念コンサートやウィグモアホールでのコンサートに出演。メニューイン設立の慈善財団に所属し病院や施設などでコンサート活動を行っている。そのほかスイス、イタリア、スペイン、イスラエル、オーストリア、シンガポールなどで演奏会を行う。スペインのサラサーテ国際ヴァイオリンコンクール第二位、チューリッヒ、キヴァニス・コンクール・ヴァイオリン部門第一位、パドヴァ国際音楽コンクールソロ部門、室内楽部門共に優勝、ヤマハ奨学金、マイスター奨学金受賞など数々の国際的な賞を受賞。ロンドン王立音楽院を経て現在スイス、チューリッヒ国立高等音楽院で世界的名教師ザハール・ブロンに師事しアシスタントを務める。また弦楽四重奏GALATEA QUARTETを結成しヨーロッパ各地で出演予定。ウィーン・マスタークラスとモーツァルテウム夏期アカデミーで教える。現在最も優れたバイオリストであると同時に後進を育てる教育者でもある。
ー 坪井さんの経歴をごく簡単にご紹介していただけますか?
坪井 最初桐朋学園の子供のための音楽教室に行っていたんですね。それからイギリスのメニューインスクールというところへ14歳のときに行きました。それは全寮制の音楽学校でした。そのあとに卒業はしなかったんですけども、3年間英国王立音楽院に行きました。そして現在チューリッヒの国立音楽院でザハール・ブロン先生のアシスタントをしています。
ー ずいぶん早い時期から海外にでているのですが、何か興味を持ったきっかけがありましたか?
坪井 小学校卒業した時は日本にいたんですけど、そのあとシンガポールにうちの父が転勤になったんですね。それでシンガポールに中学校から2年間行っていたんです。小学校は桐朋だったもので、そのあと中学校に戻って桐朋の高校の音楽科を受ける予定だったんですが、外国にかなりちょっと興味を(笑)。
ー もうもっちゃったんですね(笑)。
坪井 はい。いろいろ知り合いの方に聞いてもらって、イギリスに全寮制の音楽学校(*注:メニューインスクール)があるというのでそこに行きました。
ー それは音楽をやりたかったんですか?
坪井 そうですね。私から行きたいと言いました。
ー 何かきっかけみたいなのはありましたか?
坪井 桐朋の高校の音楽科を受験するつもりだったので、夏期講習を受けに日本に帰ってきたんですね。そのときに昔ついていた先生にお願いしたんですけども、その方にずいぶん日本にいた時と変わっているし、もう帰ってくる必要ないわよって言われて(笑)。もう私が留学しているということは伝えてあったんですけれども、その学校を先生もご存知で、行ってみたらということになって、イギリスに行くことになりました。それで母がお友達でドイツに住んでいる方に聞いて手紙を書いたらオーディションに来ないかという返事が学校から来まして、すぐイギリスに行ったんです。
ー 音楽というといろいろジャンルがあって、通常、若い時期って、若い時期というか子供の時期って、結構ポップとかロックとかに惹かれていくと思うんですが、そうではなかったんですか?
坪井 そうですね。イギリスの学校は寮で、いつも部屋をシェアしていたんですね。同世代の女の子たちと一緒に生活していたんですけれども、その子の影響でラジオや今はやりの音楽は聞いていましたけど、クラシックが小さい時から自然なものになっていたのでそういうほうに興味がありました。もちろんポップスなど聞くのは楽しかったですけれども興味は湧かなかったですね。
ー ご両親は音楽家でした?
坪井 そうですね。うちの母は音楽学をやっていてピアノも弾いていたので小さい時は一緒に弾いていたりしました。
ー じゃ、本当に小さい頃から音楽が身近にあったのですね。
坪井 そうですね。割とそうかもしれない。うちの家族は音楽を聴くのは好きです。
ー 坪井さんはイギリスとスイス・チューリッヒの2ヶ国に留学されていますよね。実際に留学するにあたってそれぞれいい点と悪い点とあると思うんです。イギリスだったらこういう所とか、スイスだったらこういう所とか、そういう事があると思うんですけれども、それぞれ簡単にこういう所が良かったなとか、こういう所が悪かったなとかそういう所があったら教えていただいてよろしいですか?
坪井 メニューインスクールというのは全寮制の学校で、みんな一緒に生活するんですね。その中で普通の授業もありますし、大学などの機関もその中でやっていたのですけども、とても密度の高い留学生活というかみんないつも一緒にそこにいるので。
ー ずっと一緒ですもんね。
坪井 そうですね。だから普通、留学したらどこかに住んで大学に通うとかそういうことですよね。ここは全寮制なので本当に密度の高い、いつもなんというか音楽に触れているという感じですね。最初の頃は、本当に良かったなと思います。友達も音楽をやっているので。
ー もう音楽づけという感じですか。
坪井 づけですね。
ー そのあとに行かれたロンドン王立音楽院はどうでしたか?
坪井 ロンドン王立音楽院に行ったのは、先生についていった形でした。それ以外は、私はそこにあまりいい思い出はないのですけれども(笑)。メニューインスクールというのは本当田舎にあるんです。ロンドンから電車で3、40分行ったところなんですね。そこの駅からずいぶん遠いところで本当に田舎なんですね。王立音楽院というのは街の真中にあって、コンサートに行くにも美術館に行くにも何をするにも近いところでした。そういう意味ではカルチャー的にいい環境だったと思いますけれども、そこでは普通の音楽大学生活を送ったと思います。
ー メニューインスクールでは日本人はいらっしゃいましたか?
坪井 私が行った当時は全部で50人くらいの学校でした。8歳から18歳までの。日本人の方はあと3人くらいいました。
ー その方はどうやってこの学校を選んだりしたのですか?
坪井 大体親御さんが誰かを通じてこの学校を知ったという、そんな感じでしたね。
ー ロンドン王立音楽院は、いい思い出が無かったというのはあんまり学校に満足しなかったのですか?
坪井 そういうわけではないですけれども、留学期間が長くなってきて、このままイギリスにいるのか、それとも他の国に行くのかというのを迷った時期だったんですね。イギリスは、大体10年間いると労働許可を申請できるんです。5、6年いたところでこのままイギリスにいるか、また先生のことも悩んでいてもうちょっと違う先生にしたいなと考えていたんです。それでイギリスで探すのか、どこか違う国で探すのか迷っていた時期でした。
ー スイス・チューリッヒの学校が浮かんできたのはどうしてですか?
坪井 ドイツの夏期講習に一回行ったときに習いたい先生に会ったと感じました。その方が新しいクラスをチューリッヒの音楽院でするのでよかったら来ないかということで、そちらに行きました。私もあともう一年でロンドン王立音楽院を卒業ということだったんですけども(笑)。三年間行ったんですが、結局それも無視して(笑)。
ー もったいないといえばもったいないですよね。
坪井 そうですね。でもチューリッヒのほうで卒業できたらしたいなと思ったので。王立はやっぱりあんまり好きじゃなかったんでしょうね。それで教師の資格をとって、そのままチューリッヒに今もいます。去年の9月にやっとソリストディプロマをチューリッヒで取りました。その前の学歴は小卒だけだったんですよ (笑)。
ー 師事する先生を選ばれたのは、知っている先生がいて夏期講習を受けたのですか?
坪井 メニューインスクールで会った先生で、いい先生だなとその時も思っていました。王立に行くときについていった先生が、前にお世話になった、すごいいい先生だという話をしていてそれで夏期講習に行ってみようかなと思いました。
ー スイスを留学先とすることで何か重要なことはありますか?
坪井 先生をやっぱり見極めることが大事かな。私がチューリッヒで習った先生はもともとミュンヘンで教えていたらしいのです。本当に気に入って教えてくれるのならミュンヘンに行こうかなと思っていたんですけど、たまたまその先生がチューリッヒに行ったのです。夏期講習などを利用して先生と知り合うなり、友人を頼りにしてどういう人がいるのかを知るのが一番いいですね。
ー スイスには、日本人の方は結構いらっしゃいますか?
坪井 チューリッヒと隣のウィンタートゥーアという町があるんですね。そこの学校がオーケストラなどで一緒にプロジェクトをしたりします。チューリッヒには、日本人は20人くらいですね。結構チューリッヒに住んでない方もいらっしゃって、他の国から時々通っていらっしゃる方もいますし、ウィンタートゥーアのほうはちょっとよく分からないのですけど20人近くいるんじゃないですかね。
ー スイスいいですものね。
坪井 中都市なりにもいろいろな催し物があるのでその点はいいです。
ー ヨーロッパは音楽的に盛んな国、例えばウィーンやドイツなどがあると思うのですが、特にどこかの国でやれば良いとか、どこかの町でやったほうが音楽的に有利とか、そういうのはあるのですか?
坪井 もちろんウィーンなどは本当にいろいろコンサートもたくさんあり、代々音楽家が活躍した場で、もちろんそういうのに触れて音楽活動するというのは夢のようですね。ただ、留学にあたっては、私にとってはいい先生についてそこから音楽活動するという事が重要でした。そういう意味でオーストリアやドイツもちろん魅力的ですけれど、別に国や街はあまり関係なく、音楽的に密度の高い環境にいる事が重要だと思います。
ー 現在は、スイスが主なお仕事の場所でしょうか?

坪井 それがまた元の話に戻るんですけれども、スイスへ師事したい先生についていたのですが、彼女が1年後に突然病気になってしまったんです。それで彼女についていた9人の学生もみんな路頭に迷っている感じになってしまいました。それでどうしようかウィーンに行こうか他の国にもあたってみようかと思っていた最中に、非常に有名な今の先生のザハールブロン先生がチューリッヒにいらっしゃることになったんですよ。
ー それはすごい。もちろん、今までザハールブロンはいなかったのですよね。
坪井 はい。彼はケルンとマドリッドの音楽院でずっと教えていたんですけども、結局友人の方の紹介で今度スイスにいらっしゃることになったということです。今までメニューインスクールにもいらしてたし、お友達も先生に付いていたので、先生のお話はもちろん聞いていました。ただ、有名な先生なので私にあうかかなり心配だったんです。ロシア流のなんとかとか、いろいろどうなるか心配だったんです。でも実際ついてみると、本当に基本を極めるじゃないですけど、音楽の原型を崩さずにどうやって教えるかというのを極めていらっしゃる先生だったのですごく良かったです。
ー じゃ本当に基本を忠実にして土台作りをしっかりしようという教え方なんですね。
坪井 そういう教え方ですね、基本的に。なんというかな、音楽のエッセンスをどうやって伝えるかという教え方だったので。もちろん自分の理論を押し付けるという面はまあちょっとありましたけれども(笑)。でも、それを自分で選択できるという形にはなっていたので、先生が言っていることでいいなと思っていることはやるし、別に必要ないと思ったことはあえてやらなかったし。
ー ディスカッションをしながらやっていく感じですね。
坪井 そうですね。先生も日本に何回も何回もいらした方だし、日本語もかなり達者なので。その中でいろいろ楽しみながらディスカッションという感じですね。それで現在は、先生のアシスタントなんですね。
ー 通常オーケストラや室内楽などもスイスで行っているのですよね?
坪井 私は弦楽四重奏をかなり積極的にやっていて、スイス人の方と結構頻繁にしています。
ー 留学をする方は、留学することが目的の一つであると思うのですが、その後に仕事をしたいと思う方は多いと思うのです。スイスで仕事をするにあたってどういうふうにすればプロとして活動できるのですか?
坪井 そうですね、私のカルテットの場合で言ったら結成した後すぐにコンクールを受けました。そういう機会を与えてくれるコンクールなどに入賞すると結構連絡があります。また、新聞に載るのでそれを見てもらうなどですね。でも、結構人づても多いですよね。もしかしたら大体人づてかもしれません(笑)。
ー やっぱり人なんでしょうか、一番は。
坪井 クラシックを好きな方は結婚式とかパーティーでクラッシック音楽をやってくれないかというのがあるのです。チェロの人が、そのような仕事をやっている仲間だったんですね。それが延長して、コンサートなどの連絡を受けて契約書作ってというようになっていきましたね。やっぱりスイスではかなり人づてが多いと思います。
ー スイスで仕事をするにあたって、日本人が有利な点もしくは不利な点はありますか?
坪井 日本人の方はだいたい時間に遅れてきたりするなどはまずありません。皆さん、一生懸命練習してくるので、変な演奏をしないというように信頼さていることもあります。演奏の面でなくても、まじめさという面で日本人というのはだいたい信頼されていますね。
ー 僕のイメージだとスイス人も含めてドイツ系というのは結構硬いですよね。それでも遅れてくるような人がいらっしゃるんですか?
坪井 スイス人は大体時間どおりに来ますね。スイス人は本当にそういう面ではきちっとしてます。でもその他の人種がねー(笑)
ー ラテン系ですか(笑)
坪井 そうですね。すごいですよ。人によるんでしょうけど(笑)。
ー 坪井さんはクラシック音楽を小さい頃からやってきたと思うのですが、そういう方にとってクラシック音楽ってなんでしょうか?
坪井 小さいときから慣れ親しんだのですが、クラシックはいろいろな事がまざって人が作り出したという感じがすごい好きですし、本当に出会ったことに感謝しています。
ー 少し話をもどさせていただくのですが、いろいろな国があってスイスを決めるという部分。先ほどウィーンなども引き合いに出しましたが、スイスを留学先に決めることで何か良かったと思うところはありますか?
坪井 学校からいろいろ頼まれたり、本当にいろんな事をさせてもらったのでそれはすごく良かったと思います。イギリスでは私はあんまり大学でそういうことをさせてもらったことはなかったので。メニューインスクールでは何でもやったんですけど、そういう面でも人づてというのはあるんでしょうけどね。
ー なるほど。
坪井 人を通して知り合ってそこからいろいろ始まるというのが。
ー あるということですね。ところで坪井さんの将来の夢を聞かせていただいてよろしいですか。
坪井 学校で先生のアシスタントという教えることを始めて、それが意外なことにすごく好きになっています。今はアシスタントなので、先生がいないときに補助をするという形です。自分がいろいろな方の役に立てるのは本当にうれしいと思っていますので、今後、自分でもこの部分を伸ばしていきたいと思っています。将来的にどこにいるにしても、今と同じように大学などで教えることを基本にやっていきたいと思っています。
ー 演奏活動をメインにするよりは、教えることをメインにしていくということですか?
坪井 両方ですね。でも教えることは本当に興味があります。二つの夏期講習会に先生と一緒に行ったのですね。そこでかなり興味も沸いたし、いろいろな人と知り合えるのは良かったです。
ー 先ほどから聞いていると人と知り合うことがお好きなようですね。どういう形であれいろいろな人と知り合っていくことで自分がどんどん面白くなっていくという事ですね。
坪井 そうですね。でも人と知り合うには、やっぱり語学力も必要ですね。最初にスイスに来た頃は知り合いも少なかったですし。
ー ドイツ語ですもんね。
坪井 ええ。だんだん慣れていって信頼を得るというか。信頼関係ですからね。
ー だいたいどのくらいかかりました。ずいぶん友達も多くなってきたなと思ったのは?
坪井 そうですね。最低2年ですね。
ー その位は必要ということですね。
坪井 スイス人は、イギリス人も同じところありますけど、最初はあまり信用しないですよね。遠めで見ていて、ああ、あいつは大丈夫だ、みたいになっていくと思います。そうやって試しているのでしょうね。多分。ラテン系の人だともうちょっと最初からフレンドリーだと思いますけど、ドイツ系の方はちょっとまあ離れて見ていますね。
ー 坪井さんにとって海外で、ヨーロッパというのですか、ミュージシャンで活躍する秘訣みたいなもの、成功する条件みたいなものはあるとお考えですか。日本人として。
坪井 海外ならもとの話になりますけど人と知り合うことですね。人脈を他の面でも広げていきたいのだったら本当にインターナショナルな環境に恐がらずにいることです。いろんな方と知り合うというのにはいろんなプロジェクトに参加するなり、面倒くさいことでも色々やってみて友達になって、その輪を広げていくとか。そういうことも大切だと思います。
ー やっぱり輪を広げていかないと物事って何も進まないですもんね。いろんなところから仕事も入ってこないだろうし、人間的にも大きくならないですよね。
坪井 電話番号回してもらうじゃないですけど、いろいろなところに可能性を広げていくとか、本当にそういうのがうまい方っていらっしゃるんですよね。でも押し付けているんじゃなくて、わきまえてちゃんとやっている方というのがいらっしゃって、見ていてすごいなと思います。まあ、あんまりやると….ですけど(笑)。でも面白いと思います。
ー 面白いですよね。どんどん人が広がっていくのって。スイスの場合でもイギリスの場合でも能動的でないと、自分のコネクションを広げられませんか?
坪井 それはそうですね。もちろんその場にいることも大切です。その場というのはいろんな事があると思うのですけど、コンクールなり、集まりなりそういうことに自分から働きかけていかないと、来てくれるわけでもないですからね。来てくれる場合もあるでしょうけど、いろんな方に話しかけたり、まめな方がかなりいいですね。
ー まめな方でないと結局いろんな人を知ることはできないですからね。最後に今後留学される方にアドバイスを頂いてよろしいですか?
坪井 とにかく自分ということをしっかり持って留学することが一番だと思います。いろいろな失敗をしても自分で選択したことだと思うと後悔しないと思うのですよね。何かやり遂げたときは自分でやったと思うと成長したなと感じるでしょうし。留学する時点になって友達などに頼る面があっても、それからは自分でやっていかなきゃいけないので、まず自分からというのが一番大切だと思います。
ー 分かりました。日本人は性格的に、消極的になりがちで、それが美徳になっています。坪井さんはスイスで教える側の立場に立って、そういうのが見えていると思うのですが、典型的に見て日本人はヨーロッパでは消極的な感じがしますか?
坪井 やっぱりそうですね。向こうの子達というのは本当に良く質問してきますし、そういう意味では違う性格だとは思います。しかし、それを無理に積極的にするように押し付けるようになっても日本人のいいところはいいところだと思います。そういうところが外国人の方達に気に入ってくれるかも知れないですしね。そういうものは結構大切にした方がいいと思います。でも、そればっかりだと何にも出来ないですけれども。控えめなところは控えめにして、それでも自分でちゃんとやっていくということでしょうね。
ー 今後の演奏会の情報を教えていただいてよろしいですか。
坪井 パドヴァというヴェネチアの近くの町でリサイタルがあります。(2005年)11月、12月は結構カルテットのコンサートがあります。一つがドイツのシュトゥットガルトです。来年の1月にはチャイコフスキーのヴァイオリンコンチェルトをアルメニアで弾きます。1月に施設のコンサート、2月、3月はピアノとデュオのリサイタル、4月はチューリッヒトーンハレで室内楽のコンサートがあります。
ー わかりました。本当に最後に留学する方にこれだけは言っておきたいなというところはありますか?
坪井 将来のビジョンって自分の中でいろいろ変わってくると思うんですけど、私なんかも全然変わってきちゃったんですね。でも細部は変わったけど大きいビジョンはあまり変わっていないように思います。そういうことを思い描くことも大事かと思います。例えば何年留学したいのか、日本かもしくは海外の活動を広めていくのか、演奏でやっていきたいのか教えるのかそれとも両方か。この二つでなくとも色々な可能性はあります。私がシンガポールにいたころは大きい夢だけを頭の中で描いていたような気がします。
ー ビジョンが大切ということですね。ありがとうございました。