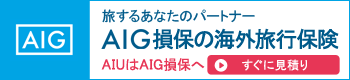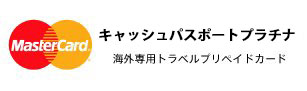金沢多美さん/ピアノデュオ/イスラエル
金沢多美さんプロフィールー

東京都出身。国立音楽大学付属高校卒業。リュエイユ=マルメゾン地方音楽院、パリ国立高等音楽院卒業。ヨーロピアン・モーツァルト財団から奨学金を得てモーツァルト・アカデミーで研鑽を積む。96年にイスラエル人ピアニスト、ユヴァル・アドモニーとデュオ結成。以来、数々の国際コンクールで優勝。2000年東京国際ピアノ・デュオ・コンクール第1位、2001年ローマ・ピアノ・コンクール、デュオ部門第1位受賞、2002年イブラ・グランド・プライズ優勝。2005年大阪国際室内楽フェスタでメニューイン金賞獲得。2008年グリーグ国際ピアノ・コンクール・デュオ部門第1位受賞。2008年にイスラエル文化省より「文化大臣賞」を受賞。現在デュオは、イスラエルを拠点に演奏活動。アジア音楽祭、ブダペスト春の音楽祭、バード・ヘレンハルプ音楽祭、オデッサ・ディアローグ、イスラエル音楽祭等から招聘。イギリスBBC放送、NHK、よみうりテレビ、イスラエル国営放送、BNRブルガリア放送、ブダペスト国営放送等に出演。2008年7月にナクソスからリリースされたリストの交響詩(2台ピアノ版)4曲を収録したCDは、世界各国で放送され、国際的に高い評価を得ている。デュオはイスラエルの芸術高校で教鞭を執り、ピティナ(日本)、韓国国立芸術大学、ノルウェー国立アカデミー等でマスタークラスを行い、後進の指導に力を注いでいる。
-最初に、簡単に略歴を教えてください。
金沢 幼い頃住んでいた所の近所にピアノの先生がいらっしゃって、当時子供がピアノを習うという流行があったこともあって、そこで兄が習い始め、後に私も4歳くらいから習い始めました。それから国立音大付属の小学校に入学しまして、付属の高校まで進みました。高校卒業後パリに留学し、最初の2年間はパリ郊外のリュエイユ=マルメゾン地方音楽院で勉強をし、その後、パリ国立高等音楽院に入学しました。卒業後、進路を迷っている時に、偶然ヨーロピアン・モーツアルト財団のモーツアルト・アカデミーのポスターを見つけたので、そこに申し込んで、奨学金を頂き、プラハで1学期、クラコフで1学年在籍しました。そこで(現在の夫である)イスラエル人のピアニストと知り合い、これからピアノ・デュオでプロとしてやっていこうと決めました。翌年、カナダのバンフ・センターという、プロを目指す人やプロとして活動する人がプロジェクトに専念するために滞在する芸術センターで、デュオを結成するため1年程滞在しました。そこでレパートリーを増やすことに取り組み、コンサートに出演し、録音もしました。それ以来、デュオを専門に演奏しています。98年からイスラエルに住み、演奏活動の他、高校で室内楽やデュオを教え、プライベートではソロのレッスンもしています。
-小学校から音楽の学校に通われましたが、それはご自身の希望ですか?
金沢 いえ、それは自分の意思ではなく、母に“手に職を持つべきだ”という考えがあって、音楽学校に行ったらいいのではないか、と思ったそうです。女の子だし、芸術に触れさせようという考えで、最初から音楽家にしよう、と考えていたわけではないと思いますが……。
-ご自身は普通の公立学校ではない学校に通うことに抵抗はありませんでしたか?
金沢 そうですね。まだ物心もついていませんでしたし、私の小さい頃は“お受験”のようなこともなくのんびりとしていたので、私も何の準備もないまま受験しました。幼稚園を休んで、入試に行ったのですが、“幼稚園を休んでまでどこに行くんだろう?”って思っていました(笑)。
-そうすると、気がついたら音楽の小学校にいた、という感じですね。
金沢 ええ、そうですね。
-その後、高校までピアノを習われていたそうですが、ご留学を考えたのはいつ頃ですか?
金沢 小さな頃から、クラッシック音楽や西洋文化に憧れを抱いていて、ヨーロッパに住んでみたいという夢がありました。小学校の頃のピアノの先生が、ウィーンに留学された方だったのですが、その先生のお話を聞いて、いつかは必ず行きたいと思っていました。音楽系の学校にずっと通っていたので、大学まで進み、卒業したら留学をして……と思っていたのですが、ヴァイオリニストの叔母がいまして、その方に高校3年生のときに相談をしたら、「早く行った方がいいわよ。高校を卒業したら、もう留学したほうがいい」と言われました。そこで、さすがに悩みましたが、両親も私の意思を尊重してくれたので、チャンスがあるなら高校を卒業したらすぐに留学したいと思いました。
-そのとき不安はありませんでしたか?
金沢 もちろん不安はありましたが、それ以上に周りが理解してくれて、行かせてもらえるというこの素晴らしいチャンスへの喜びのほうが大きかったです。

-フランスを選ばれたことには何か理由があったのですか?
金沢 私の場合、前もって国の音楽事情を調べた末選んだわけではなく、叔母が「私の知り合いがいるから」ということで、フランスに決めたんです。パリはピアノを勉強するのにいい所だし、生活も私がある程度アレンジするからそこに行きなさい、と勧められました。
-そうすると、その叔母さまがほとんどオーガナイズしてくださったんですね。
金沢 始めのうちはそうでしたね。言われたのでそこに飛び込んで行ったという感じです。
-では、留学前に先生に会ったり、レッスンを受ける機会はなかったんですね。
金沢 そう、なかったんですよ(笑)。叔母を100%信頼していましたね。いまどき、こんな方、いらっしゃらないですよね(笑)。
-そうですね(笑)。やはり先生との相性というのもあると思うので……。
金沢 そうですよね。でも、叔母の言葉だけを信じて行ったのですが、始めに入学したリュエイユ=マルメゾン地方音楽院でついた先生は、パリのコンセルヴァトワールを引退なさったルセット・デカーヴ先生という方で、昔はマルグリット・ロンの弟子で、後に彼女のアシスタントを務め、現在のパリの教授達を皆教えたような大御所の先生だったんです。そういうフランス派のピアノ奏法の真髄のような方に教わることができて、本当に幸運だったなぁ、と思っています。
-実際に受けてみて、相性はばっちりだったんですね。
金沢 ばっちりというか……、かわいがっては下さいましたし、私もまっさらの気持ちで行ったので、先生の仰ることなら、と一生懸命勉強していました。留学の形やキャリアの成り立ち方というのは人それぞれですから、こんな乱暴な留学をした人もいたんだ、とご参考になれば嬉しいです(笑)。
-その後、パリ国立高等音楽院に進まれたわけですよね。
金沢 そうですね。デカーヴ先生の勧めもあって、そうしました。
-パリ国立高等音楽院というとヨーロッパではトップクラスの学校ですが、当時の入試の様子など覚えていらっしゃいますか?
金沢 二次試験まであって、一次試験はプログラムAとプログラムBを用意することになっていました。プログラムAはショパンのエチュード1曲とクラッシックまたはロマン派の任意の曲を1曲、Bは別のショパンのエチュード1曲と近代の曲を1曲。それで試験の場で、どちらかのプログラムを弾くよう、審査員から指示がありました。
-当日までわからないんですね。
金沢 そうですね。どちらが当たるかはその場まで分からないので、どちらも用意しておかなければいけませんでした。それが一次試験で、その2週間後に二次試験があるのですが、課題曲は二次試験の1か月前に発表されました。なので、その1か月の間に二次試験の曲も完成させておかなければいけない。私達が入学した年は、バッハのフーガ、ショパンのインプロンプチュ2番、プロコフィエフのソナタ2番の2楽章が課題曲でした。その他に初見のテストがあり、その年はフルートとのアンサンブルでした。
-倍率もものすごいですよね。
金沢 そうですね。競争は厳しいですね。だいたい300名ほど受けて、受かったのが16名でした。でも、フランス人の中にはダメだったらまた来年、と何年も何年もかけて受験する人も多くいました。
-パリ国立高等音楽院の先生探しはしましたか?
金沢 私の場合は、その前にリュエイユ=マルメゾン地方音楽院にいて、デカーヴ先生についていたので、その先生が紹介して下さったブルガリア出身のヴァンシスラフ・ヤンコフ先生という方のクラスに入りました。最初の3年間ヤンコフ先生についた後、先生が引退なさり、引き続いて就任されたパスカル・ドゥヴァイヨン先生に2年間ついて勉強しました。お二人は全くタイプが違いますが、それぞれ素晴らしい演奏家で教育者でもあり、こういった方々について学ぶことができたのはとても恵まれていたと思います。
-当時、日本人の方はどれくらいいましたか?
金沢 結構いましたよ。例えば、私の入った年はピアノ科で日本人が多く、4人いて、他の楽器では、ヴァイオリン一名、フルート一名、ハープ一名、ギター一名いました。他の学年にもピアノ科の他にも弦楽器、管楽器や、作曲科に何人かいて当時から日本人に人気のある学校だったと思います。
-小学校から高校まで日本で音楽を習ってらして、その後、いきなり海外のレッスンを受けたわけですが、日本との違いで驚いたことはありましたか?
金沢 そうですね。驚いたというか感銘を受けたのは、音の響きや音の質に大変繊細な感覚をもって音楽と接し、またそれを具体的に生み出すためのテクニックを教えて頂いたことや、曲の構築性や様式について西洋音楽という自分達の文化として身についていることを教えて下さったことです。特にフランス音楽を勉強したときは、自分達の普段使っている言葉のように自然に知っていることを伝えて下さった、という感じがしました。デカーヴ先生は私が習っているときは既に80歳を越えていたので、フランス音楽の作曲家と直に交遊があったり、それこそフォーレとロマンスがあったようなんです(笑)。それくらいフランス音楽と身近な人達から、教わることができて、そのエッセンスに触れることができた気がします。それはやはり日本では得られなかったことだと思います。あと私にとっては、先生が国際的演奏活動をなさっていて、その現役の演奏家に教わることができる、ということにすごく感動して、実際に演奏されている方からアドバイスを受けると、より実感がわいて信頼できました。
-プロの音楽家として活動されようと思ったのは、この頃からですか?
金沢 漠然とですが、音楽を自分の職業にしていくんだろうな、と思い始めたのは、中学校、高校の頃からだと思います。ただ、どうやったら音楽家になって、それを仕事にできるのか、ということがよく分からなかったですね。パリに来た頃も、よしこれでやっていくんだという決意はありましたが、具体的にどうしていけばいいのかは、分からないままでした。
-ご留学して、より具体的になったりはしましたか?
金沢 才能がある人は沢山いるし、皆が夢を抱いているので、音楽で成功するというのは厳しい世界ですよね。ただ、その頃から私はアンサンブルに向いているな、と思ってはいました。
-そうなんですね。それは、どうしてですか?
金沢 舞台に立つときに一人ではない、ということが心強かったですし、人と合わせて一つの結果にするという作業が楽しくて、それが自分の性分に向いていると感じていました。

-現在は、ご主人と2台のピアノ・デュオで活躍されているわけですが、最初にデュオを始めたのはいつからなんですか?
金沢 実は、彼と出会うまではあまりデュオの経験がなかったんです。連弾は小さな頃から弾いていましたが、デュオはあまり経験がなく、どちらかというと他のアンサンブルのほうに興味がありました。でも、彼と恋をしてカップルになって、自分たちはこれから一緒に生活していくという確信があって、そこで、2人ともピアニストとして別々にキャリアを積むよりも共に力を合わせてやっていこう、という考えが彼にあり、デュオとして活動していくことになりました。
-ご主人も金沢さんと出会う前は、あまりデュオの活動をされていなかったんですか?
金沢 そうですね。ただ、彼のほうが少し経験はあったそうです。彼はテル・アヴィヴ大学やロンドンのロイヤル・アカデミーで勉強していた頃、デュオを弾く機会があって、このジャンルの可能性を信じていたようです。
-素敵ですね(笑)。
金沢 いえいえ、実質的なところもあるんですけど……(笑)。
-今までこんなにデュオで活動されたことはない、とおっしゃっていましたが、ソロとの違いやデュオならではの難しさはどんなところにありますか?
金沢 技術的なところで言えば、ピアノは複数の声部を奏でる楽器ですよね。その声部の音色を弾き分けることで、オーケストラのように弾くこともできるわけですが、それが2台になると、声部も倍になるわけです。だから、弾いている時に、自分はどの声部を押しているのか、バランスはどうか、ということを常に意識しなければいけません。そうしないと、ただ音が氾濫しているという状況になってしまうんです。遠近感を持たせるということにすごく気を使います。それは、他の室内楽でも言えることですが、特に同じ楽器でこれだけテクスチュアが厚いと、一つ一つの声部の音量、音質、キャラクター、タッチに意識を集中させて弾かなければならないのです。それは、その分自由さがないと言ってしまえばそうかもしれませんが、自分達で何を築いているのかきちんと分かっていれば、素晴らしい結果が生まれます。2人で作り上げていく作業は、本当に煩雑ですが……。

-その分、お相手が旦那さまなので、スムーズではないのですか?
金沢 うーん……、皆さん、そうおっしゃってくれるのですが、やはり、仕事に対してはとても厳しいですね。仲良くというわけにはいきません。怒られたり、怒ったり……(笑)。やはり、作り上げて行く作業は、試練があって当然ですよ。でも、私たちはプライベートでもわりと演奏のことに没頭しているので、これで2人が別々のキャリアに進んでいたら、逆に接点がなかったかな、と思うので、2人で一緒に目指すことがあってよかった、と思っています。
-イスラエルの音楽事情を教えてほしいのですが、クラッシックは盛んなところなんですか?
金沢 イスラエルというと日本では紛争の国、危険な所、というイメージがあるかもしれませんね。イスラエルは、中近東に位置するユダヤ人国家で、国家としてはまだ60年しか経っていません。国家としては若いですが、4000年もの歴史があり、ご存知の通りキリストが生誕した所であり、何千年もの離散の末戻って来たユダヤ人の築いた国です。クラシック音楽事情に関しては、ヨーロッパ各国や旧ソ連の各国から移民して来た人達が築いた土壌がきちんとある所なんです。なので、オーケストラもあれば、ホールもあるし、教育システムもきちんとある国です。特に90年代のソビエトの崩壊で、旧ソビエトから多くの音楽家も移民して来ました。そういうこともあって、音楽のレベルはすごく高いと思います。
-ロシア系の音楽がどちらかと言えば、盛んなんですか?
金沢 ロシアだけでなく、ハンガリー、ルーマニア、ポーランドなど、どちらかというと東ヨーロッパの方々が多いですね。ユダヤ人が大半ですが、そういった彼らの優れた特性に触れることができるのもイスラエルならではだと思いますし、それはとても幸せなことだと思います。
-オーケストラも沢山あるんですか?
金沢 そうですね。一番有名なのは、来日公演もするイスラエル・フィルだと思いますが、他にもオーケストラは沢山あります。
-今後、イスラエルのオーケストラに入団したい、という方がいらっしゃるとしたら、比較的簡単に入れるものなのでしょうか?
金沢 どうでしょうか。イスラエル・フィルは、空きがあるとオーディションを開いていますので、海外から来てメンバーとして演奏していらっしゃる方もいますね。
 -音楽学校は沢山あるんですか?
-音楽学校は沢山あるんですか?
金沢 大学、アカデミーに属する音楽学校は、テル・アヴィヴにあるテル・アヴィヴ大学ブッフマン・メータ音楽院とエルサレムにあるルービン音楽アカデミーがあります。あと夏期講習では、ニコライ・ペトロフなど有名な先生が教えに来るピアノのマスタークラスがあり、シュロモ・ミンツが主催しているヴァイオリンの夏期講習もあります。
-それは毎年、開催されるんですか?
金沢 そうですね。よかったら、是非、イスラエルにもいらしてください。
-そうですね、留学を考えている人の中にはイスラエルが気になっている方もいらっしゃると思います。
金沢 日常生活は非常にのんびりしたところもあって、危険なところを除けば、普通に生活もできるので、是非、考えてみてほしいですね。
-今後、夏期講習だけでなく、アカデミーに留学されたい方も出て来るかと思うのですが、受験状況はどのような感じでしょうか?
金沢 入学するのは、それほど大変ではないと思います。ヨーロッパのように留学生も沢山いて……、という環境ではないですし、あまりレベルが高くない人から既に演奏活動をされている若手の方もいます。先生と縁があれば、イスラエルへの留学も良いと思います。
-アカデミーに通われているのは現地の方が多いのですか?
金沢 そうですね。でも、多くはありませんが、テル・アヴィヴの大学は上海の大学と交流があるようで、常に何人か中国からの留学生もいますし、ヨーロッパからの留学生もたまにいます。実は、今年度ヴァイオリン科に日本からの留学生も一人いるんですよ。
-ちなみに、この音楽アカデミーに入るには語学の証明は必要ですか?
金沢 現地は、ヘブライ語ですが、英語ができれば問題ないと思います。普段の生活でもヘブライ語ができなくても、英語ができればあまり困ることはないと思います。
 -日本人がイスラエルで演奏家として活動するにあたって、有利な点や不利な点は何かありますでしょうか?
-日本人がイスラエルで演奏家として活動するにあたって、有利な点や不利な点は何かありますでしょうか?
金沢 有利な点というか……、ありがたいことに日本のイメージというのは悪くはないし、政治的にもイスラエルと摩擦があるわけではないので、温かく受け入れて下さいますね。最近では、漫画などのサブカルチャーやお寿司なども人気があります。そういう意味で興味を持ってくださるので、溶け込みやすいですね。不利な点は、日本人だからというわけではありませんが、新しく入って来た人間として、前からある音楽や仕事の輪に入っていくのは大変でした。そこにうまく認めてもらって、入れてもらうのは、後から来る者には少々不利というのはしょうがないですよね。
-それはイスラエル人の国民性というか、気質から来ているのでしょうか? 仲間意識が強い、といったことは感じますか?
金沢 そうかもしれません。何せ小さな国なので、皆が皆を知っている、という “村”のような感じがあります。でも反対に打ち解けてしまえば、顔パスというか、コネが効いてしまう社会で、例えば「洗濯機を買おうかな」と言うと、「僕のおじさんの近所に住んでいる人のいとこがそういう仕事をしているから、買わないでそこに行け」と言われたりするんです(笑)。
-面白いですね。
金沢 やっぱり、ドイツやフランスといったヨーロッパではそうはいきませんよね。やはり、キャリアを築くということを考えると、そういうこともすごく重要だと思います。1人で仕事をしていけるわけではないので、そうやって人の輪に入って、継続させていくということが必要になってくるんです。そういうことって、学校では教えてくれませんし、私達も試行錯誤を繰り返して、身に付いていったことですが、やはり、人の繋がりというのはすごく大切だと思います。それは与えてもらうだけではなく、自分が与えてもらったら、今度は与えてあげる、音楽の世界であっても、そういうギブ&テイクで成り立っている、人間の営みであるということを分かってしまうほうが楽なんですよね。だから、表面的なお付き合いでない人間関係を築くことが大事だと思っています。
-ところで、今回の金沢さんのお話を読んで、イスラエルに対するイメージが変わる人も多いと思うんですよ。
金沢 そうだといいですね。やはり、知られていないということが残念です。これだけクラシック音楽のレベルや密度が高い国だということを皆さんに知ってほしいですね。ヨーロッパからなら4時間くらいで来られますし、ユダヤ人の音楽に直接触れてみたいという方は、是非来て頂きたいと思います。
 -今後の音楽家としての目標を教えていただけますか?
-今後の音楽家としての目標を教えていただけますか?
金沢 ピアノ・デュオが自分達のアイデンティティのようになっているので、これからもデュオとして、レパートリーを増やし、演奏し続けたいです。また、このメディアをより浸透させるため、フェスティバルやマスタークラスなど開催し盛り上げていけたらな、と思います。それから、イスラエル音楽の演奏や初演など今までもやってきたことですが、これからも作曲家の方達とコラボレーションしていきたいと思っています。やはり一緒に創造する意義とその喜びがあるので。彼の方は、いずれ作曲も手がけたいと考えているので、彼の曲を二人で演奏するコンサートが未来像になっています。
-金沢さんご自身はいかがですか?
金沢 実際、演奏についての目標ですが、フランス人女優のジャンヌ・モローがインタビューで言っていたのですが、役に入っていく時は、自分を空にして、中にエネルギーが流れる管のようになると例えていました。それを聞いて、あぁなるほどな、と思いまして、私も演奏する時は、そういう境地でいたいと思いました。エネルギーがよどみなく流れる管、媒体でありたいと思ったんです。そういう気持ちで演奏できるときもたまにあって、そういう時は、あぁ良かったと思えるんですよね。
-最後にこれから留学を考えている方にアドバイスをお願いします。
金沢 今は留学に関する情報も沢山あって、気軽に海外にも行けて、逆に海外から日本に先生もいらして講習も受けやすい環境なので、皆さん、よりスマートに選択されて留学なさる方が多いと思うんです。でも例えば、留学先で希望の学校に入れなかったり、卒業できなかったり、希望の先生につけなかったり、ついてもレッスンをあまりしてくれない、という予想できないことが起きる場合もあります。はっきりしたプランがあるのは結構だと思いますが、そういう壁にぶつかってしまったときに、臨機応変に対応して、プランと違っても大丈夫、という気持ちを持ってほしいです。自分の希望や目標を大局的に見ることが大事だと思います。そういう時に、しっかり自分と向き合って、考えて悩み抜くということがいい経験になって、人間が生きのびていく力というのが養われていくと思います。一人で悩むだけじゃなくて、助けを求めることも力のひとつだと思いますし、恥ずかしがらないで、めげないで、予定と違ってもいいんだ、と。
-なるほど。
金沢 それから、留学というのは、一時的な講習会と違って、そこに住んで生活をするということなので、現地で出会う人達とのコミュニケーションするということを大切にしてほしいと思います。私自身、日本を離れて久しいですが、日本人というのはコミュニケーションに対して、気を回すことが上手だけど、その反面、依存心が強い気がします。空気を読む、というのは本当に日本人らしい表現で、空気は読めないものなんですよ(笑)。やはり、わかってもらえない時はわかってもらえないような表現しかしていない、ということなので、そういう責任感を持って、コミュニケーションをとってほしいと思います。それは、語学力の有無ではなくて、伝えたい意思があるのかが、重要だと思います。心から語りかければ、イスラエルでもフランスでもどこの国に行っても返ってくるものはあるし、人と繋がる喜びというのはあります。自分がそこに一時的に留学をして、何かを学んで帰る、与えてもらう側だけだというのではなく、自分も何かを与えられる存在で、きちんと交流ができるという認識をもって留学をしてほしいなと思います。
 -ありがとうございます。最後に、成功の秘訣があれば、教えていただけますでしょうか。
-ありがとうございます。最後に、成功の秘訣があれば、教えていただけますでしょうか。
金沢 偉そうにいうほど成功していませんが(笑)、失敗の連続で覚えたことをお話させて頂きますね。音楽を職業にしている方というのは、音楽大学やアカデミーを卒業した方が多いと思います。そういう学校を出て、スムーズにキャリアが築けるのが、いいに越したことはないと思いますが、そうでなかった場合、知恵を絞って、自分なりのクリエイティブな戦略を持ちかけるくらいの姿勢でいなければ、何も起こらないと思います。私も若い頃は依存心が強くて、きちんと弾けていればいいことがあるんじゃないかと夢見ていたのですが、ある程度戦略を持って、アグレッシブに仕掛けていかないとダメだと思います。具体的に言うと、コンクール、コンクール……というと嫌かもしれませんが、やはりコンクールで採った賞をマスコミ伝えて話題を作ったり、あまり使われていないホールを見つけて、市町村の人にかけあって、自分の巣にしてしまう、とかね(笑)。
-えー! それは、金沢さんがされたことですか?
金沢 そうですね(笑)。イスラエルで。そうやって、自分の場所を作って、そこに知り合いの演奏家を呼ぶ。そうすると、向こうも貸しがあるということで、今度は彼の巣に呼んでくれる。そうやって、自分で知恵を絞って、どんどん発言権を身につける。自分でアピールして、売り込むのっていい気持ちはしないし、難しいことだとは思いますが、出しゃばらずエレガントな線を守りながら、謙遜もせず、自分の幅を広げていく。それからチャンスというのは、自分が準備万端に用意できたときに転がってくるものではなくて、いつ転がっているかわからないものだから、そういう時にいつでもぱっと心を開けるようにしておくのが大事だと思います。一期一会という言葉もありますし、そこでもじもじしていたら、本当にもったいないんですよ。
-本当にそうですよね。
金沢 そうやって、人と繋がりができて、依頼があったら、まずイエスと答えるようにしています。交渉などは彼がすることが多いので、彼の対応を見て学ぶことも多いんです。私はどうしても日本人的なんですよね。例えば、「6月にこういう曲を演奏してほしい」という依頼を受けると、その時期はあのコンサートも入っていたから手が回らないんじゃないか、とか、二股になってしまうんじゃないか、とか考えてしまって、「少し考えさせてください」と答えるのが誠実である、と思ってしまうんですよ。でも、そうではなくて、まずは、イエス。やりたいということを伝えるのが大事なんですね。その後で、曲は変えられるか、とか、日程の相談をすればいいんです(笑)。厳しい世界なのでハッタリでもいいから、まずは、熱意を伝えていくことが大事なんですよ。
-なるほど。
金沢 あとは、そうやって行動していても、断られ続けることもあります。でもそれは、あまり個人的に否定されていると考えずに、とにかく続けていくということが大切なのではないかと思います。失敗から学んだ事ですが、少しでも皆さんの参考になればいいな、と思います。
-はい。本当に今日は貴重なお話をありがとうございました。
金沢 こちらこそ、どうもありがとうございました。
************************************************
金沢多美さんの最新情報や演奏は下記ページからご覧になれます。
デュオのサイト:http://www.kanazawa-admony.com
youtube(演奏):http://www.youtube.com/user/admony
ナクソスのアルバム:http://ml.naxos.jp/album/8.570736
東京で金沢さんのデュオリサイタルが開催されます!
世界で活躍するデュオのコンサートに足を運んでみてはいかがでしょうか?
◆デュオ・アドモニー リサイタル◆
金沢多美 & ユヴァル・アドモニー
2台ピアノによるリスト交響詩 ~人間性のドラマを奏でる~
「オルフェウス」「理想」「前奏曲」「マゼッパ」
10月26日(月)19:00 開演 東京文化会館小ホール
一般 ¥4000(全自由席) / シニア・学生 ¥3000
チケット取り扱い:
• チケットぴあ 0570-02-9999( Pコード331-570)
• 全日本ピアノ指導者協会(ピティナ) www.piano.or.jp/concert/support
• 東京文化会館チケットサービス 03-5685-0650
• IVSテレビ制作 03-5261-9545 (12:00~19:00土日・祝日を除く)
後援: イスラエル大使館/ (社) 全日本ピアノ指導者協会/ ナクソス・ジャパン(株)
助成: 財団法人日本室内楽振興財団
お問い合わせ: IVSテレビ制作
川見優子さん/ヴァイオリン/マレーシア・フィルハーモニー・オーケストラ/マレーシア
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回マレーシア・フィルハーモニー・オーケストラ(MPO)でご活躍中の川見優子(カワミユウコ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年6月)
ー川見優子さんプロフィールー

北九州市小倉北区生まれ。3才よりピアノ、6才よりヴァイオリンを始める。第43回全日本学生音楽コンクール西日本大会ヴァイオリン部門中学生の部第1位。桐朋女子高校音楽科、桐朋学園大学を経てプラハ芸術アカデミーに留学。プラハ芸術アカデミー修士課程を栄誉賞を受けて卒業。アカデミー在学中、J・ビェロフラーヴェク氏指揮、プラハ芸術アカデミー学生のコンサートミストレスを務める。弦楽カルテットの第一ヴァイオリン奏者としてオランダのチャールズ・ヘンネンコンクールで3位、マルティヌー国際音楽コンクール弦楽四重奏部門(プラハ)で2位を受賞。アマデウス弦楽四重奏団、アルバンベルグ弦楽四重奏団などから指導を受ける。ヴァイオリンを篠崎永育、三木妙子、江藤俊哉、石川静、V・スニーチルの各氏に、室内楽を、原田幸一郎 藤井一興、L・コステツキー(スメタナカルテット), P・メシエーレル(ターリヒカルテット)の各氏に師事。又、I・スターン、A・デュメイ、Z・ブロン各氏のマスターコースを受講。これまでに、韓国KBSシンフォニーオーケストラ、チェコのピルゼン・オーケストラ、パルドゥビツェ室内フィルハーモニー、プラハ室内フィルハーモニー、スロヴァキアのコシツェ・フィルハーモニーなどにソリストとして共演。2004年よりマレーシア・フィルハーモニー・オーケストラ(MPO)入団。
-まずはじめに簡単な自己紹介をお願いします。
川見 3歳からピアノ、6歳からバイオリンを始めました。中学校1年生のときに、全日本学生音楽コンクール西日本大会ヴァイオリン部門中学生の部で1位を受賞しました。高校から東京に上京して、桐朋女子高校音楽科を卒業、その後、桐朋学園大学ソリスト・ディプロマコースを経て、20歳のときにプラハに留学しました。プラハ芸術アカデミーに5年間在籍して修士課程を終了し、2004年からマレーシア・フィルハーモニー・オーケストラに入団しました。
-3歳のときにピアノを始めたのはご両親の影響ですか?
川見 はい、そうです。母がピアノの先生をしていたので、自然とピアノを聴いて育っていました。
-バイオリンに転向されたのはどうしてですか?
川見 母がバイオリンのレッスンに連れて行ってくれたことは覚えていますが、自分から行きたいと言ったのかどうかは覚えていません。気がついたら、バイオリンを弾いていたという感じです。
-バイオリンの方がお好きでしたか?
川見 そうですね。ずっと、ピアノとバイオリンを両立して同じくらいやっていたのですが、小学校4年生からコンクールに出るようになって、その頃からバイオリンが主になってきました。
-中学校1年生で、コンクール1位をとられたということですが、コンクールには精力的に参加されていたんですか?
川見 毎年コンクールには出ていました。同じバイオリンスクールに通っている周りの子たちも参加していたので、自分も一緒に参加する、という感じでした。
-1位になったときは、うまく弾けた!という感じだったんですか?
川見 あまり覚えていないんですよ(笑)。ただ、すごく嬉しくて、それがきっかけのひとつとなって、音楽の道に進むことを、考えるようになりました。
-高校に入学した頃は、音楽家としてやっていこうという気持ちはあったんですか?
川見 そうですね、ありました。桐朋の音楽教室に小学校5年生の頃から通っていたんですけれども、中学校2年生の頃から、レッスンのために上京するようになりました。その頃から自然と音楽の道に進みたいという気持ちになっていきました。
-なるほど。それで、高校を卒業されて、大学に進まれたんですよね?
川見 大学とは違うのですが、ソリスト・ディプロマコースというコースに進みました。でも結局、卒業せずにチェコに行きました。
-ご留学を考え始めたのはいつ頃からだったのですか?
川見 外国に興味を持ち始めたのは、15歳のときに北九州音楽祭で、フィンランド人の世界的指揮者オッコ・カム指揮のKBSシンフォニー・オーケストラ(韓国)と共演した時です。その後、フィンランドのクフモ音楽祭に全額奨学金をいただいて、音楽祭に参加したのですが、初めてヨーロッパを訪れて、外国の方たちと交流する機会があり、海外に興味を持つようになりました。

-なるほど。それで、プラハを選ばれたのはどうしてですか?
川見 海外留学を考えていた時に、江藤俊哉先生や石川静先生に相談しました。江藤先生も、親身になって、アメリカなら、どの学校が一番私に合っているか等、色々相談に乗って下さいましたが、石川先生が、演奏旅行で、頻繁に日本とプラハを往き来されていましたので、私の録音テープをプラハ芸術アカデミーの教授、ヴァーツラフ・スニーチル先生に持って行って下さいました。スニーチル先生がそのテープを聞いて「教えてあげるから、いらっしゃい」と言って下さったので、思い切って留学しました。何も分からないまま行ったので、不安も大きかったのですが、結果的にはとても充実した留学生活を送ることが出来ました。
-ご留学前にチェコで師事する先生のレッスンを受けずに行かれたのですか?
川見 いえ、レッスンは受けました。その時にすぐ、この先生に教えていただきたいと思いました。
-そうやって、素晴らしい先生と出会えることって、なかなかないですよね。
川見 そうですね。先生との相性もとても大事な要素だと思います。先生の音楽に対する謙虚な姿勢、研究熱心なところをとても尊敬しています。先生の音楽に対するお考えに共感する部分がたくさんありました。
-プラハ芸術アカデミーは先生がOKをくだされば、入学は可能なんですか?
川見 そうですね。他の試験もありますが、そういう部分もあります。ただ、席が空いていない場合もあって、とても忙しい先生だと、1年も2年も待たされるということもあるかと思います。

-チェコ語は勉強されてから行かれましたか?
川見 行ってから勉強を始めました。
-レッスンは英語ですか?
川見 最初のうちは英語でした。しばらくするうちに、レッスンを先生の母国語で受けたい、先生のおっしゃることを全部理解したいと思うようになり、語学学校や夏季集中チェコ語コースにも通い、チェコ語の勉強を始めました。
-チェコ語というと、あまりなじみのない方が多いと思いますが、やはり語学の習得は大変でしたか?
川見 チェコ語は難しいですね。スラブ語系の言語で、格変化が多いです。女性、男性、中性とあって、さらに複数でもそれぞれ女性、男性、中性があります。語学の習得は、とても大変でした。
-現地で音楽理論の授業もありましたか?
川見 はい。ただ、留学してすぐに本科に入ったのではなく、最初は研究生としてレッスンだけ受けていました。授業は受けなくてよかったので、その空いた時間で語学学校に通ったりしていたんです。スニーチル先生のところでもっと長く勉強したいという気持ちがあったのと、桐朋でソリスト・ディプロマコースに進んだものの、きちんと終了していないので、もう一度しっかり学び直そうと思い、アカデミーの本科に編入しました。それが留学して2年経ってからです。それからは、理論や音楽心理学、歴史も学びました。授業はチェコ語だったので、内容は半分くらいしか分かりませんでした……(笑)。

-ご留学されて感じた日本とチェコの音楽(家)の違いは何かありますか?
川見 スタイルが違いますね。チェコ人の演奏は、フレーズがすごく流れていく感じがあって、弓の使い方もサササーと流れていくんです。日本 だと、もっと歌い込むような印象があります。また、歴史的にロシアの影響を受けていますので、奏法がロシア系に近いです。
-チェコの音楽に触れて、何か戸惑いはありましたか?
川見 戸惑っている余裕はなく、がむしゃらに頑張っていた感じです(笑)。
-ご留学して、ご自身が一番変わったことは何ですか?
川見 日本にいた頃は、枠にはめて考える癖があって、こうしなきゃいけないとか、こうじゃなきゃダメだとか、そういうふうに考えていたんです。留学して、そこから解放されました。間違っていても、主張はしていいんだ、と思えるようになりました。間違っていれば、学生であるうちは先生が指摘してくださいますしね。留学してからは、ああしてみたらどうだろう、こういう方法も可能かもしれない・・と、自由に考えられるようになりました。それから、自分の意見を言うのがこわくなくなりましたね。
-そういうことは音楽にも繋がってくるでしょうね。
川見 はい。そうですね。

-チェコ・フィルに入団されたのですか?
川見 チェコ・フィルはオーディションに合格しましたが、入団はしていません。これから入団、というときに、マレーシア・フィル入団を決めました。
-そうだったんですね。ちなみにチェコ・フィルのオーディションについて、お伺いしてもよろしいですか?
川見 募集はアカデミーの掲示板で見て応募しました。一次審査は、スクリーンがあり、誰が音を出しているのか分からないようになっています。モーツァルトのコンチェルトとオーケストラ・パートの何曲かを演奏しました。聴いている人は多かったようで、弦楽器以外の人も含めて団員全員とはいかないまでも半分以上の人が聴いていたようです。一次審査が午前中に終わり、すぐに結果発表があって、午後には二次審査がありました。応募者は20人程度で、4人が二次に進んで、そのうち3人は日本人でした。
-なかなか珍しいですね。
川見 そうですね。審査の方法ですが、一人一人が100ポイントを持っていて、その合計を人数で割って出し、何パーセント以上だったら合格ライン、としていたようです。そういうシステムですので、1位の人だけが入団できるのではなく、2位の人でも合格ラインに達していて、1年以内に席が空けば入れるというシステムでした。
-二次試験はどんな内容だったのですか?
川見 ロマン派のコンチェルトとオーケストラ・パートです。スクリーンなしで、顔が見える状態でした。この時の常任指揮者はマーツァル氏で、彼がオーディションを進めていました。

-二次に進んだ4人のうち、何人が合格したんですか?
川見 覚えていません。私は2番目での合格でした。1番目の人は、チェコ・フィルにセカンド・バイオリンで在籍していた人で、ファーストに移動を希望して、オーディションを受けていました。彼女は一次審査は免除されました。
-それで、結局マレーシア・フィルに行かれたわけですよね。こちらのオーディションはどうやって知ったのですか?
川見 インターネットに募集が出ていました。音楽雑誌にもオーディションの広告を出していたようです。マレーシア・フィルは、今、ちょうどロンドンでオーディション・ツアーをやっています(注:インタビュー2009年6月)。オーディションのためにマレーシアに来てもらう、となるとなかなか、参加者が集まらないという事情もあり、毎年、首席指揮者、オーケストラマネージャー、各パートの首席の人たちが一緒に世界を旅行しています。今年は、ロンドンとミュンヘンだけでしたが、日本、中国、オーストラリア、シカゴ、ニューヨーク、ベルリン、プラハ、ブダペスト……いろいろなところを回っています。
-川見さんのときは、プラハに来ていたのですか?
川見 はい、そうです。プラハ芸術アカデミーがオーディションの会場でした。
-マレーシア・フィルのオーディションはどのようなものですか?
川見 一次、二次とは分かれていなくて、一人が30~45分くらいかけて弾きます。課題曲はモーツァルトのコンチェルトとロマン派のコンチェルト、Tuttiポジションのオーディションであれば、他に7、8曲のオーケストラ曲を弾きます。タイトルポジション付きのオーディションを受ける場合は、さらにオーケストラのソロ・ヴァイオリン・パートを数曲弾きます。
-そのときはどのくらいの人が受けていましたか?
川見 プラハでのオーディションは10人程度だったと思います。他の各都市では20人ほど受けていたようです。

-プラハでのオーディションでは何人が通ったのですか?
川見 2人でした。もう一人の合格者が私の夫(ヴィオラ奏者)で、二人で合格しましたので、チェコ・フィル入団が決まっていましたが、マレーシアに行く決心をしました。1人だけだったら、マレーシアに来る勇気はなかったと思います。
-じゃあ、二人でマレーシアに行こう、という感じだったんですね。
川見 そうですね。
-でも、マレーシアに行かれるということに不安もありましたか?
川見 そうですね。マレーシアと言われても、思い浮かぶことが、ビーチ、虎・・・くらいで(笑)。海が綺麗でダイビングスポットとして遊びに行く国というイメージですよね。でも、いつもそうですが、あまり深く考えずに行動に移してしまう性格です。
-実際に行かれてみてどうでしたか?
川見 思っていたよりも街の中心は近代都市で、私たちの働いているホールはツインタワーという一時は世界で一番高かった建物の中にあります。ホールだけではなく、ショッピング・モールやトップ企業のオフィスも入っていて、便利がよく、とても環境がいいところです。
-では、生活で困るようなことはありませんか?
川見 はい 特に困る事はありません。ただ、国としては、チェコの方が好きです。プラハの街は石畳で、お城や教会など9世紀、10世紀のものがたくさん残っていて、歴史を感じます。マレーシアは、歴史が浅く、まだ発展を目指している国です。またクラシック音楽は、裕福な層のもの、高尚なものという印象があるようで、まだ人々の間に根付いていません。一方、プラハでは、毎日、どこかの教会やホールでコンサートが頻繁に行われていて、気軽にコンサートに立ち寄れる、という環境です。マレーシアはそういう面では物足りなさを感じます。一方、だからこそ、マレーシアでのクラッシック音楽の普及に貢献できているかもしれない、と思うところもあります。
-マレーシア・フィルはマレーシアを中心にコンサートをされているんですか?
川見 はい。ほとんどがマレーシア国内での演奏活動で、毎年1カ所、海外公演をしています。今年は、9月に日本に行きます。私はこれまでに、オーストラリア、中国(上海、北京)、台湾、シンガポールに行きました。
-団員さんは国際色豊かなんですか?
川見 団員は今100人弱いますが、マレーシア人は5人しかいません。他は、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの国の人達で、全部で23か国くらいですね。日本人は8人います。
コミュニケーションは英語ですか?
川見 はい、そうです。
-先ほどもお話がありましたが、マレーシアでのクラッシック音楽はまだまだ普及していないんですか?
川見 指導者も限られていますし、教育システムがまだ整っていないんです。だから、私たちが今しなければいけないのは、しっかりとした指導者を育てる事だと思っています。まだ、間違った方向で音楽学生が指導されていることがあるんです。15歳の時に私のところへ習いに来た生徒がいましたが、本当に最初から教え直さなければいけなかったこともありました。
-でも、そうやってクラッシック音楽の普及に携わるのも素敵なことですよね。
川見 自分のできることをしようと思っています。一人の人間にできることは本当に小さなことだと思いますが、オーケストラの中には教育熱心な人もいて、管楽器のアンサンブル、弦楽アンサンブルを学生のために作り上げて指導している同僚達はいますし、学生たちに人前で演奏する機会を与えたり、底上げをはかろうとしています。私自身もアウト・リーチはしていて、病院や学校などに出向いて演奏しています。

-今、川見さんはマレーシアで音楽活動をされているわけですが、将来的に夢や目標は何かありますか?
川見 室内楽、小編成のアンサンブル、特に弦楽カルテットに惹かれます。学生の頃は室内楽をたくさん勉強しましたが、オーケストラ曲をあまり知りませんでした。モーツァルトの室内楽曲やソナタはたくさん知っていても、交響曲やオペラをあまり知らない、というのでは偏るかなと思いますので、今は色々な作曲家の交響曲を知る時期だと捉えています。いずれは、夫とヨーロッパに戻って小編成のアンサンブルで活動できたらいいな、と思います。
-ちなみに旦那さまはどちらのお国の方なんですか?
川見 スロバキア人です。
-では、旦那さまもいずれはヨーロッパに戻りたいとお考えなんですね。
川見 そうですね。話は少し変わりますがマレーシアは常夏の国ですので、四季がありません。四季は恋しいです。少し前までは、音楽をやるならどこの国にいても同じだと思っていたのですが、やはり住む国の環境というのは大きいなと思います。

-将来、音楽家になりたいと思っている日本の学生にアドバイスをお願いします。
川見 音楽だけでなく、語学も勉強しておいた方がいいと思います。私は喋れずに渡ってしまったので、あまり言えないのですが、勉強するだけだったらなんとかなる語学のレベルと仕事をしたいと思ったときに必要になる語学のレベルは少し違います。語学力で、人との交流や入って来る情報の量も変わってきます。人との交流が、豊かなほど人間的にも成長できると思いますし、その成長は音楽にも影響してくると思います。勇気を出して人と接する機会をたくさん持ってみてください。
-そうですよね。コミュニケーションは大事ですよね。
川見 ええ。また、たとえ、最初に就職したところが自分の希望と違うところでも、希望を持ち続けていれば、きっとチャンスは回って来ると思います。
-多くの方がひどく悩んでなかなか動けないという方がいます。
川見 情報収集はとても大事なことですが、「悩むより行動に移してみるほうがよい」と思うのです。不況の中、金銭的な問題もあるかもしれませんが、講習会に参加してみることで、「よく分からない」目標がはっきりと見えてくるかもしれません。いきなり留学しますと、その国や先生との折が合わなかったときに精神的にダメージが大きいので、講習会などを利用するのが一番良いと思います。音楽留学は、「この国にいく」「この学校に入る」というより、「この先生に是非習いたい」と思ったその先がチェコだったり、ドイツだったり、フランスだったりすることが、多いと思いますが、一方でフランス人の演奏スタイルが好きだとか、ドイツのオーケストラの音が好きだとか、チェコ人作曲家を深く知りたい、などということもあって、留学先を「国」で決めることもあるかもしれないですね。動機がどんなものにしても、実際にその空気に触れて初めてわかる事ってたくさんあると思います。例えばチェコで言えば、室内楽が盛んな国なので、四重奏を勉強したい、というはっきりした目標を持った人には良い国かもしれません。もう今は活動していないですが、プラハカルテット、スメタナカルテット、世界の第一線で大活躍中のプラジャークカルテット、メンバーはオリジナルと変わりましたけれど、ターリヒカルテット、ヴラッハカルテット、コツィアンカルテットや若手のハースカルテット、など、プロの弦楽四重奏団の多い国だと思います。
-最後に川見さんにとって音楽とは何ですか?
川見 3歳の頃からずっと音楽に触れているので、生活の一部になっています。

-本当に生活そのもの、なんですね。
川見 そうですね。大きな影響を受けてきました。落ち込んだ時にクラシック音楽を聴くと元気になりますし、素晴らしい作品に触れる時、わくわくします。また、演奏家として舞台に立ち、聴いて下さる方とその時間を共有しているときとても幸せです。
-ありがとうございました。
〜〜〜〜以下、MPOの日本公演日程〜〜〜〜
2009年9月にマレーシアフィルハーモニー管弦楽団(MPO)は、
日本ツアー4公演を下記の日程で行います。
9月8日19:00開演 ザ・シンフォニーホール(大阪)
9月9日18:45開演 愛知県芸術劇場コンサートホール(名古屋)
9月11日19:00開演 札幌コンサートホールKitara(札幌)
9月14日19:00開演 東京オペラシティコンサートホール(東京)
スメタナ 交響詩「モルダウ」
ブラームス ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77
ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調作品95「新世界より」
指揮 クラウス・ペーター・フロール
ヴァイオリン ワディム・レーピン
MPO公式サイト
http://www.malaysianphilharmonic.com/
また、ツアーのあとに、MPOメンバーによる室内楽演奏会を東京・ルーテル市ヶ谷センターホールで行います。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.h2.dion.ne.jp/~kikukohp/mpcs.html
渡辺泰人さん/ピアニスト/ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニスト/オーストリア・ウィーン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニストでご活躍中の渡辺泰人(わたなべやすひと)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年8月)
ー渡辺泰人さんプロフィールー

日本大学芸術学部音楽学科ピアノ専攻及び同大学院修士課程修了。芸術学部長賞を受賞し、読売新人演奏会に出演。同大学院在学中、日本大学大学院海外派遣奨学生として渡欧、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科第一ディプロマ課程修了。その後ミュンヘン国立音楽大学研究課程を経て、ザルツブルグ・モーツァルテウム国立音楽大学ピアノ演奏科に在籍。第6回モルコーネ市国際ピアノコンクール(イタリア)第2位入賞をはじめ、これまでに国内外の数多くのコンクール、及びオーディションにて入賞。現在はウィーンに在住し、ソロのみならず、ピアノ三重奏団“ヴェルトハイムシュタイン・トリオ・ウィーン”、及び“サロンオーケストラ・アルト・ウィーン”のピアニストとして演奏活動を行っている。現在、ウィーン国立歌劇場バレエ学校ピアニスト及びウィーン市民学校ピアノ講座講師。
-では、最初に、渡辺さんのご経歴をお願いします。
渡辺 日本大学芸術学部の音楽学科ピアノ専攻を経て、同大学院の修士課程まで、日本で勉強しました。そして、大学院に在学中に、日本大学大学院の海外派遣奨学生制度に選ばれ、前からあこがれていたオーストリアに渡った後、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科(今と制度が多少変わっている)に入学しました。ここで第一ディプロマを取得した後、ドイツのミュンヘン国立音楽大学の研究過程に進学しました。研究過程終了後、再びオーストリアに戻り、ザルツブルグのモーツァルテウム国立音楽大学に入学しました。その後、仕事を始め、現在に至っています。
-ピアノを始められたきっかけは?
渡辺 両親の影響が大きかったです。父が、ジャズピアノがとにかく大好きでして。生まれた子どもには、絶対にピアノをやらせたい、という夢があったらしいです。そして、僕が思いっきりターゲットになりました(笑)。
-お父様もピアノを弾かれるのですか?
渡辺 いえ、楽器はやりませんが、すごくたくさんのCDやレコードを持っていて、いつもいつも音楽を聴いていました。
-では、小さな頃から家中にジャズが流れていたんですね。
渡辺 他にももちろん、モーツァルトやショパンなどのクラシックも流れていて、幼稚園や小学校時代を振り返ると、家には、常に音楽が流れていたように思います。父の影響が大きかったのですが、母親がバレエの先生をやっていたということも影響していると思います。でも、生まれた僕の背格好や体型などを見て、「この子にはバレエは向かないな」と、初めから、その道に進ませようとはしなかったみたいです(笑)。
-ピアノを始めたのは何歳くらいですか?
渡辺 たぶん3歳半くらいだったと思います。まだ幼稚園に行っていた頃でした。
-音楽系の大学に進まれる方は、音楽家を志す方が多いと思いますが、音楽の道で生きていこうと意識されたのは、いつくらいでしたか?
渡辺 今考えると、かなり小さい頃からですね。漠然とではありましたが、ピアノを教える先生になりたいって考えていました。ピアノと一緒に生きていくというか、どこかでピアノに関わっていたいっていう気持ちは、昔からありましたね。
-お父様から、ジャズをやれとは言われなかったのですか?
渡辺 いえ、言われませんでした。まずはクラシックを勉強して、気が向いたらやればいい、という感じでした。とにかく、与えられた練習を頑張ってやりなさい、という態度で僕に接していました。
-日本の大学で修士課程まで6年間学ばれていて、派遣制度で留学が決まったということですが、それまで全く留学を考えたことはなかったんですか?
渡辺 憧れはありました。大学4年の頃に、松浦豊明先生が東京芸術大学から日本大学大学院へ赴任されて来たんです。僕は、まだ学部生でしたが、ちょっと早めに先生の門下に入れていただきました。松浦先生は、芸大の教授だったときには大変お忙しい先生で有名でしたが、僕が教わった頃は、受け持ちの生徒が少なかったこともあり、とても気さくに接してくださいました。気が向くと電話をくださって、「週末、お茶飲みに来ない?」などと誘っていただくことも多かったんですよ。先生の奥様がケーキを焼いてくださったりして、僕たち門下生はみんな、先生のお宅に月に一回は伺っていました。そのときに、先生が収集されている古い音源のレコードを聴かせてくださったり、昔ドイツに留学されていた頃の品々を見せてくださったんです。当時のコンサートのプログラムや楽譜などを。それから、先生の奥様も、同時期にドイツに留学されていたということもあって、お茶のお菓子も、当時のドイツで教わったレシピで作ってくださったんです。なので、東京にいながらにしてヨーロッパの雰囲気が先生のお宅には漂っていて、その頃から、そんな様子にとても憧れていたんです。「絶対にドイツ語圏に行きたい!」と気持ちは強かったですね。ですから、派遣奨学生として選ばれたときは、夢が現実のものになったという感じでした。

-この留学前は、ヨーロッパに短期留学などで行かれたご経験はあったのですか?
渡辺 実は、派遣奨学生に応募した前後で、受かるかどうかは分からないけれど、下見をする必要はあるなと思っていたんです。そこで、ドイツ・オーストリア周辺を南から北にかけて見て回ったんです。初めに憧れのウィーンから入りました。旅行といえば旅行なのですが、僕の中では完全に「下見」でした。
-いろいろ巡った中でも、やっぱりウィーンがいいな、と思われたんですか?
渡辺 初めから憧れはあったんですが、実際に自分の目で見てそう思いました。他の街と比べても、やはり、ウィーンに着いた瞬間の直感が違いました。今振り返ってみても、「ああ、僕はここで勉強するんだ!」っていう強い印象がありましたから。もう、確信といってもいいくらいでした。そして、派遣奨学生として選ばれた時、留学先は、迷わずウィーンに決めました。
-派遣奨学生のシステムとして、留学先で師事する先生は、大学院側が選んでくれるのですか?
渡辺 いえ、この制度は、留学先の学校や先生を、自分で決めなければいけないんです。応募時点で、コンタクトを取らなければいけなかったので、そのコンタクト取りも兼ねて下見したんですよ。ウィーンで師事することになった先生は、知っている教授や先生方を頼って、皆さんから紹介された中のお一人でした。
-では、コンタクトを取った先生は、他にもいらっしゃったんですか?
渡辺 ええ。でも、やはり、ウィーンで勉強するんだという気持ちが強くて、ウィーン国立音大の先生にしました。

-渡航前に、ご自身が抱いていたウィーンのイメージと、実際行かれてからの印象の違いはありましたか?
渡辺 やはり、渡航前のウィーンのイメージは、TVなどで見る「華やかな音楽の街」という表面的なものでした。実際に行ってみると、治安の良し悪しや、街自体が抱えている問題が分かってきたりして、華やかな部分だけではないんだということが分かりました。ショックではあったのですが、それゆえにもっとウィーンを知りたい、という気持ちにもつながりました。
-ちなみにショックだったこととは、どういったことですか?
渡辺 まずは、移民の多さですね。オーストリアは、今でこそ小さな国ですが、大戦前は非常に大きな国で、戦争に負けた代償で、多くの労働力を受け入れた背景があります。主にトルコや旧ユーゴスラビア系など東側の人々なのですが、初めは、「ここはトルコなのか!?」と思うほどで(笑)、僕にとってはすごくショックでしたね。まあ、最終的にはそれもすべてひっくるめて、ウィーンなんだと思えるようにはなったんですけど。
-確かに、日本人はウィーンに対して、そういうイメージって持ってないですよね。
渡辺 ないですよね。それこそ、ニューイヤーコンサートの映像で見るような、華やかなホールや、ドレスで着飾った紳士淑女ばかりがいるイメージですよね。でも実際、そういう方々は、ほんの一部であって・・・。
-実際、ウィーンで学んでみて、日本での勉強仕方との違いなどで、ショックを受けられたことはありましたか?
渡辺 ウィーンで勉強し始めてショックだったことは、結局は「表現すること」を勉強するんだな、ということでした。ヨーロッパ系の学生たちの、「自らの語り口で、どこまでその作品を表現し切れるか」という、彼らの突き詰めていく姿勢に衝撃を受けました。日本だと、楽譜から音楽を読み取っていく理論的な作業や、技術的なことを学ぶのが中心だったんです。でも、ウィーンでは、「ここはもっとこういう音色で弾かなければ」とか「もっとこういうイメージで」などと、何より自発的なファンタジーを持った勉強が大事だったので、そういう部分では、少し戸惑いましたね。

-生活面ではどうでしょうか、カルチャーショックはありましたか?
渡辺 土日にほとんどの店が閉まるので、すごくゆったりした生活だなと思いました。東京だと人も多くて、慌ただしい中でピアノを勉強していたのですが、突然、大きな空間にポンと置かれたような感覚でした。それが虚無感だったというのではなくて、居心地よい感覚でしたが。
-ウィーン国立音大は、ご自分で受験されたのですか?
渡辺 実は、海外派遣奨学生の制度は、一年間のみという制度だったんです。大学院からの派遣の留学生とはいえ、正規の学生ではありませんから、師事した先生に頼る形で、ウィーン国立音大に出入りさせてもらっていたんです。なので、レッスンや授業を見学したりしか出来ませんでした。そこで、先生から、「これから先もウィーンにいたいのであれば、正式に受験してみてはどうか?」と言われたんです。日本大学にもすぐに確認を取り、休学中であるということで、ウィーン国立音大を受験することは問題ないとのことでしたので、実は、派遣留学生の期間中に受験したんです(笑)。
-え!? 大丈夫だったんですか?
渡辺 はい。休学中ということと、修了演奏試験や修士論文もすべて済ませ、卒業式に出席するだけの状態で渡航していましたから、問題ありませんでした。というわけで、派遣されてから3ヵ月後に受験したんです。ただ、授業が本格的に始まったのは、さらにその3ヵ月後でした。なので、最初の半年間は、レッスンや授業を聴講したりして過ごし、半年後から正式な学生として勉強を始めた、ということなんです。
-ちなみに、ドイツ語は、日本で勉強されていたんですか?
渡辺 派遣奨学生に決まってから、とりあえず1ヶ月間だけ東京のドイツ語学校に通って勉強しました。ですが、修士論文や渡航の準備などでバタバタしていたので、それ以外は参考書をパラパラめくる程度でした。
-となると、本格的に勉強し始めたのは、現地に行ってからですか?
渡辺 はい。一応、日本の大学でも2年間ドイツ語の授業はあったのですが、それは1ヶ月間行った東京のドイツ語学校くらいの内容で。本格的には、ウィーンに行ってから勉強を始めた、という感じです。今思えば、日本でのドイツ語の勉強内容は、ウィーンでの1週間分くらいにしかならなかったな、と(笑)。
-そうなんですか! それでは、けっこうご苦労されたのではないですか?
渡辺 はい。留学したての頃、街行く人々の会話は、宇宙語にしか思えませんでした(笑)。
-レッスンは、もちろんドイツ語ですよね。
渡辺 そうです。僕がウィーンで師事していたヴァッツィンガー先生は、語学に関しては厳しくて、「出来るだけ早くドイツ語をマスターしなさい」という方針でした。ですので、ドイツ語が全く分からない生徒に対しても、英語で話すことは全くありませんでした。でも、音楽は、用語がイタリア語だったり、隣で先生が見本を見せてくれたりするので、理解できてしまうんですよ。ですので、レッスンに関しては、あまり困らなかったというのが正直なところです。

-結局、ウィーン国立音大には何年いらしたんですか?
渡辺 3年です。
-ご卒業されてから、ミュンヘンに行かれたんですよね。
渡辺 ウィーン国立音大では、実は、先の課程に進学し始める状況だったんですけれど、1年の留学のつもりが、この時点で3年になっていましたから、「この先そんなに長くない。それならば、別の環境で別の先生に会ってみたい。」という気持ちが強くなりました。なので、受験をしなおして、ミュンヘン国立音大に入学しました。結局、その後のモーツァルテウム国立音大へも、同じ気持ちで移ったんですけれども。
-ミュンヘンを選ばれたきっかけは何だったんですか?
渡辺 同じドイツ語圏の中でも、他の国であるドイツに興味があったというのと、ドイツの中でも南にあるので、オーストリアに近いことが一番の理由でした。その距離感のお陰で、ウィーン国立音大の卒業前から、ミュンヘンにレッスンを聴講しに行ったりしていました。
-先生を決められてから、ミュンヘンへ行かれたのですか?
渡辺 ヴァッツィンガー先生も本当にいろいろ力を貸してくださったんです。ミュンヘン音大の先生を推薦してくださったのも、ヴァッツィンガー先生でした。
-ドイツとオーストリアでは、音楽性の違いはありましたか?
渡辺 やはり、国民性に影響していると思うんですけれど、ドイツのほうが、構築性を重んじるスタイルですね。オーストリアは、前にも言ったように、表現することや、自分という媒体を通して自分らしく奏でる、ということに重点を置いていましたので、その違いはありました。
-住みやすさの違いはありましたか?
渡辺 物価の面では、それぞれ高いものと安いものが違うという感じで、トータルとして大差なかったのですが、決定的に違ったのは住宅環境でした。
-税金が高いそうですね。
渡辺 ミュンヘンは、アパートの家賃が高くて、探すのが大変でした。平均的に、ウィーンでミュンヘン分の家賃を払えば、ミュンヘンの部屋の2倍も3倍も広い部屋に住めるという状況でした。住環境においては、ウィーンのほうが断然良かったです。
-寮には入られてなかったんですか?
渡辺 いえ、どの街でも、ずっとアパートに住んでいました。
-ドイツとオーストリアでは、コミュニケーションの取り方の違いはありましたか?
渡辺 ドイツ人のほうが、初めは距離を置く感じなんですけれど、一度打ち解けると、それからは温かく、人間と人間の付き合いが出来る感じはあります。オーストリアは、それよりもっとラフという気がしますね。
-オーストリアのほうがラテン系に感じますが・・・?
渡辺 国がイタリアに接していますからね。簡単に言うと、ドイツ人とイタリア人をたして2で割ったのが、オーストリア人の気質なのかも知れません。
-なるほど! さて、ミュンヘンでの生活を経て、再びオーストリアに戻られ、モーツァルテウム国立音大に入学されるわけですよね。「オーストリアに戻ろう、ザルツブルグに行こう」と思われたきっかけは何だったんですか?
渡辺 本当に不思議だったのですが、始めにウィーンで感じた気持ちが、ミュンヘンに行った後も、ずっと気持ちの中にあったんです。この先、まだ勉強できるのであれば、オーストリアで勉強したいと。また、ドイツよりもオーストリアで勉強するほうが、自分に合っているような確信があったので、オーストリアに戻ろうと決意しました。
- 一度、日本に帰ろうとは思われなかったのですか?
渡辺 はい、思いました。実は、この頃から、職探しを視野に入れながら勉強を続けていたんですけれど、これといった決定打がなかったので、勉強を続けるという形を取っていました。

-ウィーンとザルツブルグで、大きく違うことはありましたか?
渡辺 決定的に違ったのは、ザルツブルグでは、シーズン中の音楽会が少ないということです。有名なザルツブルグ音楽祭はあるのですが、夏だけのものですし。ウィーンのように大きなオペラ座がないし、楽友協会のような大きなホールもないので、なかなか演奏会に足を運べるチャンスがなかった、というのが大きかったです。
-それは大きいですね。やはり、本場の音楽を観るという意味ではウィーンが一番ということですか?
渡辺 ええ。でもミュンヘンもすごく良かったですよ。バイエルン州立歌劇場やガスタイクのホールなどで、連日たくさんの演目がありましたし。
-それで、モーツァルテウムをご卒業されて・・・?
渡辺 実は、モーツァルテウム国立音大を卒業する前に、仕事のことが見え始めたので、ディプロマを取らずにそのまま出てしまいました。
-お仕事というのは?
渡辺 初めは、日本に帰って引き続き仕事を探すか、お声掛けをいただいた、ウィーンでの小さな仕事に就くか迷っていました。それで、日本で一度、区切りをつけるために、数ヶ月間、コンサートをしながら過ごしたんです。結局、この数ヶ月の間に、やはりウィーンでお話をいただいた仕事をやってみようと決心しました。
-ウィーンで仕事をしようと決意した、決定的な理由を教えてください。
渡辺 モーツァルテウム国立音大に行った時点で、留学期間がだいぶ長くなっていたので、ひょっとしたら自分は慣れ親しんだオーストリアで、充実した仕事をやっていけるのではないか、と漠然と感じていました。その気持ちに正直に頑張ってみようと、思い切って決断しました。
- 一番最初のお仕事とは、どんなお仕事だったんですか?
渡辺 最初は、現地の普通高校の音楽の先生だったんです。ピアノの個人レッスンもあったのですが、カトリック系の学校だったので、ミサが毎週ありますから、ピアノと同じウェイトで合唱のレッスンがあったんです。これに立ち会合って、指導するというのが僕の任務でした。
-このお仕事は、どのようにして見つけたんですか?
渡辺 学生時代、この高校のミサで、何度も演奏をさせていただいていたんです。当時、チャペルのパイプオルガンが壊れていたので、キーボードでオルガン部分を弾かせていただいていました(笑)。そういったつながりで、欠員が出たときに、「やってみないか?」と声をかけてもらったんです。このオファーが魅力的で、日本でコンサートをしていた数ヶ月の間に、オーストリアに戻ろうと決意したんです。
-実際に、学生さんに音楽を教えるというのはどんな感じでしたか?
渡辺 初めは、僕で勤まるのだろうか、という不安がありました。それに、僕は、カトリックの人間ではないので、ミサの流れとか、基本的なことから勉強する必要があったんです。でも、相手が高校生だったので、あの年代特有の人懐っこさで接してくれて、すぐに不安はなくなり、楽しんで出来るようになりました。

-このお仕事は、何年くらいされていたのですか?
渡辺 実は、後に得た仕事との関係で、1年足らずで辞めざるを得なくなってしまいました。音楽の授業だけでは、仕事として本当に少なかったので。大きな仕事を探さなければいけないと考え始めて、在職中からいろいろなところに履歴書を送ったり、オーディションに応募したりしていました。それこそ200~300という数です。ピアノに関わる仕事なら何でも片っ端から応募する、という感じでしたね。空いている時間に作業していました。
-現地で日本人が仕事を得るというのは、やはり難しいことなんですか?
渡辺 はい。大学以外のほとんどの音楽学校は、採用試験の規準に、「オーストリア国籍、もしくはEUの国籍を持つ者」と記載されてます。たとえば、現地の方と結婚された日本人などであれば、それでも相当大変ですが、かろうじて潜り込めるかもしれませんけど・・・。日本人というだけで、最初の採用規準にひっかかってしまうので、非常に難しかったです。友人に、自分からどんどん履歴書を送ったほうがいい、とアドバイスされていたので、そうしていました。
-そんな中で、なんとか次の職を得られたんですよね。
渡辺 はい、でも、簡単ではなかったです。地方のコンセルバトワールの採用試験を受けたときも、最終選考までパスしていたのですが、試験官から「あなたは、ウィーンに住んでいるけれど、このくらいの少ない時間枠の仕事だったら、あなたが住んでいる場所には合わないんじゃないの?」と言われて、僕の次の成績を取っていた人が採用されたこともありました。この人は、その街に住んでいるオーストリア人だったんです。こういう悲しい思いとか悔しい思いを何度もして、だんだん分かってきたことが、「明日からでもすぐ仕事が出来る」という距離感のほうが見つかりやすい、ということでした。たとえば、ドイツの大学や劇場にも応募したんですけれど、「あなたはウィーンに住んでいるようだけれど、こちらに引っ越してくる気はあるのか?」という返事を何度も受けたりしましたから。やっぱり自分は、ウィーンとその周辺で一生懸命探さなければいけないんだな、と思い始めた矢先、ある日突然、街中で携帯が鳴ったんです。それが、なんと、夢のまた夢だと思っていた、ウィーン国立歌劇場からだったんです! 「あなたの履歴書を見たのですが、明日、バレエ学校の伴奏の試験をやるので、午後来てください」と。採用試験にエントリーしていたのですが、その連絡でした。

-急な電話ですね!
渡辺 日本じゃありえないですよね(笑)。僕としては、母がバレエの先生だし、妹も踊っていることもあって、バレエには親しみがあるというだけで、ダメもとで応募していたんですよ。だから、一瞬躊躇したんです。受けても無理だろう、と思っていましたから。でも、「行けません、なんて言っちゃだめだ!」と自分を奮い立たせて、試験を受けに行きました。その採用試験を経て、今に至っているというわけです。
-すごいですね! 採用試験はどんな内容だったんですか?
渡辺 バレエのトレーニングのクラス90分を、ピアノ伴奏してくださいと言われ、その場で弾きました。バレエの伴奏に関しては、音楽大学では教えてもらえるものではないし、ほとんどのピアニストは、どうやるのか知らないと思うんです。たまたま僕は、家族がバレエをやっていて、伴奏の経験もあったというのが功を奏したのでしょうね。それまでは、母や妹とは全然違う分野で活動しているんだっていう気持ちがありましたけど、この育った環境のおかげで、なんとか90分やり遂げられたんだと思います。
-他の応募者の方と一緒だったんですか?
渡辺 僕が受験した日は、僕だけだったのですが、別の日にも試験は行われていたみたいです。定年退職される方がいたので、欠員を埋めるための採用試験だったんです。
-試験は、一度弾いただけで、特に担当官との面接などはなかったのですか?
渡辺 ディレクターと面接がありました。後から知ったのですが、試験の最中、オペラ座の関係者やバレエ学校のトレーナー、他のピアニストなどが、代わる代わる僕の演奏を審査していたようです。そして、ディレクターから、「他のピアニストが病欠のときなどにやってみないか?」と言われたんです。
-もう、その場で話があったということですか!?
渡辺 はい。その場で言っていただきました。ウィーン国立歌劇場のバレエ学校のディレクターだったんですが、その場で仕事に関する細かいことも話し始めたので、これはポジティブに取っていいんだな、と。
-それは本当にすごいことですね! 日本人の方が、そういうお仕事に就かれるということは、なかなかないですものね。
渡辺 いえいえ。運やタイミングも大きいなって、本当に思うんです。
-その後、どのくらい経ってから、そのお仕事を始められたのですか?
渡辺 すぐに、しょっちゅう電話がかかってくるようになったんですよ。バレエ学校のピアニストに病欠が出るたびに、連絡が来るようになったんです。でも、ふたを開けてみたら、定年退職されるはずだった方が、その後2年近くも在職されていたので、その期間は非常勤という形でした。正式に常勤のピアニストになったのは、去年の9月からです。
-そうなんですか。ちなみに就労ビザは問題なく下りたのですか?
渡辺 はい、幸い、勤務先がウィーン国立歌劇場ですので、非常勤でやっているときから、国立オペラ座が、労働許可書など必要な書類を発行してくださったんです。逆に、労働許可書を出さずに外国人を雇っていると、雇用者側に問題が出て来るんですよ。なので、非常勤を始めて1ヶ月くらいで、すぐ郵送されてきました。実際「こんなに早く!?」って驚きましたね。その点に関しては、本当に幸せでした。そして、これらの書類を提出したら、ビザはすぐに下りました。

-週に何回くらいのペースでお仕事していたんですか?
渡辺 非常勤のときは、まちまちでしたね。仕事のない週もあれば、病欠が出たときは一気に10日間とかもありました。いろいろな演目のリハーサルや、バレエ学校側の都合で時間割が変わったときなどに、常勤ピアニストの都合がつかなかったような場合も、電話がかかってきました。
-今は、どういう形ですか?
渡辺 今は、クラスを持たせていただいているので、毎週月曜日から金曜日までです。時々週末も入りますが。
-ソロではなく、伴奏者として弾くことに関して、何か気をつけていることはありますか
渡辺 伴奏に関しては、日本にいた頃から声楽や器楽の伴奏など、好きだったのですすんで勉強させてもらっていました。ただ、バレエの伴奏は特殊なので・・・。 気をつけることは、テンポ感とかリズムの抑揚ですね。たとえば、ジャンプのときにずっしり弾いてしまうと、重くなって飛べなくなってしまったりしますし、体の大きさには個人差があるので、回転も人によって速さが違ったりします。だから重さや軽さ、どこにアクセントをつけてどこをなめらかに、どこを歯切れ良く・・・など、拍子とか拍とかに関する部分は気をつけています。
-細かいお仕事なんですね。この仕事のやりがいは、どんなところに感じますか?
渡辺 結局、バレエピアニストという職業は、ジュークボックスのような存在にならなければいけないんですよ。「こういう動きに合わせて、何か弾いて」と言われたら、そのように弾かなければいけないですし。でも、踊り手さんたちが、自分のピアノに合わせて、楽しそうにレッスンを受けている姿を見ると、「ああ、自分の音楽で、こんなに楽しんでくれているんだ」と嬉しくなりますね。そういうことに、やりがいを感じます。
-渡辺さんのように、外国で仕事をしたいという日本人の方がたくさんいると思いますが、仕事を見つけるコツはありますか?
渡辺 「自分には、これくらいしかできないだろうな」と、自分で思っている判断よりも、もっと大きな夢を持って、そこに近づいていくエネルギーを失わないように、自分の楽器を演奏し続けていくことなのかな、と思います。
-最後に、一番難しい質問を(笑)。渡辺さんにとって、クラシックとは、そして音楽とはどういう存在でしょうか。
渡辺 ・・・・・・(笑)。やはり、僕という人間は僕なんですけれど、音楽を通して、いろいろな人間になれることでしょうか。威張った人間、悲しんでいる人間、ロマンチックな人間、コミカルな人間・・・。音楽の表現を通して、自分がいろんな役者になれるというか、そういうことがやはり魅力ですね。
-今後、海外で活躍したいという方に、「これはやっておいたほうがいいよ」など、何かアドバイスがあれば、教えてください。
渡辺 海外で働く人は、皆さん開口一番におっしゃると思うんですけれど、言葉が一番大切ではないかと。言葉の次に大切なものがあるとすれば、コミュニケーションを取ることですかね。努力をしてコミュニケーションの力をつける、というのはおかしいですけれど、音楽の世界でも、結局人と人とのつながりなので、言葉の壁を越えた、コミュニケーションの努力は必要かなと。

-日本人は、引っ込みがちですもんね。積極的になれないというか。
渡辺 日本人として活かせる長所って、たくさんあると思うんです。それを生かしつつ、自分をもっと周りに溶け込ませるようにできればいいのかな、と。全部楽しんでやってしまえたらベストですけれど。
-日本人として活かせる長所というのは、具体的にどんなこところでしょうか?
渡辺 きちんとしているところとか・・・。僕が言うのもなんですけれど(笑)。日本人は、きちんとしているというイメージを持たれています。約束に関することだったり、礼儀正しさなどは長所ですよね。そういうのを活かしつつ、自分たちが日本にいるときより、ちょっとだけ積極的に話しかけてみたりだとか、挨拶したりとか。ちょっとした心遣いでコミュニケーションは膨らむので、そこは努力すればいいのかな、と、。
-最後になりますが、渡辺さんの音楽家としての夢、目標を教えてください。
渡辺 当面は、今の状況をもっと自分が楽しめるように、バレエのピアニストとして経験を積んでいきたいです。と、同時に、今まで積み上げてきた、ソロのピアノの勉強や室内楽、その他のアンサンブルなども、並行してレパートリーを広げていけたらいいなと思っています。
-ご活躍をお祈りしています。今日は、お忙しいところ、本当にありがとうございました!
布施菜実子さん/ヴァイオリン/ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団/ドイツ・ミュンヘン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回ドイツ・ミュンヘンフィルでご活躍中の布施菜実子(ふせなみこ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年8月)
ー布施菜実子さんプロフィールー

東京生まれ。4歳よりヴァイオリンを始める。桐朋女子高校音楽科を経て桐朋学園大学を1998年に卒業。在学中には仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演したほか、東京文化会館小ホールにて新人音楽家デビューコンサートなどに出演。またカール・ライスター弾き振りのオーケストラにてコンミスを務めるなど多数の学内オーケストラにてコンミス、首席を経験。卒業後すぐに渡独。ミュンヘン音楽大学ではマイスタークラスに入学し、2000年にマイスタークラスディプロムを取得、卒業。Münchener Kammerorchesterの契約団員を経て、2000年のマイスタークラス卒業と同時にミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団に入団。現在オーケストラ以外に、室内楽などを中心に演奏活動を行っている。これまでにヴァイオリンを故鈴木共子、朱貴珠、クルト・グントナーの各氏に、室内楽を店村眞積、堀了介、村上弦一郎、バルトーク・カルテット、アルバンベルグ・カルテット、アマデウス・カルテットなどに師事。
-では、最初に、布施さんのご経歴を教えてください。
布施 4歳からバイオリンを始め、6歳で桐朋学園大学付属「子どものための音楽教室」に通い始めました。桐朋学園女子高校音楽科を経て、桐朋学園大学を卒業し、ミュンヘン音楽大学マイスタークラス(大学院)に2年間在籍しました。卒業後、すぐにミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団に入団し、現在に至っています。
-素晴らしいご経歴ですね!
布施 いえいえ。私はコンクールなどはほとんど受けていませんので、コンクール歴はないんですよ。
-それは意外です。では、音楽に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
布施 実は、それほど、音楽やクラシックに興味はなかったんです。バイオリンも、自分からやりたいと言って始めたわけではありませんでした。母親が、自分がバイオリンをやりたかったから、ということで、私に始めさせたんです。桐朋学園の高校に入るまでは、他のお友だちと同じように、普通にポップスなども聴いていました。その頃は、プロの音楽家になるなんて、全然考えてもいませんでしたね。
-それでは、クラシックに興味を持ち始めたのは、高校に入学してからなんですか?
布施 そうですね。音楽高校だったので、素晴らしい経歴を持つ子たちがたくさんいたんです。コンクールで全国一位とか、地方から出てきている人もいましたし。そんな中にいたら、かなり刺激を受けまして。やっと目覚めたというか、初めて、自分の意思で練習するようになったんです。
-大きな刺激だったのでしょうね。
布施 はい。そして、高校三年生の頃、ザルツブルグ夏期講習会・モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミーに参加したんです。そこで初めて、ヨーロッパの音楽を聴いたんです。先生だけじゃなく、参加している講習生の演奏も聴いているうちに、「ヨーロッパの音楽って、クラシックって素晴らしい!」って、感動したんです。その頃からですね、留学を考え始めたのは。

-ザルツブルクの講習会が、留学するひとつのきっかけになったのですか?
布施 はい。きっかけのひとつではありました。でも、師事していた先生に相談しましたら、「高校を卒業してすぐというのは、少し早いのではないか。」とアドバイスをいただきまして、大学で勉強してから、ということにしました。実は、大学2、3年の頃には、大学の先生から、「そろそろ留学してもいい時期ではないか。」と言わてはいたんです。でも、休学するよりは、やはり卒業してから留学したいと思いまして・・・。そして、4年生になってから、これがもうひとつの大きなきっかけになるのですが、スイスのレンクで行われた講習会に参加したんです。
-ザルツブルグだけでなく、スイスでも講習会に参加されたんですね。
布施 はい。そして、そこで、すごく素晴らしい先生に出会ったんです。ミュンヘンで教えてらっしゃる、とても有名な先生でした。「どうしても、この先生に習いたい!」と思った私は、講習会が終わってから、先生に直接、先生のもとで勉強させてほしいと話しに行ったんです。しかし、先生のクラスは、すでに入る順番を待っている方が大勢いたので、来年入るのは無理、とのお返事でした。でも、私は、そこで諦めなかったんです(笑)。今となっては、無謀だと思うのですが、日本に帰ってからも、先生に何度かご連絡したんです。もちろんお返事をいただくことはありませんでしたが・・・。そういう状況なのに、単純に、行ったらなんとかなるだろうと思ってたんですね。大学を卒業してすぐ、4月にはミュンヘンに渡ったんです。
-すごい勇気と行動力ですね!
布施 無謀ですよ(笑)。そして、渡航してからすぐ、先生にお電話したのですが、やはり、「今年は、定員が一杯だから、突然来られても無理だ。」と言われました。当たり前ですよね(笑)。ただ、一度聴いてもらったら、「マイスターのレベルには達しているから、試験には合格するだろう」と、ミュンヘン音大のマイスターコース受験を勧められ、大学の先生も紹介していただいたんです。そして、マイスターコースに合格しまして、その先生のクラスに入ることになったんですが、いろいろな事情がありまして、さらに別の先生に教えていただくことになったんです。正直、その先生のことは、全く知らなかったのですが、レッスンに行ってみたら、この方が、素晴らしい先生で・・・! 私が今いるミュンヘンフィルで、以前、コンサートマスターをやられてた方でしたので、オーケストラスタディもよく見てもらいました。人間的にも素晴らしい方で、今思えば、偶然に偶然が重なって、結果的に私にとって、とてもラッキーな出会いとなりました。
-そういう出会いって、本当、分からないものですね。
布施 ええ、あれだけ講習会で出会った先生に習いたい!って思っていたのに・・・。結果的には、すべて無駄ではなかったですね。
-元をたどれば、講習会だったわけですからね。
布施 はい。やっぱり夏期講習っていうのは、大きなきっかけになりますから、留学したいと考えている人であれば、ぜひ、積極的に参加してほしいですね。

-では、留学に関することをお伺いしますが、クラシックを勉強するに当たって、ドイツの良い点、悪い点があったら教えてください。
布施 ドイツに限らず、ヨーロッパの街では、大小関わらず、毎日どこかでコンサートをやってます。安い値段で、気軽に良い音楽を聴くことができるんです。それがすごく良いことですね。日本だと、何ヶ月も前から予約して、頑張って予定を空けて行くって感じですけど。そんな堅苦しいイメージはなくて、「買い物のついでに行ってみよう」っていう感じで、それこそ、ジーンズを穿いてても行けてしまうんです。学生時代には、学割を使って、たくさんオペラを見ました。今思えば、それが私にとって、大きな収穫でしたね。
-日本だと、そうは簡単に行けませんものね。
布施 大ごとになりますもんね。それに、こちらでは、コンサートに行かなくても、あちこちに教会がありますから、ちょっとのぞいてみたり、街の雰囲気を味わっているだけでも、大きな価値があると思います。
-そういうことも、音楽に影響するでしょうからね。
布施 はい。音楽は、やはり人間の内面を映し出すものですから。たとえば、日本の音大生のように、部屋にこもって練習ばかりしているよりは、街に出て一息入れるのも必要だと思います。外に出て、ドイツ人の生活を直接肌で感じたり、何か感動したりすることによって、それが音楽に生きてくるのじゃないのかな、と思います。
-では、何かドイツの悪い点はありますか?
布施 あまり感じたことはないですね。自分から来たくて来たので。自分にとっては、すべてが新しくて、プラスになることばかりでした。いつもポジティブに物事を考えていないと、外国で暮らしてるというだけで、気が滅入ったりすることもあるでしょうし。
-そうですね。ホームシックで、マイナス思考になったりすることもありますからね。
布施 単純なことで言うと、食事なども全然違いますから、そこでホームシックになってしまう方も多いですよね。たぶん、自分の気持ちの持ちようではあると思うんですけど。自分が、そこで何をしたいのかっていう目的があって、楽しみになる部分が多ければ、ホームシックになっても頑張れるのではないかと思うんですけど。
-まさに、その通りですね。さて、ドイツ留学するにあたって、一番重要なことは何だと思いますか?
布施 もちろん、語学は大切だとは思います。留学前に、少なくとも簡単な会話程度はできたほうがいいと思います。ただ、渡航してからでも、コミュニケーションを通して、語学は上達しますから、一番大事なことだとは思わないんです。それ以上に、現地に知り合いがいれば、事前に、なるべく多く情報をもらうことが大事だと思います。特にドイツは、ビザを取得したり、事務的なことがとても大変です。最近は、インターネットでたくさん情報は得られると思うのですが、学校や街によって、少しずつ事情が異なることも多いですからね。
-留学前の情報収集がキーなのですね。
布施 はい。私は、来たばかりの頃、練習するより、事務的なことをする時間のほうが多かったんですよ。学校の入学手続きもそうですし、滞在ビザも、たくさん書類上の手続きを踏まなければいけなくて。だから、これらの事務手続きや書類作りは、日本で準備しておいたほうが絶対にいいです。こっちに来てから、「あの書類が一つ足りない。親に送ってもらわなくては。」などというのは、本当に時間の無駄でしたから。

-では、今、お仕事をされていて、日本人で有利な点、不利な点はありますか?
布施 最近では、日本人だから、というような人種差別的なことは、ほとんどないと思います。ミュンヘンは保守的な街って言われてますけど・・・。オーケストラも、外国人はなるべく入れたくないらしいって話も聞いていたんですけどね。でも、いざ入ってみたら、とてもインターナショナルなオーケストラでしたから、あまり人種的なことは気にしなくていいと思います。ただ、ドイツで、オーディションを受けるときには、招待状が必要なんですよ。ドイツの音大で勉強しました、というだけでは、なかなか招待状は来ません。そういう意味では、受けようと思ったときが、アジア人全般、たぶん不利だとは思います。ただ、オーケストラアカデミーやプラクティカント(研修生)を受験する場合には、招待状は必要ありません。そういうところで経験を積めば、ドイツのオーケストラで弾いていたという経歴を示すことが出来ます。私の考えではありますが、相手にそれ印象付けると、招待状をもらえる確率は高くなると思うんです。そこまで来れば、人種は関係ないです。
-布施さんは、招待状をもらったんですか?
布施 私の場合も、学校と並行して、ミュンヘンフィルの契約団員として、弾かせてもらっていたんです。そのオーディションは、誰でも受けられましたから。そこで採用されて、契約団員として活動を始めてから2ヵ月後に、正式オーディションを受けられたんです。最近は、日本人の方もオーケストラアカデミーやプラクティカントで、たくさん見かけるようになりましたから、皆さんもそうやって始められているのでしょうね。
-少しでも、ドイツで経験を積んでおくということが大切なんですね。
布施 はい。学校と並行してできると思うので、卒業してからと考えずに、在学中から、少しずつ始めたらいいと思います。特にドイツの場合は。
-では、続いて、難しい質問です。布施さんにとって、音楽はどういう存在ですか?
布施 私にとっての音楽は・・・、大きな「喜び」でしょうか。家で練習してても、コンサートで演奏してても、聴衆として聴いていても、曲の素晴らしさや、それによって作曲家の偉大さに感動するようになったんです。この感動は、言葉にするのは難しいのですが、本当に、喜びというか幸せというか…。その空間にいる、何千人という人々と、一つの音楽を共有できるって、なんて幸せなことなのだろう、と思うようになりました。でも、こういう風に感動できるようになったのは、こちらに来てからです。日本にいた頃は、ただ、がむしゃらに練習していましたから。試験に向かって頑張っていた、という感じで。こちらに来てから、音楽が「身の周りにある普通のもの」と感じられるようになりました。リラックスできるようになったというか、頑張りすぎなくなったというか・・・。そうしたら、突然、音楽が、自分にとって喜びに変わってきたんです。
-違った国の音楽に触れるというのは、そういう利点もあるのですね。
布施 ええ。たぶん、自分の視点が変わったと思うんです。気張らなくなったんですね。ですから、レッスンというものを、楽しんで出来るようになったんです。そして、新しいレパートリーを増やすことに専念するのではなく、今まで日本で練習した曲を、自分の新しい感覚で、もう一度弾いてみたいという欲求も出てきました。だから、レパートリーは、そんなに増えませんでしたけど(笑)。
-日本の音大生は、皆さん「テストが・・・」って、よくおっしゃってますものね。
布施 ですよね。私もその一人でしたから、すごく分かります。年に2回、試験があったんですけど、その試験に向かって曲を練習していました。試験の点数ばかり考えていて、楽しむという余裕なんか、全くありませんでした。音楽大学に限らず、学生にとって、試験の点数は常に気になるものですけどね(笑)
-プロの音楽家として活躍するコツや、成功する条件などを教えてください。
布施 成功する条件というのは、必ずしもないと思うのですが・・・。ひとつ言えることは、日本人は、謙遜する傾向にありますけど、ドイツで、それはしないほうが良いと思います。ドイツ人は、図々しいところがあるので、それに対抗できるくらいでないと、せっかくのチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。たとえば、仕事がもらえそうなときに、謙遜して「自分で勤まるのでしょうか」などと言ってしまうと、そのまま不安として受け取られてしまいます。謙遜や社交辞令は、まったく通用しない国なので、ダイレクトに自己主張するのが大切ですね。
-自己主張は、日本人のニガテ分野のひとつですものね。
布施 ええ。日本人だと、相手のことを考えて「こういったら失礼かな?」などと考えて、自分の思っていることも言えなかったりしますよね。ドイツ人は、失礼だと思えば失礼だとハッキリ言いますから、まずは、思ったことをきちんと言うことが大事です。これは、勉強している学生でもそうだと思います。まして、ドイツ人の中で仕事をしようとしているのであれば、なおさら大切なことです。
-日本人にとっては難しいことかもしれませんが、大切なことですね。
布施 あと、よく聞くのが、こういう話です。すごく上手な方が、オーケストラのオーディションを受けて、自分でも良く弾けたと思っていたのに、不採用だったと。それは、その人の出来、不出来ではなく、オーケストラとの相性の話だと思うんです。「すごく上手だけれど、うちのオーケストラには、多分合わないな。」とか、そういうこともあるんです。受けている側にしたら、自分のレベルが低かったのか、などとショックを受けると思うのですが、プロになりたかったら、「ここと縁がなかった」って割り切って、次に向けて切り替えることも大事です。
-落ち込んでしまうでしょうけどね・・・。
布施 これに関しては、どの国の方でも同じです。どうしても入りたかったオーケストラで不採用になったら、やっぱり落ち込みますよ。でも、そこは頭を切り替えないと。

-最後になりますが、海外で勉強したいと考えている方々に、布施さんからアドバイスをお願いします。
布施 まず、自分が、海外で何を学びたいかを、明確にしておくことが大切だと思います。勉強できる時間は限られていますから、目的はハッキリ設定しておいたほうがいいです。たとえば、オーケストラに入りたかったら、学校は、オーケストラに入るための準備期間にする、という考え方もできます。また、留学後に日本に帰りたい、と考えているのであれば、ソロ活動に専念できるような勉強をするとか、やりたいことによって、勉強の仕方も変わってきますから。もちろん、現地に行ってから、自分の気持ちが変わることはあり得ることですが、ある程度は、しっかり目的を持っていくべきだと思います。
-目的を持って勉強するということですね。多くの学生さんにとって、とてもためになるお話だと思います!
布施 そう言っていただけると、嬉しいです。
-今日は、たくさん興味深いお話を聞かせていただいて、本当にありがとうございました!
根岸由起さん/ピアニスト/イギリス・ロンドン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回イギリス・ロンドンでピアニストとしてご活躍中の根岸由起(ネギシユキ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年11月)
ー根岸由起さんプロフィールー

1977年東京生まれ。父親の転勤により5歳から12歳半までニューヨーク在住。10歳からジュリアード音楽院プレ・カレッジに名誉奨学生として在籍。桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部卒業後、アムステルダム音楽院オランダ国家演奏家資格取得、英国王立音楽大学にて、Postgraduate Diploma in Advanced Performanceおよび同大学修士課程を主席で卒業し、その後、アーティスト・ディプロマを修了。第7回ジュネス・ミュジカル国際音楽コンクール第2位など多数の受賞歴がある。これまでに阿部美果子、ヤン・マリス・ハウジング、ルース・ナーイ、田崎悦子、故園田高弘、故イリーナ・ザリツカヤ女史、ドミニク・メルレ、マレイ・ペライア等に師事。ヨーロッパ、アメリカなどで年間30-40回の演奏会を行う。2008年に初のCDをリリースし、BBCプレゼンターのアンドリュー・グリーン氏との対話・演奏形式でDVDをリリース。2010年には第1回サセックス州国際ピアノコンクール(イギリス)で世界的なピアニスト・アルトゥール・ピサロ氏、英国王立音大ピアノ科主任ラタルシュ氏などと審査員を務める予定。ブリュートナー・レジデント講師、ブリュートナー・アーティスト。ロンドン在住。
-最初に簡単なご経歴を教えてください。
根岸 5歳から12歳まで、父親の仕事の関係でNYに住んでいまして、5歳のときに日本人の先生からピアノを習い始めました。10歳から、週1回ジュリアード音楽院のプレカレッジに名誉奨学生として2年間通いました。12歳半で日本に帰国しまして、桐朋学園高校、同大学を卒業しました。そして卒業と同時に、オランダのアムステルダム音楽院に入学し、3年間在籍しました。その後、ロンドンへ移り、王立音楽大学修士課程とアーティストディプロマを取得し、今に至ってます。
-いろいろな所に住まれていたんですね。音楽に興味を持ったきっかけは、ジュリアードのプレカレッジですか?

根岸 もちろん、同じ頃に五嶋みどりさんやサラ・チャンさんなど、現在第一線で活躍されている方もいらっしゃったので、そういう刺激はジュリアードでたくさんありましたが、それ以前に父母の影響が大きいですね。プロではないのですが、両親が音楽好きで、常に音楽が流れている環境でしたし、母が歌を歌ってくれたりしまして。そういうところから、私も音感が良くて、ピアノをやっていたんです。NYにいたときには、身近に音楽がありましたから。父親が、リンカーンセンターやカーネギーホールとかで開かれるコンサートに連れて行ってくれたり、子供用のコンサートやイブニングコンサートに、家族4人で出かけたりしていました。ですから、ある意味幸運ですよね、小さい頃から良い音楽に触れる機会が多かったというのは。海外の一流の音楽家の演奏を聴けましたからね。そして、当時あこがれていた、一流の演奏家の皆さんが住んでいたのがロンドンだったんです。なので、漠然とではありましたが、ロンドンに住みたいなというのが、子どもの頃からの夢だったんです。
-子どもの頃からの夢を叶えられたんですね。
根岸 縁があったんでしょうね。でもやっぱり嬉しいですし、毎日楽しいです。
-アメリカはジャズなども盛んな国なのに、クラシックを選ばれたのは、やはりご両親の影響ですか?
根岸 そうですね、うちはジャズに縁がなくて。NYには、ブルーノートという有名なジャズバーがあるのですが、子どもでしたから、夜が遅いこともあって聴きに行かなかったんですよね。なので、ジャズという音楽は知らなかったです。今思えば、平日通っていた現地の学校が、音楽が盛んだったので、その影響も大きかったと思います。クラスでミュージカルや発表会があったりしたので、日本の音楽の授業のように、勉強という感覚がなかったんですね。「音楽は楽しい」という感覚が、幸い、その後につながったんじゃないかなという気がしますね。
-日本の音楽の勉強っていうと、「四分音符は~・・・」とかですものね。
根岸 やはり、アメリカはミュージカルや映画の国ですから、そういう意味では、ジャズ以上にそちらの音楽のほうが身近にありましたね。
-では、留学先でオランダを選ばれた理由は何だったんですか?
根岸 大学3年生の夏に、夏期講習に参加したのですが、それがオランダの音楽祭だったんです。そこに行ったきっかけは、各国からいろいろな名教授が集まっていたということでした。私も留学を視野に入れていましたから、どの先生に習おうか、という選択肢が多かったので、そこを選んだんです。そこで意気投合したのがオランダの先生だったというわけです。全く決めて行ったわけではなかったですし、他にも著名な先生がいらしたんですけど、その先生が、そのときの私にぴったり合った方でした。そして「では、ぜひ翌年からオランダへいらっしゃい」と言っていただいて。それから1年くらい留学準備をして渡航しました。

-ピッタリの先生に出会うというのも縁ですね。
根岸 はい。決めるときも、そんなに悩まずにパパっと決めてしまったんです。そのときの若さというか、勢いというか(笑)。あと、オランダは英語が通じますからね。オランダ語もあるのですが、すごく難しいですし、オランダ人も英語を話してくれるので、私としては「英語で話せる国」っていうのだけでも魅力的だったんです。他の語学を勉強してはいても、やはり気が進まなかったので(笑)。
-オランダは、お店などでも英語なんですか?
根岸 オランダ語なんですけど、外見がどうしても日本人なので、英語で話してくれましたね。オランダ人は、そういうところが柔軟なんですよ。
-では、オランダという国を選んだというより、先生を選ばれたということなんですね。
根岸 先生ですね。基本的に、音楽とオランダが結びついていなかったですからね。オーケストラとかが素晴らしいのは知っていましたけど、そんなに身近ではなかったので・・・。

-オランダの学校はどんな雰囲気ですか?実践が強いのでしょうか、学術的なのでしょうか?
根岸 オランダって、ロマン派の作曲家がいないんですよね。現代ものが著出しているんですけど、ある意味、ピアノは特別強いっていう感じではありませんでした。ただ、ドイツや北欧、インドネシアやメキシコなど世界中から学生が集まっていまして、学校のカラーというよりは、そういうインターナショナルな雰囲気がありましたね。よく来日されるブロン先生という先生がいらしたので、日本からも留学生が来てましたし。ジャズもありましたので、自由な雰囲気でしたよ。ピアノやバイオリンは、学術や実践が強いというわけではなくて、それぞれの先生のクラスで成り立っていたって感じですね、。
-最近オランダへ留学を希望される方が多いので、どんな感じなのかお聞きしたくて。
根岸 素晴らしいところですよ。コンセルトヘボウという、オーケストラもホールも素晴らしいですし。すぐ目と鼻の先にそれがあったので、わたしは、練習の後に出かけたりしてました。あと穏やかで、住みやすい国ですよね。
-留学が初めてという方でも行きやすいですか?
根岸 そうですね、英語も通じますし、人が親切で治安もいいし、街も素敵で住みやすいですよ。ロンドンみたいに大きい街でもないし。私の経験からなのかもしれませんが、次へ行くためのステップアップの場所っていうイメージもあります。
-さて、オランダを経て、イギリスに移られたわけですが、それはやはり夢だったからですか?
根岸 アムステルダムからロンドンは距離も近いですし、アムステルダムに留学していたのは、まだ20代前半でしたから、もう少し勉強したいという気持ちがありました。夏期講習も毎年参加していたんですけど、3年目の夏期講習で、ロシア人の先生で、ショパンをすごく素敵に演奏される方がいらして、その先生がロンドンで教えられているということを知ったんです。その当時、先生ももちろん大事でしたけど、住む場所も大事に考えていましたから、その先生と出会ったとき、「あ、ロンドンだ!」と。これは行くしかないいう感じで飛びつきました。しかし、私が王立音大を受験した年に、その先生が心不全で亡くなられてしまったんですよ。これが初の留学経験だったら、たぶん動揺して日本に帰ってたかもしれないですね。でも、私の場合は、ロンドンに住みたいという気持ちがありましたし、学校も決まっていたので、移ることにしました。なので、先生に習いに行くというより、ロンドンに行く、学校に行くという目的で行きましたね。
-では、師事する先生は、渡航してから決められたのですか?

根岸 そうです。大学の主任が、亡くなられた先生の生徒を集めて話し合い、振り分けたんですけど、私は新入生だったので、代わりに入られた新しい先生につく形になりました、その方はオーストラリア人でしたが、長年イギリスで教えられていた経験豊かな方でした。息も合いまして、在学中はずっとその先生についていました。
-先生との相性は大事ですよね。
根岸 何を求めるかによりますが、私の場合は、ピアノを極めたいというか、勉強したいという気持ちがありましたので、学校も大事ですが、先生との個人レッスンが一番の核となりますから、重要ですね。
-そう考えると、本当に先生に恵まれてらっしゃいますね。
根岸 そうですね。私の場合は、合わない先生は初めから興味がなくなってしまうので(笑)。留学先を決めるにも、この先生とは合う!と強く思わないと、決められなかったと思いますよ。
-先生との相性が分からないと、留学先も決められないということですね。
根岸 ええ。今の時代、どこにでも行くことが出来ますよね、特に日本は選択肢がありすぎて、何で決めるかといえば、音楽の場合は先生になるんでしょうね。研究だったらその研究内容や教授によるんでしょうけど。
-さて、今現在はロンドンでどんな活動をされているんですか?
根岸 3年前に卒業しまして、そのまま居続けているのですが、ピアノの場合は、オーケストラに入ることが出来ませんので、ピアノを教えることが生活の基盤となっています。今、18人生徒を持っているのですが、それが限度ですね。演奏活動したいので、とにかく練習時間や移動時間を工面しながら、演奏の機会を作っているという感じです。
-生徒さんはイギリス人が主ですか?
根岸 半分は、日本人の大人の方ですね。ロンドンには日本企業もたくさん入っていますので。これも縁なのですが、ネットワークの広い方と出会いまして、その方を通して日本人の生徒さんとたくさん出会うことができました。あとの半分は、現地の子どもとか、ドイツ人やオランダ人ですね。国際都市の象徴という感じですね。

-楽しそうですね!
根岸 そうですね、和気あいあいとやっていますよ。でも、割り切って、深入りしないでやっています。本業は演奏と考えていますから。
-なるほど
根岸 これも出会いだったんですけど、学生の頃とにかく演奏の機会を持ちたくて、ロンドンの教会のランチタイムコンサートで演奏していたんです。そのとき、あるドイツのピアノメーカーのイギリス支店の方に出会ったんです。そして、卒業と同時に、生徒さんの紹介や、演奏会の紹介、CDリリースなどのお世話になるようになりました。半分エージェントのような感じです。そこを通して演奏会の機会を持たせていただいてます。
-本当に素敵な出会いに恵まれてらっしゃるんですね。
根岸 次から次へつながっていくというのは、縁ですよね。人生おもいしろいなと思いますね。ロンドンの素晴らしいところは、トップの現役の演奏家が住んでいますから、エージェントからの情報が多いんですよ。オーケストラやホールもたくさんありますし、機会も多いです。ショパンコンクールとか大きなコンクール以外にも、小さなオーディションも多いです。ピアノのエージェントを通してつながると、さらに広くつながるというか。
-人脈が大事なのですね。
根岸 本当にそうですね。才能や経歴があれば良い、という時代ではなくなってきたんでしょうね。人との出会いを大事にして、礼儀を尽くすということが出来ない人は、演奏が上手でも嫌われていきますからね。あと、日本は肩書きや経歴を重視しますが、他の国では関係なかったりすることもありますからね。もちろん、国際的なコンクールも素晴らしいですが、今はそれも世界中でたくさんあって、1位の人もたくさんいるわけでしょう。クラシック業界は飽和状態なんですよね。だから、インターネットも発達していますけど、トップの方でもブログを書いていらしたりして、いかに情報を発信するか、になってきましたよね。だから、「私はこんな経歴がある!才能がある!」と気取っていても何にもならないですから。周りのイギリス人を見ていても、情報の発信が上手だから演奏の機会が多いという人ってたくさんいますよ。

-なるほど。では、仕事をするに当たって、日本人が有利だなと思う点や不利だと思う点は?
根岸 信頼度が高いという点では日本人がトップですよね。金銭感覚もそうですし、何か頼んだ場合でも、必ずそれをやり遂げるという確実性が信頼につながっているんでしょうね。それはよく言われます。不利な点としては、受身がちという傾向があるかもしれないですね。あと、私の場合は、幸い語学で苦労はしていないですが、語学って本当に大事だなと思います。いくらコンクールで優勝しても、自分から積極的にいろいろなところにコンタクトを取ったりしないと、実際やっていけないですから、それには語学はどうしても必要ですね。
-言葉が通じる人と通じない人とだったら、やはり通じる人のほうが採られるということでしょうか。
根岸 もちろん演奏の内容が大事なのでしょうけど、表現に対する積極性ですね。英語がペラペラじゃなくても、やる気を見せて、意思疎通を図ろうとすればいいと思います。つまり、受身ではなく積極的にということですね。
-日本人は、間違えたら恥ずかしいということを気にして、消極的になりますものね。
根岸 そうですね。でも、最近周りの日本人の方々を見ると、皆さんたくましく生きてらっしゃいますよ。慣れもあるのでしょうが、度胸がついてくるのでしょうかね。日本にいても、積極的に出て行かないと、芸の世界は限られた人しか出来ませんので、積極性は必要でしょうから、それは世界共通でしょうね。
-よく、留学を希望される方に、「言葉が分からなくてもどうにかなりますよね?」と言われますが、結局帰ってくると「言葉が分からないことが悔しかった」という感想が一番多いんですよ。言葉が分からないことにより、消極的になってしまったというか。
根岸 分かります。私自身もそうなんですよ。英語はともかく、ドイツ語やフランス語は苦手なので、そこには留学しなかったというのもありますし。無意識に避けてたかもしれませんね。
-ドイツ語やフランス語は勉強されていたんですか?
根岸 大学では習っていたのですが、やはり英語が身についていましたので、ついついそちらに流れていったというか・・・(笑)。フランスやドイツに行ったとき、ちょっとした会話は出来るのですが、込み入った話は分からないですからね。それを今から勉強するかと考えると、ちょっと気が遠くなりますね(笑)。
-難しいですものね。
根岸 友人でドイツやフランスに留学して、長年暮らしている人たちを見ると、本当に尊敬しますね。
-でも、根岸さんは、何かあってもプラスに変えたり、偶然をチャンスに変えていく力はすごく強いと感じたのですが。

根岸 それは、アメリカで育ったという特性なのかもしれません。アメリカの学校では、「間違ってもいいからとにかく手を上げろ」という教育でしたので。日本や他の国だったら、答えが確実に分かっていないとい手を上げないという雰囲気があるかもしれないですが、アメリカ人は口が達者で目立ちたがり屋なので(笑)。
-日本人は間違えることが恥ずかしいんですよね。アメリカ人は積極的ですものね。
根岸 くだらないことを話しても説得力があればいいんですよ、アメリカという国は(笑)。
-そういう積極性は、やはり大事なんですね。
根岸 最終的に、表現したいものや意欲が強ければ強いほど、世の中を渡っていくときに強いと思います。アメリカ人だけでなく、いろいろな国の方を見ていてそう思いますね。先生に言われて、それを受身でとらえているだけでは、それっきりですから。自分で試してみたり、断られるのが前提でも、いろいろなところににコンタクトを取ってみたりするのが大事なんだと思います。
-一度断られると消極的になってしまうということもありますよね。
根岸 それもあるかもしれませんね。日本人は良い意味でも悪い意味でも、真面目ですからね。
-自分から出て行く力がないとダメなんですね。
根岸 日本ではどうか分かりませんが、ロンドンという街ではそうですね。今年で9年目になるんですけど、今でもそう思います。
-そういうのが活躍の条件なのかもしれませんね。
根岸 やはり、大切なのは実力なのでしょうけど、実力がある人は、本当にたくさんいますから。その中で少しでも秀でるためにはどうするか、そういうことを考える力が大事なのかなと思います。
-人間力が大事なんですね。実力もありつつ、人間としても素晴らしい方というのが成功するのでしょうね。
根岸 全てにおいて秀でているというより、個性があるというか、それが強ければ強いほどいいんじゃないかなと思います。生まれ持ったものもありますけど、ある程度は成長していく中で身につくものもあると思います。

-どうしても日本の方は、「この学校じゃなきゃダメ、有名だから」とか言ってしまいがちですが、自分で何が重要か見極めることが大事なんですね。
根岸 そうですね。業界の方の話を耳にすると、クラシックの名曲CDなんて出尽くしちゃっているんですよね。この時代、足りないものってないんですよ。だから、自分の出来ることを探したほうが、むしろ個性につながるんじゃないかと思います。演奏会のプログラムひとつでもそうです。有名な作曲家の曲を演奏するのも素晴らしいことですが、その中に新しい作曲家の曲を入れてみるとか、ちょっとテーマ性を入れてみるとか、工夫をしたほうが受けますね。それと、壇上でお話することも、お客様から受けがいいですよ。
-ただ上手であることより、少しでも自分らしさを持っていたほうがいいんですね。
根岸 今は、ほとんどそれが必要なんだと思います。特に、イギリスはビートルズなどのロックスターが出たり、とにかく芸能人が好きな国なので、エンターテイメント性を求める傾向があるかもしれません。ドイツとかならバッハやベートーベンを完璧に弾いてもらいたい、という傾向があるかもしれませんが・・・。イギリスは、アメリカよりも、英語という言葉が文化なんですね。演劇・舞台も充実していますし、そういう背景があるので、ただ演奏するだけでなく、そのほかの要素を求められるのかもしれません。

-ちなみに、アメリカ英語とイギリス英語の違いなどは感じましたか?
根岸 はい。実はそれ興味がありまして、日ごろから笑い話として情報を集めているんですよ! やはり、まずは発音が違います。アメリカは丸い感じの発音なのですが、ヨーロッパの人はアメリカ英語をバカにするんですよ。18歳のとき、初めて講習会でヨーロッパに行ったのですが、みんなに「アメリカ帰りか?」って言われましたね。そのときは「何で、そんなにいちいち言うのかな?」って思ってたんですけど。10年くらい経った今では、アメリカ人に「イギリス英語になってきたね」って言われるんです。でも、今でもイギリス人にはアメリカに住んでた?って聞かれるんですけどね(笑)。舞台を観に行って思うのですが、発音って大きいんですよ。アメリカ英語で、シェイクスピアとかを演じられても違和感があるんです。それを、少しだけカドをつけたイギリス英語でやるだけで、しっくりくるんですよ。
-それは、おもしろいですね!
根岸 それが表面的な違いなんですけど、言い回しもけっこう違いますね。同じ意味でも言い方が違うとか、地下鉄とかズボンとか、そういう単語も違いますし。やはり、ちょっとした違いはありますね。通じないことはないんですけど、それ何?みたいな事はありますね。それと、言葉ではないのですが、ここで育ってないから分からないということももちろんあります。中学高校時代に流行った歌とかジョークとか。これはしょうがないですけど。
-日本人は知っていても、外国の人は知らないことなどは多いですよね。
根岸 私も帰国子女ですけど、日本語の言葉遣いがすごく変だといわれましたね、小さい頃日本で育っていないので、かしこまった感じでしゃべっていたようです。
-私は、短期でアメリカに行ったことがあるんですけど、話す言葉があまりに硬すぎるようで、逆に伝わらないこともありました(笑)。こちらもスラングが分からなかったですし。
根岸 私も今の日本語分かりませんよ! ネットでニュースを見るのですが、「アラサー」とか「アラフォー」とか、何だこれ?みたいな(笑)。あとで調べて分かったんですけど。
-言葉はどんどん作られていきますからね。さて、ここで、難しい質問なのですが、クラシック音楽は根岸さんにとって、どういう存在ですか?
根岸 子どもの頃から身近にありましたし、大げさですが、私にとっては人生そのものですね。語学のお話をしましたが、もうひとつの「音楽語」という感じで、表現の手段の一つです。感情や経験、すべてが表現できるもので、自分自身から切り離せないものですね。あと、もう少し大きな意味で言うと、人類が残している素晴らしいもののひとつだと思います。バレエ、絵画、小説、映画、建築などに匹敵するというか、それ以上に残していくべきものだと思います。伝統文化であり、流行で消えていくものではないですから。
-今の音楽の多くが消えていってしまう中で、クラシックは残っていくし、残すべきですね。
根岸 どんな国のどんな人種でも、心を動かす力があると思います。不景気の中、戦争の中、テロの中、災害の中でも、音楽ってやはり人々を救う力あると思うんです。希望を与える力や、癒す力もあると。

-では最後に、海外で勉強したいと考えている方へ、アドバイスをお願いします。
根岸 やはり、積極的にいくということと、目的意識を持つということが大事ですね。夢は大きく、目的意識を持ってほしいです。現実的な話をすれば、自分に合ういい先生を見つけましょうとかになりますが、それにしても、まずは「自分はこういう演奏家になりたい」という信念が根になりますから。その信念に従って講習会に参加してみたり、旅に出てみたりしてほしいですね。あとは、語学を少しは身に着けておくと楽だと思いますよ。
-目的意識や目標がないと最後にぶれてしまいますもんね。
根岸 そして、何をやるにも、自分が楽しむという姿勢が一番ですよ。
-そうですね。本日は素晴らしいお話とアドバイスをありがとうございました!
花岡伸子さん/チェロ/英国フィルハーモニック管弦楽団/イギリス・ロンドン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回英国ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団でご活躍中の花岡伸子(ハナオカシンコ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年12月)
ー花岡伸子さんプロフィールー
 1971年生まれ。8才より中島隆久、藤原真理、山崎伸子の各氏に手ほどきを受ける。桐朋女子高等学校音楽科卒業後、同ディプロマコースを経て、アメリカに留学。岩崎洸氏に指導を受ける。1994年、伝説のチェリスト、ジャクリーヌ・デュプレを育てたウイリアム・プリース氏に招かれ、英国ロイヤル・カレッジに入学。同氏のほかスティーブン・イッサーリス、コリン・カー氏らに師事。ロイヤル・アカデミー音楽院大学院を首席で修了後BBCヤング・アーティストシリーズ、スピタフィールド国際音楽祭などに出演、スペンサー伯爵邸でのダイアナ妃メモリアル・コンサート、ヴィクトリア&アルバート美術館での天皇・皇后両陛下訪英記念晩餐会での演奏などがある。また、トーマス・ツェトマイヤー音楽監督率いるノーザン・シンフォニアのゲスト首席チェリストとして演奏し、絶賛を博す。日本人初の英国ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団員として活動するなど、現在ロンドンを拠点に、様々な音楽シーンで幅広く活躍している。
1971年生まれ。8才より中島隆久、藤原真理、山崎伸子の各氏に手ほどきを受ける。桐朋女子高等学校音楽科卒業後、同ディプロマコースを経て、アメリカに留学。岩崎洸氏に指導を受ける。1994年、伝説のチェリスト、ジャクリーヌ・デュプレを育てたウイリアム・プリース氏に招かれ、英国ロイヤル・カレッジに入学。同氏のほかスティーブン・イッサーリス、コリン・カー氏らに師事。ロイヤル・アカデミー音楽院大学院を首席で修了後BBCヤング・アーティストシリーズ、スピタフィールド国際音楽祭などに出演、スペンサー伯爵邸でのダイアナ妃メモリアル・コンサート、ヴィクトリア&アルバート美術館での天皇・皇后両陛下訪英記念晩餐会での演奏などがある。また、トーマス・ツェトマイヤー音楽監督率いるノーザン・シンフォニアのゲスト首席チェリストとして演奏し、絶賛を博す。日本人初の英国ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団員として活動するなど、現在ロンドンを拠点に、様々な音楽シーンで幅広く活躍している。
-まずは、簡単なご経歴をお願いします。
花岡 8歳でチェロを始めて、桐朋学園の「子供のための音楽教室」に通いました。そして、桐朋女子高等学校音楽科を経て、桐朋のソリストディプロマコースに進学。その後、イリノイ州立大学、英国王立音楽院に留学しまして、現在は、ロイヤルフィルで活動しています。
-いろんな学校に通ってらっしゃったんですね。チェロを勉強したいという気持ちが強かったんですか?
花岡 音楽の勉強というのは、だいたい先生を頼っていくので、自分が習いたい先生がいるところに行くっていうのが普通なんですよ。そうなると、どんどんこうやって進んでいく形になっちゃうんですよね。イリノイに行ったときも、日本人の先生だったんですが、その方が州立大学にいらしたので、そこに行ったというだけです。その後、英国に関しては、ロータリー奨学金というのをいただいたので、それの関係で英国に行くっていうのは決まっていたんですけど。
-ロータリーって取るのがすごく難しい奨学金ですよね!優秀でいらしたんですね。
花岡 ラッキーだったんですよ。
 -花岡さんがチェロを始めたきっかけを教えてください。
-花岡さんがチェロを始めたきっかけを教えてください。
花岡 姉がバイオリンを習っていまして、最初は、私もなんとなくバイオリンを始めました。その後、姉妹一緒というのもつまらないので、私はチェロに変えたという感じです。
-お姉様は、今もバイオリンを続けていらっしゃるんですか?
花岡 いえ。アート関係ですが、音楽とは関係ない仕事をしています。
-花岡さんが、チェロの魅力に目覚めたのは?
花岡 もう、成り行きというのでしょうか。それが自然な道だったというか、なるべくしてなったという感じでしたね、私の場合は。自分からどうしてもチェロをやりたい!という感じでもなかったので。
-生活の一部だったという感じですか?
花岡 そうですね、。それがそのままずっとここまで来た、という感じですね。
-チェロをやっていたから、クラシックに興味を持ったという感じですか?
花岡 うちは、小さいころテレビが無かったんですよ。あっても見させてもらえないという環境だったので。ですから、ポップスとか流行歌とかに疎かったんです。特に、両親がすごくクラシックが好きというわけではなかったんですけど、クラシックの方が他のジャンルの音楽より聞く機会が多かったんですね。
-当時は、どんな作曲家が好きだったんですか?
花岡 バッハが好きでしたね。あと、バロックやルネッサンス音楽とかがすごく好きでした。
-チェロの演奏家になろうと思い始めたのはいつ頃からですか?
花岡 プロを目指してっていうのは10歳くらいですかね。桐朋の「子供のための音楽教室」に通い始めた頃からでしょうか。桐朋の場合は、高校に入る前の段階からスペシャル教育が始まるんですよ。
-その時は、チェロの実技の他にも勉強することはあったんですか?
花岡 ソルフェージュや聴音などですね。これは、すごく勉強しなければいけませんでした。
-週一回のレッスンですか?
花岡 はい、毎週土曜日に桐朋の大学の校舎で行われていました。まず聴音やソルフェージュをやって、その後にオーケストラがありました。受験が近くなったら、プライベートに先生のところに行って、レッスンを受けましたね。実技ではなく、やはりソルフェージュや聴音の。
-受験対策のための塾通いという感覚ですね。
花岡 そうですね。それを経て桐朋の音楽高校に進んだんです。だいたい皆さんは、そのまま桐朋の大学に進むんですけど、私は、もうひとつのソリストディプロマコースという演奏家養成コースに進みました。その時には、すでにアメリカに行くということは決まっていたので、そこで1年過ごしてからアメリカに留学しました。
-漠然とでも、留学をしたいと思い始めたのは、いつくらいからだったんですか?
花岡 留学したいと思っていたわけではないんですけどね。高校2、3年のとき、桐朋のマスタークラスに、岩崎先生という方がいらしたんです。その時、「この先生につきたい!」と思いまして、そこで、アメリカに行きましょうということに決まったんです。でも、たぶん小さいころから漠然と、外国に行くのかなっていうのは、頭のどこかにあったんでしょうね。昔の日記に書いてあったのを見て、強く思っていたわけじゃなくても、自分の中で決まっていたというか、なんとなく口にしたことでも、後でそうなっていることってあるんだなって思いました。
-行きたい!と強く思っていたわけではなく・・ですか。
花岡 自分はこういう風になりたい!って言っていたわけじゃなくて、ぽろっと口にしたって感じですね。イギリスに行った頃に、ふと思い出したんですけど。小学校時代、友達同士で交換日記をやっていて、私そういうこと書いていたんですよ、そんなに知識もないのに、「何歳でイギリスに行って・・・、王立音楽院に行って・・・」って。チェロもそんなに熱心にやってた時期じゃないのに。そういうのもあるですね。
-なんだか運命的ですね。
花岡 結構、そういうのって皆さんにもあると思いますよ、。こんなことをやりたいなって漠然と思ってたことが、そういえばその通りになっているって。
-あったかな、私?(笑) では、アメリカへは先生に出会ったことがきっかけで行かれたんですね。
花岡 たまたま、アメリカに習いたい先生がいたからという理由ですね。その後、イギリスに行くと決まったのも、奨学金制度の規定によるものですし。ロータリー奨学金制度の場合は、留学先の言葉ができていないと奨学金が下りないんです。私は英語しか話せませんでしたから、ヨーロッパに行きたいならイギリスしかなかったわけです。フランスに興味はあったんですけど、フランス語は話せませんでしたからね。なので、私の場合は、強く望んでそこに行ったというわけではなく、最終的にそうなっていたという感じです。
 -そういうきっかけだったんですね。では、イギリスに長くいることになった理由はなんでしょうか。
-そういうきっかけだったんですね。では、イギリスに長くいることになった理由はなんでしょうか。
花岡 イギリスでは、特別先生に恵まれたというわけではなかったんですけど、居心地が良いんですよ。言葉だけではなく、イギリスの雰囲気や生活、ロンドンの街、音楽に対するみんなの姿勢っていうのが、居心地が良いというか。これも成り行きですよ(笑)。
-運命付けられているような感じもしますけどね。流れに逆らわずに行くというのも方法なんですね。
花岡 それも人それぞれだし、その人の選択ですからね。
-イギリスとアメリカで音楽を勉強することについてお伺いします。まずは、アメリカでクラシックを勉強するにあたっての、長所と短所を教えてください。
花岡 私が行ったのは、アメリカといっても、ニューヨークなどの都市ではなく、イリノイ州という田舎だったんです。なので、アメリカ全体の音楽のことはわからないし、19歳からの2年間だけだったので、音楽業界に詳しいわけではないのですが・・・。でも、アメリカはやっぱりアメリカかなっていう感じですね。クラシック音楽というのは、ヨーロッパの音楽だから、アメリカにとってもクラシック音楽というのは、外国の音楽なんですよ。アメリカ人がプロデュースするクラシック音楽は、ヨーロッパ人のするそれとは全く違います。音楽の種類が全然違うんですよ。日本のクラシックも違うと思いますけどね。ただ、アメリカで勉強する子たちは、いわゆるスターダムに上る、大きな通過点として考えていますから、層は厚いですよね。
-お国柄が音楽の違いにも表れるんでしょうか。
花岡 アメリカはヨーロッパではないですからね。欧米ってひとくくりにしますが、アメリカはアメリカです。これから行かれる人も、どっちが肌にしっくりくるかだと思うし、何をやりたいのかにもよって違うと思います。テクニックをとことん勉強したいっていうのであれば、アメリカも向いていると思うし、そうではないもっと根底にある、香りや血のようなものを感じたいなら、アメリカに行ってもそれはない、ということですね。
-英語圏ということで、イギリスとアメリカをセットで考える方も多いですけど、全く別物ですよね。
花岡 そうですね、でも、イギリスも特殊なんですよ。島国ですから、他のヨーロッパ大陸の国々と比べると、またちょっと違うんです。イギリスはイギリスなんですよ。もっともっとヨーロッパらしいっていうか、音楽というものを本当の意味で体感したいなら、ヨーロッパ大陸に行ったほうがいいと思います。ドイツやオーストリアなどに。楽器によっては、フランスもいいかもしれないですね。
-なるほど。では、イギリスでクラシックを学ぶ長所と短所を教えてください。
花岡 イギリスは、何でもある程度、適当っぽくて自由です。ただ、その分、教育メソッドがしっかりしていないというのはあります。フランスやロシアなどは、すごく教育メソッドがしっかりしているんですよね。それをAtoZで、最初から最後までやると、ある程度のところまでいけますっていう保障がありますが、イギリスはそういうのはないです。先生も系統立てて教えてくれませんし。本当に才能がある人は、たまにポーンと出てくることはあっても、教育によって出てくることはほとんどないです。
-すごく勉強になりました。イギリスは教育もしっかりしていると思っていました。
花岡 しっかりしてないですよ、音楽に関しては。こんなことを言うのもなんですけど、音楽的に素晴らしい国かというと、いろんな意味で、そうは言いがたいですね。それに、音楽をやっている人に対して、国からサポートがあるかと言えば、すごく少ないですし。ということは、外国人アーティストやミュージシャンにとっては、生き難い街と言えますね。私は縁あってここにいますけど、音楽を離れたところで、国の雰囲気が肌に合うとか、そういう部分ですよね。
-けっこう現実は厳しいんですね。
花岡 行ってみないと分からないこともありますね。イギリスに夢を持って来ても、生活の面で不便だったりすると、うーん・・・って思うこともあるだろうし、決める前に講習会などに行ってみたりするのも、ひとつの手だと思いますよ。
-それで、合う合わないは、何となくわかりますものね。ちなみに花岡さんは、行かれたんですか?
花岡 行きました、っていうよりも、ロンドンっていうのは決まっていたんですけどね。先生や学校を決めるために一回行きました。その時に、好きだなって思いましたね。リージェントストリートとか歩いて、「ああ、いい感じ!」って、心がワクワクしました。それも大事な要素ですよね。
-たとえば、アメリカに行きたいから、とりあえず行くっていうのは、少し危険な面もあるのでしょうか。
花岡 一回行ってみるのもいいでしょうけど。イギリスとアメリカで迷っているんだったら一回行ってみたらいいと思います、全然違うから。アメリカに行くって決めてるなら、それでいいと思いますけど。
-音楽的に魅力があっても、ドイツという国が合わない人もいるでしょうからね。
花岡 それ、わたしですね。ドイツなんて絶対ヤダって思うから(笑)。音楽的に素晴らしいのは分かっているんですけど、もう少しパーっとしたところがないとイヤなんですよね。これは、性格でしょうね。ドイツはすべてが田舎で小さいし、ダサめだし(笑)。人それぞれですけど、私は、もうちょっと都会的な場所が好きなので(笑)。
-人にそれぞれ合う合わないはあるので、一概にどこが良いとは言えないですもんね。
花岡 行ってみて失敗するのも、ひとつの経験だと思いますよ、若い人は特に。そのうち流れ着きますから、自分のベストな場所に。
-アメリカ、イギリス両国に留学を経験されて、最も留学に重要とされるものは何だと思いますか?
花岡 やはり、語学は必要だと思います。でもそれに関しては、行ってからでも社交性があれば大丈夫だとは思いますけどね。出来るようになるものだから。私も、アメリカに行ったときは、「How are you?」も言えないくらいでしたからね。準備なんかしていくタイプじゃないし、出たとこ勝負みたいな感じでした。わたしも社交的なタイプではなかったですけど、コミュニケーションは1対1でも取れるものだから、そういう意味で、人と関わるのがイヤでなければ上達していくものですよ。
-レッスンの時はどうされていたんですか?
花岡 一番最初は日本人の先生でしたから。でも、レッスンは意外と分かるんじゃないかな、と思います。弾いて見せてもらえたりするわけだから。あと大事なことと言えば、柔軟性かな。柔軟性と楽天的な考え方(笑)。それは留学とは関係なく、なんでもそうだとは思いますけど。
-それが顕著に出るのがやっぱり留学なんでしょうね。ある程度は流れの中でやっていくっていうのも大事なのかもしれないですね。花岡さんは、イリノイに行ったときは、英語の学校に通ったりしたのですか?
花岡 行きましたよ、海外留学生のための語学学校を大学が設けていまして。アメリカはTOEFLのスコアがないと大学に入れないじゃないですか。私はそんなの用意してないし、点も低かったので、最初の半年はそこに通っていました。大学の寮には住んでいましたし、レッスンは受けてましたけど。
-英語のスコアをとった後に、入学になるんですね。
花岡 生活は、大して変わりませんでしたけどね。
 -音楽科目以外のことは勉強されたんですか?
-音楽科目以外のことは勉強されたんですか?
花岡 はい。一応普通の大学でしたから。その頃は、全然語学が出来ていなかったから、なるべく言葉が必要ないクラスを取っていました(笑)。それに、そこには2年くらいしかいるつもりはなかったし、卒業するつもりもなかったから。レッスンが受けられれば良いという感じだったので。
-ある程度は、語学はできていたほうがいいのですね。
花岡 あと語学じゃなくてコミュニケーションスキルがあるというのは大事です。人との関わり方ですね、特にアメリカでは。
-やはり話さないとだめですか?
花岡 言語を通さないと最初のコミュニケーションはできませんからね。人と人とがコミュニケーションをするっていうことが出来ないと、誤解が生じたり上手くいかないことが出てきます。語学が出来てなくても、コミュニケーションをとろうという、基本的なマナーや姿勢があれば絶対伝わりますし。それが日本語でも出来ないような人っていうのは、語学とは別に問題が出てくると思います。
-日本で出来なかったら、外国語ではできませんよね。
花岡 生活面でも、大家さんとのやり取りとかがうまくいかなかったり、そういうのは語学の問題だけでなく、コミュニケーションスキルの問題。結局仕事だってコミュニケーションに左右されますから。
-どんな仕事をしているにしても大事なことですもんね。今、イギリスでお仕事する上で、日本人が有利な点や逆に不利な点はありますか?
花岡 有利な点は特にない!(笑) 不利な点はビザ!イギリスでビザを取るのは非常に難しいんです。最近は、少し変わってきて、オーケストラの仕事でも、ビザを取れる枠っていうのが出来たみたいですけど。だから、アジア人や外国人が、イギリスのオーケストラにいないっていうのはそういう理由です。帰らざるを得ないんですよ。
-そういう意味で、音楽を学ぶ人には優しくない環境なんですね。
花岡 それも含めて、ですね。大きな意味でいうと、アートに関して、国がそんなにお金を出さないんですよね。ということは、アーティストは非常に苦労するんですよ。アートってサポートがなければ成り立ちにくいんです。ビジネスなんですけど、他のビジネスとは違いますからね。
-ドイツなどでは、割とサポートされていますものね。
花岡 アーティストが労働条件の面などで守られているんですよね。そういうのが、イギリスは全くないですね。
-そう考えていくと、合う人は合うでしょうけど・・・という感じでしょうかね。
花岡 確かに魅力的な街ではあるから、金融も文化的にもいろんな物が集まってきていますし。
-今、オーケストラに日本人は花岡さんだけですか?
花岡 私が8年前に入った時は、ロイヤルフィルは私が初めての日本人でした。最近2人入りましたけど。すごく最近の話ですね。
-基本的には、イギリス人の割合が多いんですね。
花岡 9割方イギリス人です。音楽家の人たちが、外国人は入れたくないと言っているわけじゃなくて、国のシステムがそうだから入れないんですよね。高いハードルですね、ビザ取得は。大変なことなんです。
 -イギリスでプロの音楽家として活躍する秘訣や、成功の条件はありますか?
-イギリスでプロの音楽家として活躍する秘訣や、成功の条件はありますか?
花岡 私は、オーケストラという世界で今のところ生きているので、そこに限って言うと、ある程度の器用さは必要だと思います。なぜかと言うと、すごく仕事のスケジュールが厳しいんですよ。まったくリハの時間がなかったりとか、毎日毎日違うプログラムのコンサートをこなしていかなきゃいけないっていう状態。なので、しっかり練習してからでないと弾けないっていうタイプの人は難しいです。ある程度パッと見てパッと出来るような、器用さと集中力が大切なんです。あとは、パッと出て行ける度胸。
-日本人には、不得意な部分かもしれないですね。
花岡 イギリス人は意外と日本人っぽいっていうか、そこまで個人主義じゃなく、グループメンタリティも持っています。フランス人のように、みんながみんなが個人主義というわけではないので、それを無理なく築いていけるような、センシティビティとインディビジュアリティの両方を持っていることが大事ですね。かといって、日本人ほどは、繊細な神経は持ち合わせていませんので、あまり神経質になるとつぶれてしまいます。そういうバランス感覚は大事ですね。
-複雑ですね。
花岡 意外と複雑だし、複雑そうに見えて単純だし。
-日本人は迷ったりするかも知れませんね。
花岡 ある程度、お気楽な気持ちを持っていることも大事ですよね。イギリスはそういう人も多いので。
-やっぱり、いろんな意味でその国の状況に順応できないといけないですね。
花岡 それは向き不向きだったりしますね。おのずと自分の合ったところに流れ着いていくっていうのは、そういうことだと思います。合ってなければ流れ着きませんから。
-では、難しい質問になるかと思いますが、花岡さんにとってクラシック音楽とは何ですか?
花岡 クラシック音楽は難しいですよね。様式や理論の枠が、ものすごくキチンとあるものですから。それを超えたところにある、自由や美を表現出来たときに、揺るぎない感動とか大きい波が作れるものですね。ポップスやロックはノリで出来るものだけど、クラシックはノリだけでは無理ですからね。様式や理論がガッチリ出来たところで、ノリや自由っていうのが加えられると、いわゆる「マジカルモーメント」っていうのがクリエイトできます。そんじょそこらの人じゃ、たどり着けない世界ですけど。そこまで行きつくような才能がある人も少ないですし。
-なるほど。すごく説得力がありますね。さて、花岡さんの今後の音楽的な夢は何でしょうか。
花岡 結局、シンプルなところに行きつくんですが、私は、チェロが自由に弾ければ幸せだと思っているんです。それを聴きたいという人がいてくれて、それを表現する場所があれば、それでいいと思っています。一人でも聴きたいと言ってくれる人が多くなっていってくれればなと思います。自分の時間を使って来てくださるわけですから、その時間が価値のあるものだと思っていただけるような場を作って行きたいですね。私の音楽を通してそれが出来て、その場が増えていくことが理想ですね。
-そういう原点の部分を忘れないでいることは、素晴らしいですね。
花岡 素晴らしいかどうかは分かりませんが、それしか意味がないじゃないですか。そこが楽しいとこで、その中で「じゃあ具体的にどうやっていこう?」などは、もちろん一人のミュージシャンとして、色々頭の中にはありますよ。これをやってみたい、あれをやってみたいって。でも、結局は原点の上に成り立っているんですよ。
-では最後に、海外で勉強したいという方にアドバイスをお願いします。
花岡 海外に行きたいなら、行けばいいと思います。でも、場所はどこでもいいんですよ。結局は、自分の道を歩いていくことが大事で、それが海外なのか日本なのかは、おのずと決まってくることですから。やりたいことをやっていけばいいし、目の前にあることを頑張っていくことが大事なんです。やってみなきゃ分からないこともありますしね。留学してもイヤになって3ヶ月で帰ってくるかもしれないけど、それはそれで良し!その時その時で、一生懸命やっていれば、自分のデスティニーの方に行きますから、自分でも知らないうちに(笑)。
-素晴らしいメッセージをありがとうございます!今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
赤坂-SCHAUPP 知英さん/ヴァイオリン/リンツ・ブルックナー管弦楽団首席/オーストリア・リンツ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回オーストリア・リンツ・ブルックナー管弦楽団でご活躍中の赤坂-SCHAUPP 知英(アカサカ-シャウプチエ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2009年12月)
ー赤坂-SCHAUPP 知英さんプロフィールー

4歳よりヴァイオリンを始める。桐朋学園大学音楽学部卒業、併せて卒業演奏会出演。ドイツ国立デトモルト音楽大学を最高点(1,0)で卒業。卒業と同時にリンツ・ブルックナー管弦楽団第二ヴァイオリンに合格、入団。翌年には、ウィーン国立音楽大学postgradualに入学、最優 秀”Sehr gut”で終了した。同年リンツ・ブルックナー管弦楽団第一ヴァイオリンに合格。さらに08年からは同楽団第一ヴァイオリン首席奏者に就任。これまでにヴァイオリンを山岡みどり、篠崎功子、トーマス・クリスチャン、ゲーザ・ハルギタイ、クラウス・メッツェル他に、室内楽をヨハネス・マイスル、 アルテミスQ、バルトークQ他に師事。近年は新鋭ヴァイオリニストとして抜擢され、自身のオーケストラと共演したり、同オーケストラ団員を含めた弦楽四重奏団を結成。ウィーン、リンツを中心に 演奏活動、企画にも積極的に取り組んでいる。
-まずは、簡単なご経歴を教えてください。
赤坂 4歳でバイオリンを始めました。桐朋学園大学音楽学部を卒業しまして、ドイツの国立デトモルト音楽大学でディプロマを取得しました。卒業と同時にリンツ・ブルックナー管弦楽団、第二ヴァイオリンに合格し入団しまして、 翌年には、ウィーン国立音楽大学に入学し1年在籍しました。同じ年に、リンツ・ブルックナー管弦楽団第一ヴァイオリンに合格。さらに08年からは同楽団の第一ヴァイオリン首席奏者に就任して今に至っています。
-バイオリンを始めたきっかけは?
赤坂 兄がバイオリンをやっていまして、当時、兄のレッスンに連れて行かれていたんですが、そこで見たレッスンの様子が、とても楽しそうだったんです。そして、「あれをやってみたい!」と、母に言ったのですが、本気にされず、無視されてまして(笑)。翌週、先生にやらせてほしいと直談判しました(笑)。
-積極的というか、行動派だったんですね(笑)。
赤坂 そうなんです。
-お兄さんがバイオリンを習っていたのは、ご両親からの影響だったんですか?
赤坂 いえ、全然。母が小さい頃、バイオリンに憧れていたらしく、子どもがやってくれればいいな、という程度だったようです。でも、兄は男の子なので、すぐに別のことに興味が移って辞めてしまったんですけど。
-赤坂さんは、クラシックに興味があったんですか?
赤坂 当時は、音楽の入り口がクラシックだったので「音楽=クラシック」という感じでした。大きくなってからは、ポップスやジャズも聴いたりしましたけど、基本はクラシックでしたね。
-4歳で始められてから、プライベートレッスンでバイオリンを習い続けたんですか?
赤坂 そうですね、4歳から中学生くらいまで、定期的にレッスンを受けてました。でも、両親が、音楽の道に進むことを反対していまして。音楽の道でやっていくのは、かなり苦労するだろうと。それで、音楽高校はあきらめて、普通高校に行きました。その受験勉強があったので、レッスンは一時お休みしました。
-赤坂さんご自身は、いつから音楽の道に進みたいと思い始めたんですか?
赤坂 実際、普通高校に行ったんですが、やはり大学は音楽をやりたいと両親を説得して、桐朋に入ったんです。でも、桐朋って、小さい頃から専門的な音楽の勉強をしている方がたくさんいますから、カルチャーショックを受けて、自信を失ってしまったんですね。これでは、プロでやっていくなんて、到底無理だと思ってしまったんです。なので、実際にプロでやっていこうと思ったのは、留学を決めたあたりですかね。
 -留学を考え始めたのは、いつくらいですか?
-留学を考え始めたのは、いつくらいですか?
赤坂 大学在学中、仲間と室内楽を組んでいまして、ドイツでマスタークラスを受ける機会があったんです。そこで、自分は井の中の蛙だったんだと、ショックを受けまして、海外で勉強をしたいと考えるようになりました。その時、デトモルトとウィーンで教えられている先生と出会って、僕のところで勉強してみたらどうかとおっしゃっていただいたんです。ウィーンかデトモルトで教えていただくことになるわけですが、当時デトモルトってどこ?って感じだったので(笑)、ウィーンでお願いしますって言ったら、「ウィーンには日本人が多いから、キミのような人は日本人の少ない環境で、集中して勉強したほうがいいのではないか」と言われたんです。結果的にはそれが当たりで、ありがたかったですけど。
-ちなみに桐朋に入学された時の挫折感から、どう立ち直って、留学を決意するに至ったんですか?
赤坂 やっぱり、ひとつ大きな自信になったのは、卒業演奏会に選ばれたことですね。バイオリン科約30名の中から3人選抜されるんですが、それに入ったんです。当時コンクールなどは受けたことがほとんどなかったので、自分がどの程度の実力なのか分かっていなかったんですよね。
-それまでは、「自分なんてプロは無理」って思っていたんですか?
赤坂 夢物語でしたね。プロになれたらいいなというのは。自信がなかったんですよ。NHK交響楽団のエキストラとして演奏させていただいた経験があったんですけど、相当レベルの高い楽団ですし、自分がこういう中で、ずっとやっていけるなんて考えられなかったんです。なので、海外に出て世界を広げてみようと行ってみたら、海外の方が肌に合っちゃったんです。2年半では帰りたくない、こっちで働きたいって思うようになっちゃったんですね。
-日本と比べてどこが合っていたのでしょうか。
赤坂 東京の近くで生まれ育ったせいもあると思うんですが、ヨーロッパ全体として、時間の流れがすごくゆっくりですよね。それと、普通に生活している中で、ごく自然に音楽が身近にあるという空気がとても合っていました。
-デトモルトのような小さい街でも、やはり音楽にあふれているのですか?
赤坂 デトモルトは音楽大学でもっているような街だったので、学生も多かったですし、音楽会もありました。ただ、有名なオーケストラは来ないので、演奏会などは、近くの大きな街に行くという感じでしたね。

-音楽をする上での違いはありましたか?
赤坂 日本では全く接することがなかった、いろんな国から来た音楽家の方々との出会いが、とても刺激になりましたね。
-渡航されてすぐの時、戸惑いはありましたか?
赤坂 ありましたよ、最初は。お友達もいないし、食べ物も違いましたし、ホームシックになって、日本に帰りたい!って思っていました。
-語学の面では、いかがだったんですか?
赤坂 私は、日本で2ヶ月くらいしか勉強して行かなかったので、すごく大変でした。これから行かれる方は、語学は勉強してから行ったた方がいいと思いますよ。
-デトモルトは、入学の時、語学の証明書は必要なかったんですか?
赤坂 私が入学した頃はありませんでした。今はあるみたいですけど。
-2年半で卒業されて、リンツに移動されたんですよね。 ブルックナー管弦楽団に入団されようと思ったきっかけは?
赤坂 留学して1年半くらい経った頃、こっちでチャレンジしてみたいと考え始めるようになり、先生に相談したんです。先生は、「ぜひ挑戦しなさい。いったん帰ってからだと、戻ってくるきっかけを失ってしまうよ。」と背中を押してくださいました。専門雑誌に、オーケストラの募集広告が出ているので、それを見てセカンドバイオリンの募集に応募してみたんです。でも、ヨーロッパでは、オーディションを受けるのに招待状を受け取らないといけないんですね、それがなかなかもらえなかったんです。
(編集注:ヨーロッパの中で、国により、招待状が不要な国もあります。)

-オーディションを受けるのに招待状が必要なんですね。
赤坂 はい。現地のオーケストラで活動した経験という基準がないとだめなんですよね。なので、プロではないのですが、ユースオーケストラがあったので、まずそこを受けてみたんです。大きな基準になりますから。幸い、約100人中10人の合格者に入って、ドイツ国内外での演奏の機会が与えられました。そういう経験をしていくうちに、少しずつ招待状が来るようになったんです。でも、その招待状も、エキストラや研修性のオーディションだけでした。私は、絶対にヨーロッパでやって行きたいと思っていたので、先生に相談し、国は変わりますが、先生の出身地である、リンツのオーケストラの正団員募集の空きを見つけて応募したんです。
-ドイツとオーストリアの違いはありましたか?
赤坂 入団オーディションで言うと、オーケストラスタディの課題曲が違います。もちろん、オーケストラによって少しずつ違いますが、ドイツの場合は、ファーストでもセカンドでも大抵の場合ファーストのオーケストラスタディが出るんです。オーストリアは、セカンドならセカンドのスタディが出るんです。なので、急いでそれを勉強し直しました。それから国の違い、ということではありませんが、ブルックナーオケは大抵課題とされるロマン派の協奏曲でなく、バッハのソロソナタが課題だったので、バッハも急いで勉強し直しました。
-オーディションの様子はいかがでしたか?
赤坂 1次予選がカーテン審査でした。45人いて、1次予選を通ったのが8人でした。2次通過が4人で、そのまま4人で4次審査まで続きました。
-最終的には、赤坂さん1人合格だったんですか?
赤坂 そうです。
 -受験者は、現地の方が多かったですか?
-受験者は、現地の方が多かったですか?
赤坂 私が受けた時は、日本人も何人かいました。オーストリアで勉強されている方達でしたね。あとは、やはりドイツの方も多かったですね。全体的にはヨーロッパ人が多かったです。
-45人中1人選ばれたわけですが、合格の秘訣みたいなものはありましたか?
赤坂 ひとつは、無欲だったということですかね。絶対受かるわけないと思ってなかったというか、力試しって思っていたので、上手く力が抜けてたんでしょうね。緊張はしてましたけど、挑戦でしたからね。私のモーツァルトは、どういう風に評価されるのかなっていう程度で。
-変に力が入ってなかったんでしょうね。他には?
赤坂 やっぱり、無欲だったと言う中で、音楽がとても楽しめたんです。全部で3回オーディションを受けたんですけど、初めのオーディションが一番楽しかったですね。
-面接はなかったんですか?
赤坂 4次予選が終わってからありました。一人ずつ呼ばれて、いつくらいから仕事できますか?という程度のものでしたけど。
-結果を聞かれた時どう思いましたか?
赤坂 やっぱり嬉しかったですね。これでヨーロッパで、プロとして仕事していけるんだ!っていう喜びは大きかったです。
-第二バイオリンにも試用期間はあったんですか?
赤坂 はい、半年から1年ありました。
-実際に入ってみて、改めて発見したことはありましたか?
赤坂 最初は、外国人として西洋音楽を演奏していくことにコンプレックスを持っていたんです。でも、皆さんの日本人に対するイメージや、接し方が良い意味で違ってたんです。東洋人だからというマイナスイメージではなくて、むしろ、「日本人は的確に仕事をする」というように、評価が高かったんです。
-日本人だから不利と言うことはなかったんですか?
赤坂 今だったら全くないですね。もちろん、ウィーンフィルなどは、オーストリアの伝統を守るために、オーストリア人の男性、もしくはオーストリアの音楽教育を受けた者でなくてはいけないとかありますけど。他は一次予選はカーテンが多いですし、実力主義ですね。日本人だからといって不利になることはないです。むしろ、同じ点数なら、日本人は的確に仕事をする、というプラスの評価をもらえることも意外と多いのではないでしょうか。
 -オーケストラでやって行くときに重要なことは何でしょうか。
-オーケストラでやって行くときに重要なことは何でしょうか。
赤坂 首席奏者になって勉強したことですが、あえて我が道を行くべきですね。日本人って、どうしても周りを気にしがちですが、それをしているとダメになってしまうので。良い意味でマイペースに、自分がやることをやる、自分の音楽を確立することが重要だと思います。
-首席となられた今と、第二バイオリンをやっていたときとの違いはありますか。
赤坂 まずは、コンサートマスターに代わって、皆を引っ張っていかなきゃいけない責任ですね。また、団員に代わって、指揮者に意見しなきゃいけない場面もありますので、語学がより重要になってきましたね。あと細かいことで言うと、大きめに動いて引っ張っていかなきゃいけないとか、準備なくして仕事に行けなくなったことなど、いろいろありますね。
-ご自身の音楽に対する意識は変わりましたか?
赤坂 以前より、もっと世界を広げたいと思うようになりました。日本人としてオーストリアで働いていますから、日本とオーストリアをつなぐような演奏をしたいと思うようになりました。以前は全く思いませんでしたけど。
-話は戻りますが、第二バイオリンをしていたときにウィーン国立音大に入られたんですね。
赤坂 はい。普通科ではなく、仕事をしながら通えるコースですけど。それまでドイツで勉強してましたから、ウィーンの空気も勉強したいと思いまして、1年間通いました。
-どのくらいの割合で通っていたんですか?
赤坂 レッスンだけなんですけど、仕事の関係で1ヶ月全く行けないときもありました。そういう時は、翌月に1週間ごとに通ったり。そのへんは臨機応変でした。先生も理解がありましたし。
-ウィーンとドイツの違いはありましたか?
赤坂 音楽の違いとはあまりないですけど、国民性がだいぶ違いますね。ドイツ人の方が日本人に近い感覚で、生真面目というかピリッとしているという感じです。オーストリア人の方が和やかで穏やかな感じですね。
-どっちが合っていますか?
赤坂 私はオーストリア人のほうが合っていますね。

-リンツの街の様子はどんな感じなんですか?
赤坂 2009年に芸術文化都市に選ばれて、芸術面で活気がありますね。街自体はこじんまりとしています。空気の流れがゆっくりで、とてもいい環境ですよ。
-リンツには音大がありますよね。レベルは高いんですか?
赤坂 以前に、ここに通われている方のレッスンさせていただいたことがありましたけど、ウィーンと比べて、絶対的に生徒数が少ないですから、そういう意味で、切磋琢磨している感じはなかったですかね。
-赤坂さんは、このまま首席バイオリニストとして、活動を続けていかれるのですか?
赤坂 そうですね。おこがましいようですけども、コンサートマスターの席に空きが出たら、モチベーションがあるうちに挑戦してみたいと思います。
-オーケストラの団員としてのやりがいは何ですか?
赤坂 一人で演奏するのとは違って、「みんなでひとつのものを作り上げていく」という感覚が喜びですね。同じ目標に向かっていく感覚というか。
-難しい質問かもしれませんが、赤坂さんにとって音楽とはどんな存在ですか?
赤坂 私にとっては、心に感ずるままに表現できる、魂の叫びみたいなものです。そして、もう一方では、お薬のようなものですね。精神的につらい時も、音楽があったから立ち直ってこれたし、喜びなどを表現できる道具でもあるので。生きてきた半分が音楽ですから、私から音楽を取ったら何もなくなりますね。
 -赤坂さんのように、将来、海外で活動したいと思っている方に、プロとして活躍する条件や秘訣を教えてください。
-赤坂さんのように、将来、海外で活動したいと思っている方に、プロとして活躍する条件や秘訣を教えてください。
赤坂 秘訣は、あったら教えてほしいくらいなんですけど・・・(笑)。あきらめない気持ちでしょうかね。絶対に夢は叶うんだ!って、強く思い続けている人が成功すると思います。あと、オーディションで審査させていただく立場からすると、音楽って繊細な感性が必要ですが、もう一方で、絶対的に強い神経を持っている人でないといけないんです。家で練習して上手にできても、オーディションでも演奏会でも弾けなかったら、プロとしては残念ながら難しいですね。なので、図太い神経が必要なんです。そうでないと、外国でやっていく上で病んでしまいますからね(笑)
-持って生まれたものでしょうか。
赤坂 それも、もちろんありますし、周りを気にせず、意識して我が道を行くということで養われることもあると思います。
-海外で勉強したいと考えている人にアドバイスをお願いします。
赤坂 目標は漠然としたものではなく、明確な目標を持つことが必要です。近い目標と遠い目標を両方持ちましょう。あと、海外に行くのは語学が大事ですよね。英語が出来ることも有利ですが、音楽の世界の共通語としてはドイツ語。英語以外にも勉強していると楽しくなると思いますよ。
 -赤坂さんは2ヶ月の勉強だけで渡航されたそうですが、渡航後、どうやって語学を身につけたんですか?
-赤坂さんは2ヶ月の勉強だけで渡航されたそうですが、渡航後、どうやって語学を身につけたんですか?
赤坂 てっとり早くお友だちを作ることですね。語学学校にも通いましたけど、それより、おしゃべりしていく中で覚えることが多いですからね。
-そういう交友関係の中から、すぐに上達しましたか?
赤坂 普通に生活する上では徐々に楽になりましたけど、結局は、仕事を始めてからだいぶ上達したのではないでしょうか。まだまだですけどね・・・(笑)
-首席で意見を述べるときに語学力は絶対必要ですもんね。
赤坂 きちんとした言語を話さないと、馬鹿にされますからね。あとは、外国人としてやって行く中では、ある程度、力を抜いてやっていくことが大事というか、切り替えが大事ですよね。私も、最初それがすごく苦手で、失敗すると引きずりましたし。ただそれをやっていると、病んでしまうんですよ。あとは、たまに日本に帰ってきて、家族と過ごすことなども、エネルギーの補給として必要でしたね。
-赤坂さんの今後の目標を教えてください。
赤坂 日本人としてオーストリアでやっていく上で、ウィーンワルツですとか、日本の方にもっと聴いてもらえたらいいなと思っているんです。企画・構成・演奏に携わって、日本とオーストリアの両方でやっていけたらいいなと思っています。
-来日コンサートの予定などはありますか?
赤坂 オーケストラで日本のツアーは、2~3年後にありますけど、個人としてはまだ全然実現できてないですね。
-今後のご活躍をお祈りしています。今日は、音楽を志す学生さんにとって、素晴らしいお話をたくさん聴かせていただきました。本当にありがとうございました!
外川千帆さん/伴奏ピアニスト/ドイツ・ミュンヘン
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回ドイツで伴奏ピアニストとしてご活躍中の外川千帆(トガワチホ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽留学」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います。
(インタビュー:2010年12月)
ー外川千帆さんプロフィールー
 東京芸大附属高、芸大、芸大大学院修士課程ピアノ専攻卒業。ロータリー財団国際親善奨学生、文化庁在外派遣研修員として、ミュンヘン音楽大学、チューリヒ音楽大学歌曲伴奏科卒業、演奏家資格を得る。ミュンヘン音楽大学の伴奏員を在学中から2007年まで務める。第73回日本音楽コンクールにて、コンクール委員会特別賞(共演賞)を受賞。第6回国際フランツ・シューベルトと現代音楽コンクールのリートデュオ部門と、フーゴー・ヴォルフ・アカデミー国際リートデュオコンクールにて第3位を受賞。第4回ヒルデ・ツァデック国際声楽コンクールにおいて公式伴奏者。ルードヴィヒスブルク音楽祭等、ヨーロッパや日本で演奏活動を行っている。これまでに歌曲伴奏をH・ドイチュ、白井光子&H・ヘルの各氏に師事。
東京芸大附属高、芸大、芸大大学院修士課程ピアノ専攻卒業。ロータリー財団国際親善奨学生、文化庁在外派遣研修員として、ミュンヘン音楽大学、チューリヒ音楽大学歌曲伴奏科卒業、演奏家資格を得る。ミュンヘン音楽大学の伴奏員を在学中から2007年まで務める。第73回日本音楽コンクールにて、コンクール委員会特別賞(共演賞)を受賞。第6回国際フランツ・シューベルトと現代音楽コンクールのリートデュオ部門と、フーゴー・ヴォルフ・アカデミー国際リートデュオコンクールにて第3位を受賞。第4回ヒルデ・ツァデック国際声楽コンクールにおいて公式伴奏者。ルードヴィヒスブルク音楽祭等、ヨーロッパや日本で演奏活動を行っている。これまでに歌曲伴奏をH・ドイチュ、白井光子&H・ヘルの各氏に師事。
-まずは、簡単なご経歴を教えてください。
外川 東京芸大の附属高校から芸大ピアノ科に進学し、大学院まで進みました。大学院在学中に、ミュンヘン音大の歌曲伴奏科に留学しまして、ミュンヘン音大と東京芸大の両方を卒業しました。ミュンヘン音大に在学中から、伴奏助手として働き始めたのと並行して、チューリッヒ音大に入学し、月に1週間ほどレッスンを受けていました。チューリッヒ音大を卒業した後、子供の出産を経て、2007年まではミュンヘン音大で伴奏助手をやっていましたが、今はフリーで働いています。
-音楽を始められたのはいつですか?
外川 4歳です。私は、岩手県出身なのですが、母がピアノ教室をやっていましたので、まずはそこで始めました。
-ご自分からやりたいと言って始めたのですか?
外川 4歳だったのでよくは覚えていませんが、そうかもしれないですね。生まれたときから、身近にピアノはありましたし。近所の子どもたちがレッスンを受けているのを見ているうちに、弾き始めていたんじゃないでしょうか。母が熱心に勧めたわけではなかったと思います。
 -小さいときから練習量は多かったんですか?
-小さいときから練習量は多かったんですか?
外川 いいえ、いなか育ちなので、本当にのんびりやっていました。 東京とか大きな都市だと、皆さん子どもの頃からすごく一生懸命やるじゃないですか。私は競争する相手もいませんでしたから、本当にのんびりと・・・。ほかの方のインタビューを読むと、皆さん素晴らしいですよね。
-そうだったんですね、それは意外です。中学校までは普通の学校だったんですね。
外川 高校も1年間は普通高校に行っていました、芸大付属高校には入り直した形です。
-芸大附属高校に入るまで、お母さんのレッスンを受けていたんですか?
外川 最初の頃は母に習っていたんですけど、親子だと難しいものがあるので、すぐに近所の先生に習いました。母の先生に当たる人でした。あと、東京の先生が出張レッスンに来てくださったり、こちらから出向いたりしていました。
-東京の先生にも習っていたんですね。
外川 小学生の時、ヤマハの音楽教室が、東京からの先生を呼んでレッスンをするというのを始めたんです。それがきっかけですね。そして、芸大附属高校の話も出て、受験してみようと。受かったら受かったで、皆さんすごく素晴らしくて、場違いなところに来ちゃった!と焦りました。(笑)
-本格的にピアノをやっていこうと思ったのは、芸大附属高校に入学してからですか?
外川 受験するときです。それまでは、どういう風に練習したらいいかとか、みんながどういう風に受験対策しているかとか全然知りませんでしたから。「朝9時に試験で弾かなければならない場合、5時から練習開始するべき」みたいなこととか、ソルフェージュのスキルとか、初めて本格的に教えていただいて。入学してからは、周りにすごく刺激されました。
 -高校に入ってからの練習量はどのくらいでしたか?
-高校に入ってからの練習量はどのくらいでしたか?
外川 クラブ活動がないので、学校は午後1時とかの早い時間に終わるんです。なので、寮に帰って3時くらいから練習を始めて6時くらいまでやって、夕食を食べて7時くらいからまた3時間練習して、という感じですね。中には、お風呂に入ってから、1時、2時までやっている人たちもいましたよ。
-始めはキツかったですか?
外川 今、思い出せないくらいキツかったですね。お友だちとの楽しい思い出ってないんですよ。他の人たちも、自分の音楽に気持ちが向いている人たちばっかりだったので。学校終わったら、まっすぐ帰って練習、朝は授業が始まる一時間前から練習って感じでしたね。特に、私は全然余裕がありませんでしたから。
-高校生の時はコンクールなどには出られたんですか?
外川 いいえ。あの時代は、芸高に通っている生徒がコンクールに出るというのはタブーのような風潮があったんですよね。出るなら、絶対に賞を取らなくちゃいけないみたいな。
-それでも出られている方はいらっしゃったんですか?
外川 一人だけだったとおもいますよ。受けることも秘密にしていたと思います。
-大学に入られてもそういう感じだったんですか?
外川 いえ、大学に入ってからはみんな出ていましたね。私も、日演連の新人演奏会のオーディション等を受けたりしました。でも、私の場合は、大学に入ってからは伴奏のほうを沢山やりたくて。声楽の方の伴奏を主にやっていました。伴奏のほうではずいぶん色々なオーディションやコンクールに出たりしました。
-実際にプロを目指そうと思い始めたのはいつくらいですか?
外川 大学に入ってからですね。高校には声楽科がなかったので、声楽を勉強している人に出会ったのは、大学に入ってからだったんですよ。声楽科に友達がたくさん出来たこともあるのですが、伴奏をやっていくうちに、どんどん楽しくなってきまして、伴奏のお仕事が出来たらいいなと思うようになりました。
 -伴奏の魅力は何でしょうか?
-伴奏の魅力は何でしょうか?
外川 もともと、ソロとして、舞台で弾きたいと思わなかったというか・・・。それよりも、音楽と言葉が密接に結びついていている声楽の伴奏をすることが、おもしろいと思い始めたのです。どっちかというと演劇作品に近いというか、ピアノとは違って言葉を使いますし、言葉と音楽で表現することに魅力を感じますね。演奏会の形態もそうですけど、一曲一曲が短くて、いろいろな情景が変わっていくこともおもしろいと思います。
-なるほど。さて、外川さんがドイツに留学されたのはいつのことですか?
外川 大学院に入ってからです。大学院受験は自分では試金石だと思って望みました。これでだめだったら自分はここまでだ、と言うことにしようと思って。でもおかげさまで合格できたので、大学院に入ってからは、もう伴奏をやっていこうと、授業などもその方向のものばかりとっていました。留学を考えたのはそれからです。私のソロピアノの先生も、伴奏をやることについては、理解してくださっていましたので、リートの先生を紹介してくださるなど、手助けをしてくださいました。
-ミュンヘン音大を選んだきっかけは?
外川 語学留学で一ヶ月ミュンヘンに行ったことがあったんですけれど、街がすごく好きになったというのが一つの理由です。 でも、直接のきっかけになったのは、東京で鮫島有美子さんとそのご主人であるヘルムート・ドイチュ先生の公開レッスンを受けさせていただいたことですね。 そのドイチュ先生がミュンヘン音大の先生だったのです。そこで先生にいろいろご相談させていただいて、具体的に留学することに話が進んでいきました。あと、たまたまミュンヘン音大で、歌曲伴奏科ができた年だったので、タイミングも良かったこともあります。
-音楽留学の前に、ミュンヘンで語学留学を経験されていたんですね。
外川 はい。フルタイムコースがあるのは大きな都市しかなかったので、ミュンヘンを選びました。ミュンヘンは、比較的安全な街ですし、地方の都市という感じで小さくまとまっていて住みやすかったので。その時は、語学学校で手配してもらったアパートで、同じ学校の人とシェアして一ヶ月生活しました。
 -では、ミュンヘン音大に留学されたときには、語学では困らなかったんですね。
-では、ミュンヘン音大に留学されたときには、語学では困らなかったんですね。
外川 一ヶ月みっちりドイツ語を勉強したのは大きかったですね。 いただいた奨学金も、何に使ったかと言えば、ほとんど語学に費やしました。時間があるときに個人で習ったり、できるだけコースに通ったりしました。ピアノの人って、一人でこもって長い時間練習するじゃないですか。なので、意識して勉強しないといけないと思ったのです。よく、「現地の友達と話していると、すぐ覚えるよ」って言われますけど、それだけでは足りないですよ。友達と話していてもなかなか直してくれないですから(笑)。高校生とか、若いうちの留学ならそれもアリかもしれませんが、私は26歳になってからだったので。
-ミュンヘン音大では、語学の試験はあったんですか?
外川 私のときはなかったです。今はあると思いますけど。
-留学はどのくらいの期間だったんですか?
外川 間が開いていますけど、計4年です。Aufbaustudium(大学院課程)は2年間ですが、途中1年間は芸大の大学院のために帰国していましたので。また、ミュンヘン音大卒業後に、スイスのチューリッヒにも2年通いました。本当はミュンヘンの後、カールスルーエ音大に行きたかったのですが、ドイツの教育システムでは、一番上の段階を卒業していると、他大学の同科には入れないのです。なので、聴講生という形で入ったのですが、ちょうど良く先生がチューリッヒで教えることになったのです。チューリッヒはスイスですから、また学校で勉強できるということで、そちらにも通いました。
-クラシックを勉強するに当たって、ドイツの良い点と悪い点を教えてください。
外川 ドイツの音楽ひとつにしぼって勉強したいという方には、すごくいい環境だと思います。ただ、大学で勉強するプログラムでは、グローバルなことはあまり学べないように思います。ドイツの大学では、ひとつのことをじっくり深く勉強する傾向なので、時間がかかるように思います。歌に関して言えば、ドイツの先生が専門的に教えられるのは、やはりドイツのものになりますので、フランス音楽もイタリア音楽も突き詰めてというのは難しいかもしれません。伴奏に関しても、たとえばアメリカだったら、リートのみならずオペラとか、いろいろな国の音楽を広く浅くやる傾向がありますが、ドイツではそこまでは手広くないように思います。日本でやってらっしゃる方のほうが、フランスやイタリアの音楽を知っているかもしれないです。
-外川さん個人にとってはいかがですか?
外川 わたしはドイツリートを勉強したいと思って来たので、良かったと思っています。
-どういう経緯で、伴奏の仕事に就くことになったんですか?
外川 大学内で募集があったのです。オーディションに応募して、採用していただきました。
-実際伴奏者として仕事をしていく上で、一番大事なことは何でしょうか?
外川 まずは、歌い手とのコミュニケーションですね。人間的にオープンであると言うことが大事だと思います。そうじゃないと、二人で一緒に音楽を作ってはいけませんからね。言葉でコミュニケーションするときにも、オープンでいるって言うことは大事ですね。でも変に主張しすぎると嫌われますけど(笑)。
 -相手の気持ちを受け入れてコミュニケーションを取っていくということですね。
-相手の気持ちを受け入れてコミュニケーションを取っていくということですね。
外川 そうですね。いろんなタイプの演奏者の人がいますから、一概にこうするべきっていうのはないと思いますが。あと、やはり一番は演奏です。歌の人を支えられるような演奏ができるか、いろんなジャンルや音楽様式を理解していて、それぞれの音楽を表現できるか・・・、つまり技術ですよね。
-プロの演奏家を目指して、留学を希望している人はたくさんいますが、ずばり、プロになれる人となれない人との違いは何だと思いますか?
外川 難しいですね。いろんな要素がかみ合っていますから・・・。もちろん第一前提は技術ですが、ほかにも大事なことは意識じゃないでしょうか。プロとしてやっていくという、強い気持ちを持っていることが大事だと思います。せっかく技術を持っていても、そこに甘んじないで、限界を突き抜けてまでもやっていこうという意識がないと。プロの音楽家は、気持ちも生活も、すべてが音楽に向いている人だと思います。たとえ子供を持って家庭と仕事の2足のわらじを履いている状況でも、いかなる状況でも、です。
-外川さんがプロとして意識していることは?
外川 今、プロとアマチュアには、大きな差がないように感じています。特に伴奏は、大学に出ていなくても、技術があればできますからね。経験がものをいう仕事でもありますから。私自身は、自分の演奏に対しては、表面的ではない、心をこめた自分の納得できる演奏ができるようにと思っています。なおかつ歌手の方を支え、引き立て、より良いものをと思っているので、いつも、120パーセント以上の用意ができている状態でなければと思っています。
-ドイツで、プロの音楽家として活躍していく秘訣は何でしょう?
外川 アジア人だからといって、あきらめずに、躊躇せずに前に進んでいくことですよね。自分には出来ないのではないかって思うときでも、もう一歩勇気を出して進んでいけるかどうかです。あとは、人間としてオープンでいることですね。日本人は控えめですけれど、そういうのは美徳とされないし、むしろ印象が悪くなってしまうので。最初は難しいかもしれませんが、失敗しても次があるという強い気持ちを持っているくらいがちょうど良いように思います。
-外川さんは、くじけそうになったりしたことはありましたか?
外川 いつもですよ(笑)。
-そういうときに立ち直る方法は?
外川 主人が韓国人の歌い手なのですけど、彼のポジティブさにはいつも助けられています。ドイツに限らず、今では世界で日本人より韓国人の方が成功しているのではないかと思うのですが、アイデンティティが強い国民性なのですよね。自分に自信を持っているというか、ちゃんと自己主張できる。彼は、オペラ座で働いているのですが、他のドイツ人と対等にやっていかなきゃいけないので、かなり自己は強く持っていますね。留学したことのある方なら、中国や韓国など、同じアジアから来ている人たちに、圧倒された経験を持つ方は多いと思います。
-ドイツで伴奏者として仕事をする上で、日本人として優位な点はありますか?
外川 日本人は細やかな仕事をするので、重宝がられることもまれにありますが、日本人で得をすることは、ほとんどないです。やはり、ドイツではドイツ人がすべて優先されるし、ドイツ人はドイツ人と演奏したいと思うでしょうから。ドイツ人がダメならせめてEU圏の人という風に。なぜ、アジア人と演奏するのか、という理由がないですからね。国民性も全然違いますから、いつまでも日本的だと仕事は取れないです。言わなくても察してもらうことを期待してはダメですね。何考えているのかわからないとか、シャイだっていうのはマイナスイメージですから。そういう意味では、大きな改革が必要だと思います。まあ日本人と言ってもいろいろな方がいますから、そういう垣根をとびこえて、海外で生き生きと活動していらっしゃる方も、もちろん沢山いらっしゃいます。
 -そんな中で、たくさんお仕事されているんですね。素晴らしいです。
-そんな中で、たくさんお仕事されているんですね。素晴らしいです。
外川 いえいえ。たまたま、有難いことに外川さんと仕事がしたいとか、またお願いしたいと言ってくださる方々がいるので、やらせていただいている感じです。そういう方々と出会うことができたのは幸運だったと思っています。
-なるほど。ここで難しい質問になるかもしれませんが、クラシック音楽は外川さんにとって何ですか?
外川 難しいですね。ほかの皆さんは、すごく上手に答えてらっしゃいましたけど(笑)。私のイメージでは、クラシック音楽は、ポップスやジャズなどのほかの音楽に比べて、自然の波長に近い音楽だと思っています。森の木々が揺れたり、花が開いていい香りが漂ったり、湖の水面に太陽の光が差しこんできらきらしている様子など・・・、そういうのと一番近いというか。またクラシックってすごく人間的だとも思うのです。人を愛する気持ちとか苦悩とかユーモアだとか、そのようなものがそこかしこにちりばめられている。音楽を通してそういう自然の情景や人間の生きざまとかを表現できたらいいなと、いつも憧れを持ってやっています。自然って限りなく美しいじゃないですか、そして人の人生というものも。クラシック音楽も、いろいろな表現があると思いますが、最終的には限りなく美しいものでなくてはと思っています。
-自然と同じように、クラシック音楽も存在していると言うことですか。
外川 近づくのは難しいですけどね。クラシックは型もありますし。でも、伴奏者の仕事って、型にはまるだけではなく、自由で柔軟でいるって言うこともすごく大事なことですが。
-外川さんの、音楽家としての今後の夢を教えてください。
外川 去年から日本で、「歌曲の響」と言うタイトルで、コンサートシリーズを始めました。毎回違う歌手をおよびして、さまざまな歌曲を皆さんに紹介してゆけたらと思っています。今年2月には、音楽だけではなく映像とコラボレーションしたコンサートもやらせていただきます。日本では外国語の歌曲を歌われる際に、聴き手にダイレクトに伝わりにくいという問題があります。今回は舞台上に映像を流して、歌曲の世界を耳だけではなく、眼からも楽しんでいただこうという企画です。またヨーロッパでは、さらに引き続きリーダーアーベントをすることができたらと思っています。
 -主催されているコンサートは、東京で開催ですか?
-主催されているコンサートは、東京で開催ですか?
外川 今回は初めて東京でさせていただきます。以前から、そういうコンサートをやりたいと思っていたのですが、今回、共催してくださることになった会社が、演奏者を募っていて、それに応募して採用していただいたのです。それ以外は私の故郷である岩手でもコンサートをさせていただいてます。
-最後になるんですが、海外で勉強したいなと考えている人にアドバイスをお願いします。
外川 自分なりの目的を持って留学をすることが大事だと思います。みんながプロを目指さなきゃいけないというのではなく、「ヨーロッパを見に行きたい」っていう理由でもいいと思うのです。目的は持っていなければ、時間とお金の無駄になります。過ごしていく上で、目標が変わっていってもいいと思いますが、とにかく目的や目標がないと、外国に行く意味がないと思います。自分を見失わないように、という点から言っても大事なことだと思います。
-何か一つ強い信念を持ってないと、ということですね。
外川 あとは言葉!誰でも最初はできないので、勇気を持って望むことです。語学に関しては、できるだけ勉強しておいた方がいいです。音楽留学の前に、一度語学留学だけをしてもいいと思います。特に歌の場合は言葉がなんと言っても重要で、いくら声が素晴らしくても言葉ができないと評価されません。大学の先生もそれに関してはよくおっしゃいますね。大学に入りたい人は、ドイツ語が無理なら、最初のうちは英語でもかまわないので、何かしら先生とコミュニケートできる手段を持っておいたほうがよいです。
-今日は長い時間、貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。
 -----外川千帆さんのコンサート情報-----
-----外川千帆さんのコンサート情報-----
ソノリウム「映像と音楽」共催シリーズ2011参加企画
ラファエル・ファブル&外川千帆 リートデュオ・リサイタル[歌曲の響]vol.3
「ハイドンとシューマンの歌曲」~写真家・山本英人氏とともに~
本場ドイツをはじめ、ヨーロッパ各地で注目を集める、ラファエル・ファブル(テノール)&外川千帆(ピアノ)の二人による、繊細で洗練されたリートデュオを、ドイツの風景映像を背景にご堪能いただきます。耳と目で、ドイツリートの心をお楽しみください!
<プログラム>
ハイドン作曲「さすらい人」「彼女は決して愛を語らず」
シューマン作曲「リーダークライス op.24」「6つのレーナウの詩による歌曲とレクイエム op.90」
<出演>
ラファエル・ファブル(テノール)
外川千帆(ピアノ)
開催:2011年2月27日(日) マチネ 14時
ソワレ 18時30分
入場料金 4,000円
会場/ソノリウム Tel: 03-6768-3000
168-0063 東京都杉並区和泉3-53-16 FAX 03-6768-3083
http://www.sonorium.jp/index.htm
【チケット取り扱い・コンサート詳細】
カノン工房
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Tel:03-5917-4355(平日10-17時) fax:03-5917-4356
http://www.atelier-canon.jp/ (サイトからもお申し込みいただけます)
奥山彩さん/ピアニスト/フランス・パリ
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロの皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回はフランス・パリでコンサートピアニストおよび音楽院講師をされているピアニスト奥山彩(オクヤマアヤ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「パリで学ぶピアノ・パリでの音楽活動」をテーマにお話しを伺ってみたいと思います(インタビュー:2005年12月)。
ー奥山 彩さんプロフィールー

岡山生まれ。幼少よりピアノを始める。フランス、エコール・ノルマル音楽院を経て、パリ国立高等音楽院ピアノ科、室内楽科卒業。パリ高等音楽院古楽器科卒業(フォルテピアノ)。ピアノをブリジット・エンゲラー、ミシェル・ベロフ、室内楽をアラン・ムニエ、ピエール・ロラン・エマールに師事。フォルテピアノをパトリック・コーエン、歌曲伴奏をケネット・ヴァイスに師事。フランス、サン・ノム・ラ・ブロテッシュ・ピアノコンクール1位。日本教育連盟主催ピアノオーディション奨励賞。フランス、スペイン、ドイツ、スイス、オーストリア、ベルギーにて、ソロ、室内楽のコンサート、リサイタルを行う。鎌倉FMにて横浜みなとみらいホールのリサイタルを放送。オリヴィエ・マレシャルと2台ピアノのデュオを組み、フランス各地でリサイタル。ピアニスト、イヨルク・デムス氏に招かれ、トゥーロン城で演奏。ベルギー、オーステンドにおけるPianoFest'招待。現在、パリで演奏活動のほか、ヴェジネ市立音楽院、パリ6区ラモー音楽院にて非常勤講師、試験審査員など、後進の指導を行っている。

— 簡単な経歴を教えていただいてよろしいですか?
奥山 近所にたまたまピアノを教えていた先生がいらしたので、三歳半くらいから遊びがてらピアノを始めました。
— ピアノはご自分で始めようと思われたのですか?
奥山 ほんとに小さかったので、あまり覚えていないのです。両親は音楽家ではないのですけど母が小さい頃にピアノをやっていたので家にアップライトピアノがありました。ピアノの先生のお子さんも同じ年くらいだったので一緒に遊んだりしました。それで興味を持ってちょっとずつ教えてもらいに行くようになりました。幼稚園くらいからみんなもうピアノをやっていたのでそれで一緒に始めました。小学校三年生くらいの時にもっと本格的な先生に習うというふうになって、鎌倉に住んでいる宮原峠子先生という先生のところに習いに行くようになりました。先生は桐朋を出て、ドイツ留学をされた方でした。今は愛知芸大の先生をされています。その先生の勧めで実家が鎌倉なので、鎌倉の桐朋大学付属子供のための音楽教室へ通うになりました。
— 桐朋の子供のためのピアノ教室はいつから行っていたのですか?
奥山 小学校5年の時から行くようになってそれで音楽をやっている友達が出来るようになりました。それで小、中と普通の公立の学校だったんですけど高校受験の時に音楽高校に行くか普通高校に行くか選択がありました。それで私はまだその頃、それほど音楽を一生やっていこうとか決意みたいなものはまだなかったのですが、たまたま才能があるから音楽をやりたいのだったら、音楽高校を受けたらいいのではないかというふうに勧められて、受けてみたのですけど駄目だったんです。それで結局、普通の高校に行きました。でも音楽は好きなので将来的にピアノはどうしようかなと迷っていたんです。ずっと宮原峠子先生に習っていて、先生に小学生のころからあなたはどちらにしろちょっと変わっているから早いうちに日本のシステムに入るのじゃなくて、例えば音高に行ったとしても途中で辞めるくらいの感じで外国に出たほうがいいんじゃない、というふうに言われていました。
— 変わっているというのはどういう部分でしょうか?

奥山 まあ感性が(笑)。型にはめようとしてもはまらないというか。
— 素晴らしいじゃないですか音楽家としては。
奥山 そのへんの言葉は良く分からないのです(笑)。小学校六年生の時から先生になんとなく言われていたことなので。先生の生徒さんでフランスに行かれた方がいらしたこともあってだと思うのですけど、そういうふうになんとなく教え込まれていたので。
— 小さい頃から将来外国に行くんだ、と思っていたのですか?
奥山 なんとなくですね。フランスに行ったら素敵かな、くらいです(笑)。小学生なので(笑)。
— そこまで意志ががっちり固まっているわけないですよね。
奥山 固まってないですよ、本当に。私もふわふわしていたので、高校生の時は。普通の高校生活は楽しかったし(笑)。それで高校1年と2年の春休みにフランスのコンクールを受けに行ったらどうですか、と先生に勧められたんです。日本でぼんやり過ごしているより、一度外を見に行ったらいいのではないかということで。
— フランスですか?
奥山 宮原先生の生徒さんだった方で、フランスに留学されたあとエコール・ノルマルの先生になった方が、私が16歳の時、私の演奏を名古屋で聞いてくださったんです。それで、フランスの小さいコンクールがあるから受けてみたらと言われました。それがいいきっかけになると良いのではないか、ということでセッティングして下さいました。3月か4月だったかな。春に受けることになって、その時1ヶ月パリに来てレッスンを受けたりコンクールを受けて賞を頂いたりして、ああフランスはいいな、と思いました。コンクールで演奏を聴いてくださる審査員の雰囲気もとても暖かく、また、フランス留学されている方の話を聞いて、こういう方向に行ってみようかなと思うようになったんです。
— いつごろクラッシックの専門になろうと思ったのですか?
奥山 高校生位ですね。高校生の時にすごくいろいろ考えたんです。何でピアノをやるのかとか、なんで音楽を続けているのかとか、世の中の役に立つのかなとか。それで、フランスに初めて行った後の次の夏に、ザルツブルグ音楽祭のザルツブルグアカデミーに行きました。ヨーロッパで勉強している人のレッスンや演奏会をたくさん見て、今やっているままだと自分は駄目だなというふうに感じたんです。たまたま小さい頃からお世話になっている調律師の方が田崎悦子先生を車に乗せていた時に私の弾いているカセットテープを先生に聞かせてくださって、それがきっかけで田崎悦子先生に教えていただくようになりまして、先生はすごく素敵な方で憧れるというか、そういうふうになりたいなと思って、何か引っ張られるような形で、クラッシックをやろうと、本気でやろうと思ったんです。
— プロになろうと思ったのはどうしてですか?
奥山 田崎悦子先生にレッスンしていただけますかとお電話を差し上げました。田崎先生は18歳の時から一人でアメリカにいらした方で、親が電話してくるより自分でするほうが良いと言われました。それで、電話で先生に「あなたはピアニストになりたいの?」と聞かれて、「はい、なりたいです。」と言いました。「なりたくないです。」なんて、言えませんよね(笑)。
— 自分に言い聞かせたわけですね。
奥山 それが初めてピアニストになりますというふうに言った事でした。だから田崎先生に習うということはピアニストになると思って習うことなんだなというふうに理解したんです。途中で辞めさせられそうになったりしたんですけど(笑)。
— 何故ですか?不真面目だったりしたんですか(笑)?
奥山 その時は曲をいろいろやっていて、自分の曲をやっていたのと人のバックの曲を頼まれてやっていました。先生の生徒のレッスンの時にコンチェルトの伴奏を頼まれたんです。でも自分の曲は練習しているけど人の曲は全然練習していなくてそれで先生が怒っちゃって。
— それはまずいですね。今ではあり得ない事でしょうね(笑)。
奥山 本当ですね(笑)。プロだったら全部しないとだめです。引き受けたことは最後までちゃんとやるという。仕事だったら許されないですよね。初見でもなんでも本番なら、寝なくでもやるじゃないですか。だからそういう意味で良くなかったですね(笑)。
— 日本で高校を卒業してすぐにフランスに行こうと思ったのですか?
奥山 普通高校に通いながら、田崎先生に習っていて、留学というのはしたいと思っていたんです。でも、音大や普通大学の選択肢もありました。大学受験して、大学に通学するのも日本だと住宅事情から通学時間などがずいぶんかかりますから、その分、ピアノの練習や語学など留学の準備をして、私にとっては、そのままフランスに行くチャンスに賭けたほうがいいんじゃないか、ということになったのです。
— 言葉はどうしていたのですか?
奥山 高校生の時からフランス語を勉強していました。高校生のときは週1回学校に通って、高校卒業してから週2、3回くらい行っていました。卒業しても1年半くらい日本にいたのでその間に勉強していました。
— ドイツ、オーストリア、アメリカなど他の国もあるのに何故フランスなのでしょうか?

奥山 きっかけが結構ありましたからね。それに感性としてはドビッシーが好きです。フランスものは全体的にやっぱりすごく好きです。かっちりしたものよりも流動性のあるというか、ハーモニーというか色がある感じの曲が好きです。それに自分自身ではドイツはちょっときっちりとしたイメージがあったので、フランスのほうがあっているんじゃないかしらというふうに言われて。あとは実質的な問題で、アメリカの学校はTOEFLとかあるじゃないですか。ドイツの学校は大学卒業してないと行けないんですよね。第2期から入るには。1期から入るとドイツ語が出来ないといけないし、心理学とかそういう外国人には難解な授業もあるし。そして、フランスは下の年齢制限がないんです。上の制限は22歳未満と決まっているんですけど。私の時は入学試験は実技だけだったんですけど。今はソルフェージュの予備試験とかあるようですね。私は本当に実技一発勝負だけだったので、そういう意味でシンプルでした(笑)。
— 音楽が出来れば入れたということですか?
奥山 そうですね。あと年齢も関係ないですね。フランスの学校は、どちらかというともともと完成している人よりも今後の才能を見るという試験なようです。ものすごくテクニックとか完璧に出来ている人よりは、いろいろな可能性がある人の方が入りやすいらしいですよ。そういうふうに言われたので、だったら可能性があるかなと思ったもので。
— 最初は、エコール・ノルマルに行かれていますよね。そのあとパリ国立高等音楽院に行かれている。
奥山 最初、エコール・ノルマルに登録して。それでその間にパリ国立高等音楽院の試験を受けたりしていました。エコール・ノルマルは実質8ヶ月くらいしか行っていないんです。エコール・ノルマルという学校は私立の学校で誰でも入れるんです。普通に登録して、授業料を払えば(笑)。レベルはいろいろで、入る時に先生がレベルを決めます。1から6まであって、6段階というのはなかなか難しいので日本で音大を卒業した人だと5か6で入るんです。そういう感じで一年ずつ試験を受けて上がっていって、コンサーティスト・ディプロマ(演奏家資格)まであります。入ることよりは試験を受けてディプロマをもらうことに意味があるという学校です。先生は有名な先生から、若い先生までいろいろです。ピアノ科だと何人くらいいるのかな。たくさんいらっしゃるんですよ(笑)(編集注:注:2005年12月現在 ピアノ科講師46人)。
— 学生さんは何人位いるのですか?
奥山 ちょっと把握できないくらいです。
— 日本人の方はどの位いるのでしょうか?
奥山 エコールノルマルは、どちらかというと日本人、韓国人の生徒が半分以上だと思います。実質外国人がとても多い学校だと思います。
— 現地の方というよりも外国人が多い学校ですね。
奥山 外国人はたくさんいます。中にはエコールノルマルに登録しているけれどもレッスンはあまり受けないでディプロマ試験のみを受ける人もいます。
— そういうのもいいのですか?
奥山 いいみたいですね。
— 結構自由なんですね(笑)。
奥山 とても自由です。先生さえ承諾してくだされば、何でも自由な感じです。だから求めるものさえあれば、いろいろできると思います。
— 人によるでしょうが、奥山さんは、エコールノルマルよりコンセルヴァトワールの方が合っていると思ったわけですね。
奥山 コンセルヴァトワールというのはフランス各地にいろいろあります。国立高等音楽院と言われているのはパリとリヨンにあります。そこはエコールノルマルと違って入学試験があってピアノ科だと200人くらい受けて、入るのは15人から20人位です。年によるんですけど、卒業生が出た数だけ入れるということになります。コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)は、ピアノ科全体の生徒が80人位いると思います。授業料は完全に無料です。
— それは国立だからですか?
奥山 国立なので授業料は完全に無料です。学校に登録するための登録料のみ必要で、日本円で4万円位です。それだけで1年間通えますのでほとんど無料みたいなものですね。それで学校の施設や練習室の利用、ピアノ科ですと先生のレッスンが受講できます。レッスンが週に2回1時間ずつあって、その他いろいろな授業もあります。それが本当に全部国の予算でまかなわれています。
— 実際エコールノルマルと比較してレベルはいかがでしたか?
奥山 レベルはエコールノルマルのトップの人とコンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)のトップの人とそんなに変わらないと思います。ただ、コンセルヴァトワールの生徒の方が全体的に年齢は若いですね。コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)に、フランス人は15歳位から入学試験を受け始めます。平均年齢だと20歳をいっていないくらいです。20歳で入るとちょっと年上の人って感じがしますね。
— 学校に入る前に師事する先生を見つけておくのですか?それとも学校に入ったあとに師事する先生を見つけるのですか?
奥山 学校に入る前に師事した方がいいです。まったく先生を知らないで試験を受けに行かないほうがいいです。
— まったく先生を知らないと入りにくいのでしょうか?
奥山 どうなのでしょうね。大体先生を指定して、試験を受けるので。先生を知らないと先生の方もその生徒を取りにくいと思います。結局、試験があって一番から順番に並んで、一番の生徒から希望の先生の所にいけるんです。ただ、先生が気に入られている生徒だと、順番を無視して、とってくださるケースもありますね。
— 先生が引っ張ってくれるということですね。
奥山 学校に習いに行くというよりは先生に習いに行くという感じですね。
— コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)には、一般的な授業や講義みたいなものはあるのですか?
奥山 ピアノと室内楽とソルフェージュは、年の初めに試験があります。それで免除される人がたくさんいるのですが、免除されないとそれらの科目は受講しなくてはいけないのです。あとは、楽曲分析とオプションで好きな授業を二つ以上取れます。オプションはいろいろあります。即興、合唱、理論、指揮、音楽史、美術史、音響に関することなどいろいろです。選択で授業を受ける感じですね。
— 自分の好きなように選んでいいということですよね。
奥山 私はそこでフォルテピアノ(編集注:初期のピアノ・古楽器)や即興演奏を習いました。
— フランスは非常に楽曲分析が厳しいというか、よくやるなと思うのですけど、かなり細かいところまで分析するのですか?実際その辺りはどうなのでしょうか?
奥山 コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)の授業で、外国人で一番大変なのがその授業です。週に1回3時間ぶっ続けであるんですよ。1回1時間半やって途中で10分くらい休むんですけど、また1時間半あるのでほとんど3時間ぶっ続けです。だからやっぱりすごい気分的に重いですよね。レベルは初級レベルから上級レベルまであるんですけど。私のように普通の楽器の生徒がやるのは初級レベルですね。知らない曲を聞いてどんな曲でも大体どの時代のどの作曲家のどういうスタイルの曲かというのを口頭で言えるような感じです。
— 結構厳しそうですね。
奥山 時代背景や曲のスタイル、調整とかいろいろありますよね。そういうことが出来るようになるわけです。試験も、選択式などの質問形式ではなくて分かることを全部言わなければならないので。
— 試験は質問に答えるわけではなくて全部答える感じですか?
奥山 一曲聞いて、分かることを全部紙に書くという感じです。
— そういう試験なんですね。これは辛いですね(笑)。
奥山 そうですね。曲の名前と時代だけ書けばいいというわけではないので。
— ちょっと知っていればいいというわけではないですね。

奥山 ちょっと知っていればいいというわけではなくて、ここから自分で分析して、使われている楽器だとかそこから何を言っているかとか、そういうところまで勉強しなくちゃいけないのである意味きついですね。そういうアナリーズ(Analyse)というのは音楽ではメシアンが始めたらしいのです。メシアンは最初その授業をフィロゾフィー・ドゥ・ラ・ミュジック(philosopie de la musique)、音楽哲学というふうに呼ばれていたそうですね。だからもう哲学なのです。
— 哲学ですか?非常にフランスらしいですね(笑)。
奥山 深い。深く分かっていくのだという。
— 楽器分析と聞くとただの分析かなと思うのですけど、実際は哲学なのですね。
奥山 そうなんです。音楽家としての音楽哲学なんです。そういうふうにお聞きしました。それでそういう授業を始めたのだと。そういうふうに歴史的に今につながってきているんですね。私が習っていた先生は実際にメシアンに作曲を習われた方でした。
— メシアンですか?本物ですか。すごいな。
奥山 そうですね。今先生をしている方はメシアンに習われたりした方です。メシアンに作曲を習われたという人がそういう楽曲分析の先生をしていらっしゃる。
— すごい。
奥山 すごいですね、考えると。そういうふうに歴史的に私たちまでつながってきている。そういう意味では、私はピアノをブリジット・エンゲラー先生とミシェル・ベロフ先生に習ったんですけど、ある意味ラッキーですよね。
— そうですよね。先生にはどうやってコンタクト取ったのですか?

奥山 もともと習いたかった先生は別にいらっしゃって、彼に入学前にレッスンしていただいていました。私がコンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)に入学した年は彼のクラスに一席しか席が開いていなくてこの先生にとっていただけなかったんです。それで、ロシアで勉強されて、素晴らしいコンサート・ピアニストであるブリジット・エンゲラー先生にコンタクトを取って入れてくださいって言ったのですね。それで、彼女のところに入りました。先生と三年間やってそのあとエンゲラー先生に、私は現代のレパートリーが好きだったので、ミシェル・ベロフ先生と合うのじゃないか、と言われてベロフ先生に途中で変わったんです。
— 先生に紹介してもらってミシェル・ベロフ先生に変えてもらったんですか?
奥山 私はミシェル・ベロフ先生に習えると全く思って入ってなかったのでラッキーでした。
— 紹介がなければ習えないわけですもんね。
奥山 直接行っても当時は彼も生徒をあまりとらなかった時期だったので、なかなか難しかったでしょうね。
— コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)は、フランスの音楽を多く勉強するのですか?
奥山 他の国よりはフランス音楽を多く勉強する、というくらいの感じです。でも全部やりますね。それに、コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)は現代曲を必ずやります。あと初見のクラスというのが結構進んでいます。初見のクラスも週に1回あるんですけど、それもかなり難しい楽譜をいきなり見て弾くという感じです。現代曲を2分くらい見て大体の構造をぱっと見て骨組みだけ弾く感じです。曲の感じをすぐつかむとか、読み方ですね。完璧に弾くのではなくて大体こんな感じの曲みたいな訓練はかなりさせられます。
— それはプロになるためには初見で弾けることが重要だということですよね。
奥山 完全にそうですね。専門家になるための訓練ですよね。
— コンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)の場合は語学の試験はないと仰ってましたが、どの程度語学はできればいいのでしょうか?
奥山 今は、ソルフェージュの予備試験というのがあるので、言っていることなどある程度聞き取れないと難しいと思いますが。ただ、普通に出来れば入ることは入れます。でも、入ってからがすごく苦労するかな、と思います。語学が出来ないと授業も分かりませんし。
— 授業は、全部フランス語でやりますもんね。
奥山 全く出来ないよりは中級レベル位までやって来られる方がいいと思います。自分にとっても先生にとっても。先生もいつも語学力については文句を言っていますので。
— 語学力ですか?
奥山 言葉のわからない生徒は先生も大変じゃないですか。日本人は日本人同士で固まりがちなのでなるべくフランス語は礼儀としてというか、外国の社会に入っていく立場から最低限勉強していったほうが私はいいと思います。
— コミュニケーションの出来る人のほうがフランス人と仲良く出来ますしね。
奥山 コミュニケーションというか言葉が出来たほうが来てから早くいろいろ吸収できますよね。
— 長い間フランスにいらしてフランスのいい点、悪い点がいっぱいあると思うのです。音楽をやるにあたって。それは何か教えていただけますか?(編集注:在仏12年)

奥山 パリに限定して言うとやっぱり音楽家や芸術家の人口密度が高いというか、可能性がたくさんあることですね。それがすごくいいと思います。この土地に、ある意味芸術的レベルが高い人がたくさん集まっているので。学校にも先生はいますし、この先生のレッスンを受けたいということになっても、パリに住んでいる方がものすごくたくさんいらっしゃるので、そういう意味ではチャンスが多いです。
— 逆に悪い点って何かありますか?
奥山 なんかすごい時間にルーズです。時間にルーズというよりは日本人の感覚から言うと口で言ったら実行するじゃないですか。口だけでいつまでたっても実行がないというか…(笑)。もちろん人によりますけど。あとはお給料も安いと思います。音楽のお仕事というのは日本でもパリでも大変なのは一緒だと思いますが。パリではちょっとしたサロンコンサートの機会は探せば結構あります。
— フランスで仕事を始めるにあたって留学する必要性はあると思いますか?
奥山 留学はビザなどの点から見ても、外国に出るのに、ある意味一番簡単な手段だと思うんですよ。それを利用するのは最初の手段として良いと思います。あとは最低限のコミュニケーション能力は必要だと思うので慣れる意味でも留学するのはいいと思います。
— フランス人は時間にルーズということでしたが、レッスン時間には遅れるのですか?
奥山 例えばブリジット・エンゲラー先生は演奏家なのですけど、自分が遅れてきても生徒は絶対先にいるべきだという人でした。上下関係とか、常識的な礼儀として。でも、本当のプロの人は、時間は正確です。一流の人はやっぱり遅れたりしないですね。時々、演奏家の先生はお忙しくて遅れてきたりはしますけど、来なかったりとか(笑)。
— 来なかった?
奥山 行ったら来なかった。でも一般的に一流の方は、すごい時間にきっちりしています。例えば現代曲で有名なピエール・ロラン・エマールという先生に習っていたのですけど、彼なんて5分刻みみたいな感じです。大げさに言えば、来週の13時5分にレッスンをしようという感じです(笑)。
— そんな感じですか(笑)。
奥山 どんなに忙しくても必要であればレッスンを入れてくださいます。でも本当に細かいです。フランス人には、そういう人も中にはいますね。通常は、レッスン時間がずれたり、やっていて長くなったりは良くあります。レッスンはほとんど時間が決まって無くて順番だけ決まっていたので2時間位ずれてずっと待っていたりします。でも私の先生はそうやって待たせて違う人のレッスンを聞かせるのが好きだったのでそういう意味もあるかと思います。
— フランスで仕事をするという意味で、日本人で有利な点、不利な点はありますか?
奥山 不利な点のほうが多いと思うのです。ヨーロッパで勉強されている、または活躍されている日本人の優秀な音楽家の人数がものすごく多くいるので。だから日本人が来るとまた日本人が来たというふうに思われることが多いです、現実的に。
— それはどういう意味ですか?
奥山 やっぱりヨーロッパやフランスでもどこでも外国人に仕事をとられるというのがあるじゃないですか。音楽は伝統芸能なので、外国人がアジア人が演奏しているよりは、ヨーロッパ人の顔をしている人が演奏した方がある意味自然と言ったらおかしいんですけど、そういう事があるのかなと。
— 日本でお琴を弾いている人が西洋人だったらちょっと違和感があるみたいな事ですね。
奥山 言い方はおかしいのですけど、そういう変な固定観念を持っている人はやっぱりたくさんいると思います。もっと開いたことを言っている人がいてもやっぱり心の中ではヨーロッパ人の方が優れていると思っているのに決まっているので。日本人はたくさん勉強して自分たちの音楽というか芸術を素晴らしく真似して、と言ったらおかしいけれども勉強して、そこまでやってくれてえらい人達だ、みたいなところがあると思います。その中で自分の個性とか壁というのを壊して超えて行くというのには時間かかかると思いますね。だからいきなり来てぱっと入るのだったら相当の実力がある人だったら、来られる人もいらっしゃいますけど実際はかなり難しいと思います。
— 人脈が大事ということでしょうか?
奥山 人脈ですね。つながりとか。一つ一つ仕事をしてある意味最高の仕事というか自分の最高の音楽を見せていくことだと思っています。後はやっぱり言葉という意味でもコミュニケーションという意味でもいきなり「こんにちは」と言ったくらいではしゃべれないと向こうは頭で思っていますので。
— 有利な点はいかがですか?
奥山 例えば伴奏ピアニストとしてやっていく場合、仕事をするという意味では期限内にちゃんと仕上げるとか、技術面もしっかりしているという評判があるので、そういう意味では信用されやすいと思います。
— 日本人のほうが信用されやすいのですね。
奥山 そうですね、まじめな人種っていう事でしょうね。でも逆に利用されているような場合もあるので気をつけないといけないと思います。言ったらやってくれるだろうと。ある程度自分がやりたい事というのを提示していかないと流されて、その場限りみたいな感じになることも結構あると思いますね。
— 奥山さんにとってクラッシックもしくは音楽とはどういうものですか?
奥山 「今の時点」だと人生そのものですね。音楽をやって初めて自分が一つになるというか、とても深いものですね。
— それはやっぱりクラッシックですか?
奥山 クラッシックというのは100年、200年前に作曲家というか芸術家がいて、それで作品を書いてそれがずっと残ってきたものです。それはモネの絵とかゴッホの絵とか画家の中でもたくさん人がいるうちで素晴らしいものが残っているのと同じように、音楽も、時間をかけて理解して表現して磨いていくような過程がやっぱり好きですね。
— なるほど。
奥山 クラシックは、時間をかけて深めて理解して、自分の人生をかけてといったらおかしいのですけど、そういう感じで細部まで磨くというのでしょうか。音に対しても非常にこだわりを持って全てが重なった時に、ある意味感動が生まれたりします。自分一人だけ感動するのではなく。だから演奏会があったら演奏会の時点だけではなくて前々から、積み重ねていってそこで到達するような感じですね。
— 音楽を日常でやっていて、喜びが最高潮に達する時があると思うのです。演奏会でも練習でも。それはどういう時でしょうか?

奥山 演奏会というのはある意味ゴール地点なので、入った瞬間というのはそんなに面白いという感じではないのですけど興奮みたいなのはあるんです。面白いなと思うのはやっぱり楽譜と向かい合って勉強していく過程で一つ一つ発見していくことですね。発見というか、インスピレーションがだんだん湧いてきて形にしていく過程が面白いです。出来てしまったらあとは人に見せるんですけど、人にみせるというのは別のことだと思っています。それは例えばコンディションを整えたりすることです。演奏会が一番好きで、来てくださった方々とそういう濃い時間を分かち合うのがやりたいことなんですけど、一番脳が面白がるのは発見の過程ですね。他のミュージシャンと弾いて新しいものが生まれてきたりするのも面白いです。
— 「お客さんに見せる」段階よりもその「前段階」が面白いということですね?
奥山 それが一番面白い。でも、お客さんに見せた段階でやっぱり音楽が変わるんです。自分がとことん理解して勉強して時を重ねても見せる時になるとまた変わるんですよね。ある意味そこで一段階ステップアップするんです。それもまた面白いです。それは自分だけの力とかいうんじゃなくて、その時の雰囲気だとか、アコースティックだとか感じることだとかあるんですけど。そこで生まれてくるものというのは。
— これは面白いと思いますよ。今まで一生懸命練習や解釈をして自分が最高だと思っていることが、お客さんやいろいな条件によって自分が思っていないことが出てくるのですからね。
奥山 そうですね。急に違うことやったり(笑)。
— 違うことやるのですか?
奥山 本筋は変わらないのですけど、もっとよくなることもあるし、悪くなることもあります。例えばお話する機会があったとしても、話し方というのは目の前にいる人によって変わりますよね。それと同じ事が起こりますね。自分の中ではこういうものを作ろうと決めてやっているのですけれど。
— ソロとアンサンブルとどちらのほうがお好きなんですか。
奥山 私はアンサンブルすごく好きなんです。パートナーは、すごくあう人じゃないと出来ないんですけど。
— 自分の方が合わないなと思うのですか?
奥山 いろんな人と試してやってみようと思って、実際にやってみてもいるのですけど、この人とやったほうが良いというのが最近分かってきましたので。レベルとかフィーリングとかいろいろあるんですよね。やっぱり気質がソリスト気質というふうに言われてしまうことが多いんですね。自分ではどうにもならない(笑)。
— 日本人の方と演奏する機会もあるでしょうし、現地フランス人の方と演奏する機会もあるでしょうけれども、どちらの方がやりやすいのですか?
奥山 日本人は正直やりやすいです。すぐにあいます。
— やっぱり奥山さんが日本人というのがあるんでしょうか?
奥山 何かテンポの感覚とか拍子の感覚とかでしょうか。それに日本人は合わせるのがすごく上手です。誰でも、日本人同士だと、ほとんどずれません。
— フランス人はずれるということですか?
奥山 ずれる。もう信じられない。こんなにずれないというくらいずれます。本当に神経疑うくらい(笑)。プロ同士だったらずれないように最後はやります。でも、ずれる人は本当にずれますし、勝手に弾いてます(笑)。だからというわけではないのですが、合う人と会えば非常に合うのでそれはすごく面白いですね。
— 奥山さんの今後の音楽としての夢を聞かせていただけますか?
奥山 音楽としての夢はいっぱい演奏の機会を増やすこと、それにいろいろ人とコラボレーションしていきたいです。アンサンブルとしてもそうですし、例えば他の分野、映像や舞踏の人などそういう意味でもいろいろやっていきたいですね。なんか私は「交換(Echange)」と、「分け合う(Partage)」みたいなことに今すごく興味があるのです。
— それはあるものを、気持ちを通して、「交換し」「分け合う」のですか?
奥山 いや自分の気持ちというか持っているものですね。それは例えば芸術家の「フィーリング」だとか「インスピレーション」などです。興味としては、知らない作曲家の人も新たにやってみたいし、持っているものを深めるのもいいのですけれども、一番興味を持っているのはそれを「交換」することなのです。
— 面白いですね。
奥山 一人でやるにはやっぱり制限があるし、今の時代だとショパンコンクール1位とかチャイコフスキーコンクール1位などを目指すのは、20代までは良いと思うのです。でも、そういうことには限りが出てくると思います。いろんな人と関わり合って自分を高めてオリジナリティーを探求していった方が良いかなと思います。
— 確かにショパンコンクール1位とかチャイコフスキーコンクール1位とかというのはすごいのですけど、それ以上ではありえないですよね。例えば先ほど言われた映像の方といっしょにやるとか、ダンスの人と一緒にやるとか、そのほうが面白いと思いますね。
奥山 選択肢をコンクールだけにしたら、他の人と関わるというのは絶対無理じゃないですか。一日10時間、家に閉じこもって練習するしか道はないような感じになりますよね。それにチャイコフスキーコンクールを受けるとしたらコンクールのための曲を弾くしかないのです。そうではなくてもっとテクニック的に難しくない曲や、もっと単純なコンクールでは栄えなくても素晴らしい作品を勉強する時間もとれないことが多いのです。20代にそれを全然勉強しないことになるんですよ。感性が鋭くて一番吸収できる時期に、それもまたもったいないと思います。
— いろんな人と一緒にやるというのは次のステップということですね。
奥山 いろんな人と一緒にやるとか、いろんな世界の人と関わりたいというのは次のステップとして、そういう経験を通して、自分を深めたいという感じです。
— いろんな人とやるのは一番面白いことだと僕も思うのです。観客も含めて、音楽というのは一人のものではないと思うので。いろんな人とやるのが一番面白いのかなと思いますね。
奥山 ソロと言われながらも他の人とやってソロの演奏の中にもそれを取り込んで、こう色彩というか。自分のパレットを増やしたいと思っています。
— プロのミュージシャンとして、フランスで活躍出来るような秘訣とか、仕事がとれるような理由とか、成功する条件は何かあるとお考えですか?
奥山 最終的には成功する条件はどこでも一緒だと思うのです。やっぱり努力と、努力して人への思いやりを持つことです。あとは自分のやりたいと思っているチャンスを常に逃さないように待機している状態にすることです、精神的に。
— 精神的にですか?
奥山 そうですね。精神的なテンションを保つのって結構難しいと思うんです。ある時やりたいな、と思うことがあっても、一週間くらいたったら、もういいかな、と思ったりするじゃないですか(笑)。そういう意味で続けること、継続が大事ですよね。途中で失敗してもそんなにあきらめないで何度もトライしていくことが大事だと思います。
— 人間なんでやる気が落ちる時もあるし、これを保っていくということは難しいと思いますね。
奥山 保つということは難しいですよね。私も結構落ち込むので。一人の時間がすごく多いので。特にピアノをやっている人は。だから自問自答ばっかりしている人がたくさんいると思います。でもある意味捨てていかなきゃいけないものがあると思うんですよ(笑)。学生の時はやっぱり可能性をいっぱい探るので可能性の中でおぼれてしまうような感じです。でもやっぱりプロになろうと思った時点でなんといったらいいのかな、開き直りというのとは違うと思うのですけど捨てる部分があるんです。
— 学生のときは、自分が世界のトップピアニストで、例えばニューヨークのカーネギーホールでいつも演奏するだとか、常時、そのような場にのみ自分がいると思っているのでしょうね。

奥山 そうですね。でもプロになるということはいきなりそんなカーネギーホールに行くことではないですよね。一つ一つ積み重ねていって、その頂点にカーネギーホールがあればすごく素晴らしいことなのだと思います。やっぱり音楽家、特にクラッシックだったら20代で最高を目指すなんてやっぱりありえなくて、 20代があって30代があって40代があると思います。80才でもまだ現役でコンサートやっている方もいらっしゃいますので。やっぱり上には上がいて、何というのかな、謙虚な姿勢というか長い目で見るようにした方がいいと思います。プロというのは、中学校の上は高校とかそういうのではないので今やっていることが40代になった時に花開くといいなという長いスタンスでいるとやっぱり気持ち的にはいいんじゃないかなと思いますね。
— フランスで音楽を勉強したいと考えている日本の方に何かアドバイスがあれば教えて頂いてよろしいですか?
奥山 フランス留学する方は、まずとりあえず来てみてください。いきなり長期で来ないで例えば2週間とか1ヶ月とか期間を決めてトライしてみると良いと思います。とにかく一回来て本場を見ることが大事だと思います。そして、もし来たいと思われたらあきらめずに頑張ってください。
— 長期留学する前に短期で一回見るというのは大切ですよね。
奥山 私も一回見るチャンスがあったので。夢というのはどんどん膨らんでしまうのでやっぱり見ないといけないと思います。来て、見て、触ってみないといけないですね。
— 考えてばかりだと実際は違ったというのもありますしね。
奥山 来た後に、もしかしたら来たくないかもしれないですし。文化の違う所で生活するのは大変ですので、日本に居た方がいいと思うかもしれないし、違う国の方がいいと思うかもしれません。学校を見学したり、短期で2週間〜1ヶ月くらい春休みや夏休みを利用して一度来られるのがいいと思います。
ー ありがとうございました。
福森道華さん/ジャズピアニスト/アメリカ・ニューヨーク
「音楽家に聴く」というコーナーは、普段舞台の上で音楽を奏でているプロに皆さんに舞台を下りて言葉で語ってもらうコーナーです。今回はニューヨークでご活躍中のジャズピアニスト福森道華(フクモリミチカ)さんをゲストにインタビューさせていただきます。「音楽家としてニューヨークで活躍すること」についてお話しを伺ってみたいと思います。
ー福森道華さんプロフィールー

愛知県立芸術大学音楽部作曲科を卒業。上京後、鈴木コルゲン宏昌さんに師事し、東京で8年間活動。2000年に渡米。Steve Kuhnにジャズ・ピアノを師事 し、ニューヨーク市立大学大学院音楽学部ジャズ科を卒業。Lenox Lounge、Cleopatra's Needle、University Street、Beekman Tower Hotel等に出演。ギリシャツアー、アルバムのレコーディングと音楽活動を広げています。ジャズライブハウス「ブルーノート」へも出演し、実力が高く評価されています。また、「CDで学ぶピアノの弾き方/気楽に楽しむポップスピアノ」(ナツメ社)の著者であり「ハモンドオルガン/キーボード ジョーイ・デフランセスコ イン」(ATN)の翻訳なども行っています。
ー そもそも音楽に興味をもったきっかけを教えていただけますか?
きっかけですか?3才のときに母親に地元の音楽教室に連れて行かれたことですね。自宅にピアノがたまたまあったので...。
ー 小さい頃だと興味があったというわけではなかったと思うのですが、やり始めていって、プロになろうと思った瞬間とかがあったわけですか?
そうですね、3才以降、常にやっていたので、そのまま何も考えずに音大に行き、今はジャズをやっているんですけど、あえてこの道に入ろうとしたのは、音大を出てからですね。
ー 日本ではクラシックから始めたようですが、何故ジャズに行き着いたのでしょうか?
あんまり大きくは言えないんですが、音大まで行って、私はクラシックがあんまり好きじゃないと思って。音楽教室はクラシックもやらせるし、ポップスみたいなのもあるんですが、よく考えてみるとそっちの方が好きだったな、というのに気がついて。それまでは学校でも音楽の時間は普通の授業より好きだな、とか音楽だったら何でも好きだったんですが、いざ100%クラシック音楽の環境に入って、ちょっと違うなっていうのがあって。よくよく考えたらテレビでやってる歌謡曲の方が好きって。
ー 今でもクラシックはあまり?
ジャズの道に入ってからは、こっちに必死なんですよね。時間がないから聴いていないですね。
ー ブラジル音楽がお好きだそうですが、ジャズに進まれたのはなぜですか?
ブラジル音楽はそれで仕事が出来るとは知らなかったんですね。ホントは大学卒業してから、商業音楽家になりたかったんですよね。歌手の人に楽曲を提供する作曲家みたいな。で、そういう人になるならジャズの理論とか知っていた方が良いかな、と思って、テレビでたまたまジャズフェスティバルみたいなのをやっていて、このアレンジがすごい!、この人につきたい、と思ったときに、Dr.JAZZとして日本のジャズを支えて育ててくださった内田修先生にお会いして話したら鈴木君につきたいのか、紹介してあげるから、是非つきなさいと言われて..。鈴木先生が教えているのがアンミュージックしかなかったんですね。それで鈴木先生についてからすごく奥深くて、のめり込んで、難しくて、ジャズしかできない、他のことをやる時間がなく、今に至るという感じですね。
ー そのころから一気にジャズに変換して、東京でもジャズという感じだったんですね。

変換というか、ふと考えたら他のことをやる時間がなかったし、難しかったし。自分にもあっていたし、すごく好きだったので。たまたま拾ってくれるバンドとかもあったので、東京に行った瞬間からジャズにドボっとはまったという感じですね。ご縁があったんですね。横道を考える暇がなかった。そんな中でブラジル音楽がすごく好きでよく聴いていたのですが、ニューヨークに行ってみたところ、そのブラジル音楽とジャズの両方がすごいクオリティーで存在するので、ニューヨークに住もうかな!、将来あこがれのバーに出れたらいいよな〜!みたいに思って。ZINC BARっていう憧れのBarにでれたらいいよな〜と思ってたんです。そこのバーでは、ぱっと見たらどう考えてもブラジル人しか弾いてないので、まさか自分がステージに出れるとは思っていなかったんですけど。次の人生はブラジル人なりたいと思いますけどね(笑)。本当はブラジル音楽とジャズ一緒にやりたいと思うんですけど、ブラジル音楽もすごい難しいんですよね。リズムの問題で。天才だったら出来たかもしれないんですけど自分の容量はよく分かっていますので(笑)。
ー 渡米を考えたきっかけを教えてください。
ジャズを初めたときから私を育てて頂いた、歌手の植村美芳子さんに、会ったときからニューヨーク行こうよって言われていたんです。でも、お金がないじゃないですか、もちろん。どうやってニューヨークへ?日々手一杯なのに、どうやってお金を貯めてニューヨークへ行くんだ?という感じだったんです。ある日、お金がようやく貯まったので、植村さん今年は行けそうなんですけど、と言ったら、ホントに〜って言われて。私が部屋借りるから、居候でいいから連れって言ってあげるわよ、っていわれて、行ったら初日からはまってしまったんです。私はもうここに住んでしまえ〜、これは住むしかないな、という風に思ってたんですね。
ー 1番そういう風に思われたのはどう部分なんですか?
やっぱり音楽ですよね。すごいショックを受けたんですよね。レコードしか聴いたことがないじゃないですか。いわゆる勉強するとか、ブラジル音楽にしても CDを聴いてう〜んという感じがあるみたいな(笑)。生を聴いて、生ってCDの百倍ぐらい迫力が有るじゃないですか、もちろん東京でもブルーノートとか行ってましたけど、それを1/10ぐらいの値段、もしくはタダで聴ける生活があるなんて。自分がそこに入るなんて夢にも思っていなかったので、とりあえずすがるように、聴けるだけでもいいや〜、という感じで。まさか自分が、そういう人たちに混じるとか、そんなおこがましい事は全然考えていないです。ほんと聴けるだけで有り難うございます、という感じで。
ー 現状で福森さんの音楽スタイルはご自分ではどのようなものだと思っていらっしゃいますか?また、ご自分の音楽をどのように作っていくのですか?
アメリカ来てから音楽に対して、変わったと思うのは、日本にいるときはすごく頭で考えていたんですよ。音楽のことを。とにかくすごい頭で考えていたんですね。こっちに来てからジャズが生まれた国で、ジャズが発展してきた土地で、こうして聴いている訳じゃないですか。しかも、びっくりするような大御所を間近で聴いて、その人たちの音楽を浴びるように聴いからは、頭で考えるんじゃなくて、心から伝えなきゃいけないんだ、っていうのがありますね。自分が日本とニューヨークにいてすごく変わったと思うのはそこですね。それで、それを感じられたのは幸せだなあと思うんですけど。Steve Kuhnに付いているというのもありますし、こちらでは全てがそういう思考なので。Steve Kuhnからは、君は何のために音楽やっているの?って。伝えるものがなければ意味がないじゃないかと。わたしが100万回練習した曲をSteve Kuhnが、なんだこれは〜!って言って、僕はこんなの30年ぐらい弾いていないけどね、と言って、30年ぶりに弾いた彼のその一発が、私の100万回の練習よりも100万倍うまいんですよ、というかずっと良いんですよ。
ー 舞台の上ではどのような事を考えて演奏しているのですか?それとも自然に演奏しているんですか?

日本にいる時は考えて演奏していたんですよ。今は、自然が自然にでるようする、という事ですね。そして頭で考えなくて良いぐらい、練習する。自然に自分がでるように、自分が何を感じているかがすぐに手に伝わるような訓練をしておく。日本ではそれをしていたつもりでも伝わっていなかったんですよね。回路が間違っていた、というか、間違っていたとは言わないですが、あれはあれでよかったんですけど。実際気持ちよくスイングするというのはどういうことか、っていうのを、今自分がスイングしているかということをおいておいても、体でこういうことじゃじゃないのかなっていうのを何となく感じ始められたんですね。そのことは一生考え続けることです。だいたいこっちで育ってないし(笑)。そういうことは良く言われるんですよ、僕達はこちらの音楽を聴いてきて、英語を話してこういう風にスイングしているけど、だいたい君思考回路日本語でしょ、って(笑)。
ー やっぱりジャズって、ツーカーの部分があると思うんですけど日本人と演奏するときと外国人と演奏するときと、一緒にやるときは感覚はちがうものですか?
やりとりの仕方は一緒です。日本で学んだHow to Jazzでも全然OKです。でもその先のどうやってスイングするとか、あこがれのレコードで聴いていた演奏に近づくには、っていう答えが、今でもずっと探しているんですけど、先生にも言われるんですけど、難しいんですよね。それはもう心で感じるっていうことなんですね。
ー 体に染みついてくるっていうような感じですか?
やっぱり年中浴びるようにあの音楽を聴いて、ですかね。
ー それはやっぱりずっと住んでいないと分からないような感じですか?
世の中には分かる人もいると思います。私のような人間は、住んで5年たって、やっとなんとな〜くわかりはじめて、でもやっぱり分かってないんだろうなって、感じですかね。こんなこと言っていてもSteve Kuhnに言わせればNever ever swingとか言われちゃうんですけど。やっぱり本では勉強するじゃないですか。奴隷制度があって、アフリカ音楽と西洋音楽の融合みたいな、そういうのをものをこちらにいると身近で感じるんですよね。例えば、ゴスペルとかを見ると、こういうのが根底にあるのね、とか。
ー ニューヨークに住んでると浴びるように感じるって事ですよね。
ニューヨークに住んでるとテレビも英語でCM流れても英語じゃないですか。その行間に流れる音楽も英語で流れるじゃないですか。日本に帰るとそれが全部日本の音楽、そこにまず、違いを感じます。だから、例えばただテレビでもこれを30年聴いて育ってきたか、きてないかで違うだろうなと。
ー その部分で根本的な違いが出てくるってことですか。じゃあ更に30年間そちらに住み続けていけば、いわゆる自分の目指している音楽に近づけるということなんですか?
近づけたら良いですね。でも、そういう意識をずっと持ち続けることが大切だと思っています。
ー 音楽活動をする上でどのようなこだわりをお持ちですか?
う〜ん。ないです(笑)。今は電話がかかってくれば何でもお受けしています。
ー 演奏上でもないですか?
ないです。言われたものは何でもやります(笑)。よく分からないんですけど、どうやら私はたくさんの曲を知っているらしいのですよ。日本で最初に入れてもらったバンドがデキシーランドジャズで、普通の人が知らない古い曲から、歌伴をたくさん演らせて頂いていたので、歌手の人達が好む曲まで。そういう意味でも使ってもらえることが多いです。なので、雇ってくださった日本のバンドリーダーに感謝しています!。よく言われるんですよ、あなた多分日本人で結構若いわよね、なんでそんなおばあちゃんが知っているような歌知っているの?って(笑)。
ー 音楽活動して最も興奮することはどんなことでしょうか?
一緒に演奏している人達と、今なんかすごく通い合ってるなって感じるときですかね。その瞬間ってすごい曖昧なんですけど、グルーブしてるというか。自分なりにスイングしているってときですね。
ー その時はお客さんにも伝わるものですか?
伝わると思います。のってない時ってお客さん、聴いてないんですよ。Zinc Barとかでもざわざわざわ〜っとしてて。で、やっぱりワッってバンドがするとお客も聴いてるんですよ。正直ですよね(笑)。
ー 自分たちが今日はのってないな、という時はお客さんものってないなってなっちゃうんですか?
うーん、自分たちは100%でやっていたとしても、なんかのきっかけでうまくいかないことがあるんですよね。わかんないですけど。常に良い状態を目指してはいるんですけど。音楽からエネルギーを感じるか感じないかでうまくいかないことがあるんです。ダラダラした演奏をしようと思ってなくても、結果的にエネルギーが音楽に行き届いていないとそれがお客さんに伝わるんですね。
ー ミュージシャンは盛り上がっていこうとしてもいまいちのれないときがあるって言うことですよね?
そうですね。いつも音を出した瞬間にときにバーンと来るのが理想なんですけど。
ー 日米の観客の違いはありますか?

そんなに違いはないような気がしますけど、例えばレストランで演奏する時にお客さんは聴こう、聴かないはあまり関係ないはじゃないですか。ただ、アメリカ人の方が楽しもうという雰囲気を持っていますよね。日本人の方がちょっと構えちゃう?っという感じ。でも日本人の人は慣れてきたら、良い感じで聴いてくれます。
ー ジャズクラブのお客さんも日米で違う感じですか?
ジャズクラブはジャズが流れてるって分かってるから、そんなに違いは感じませんね。
ー 福森さんにとって、ジャズって、音楽ってどんなものでしょう?
なんでしょう、もうこんなに長くやってしまったんで、人生の相棒といったところでしょうか。そんなこと言いながら、いろいろ趣味はもっているんですけどね(笑)。
ー ニューヨークで最も受けた影響って何ですか?
ニューヨークで音楽的に、う〜ん、やっぱりSteve Kuhnに付いていたんですけど、やっぱり一番影響を受けましたね。音楽に対する姿勢というか。姿勢って言っても私よく分からないんですけどね。ああいう偉大な人って、1時間半ぐらいのレッスン受けるだけでもものすごい、なんかワーって言うオーラみたいなものがあるんですよ。天才オーラというか。横で弾いてくれてるだけでも影響は受けますよね。
ー 技術とか、うまい下手とかそういうわけではないんですよね?
そういうんじゃないです。多分Steve Kuhnの人生がその音に詰まっていて、その音を通して、影響を受けるみたいな感じでしょうね。
ー それがご自分の演奏にも出てくるって感じですよね。
ええ、マニアですので。オタクやなあ、と思うんですけど。彼のレコード集めてるし、ニューヨークでのライブはほぼ100%聴きに行ってます。
ー 将来の夢を聴かせて頂けますか?
もっとうまくなりたいですよね(笑)。(技術的ではなく)もっと自分を伝えられる音楽家になりたいですね。結果的に自分を伝えて、ハッピーを共有できたらいいですよね。
ー お客さんがいいと思っている事はミュージシャンに伝わるものなんですか?
伝わります、さっきのざわざわしているって言うのと同じで、のっているときはエールの交換みたいな。そうするとミュージシャンものってきて。相互に良い感じですよね。
ー 海外でミュージシャンとして活躍する何か秘訣というか成功する条件はあるとお考えですか?
私が成功しているかどうかよくわかんないんですけど、やっぱり必死になることですかね。ジャズの場合、ニューヨークが本場じゃないですか、それで、そこを毎日毎日憧れてくる人が何百人といる訳じゃないですか。で、自分の前には何万人といる訳じゃないですか。だから必死でやっていかないと、ついて行けないですよね。
ー 逆に言えば、必死でやればチャンスがあるって言う感じですか?
そうですね。
ー 海外で勉強したいと考えている、読者にメッセージをお願いします。
海外で勉強するという夢は絶対叶うと思います。それはもう自分で努力して、お金を貯めれば叶うじゃないですか。勉強して卒業するまでは出来ると思うんですよ、誰でも。でもそこから先がスタートって言うか。それを活かせるような心がけというんですか、あと熱意です。それと努力の方向を間違わないようにする事。留学する方に取っては先の先かもしれないんですけど。演奏家になりたいといっても演奏家になれる人は、ほんの一握りの人達だけなので、演奏家になりたい場合はやはり覚悟を決める事です。必死さと方向を間違わないことですね。やっぱり難しいので空回りしてしまうこともありますし。自分の必死が報われるような努力をしないとダメです。あと練習だけではなく、アンテナも張らなくてはいけない。仕事を取るという意味です。やっぱりいろんな人と交流をはかっていないと、情報が入ってこないですね。そういうのも大事だと思います。もちろんチャンスが来たときに、自分の実力がそれに伴っていないとダメです。夢を持って留学されて、その夢を叶えるためには、常に自分の実力が伴っていないといけないので、そういう状態である事が必要ですね。
福森さんのオフィシャルホームページでもライブ情報を公開しています。