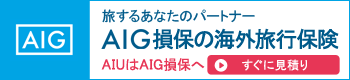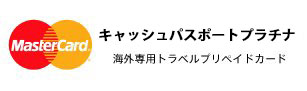小野麻衣子さん/ジャズドラム/ニュースクール大学/アメリカ・ニューヨーク
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

今回はニューヨークのニュースクール大学、Jazz & Contemporary Music科にてジャズドラムのお勉強中の小野麻衣子さんにお話を伺いました。小野さんは日本でもライブ活動を行うなど、日本でも活躍中の彼女のニューヨーク生活は一体どんなものでしょう?
ー 改めて、まず簡単なご自身の紹介と、現在の学歴を教えてください。
出身は大分県大分市で、一人っ子です。熊本の大学を出た後、実家のジャズ喫茶を手伝いながら音楽活動をしていました。現在マンハッタンにあるニュースクール大学Jazz & Contemporary Music科にて勉強中です。
ー 今は、ニューヨークは何年目になりますか?
2004年1月に渡米したので、1年半になります。
ー 日本では何をなさっていましたか?
日本では実家のジャズ喫茶を手伝いながら音楽活動を行っていました。
ー 留学する前までの音楽の経験は何歳からなさっていましたか?
大学のビッグバンドに入部し、ドラムを始めました。父がドラマーであるため、小さい時から遊びでたたいていましたが本格的に始めたのは大学に入ってからです。
ー 留学したきっかけというのはなにかありますか?
友達のギターリストが渡米したのをきっかけに、私もニューヨークで勉強したいと思うようになりました。
ー どうして音楽を選んだのですか?お家の影響ですか?
そうですね。ジャズ好きの父の影響で小学生の時からジャズを聴くようになりました。いろんなライブハウスへ連れてってくれたのも父です。とても感謝してます。
ー 学校はどうやって選びましたか?

ニュースクール大学はジャズを勉強する場所としてとても有名な学校なので前々から興味を持っていました。旅行でニューヨークに初めて来た時に友達になったドラマーがニュースクール大学に入ろうとしていたところでしたので、彼からいろいろと話を聞いてますます入学したいと思うようになり、それがきっかけでニュースクール大学入学の準備を始めました。
ー 学校はどのような試験・出願書類が必要でしたか?オーディションはありましたか?
2003年の9月から3ヶ月間ニューヨークに滞在し、その間にオーディションを受けました。願書手続きもすべてニューヨークにて行いました。父から銀行の残高証明書をファックスで送ってもらい、大学の成績証明書も日本から送ってもらいました。あとは自己アピールのエッセイを制作して学校に提出しました。
ー エッセイの書き方のコツはありますか?
エッセイの書き方のコツは、とにかく自分の良い所をアピールすることです。日本人の性格からして、恥ずかしいと思いがちですがそれは間違いです。自分の良い所を自分で理解する事が大事ですし、それをアピールしていかなければ意味がありません。「謙遜」という文字はアメリカには無いのではないでしょうか。
ー TOEFL対策はどのようにしましたか?日本での英語勉強法は?
特に勉強していません。少しだけ語学学校に通ってただけです。
TOFELは受けていません。入学前に一ヶ月間ニュースクール大学の英語科で勉強することによってTOFELは免除されました。
ー 留学するまでにどのくらい前から準備しましたか?
本格的に準備しはじめたのは4ヶ月前です。
ー 出発前に不安に思っていたことは何かありますか?
英語が喋れるかどうか不安でした。
ー 実際は留学当時の語学はいかがでしたか?
留学してすぐは全くと言っていい程、喋れませんでした。
ー ニューヨークを選んだ理由というのはありますか?
やはり、素晴らしいジャズミュージシャンが生活して活躍している街だからです。
ー 学費はどのように捻出しましたか?学費の支払い方は?
父にサポートしてもらってます。
ー ニュースクール大学はどんな雰囲気ですか?ニュースクール大学ならではの特徴ってありますか?
そんなに人数は多くないので、生徒も先生もみんな家族みたいに仲が良いです。とても雰囲気が良いと思います。
ー 人種はどんな人たちが多いですか?

アメリカ人65%、イスラエル人15%、韓国人8%、日本人7%、ヨーロッパ人5%くらいでしょうか。
ー 日本人はどのくらいいますか?
15人くらいいます。
ー ジャズドラムをやっている人はどのくらいいますか?女性はめずらいしいですよね?なぜドラムをえらばれました?
ドラマーは学校に現在30人くらいいます。女性は私の他にもう一人です。ドラムは父の影響だと思います。
ー 日本と留学先では何が大きく違うと感じましたか?
他人が何をしていても気にしないところが好きです。日本だと、流行ったら誰もがそれを身につけ、携帯する。こちらにはそういった慣習がないように思われます。自分が好きなものを身につけ、好きなものを食べて、好きなものを聴いているような気がします。楽でいいですね。みんなが肩肘はらずに自分をアピールしながら生きているような気がします。
ー 専門用語はどのように勉強しましたか?
音楽の専門用語は学校で学びました。
ー 学校の授業はどのような感じですか?
音楽の理論やジャズの歴史、アンサンブル、ドラムのテクニック的なものの勉強などいろいろです。
ー 学校の音楽の実技レッスンはどんなことをしますか?
アンサンブルの授業で先生が持って来た譜面を見ながら演奏したり、生徒が持って来たオリジナルの曲を演奏したりしてます。演奏のあとに先生がコメントをしていくといった感じです。
ー 先生はどうやって見つけるのですか?
一応先生のリストがありますが、ニューヨークに住んでいるミュージシャンなら誰でも選べます.学校側からミュージシャンにコンタクトを取ってくれるのでとても安心です。
ー 先生の教え方はどんな感じですか?どのように教えてくれますか?
先生によっていろいろですが、私のプライベートレッスンの先生は私の質問に丁寧に答えてくれます。また、レッスンの後に教えてくれたことをすべてノートに書きうつしてくれるので安心です。
ー 練習はどのようにしていますか?
学校の練習室で練習してます。教則本をみながらの基礎練習が主です。たまに友達のサックスプレイヤーやベースプレイヤーを呼んで、練習室でセッションしてます。おウチでも昼間であれば練習できますので、たまにやってます。
ー 学外でのセッション、コンサートなどは行われますか?
毎日のようにあちらこちらでセッションをやっています。
ー 音楽のレッスンで苦労することはなんですか?
はじめは英語が理解できず大変でした。
ー 1日の大体のスケジュールはどんな感じですか?
朝から夜遅くまで学校に居ます。授業の合間に練習をするといった感じです。
ー 音楽業界へのツテってできますか?
私は日本のミュージシャンの知り合いがたくさんいますのでツテはあるほうだと思います。
ー 学習態度に関しては、日本とどう違いますか?例えばどのような点が?
お菓子をたべながら授業を受けても、寝転がって授業をうけても誰も何もきにしないのが面白いとおもいました。先生もコーヒー飲みながら教えてます。でも決して不真面目というわけではありません。みんな積極的に質問し、先生が間違っていると思ったら積極的に指摘してます。はじめはびっくりしましたが、そうでなければいけないのだろうなと思いました。
ー 授業以外はどのように過ごされていますか?
ライブを聴きに行ったり、映画を見に行ったり美術館に行ったりしてます。最近はお料理にもはまってて、料理本をみながらクッキングしてます。テキサス料理を勉強中。
ー 日本人以外の人たちと交流はありますか?付き合うコツなどはありますか?
アメリカ人や韓国人のお友達はたくさん居ます。とにかく自分の英語の下手なのを忘れて、話す努力をすることだと思います。
ー 宿泊はどのようにしていますか?
2ベッドルームの一部屋を借りてます。
ー 1週間の生活費はどのくらいですか?
$100くらいでしょうか。
ー 1日の平均勉強時間は?
3〜5時間ぐらいですね。
ー 現在の語学レベルは?
普通の会話なら困らず喋ってます。映画などの理解は、いまだに難しいです。
ー 留学先で苦労したことは?
勉強面ではとにかく英語です。生活面では困ったことはありません。
ー 留学して自分が変わったというところはありますか?
特に変わっていないと思います。
ー 実際のところ、治安はどうですか?
場所にも寄りますが、良い方なのではないでしょうか?
ー これから留学する人にアドバイスしておきたいことは?
日本のように学校側の管理がきちんとしていません。書類を送るといって忘れていたり、送った書類をなくされたり等々。信用してばかりいると手遅れになる事が度々起こります。早めの行動を!!!
ー 留学してよかったと思える瞬間は?
素晴らしいミュージシャンに、素晴らしい友達に出会えた事。
ー 今後はどのような進路を考えていますか?
学校卒業後もニューヨークを起点に音楽活動ができたら幸せです。
ー 今後も夢が実現するように頑張って下さい。今日はありがとうございました。
東かおるさん/ジャズボーカル/ニューヨーク市立大学シティカレッジ/アメリカ・ニューヨーク
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

今回はアメリカニューヨークにあるニューヨーク市立大学シティカレッジ校にてジャズボーカルをお勉強中の東かおるさん(本名:川東郁さん)にお話を伺いました。大阪でも定期的にライブ活動を行う彼女がニューヨークで得たものとは?
− ご自身の簡単なプロフィールをご紹介いただけますか?
えっと、日本では理論とかは自己流で、短大のときからプロについてレッスンを受け始めました。そこの先生に本気でやりたいなら、一刻でも早くニューヨークに行くようにといわれて、それで留学をしようと思ったんですが、資金の面もあり、6年間日本のジャズバーで、ウェイトレス兼シンガーとして働いて、貯金しました。現場で生演奏できる環境で、ボイストレーナーにもついていました。あとはクラシックの基礎知識もつけようと、そういった学校でも習いましたね。
− 短大に行かれるまでは、音楽のご経験はなかったのですか?
3歳から10年間ピアノはやっていました。高校のときに歌手になりたいと思って、タレントの養成所で基礎の勉強をしました。音楽をいろいろ聴くようになって、ジャズにたどり着いた感じです。
− 歌手になりたい、というきっかけはありますか?
何か自分の気持ちを伝えたいというのがあって、あまり自分はしゃべるほうではないので、演奏とか歌を歌って、表現したいというのがありました。あとは、父が英語の教師で、英語のリズムに昔からなじんでいて、洋楽を聴くようになって、というのが大きいと思います。
− ジャズに関わってからは何年ぐらいですか?
19からレッスンを受け始めているので、8年になります。
− 現在はシティカレッジの何年生ですか?
学部の2年生にあたります。あと2年ありますけど、資金面が大変ですね(笑)とにかく近い将来の目標というのは、卒業するってことです。その後は1年間Practical Training Visaが出るので、ニューヨークにいながら、どこを活動の拠点とするか考えて生きたいと思います。
− ライブ活動を結構なさっていますよね?
毎年1回は日本でライブをしています。卒業後も年1、2回は日本でもやりたいし、ニューヨークか日本、どちらを拠点にするかというのはまだ考えていないですね。
− 学費についてですが、どのように準備しましたか?
6年間働いて貯めて、4年分の学費と1年分の生活費程度は準備できました。生活費に関しては苦しいですよ。アパートをシェアしたり、親にも工面してもらったりしながらやっています。
− 学校生活についてですが、やはりアメリカの大学はかなり宿題が多いですか?

そうですね、かなり多いです。編入なので、22単位は短大から移行できたのですが、あと100単位近くはこっちで取らないといけないですね。音楽学部の宿題は多いし、練習をしないといけないのがほとんどなので、学校が終わってから練習したり、学校の練習室でみんなでやったりしています。ボーカルのクラスは 1,2個で、後は理論中心なので、ピアノを触りつつ、頭で練習という感じです。
− 一般教養に関してはいかがですか?
専門外のことをやるので本当に大変です。今サマークラスで数学を取っているのですが、日本とやり方も違うし、テストとかちんぷんかんぷんで。大学レベルの数学で、分析みたいなこともしないといけないし、英語がずらずらと黒板に書いてあるので、国語みたい?な感じですね。語学力がもっとあれば、と思います。
− TOEFLはどのようにお勉強なさいましたか?
1 年半費やして勉強しました。ほんと思い出したくないぐらい悲惨な1年半でしたね。ライブの仕事もしつつ、学校にも通ったんですが、点数は入学基準ぎりぎりぐらいでしたね。そのときはとにかく基準値に達していればいいや、と思っていたんですが、あの時やっておけばいま苦労しなかったのに、って思います。
− 語学で苦労なさることありますか?
やっぱりさっきの数学とかでも一瞬のうちに言ってることを理解して、受け答えする、というのが難しい。音楽の面でも表面的にしか意味が理解できていないと、表現に厚みが出ませんし。大量に宿題があると、飛ばし読みして、大切なところだけ追っていくんですけど、短い文の中でも内容がぎっしりだと、どう深く問われているのかがわからなくなっちゃうんですよ。消化した上で、一呼吸おいてから答えを出すことならできるんですけど、キャッチボールのようには出てこないという感じです。1年経ってやっと慣れてきたところですね。私は語学学校とか一切行かなかったので。
− アメリカ入りして、すぐに大学の授業だったんですか?
そうなんです。だからクラスメイトとランチを食べに行っても話すスピードについていけず、答えようとしたらもう次の話題になっちゃっている、って言うような感じで、「かおるはなんて静かな子なんだ」って思われてましたね。
− 着いてすぐに学校だと、宿泊先探すのとか大変だったんではないですか?
宿泊先は、その前に観光ビザで3ヶ月滞在している間に見つけました。インターネットで見つけて、抑えておいたんです。インターネットとか、口コミとか、新聞なんかで物件自体はわりと見つかると思うんですが、ルームメイトの問題だとか、考えても見なかったようなことが起こるんで、なかなか気に入ったところを見つけるのは大変だと思います。
− もうすでに2、3回お引越しなさってるんでしたっけ?
そうですね。周りを見ていてもそのぐらいはしていますよね。それだけのエネルギーは蓄えておいたほうが良いと思います。(笑)
− いろいろと大変ですよね。ところで、学校ですが、どのように選ばれたんですか?
18 歳のときに歌の先生にニューヨークへ行った方がいい、と言われたときには、大学に行くつもりはなかったんです。最初は語学学校に行ければいいかなと思っていたんですが、シンガーの人に行くなら語学よりも、今からTOEFLの勉強だけやって、大学行った方がいい、ってアドバイスを受けて、その人もシティカレッジ卒業していたので。あと親友がちょうどシティカレッジに入って、「すごいいいよ」って聞いて、ここに決めたって感じですね。自分一人ではとてもじゃないけど、検索とかしてもCity Collgeにはたどり着けなかっただろうなと思います。
− 学校には満足してらっしゃいますか?
そうですね、もうちょっとボーカル系のクラスを作って欲しいと思いますけど、理論をやらないことには先に進めないので、楽器向けのカリキュラムもシンガーには難しいんですが、やっています。理論がシンガーにとってどれだけ必要なのか?って言われるとどうだろう?とも思うんですが、ジャズをやる上では、とてもいい学校だと思います。
− 先生はどのように見つけてらっしゃいますか?
ジャズのワークショップがあったり、公開レッスンに行ったりしています。個人レッスンも交渉したり、知り合いからの紹介や、お誘いで行きますかね。ほとんどが口コミなんですが、ホームページにもレッスンのお知らせがあったり、大学に来ている先生のプライベートレッスンを受けたりという感じですね。後は、別の学校のプライベートレッスンで、クラシックの声楽を勉強しています。
− クラシックとジャズ、どうして両方なさっているのですか?
まずボーカリストとしては、基本は発声になるんですね。ジャズとクラシックは別って言いますけど、ジャズであろうと、クラシックだろうと、ポップスだろうと、隔たりなく発声というのが基本なんです。どんな音楽も基本はクラシックからなので、クラシックをやっていると、音のクオリティといういのを求められるので、ちゃんと音が出ないと格好がつかない。まずクラシックの曲で発声をやって、声が出てきたらジャズを消化しながらやるというのが日々ですね。一日でも練習してないと忘れちゃっているので、毎日しないとなかなか声をキープしていくのが大変なんですよ。
− 授業はどのような感じで進められますか?
ボーカルは、アンサンブルとコーラスのクラスがあるんですが、みんなで歌う形ですね。ジャズシンガーというクラスはソロです。課題曲があって、練習しつつという形です。
− 先生はどのように教えてくれますか?
シティカレッジでも個人でクラシックボーカルをやっているのですが、その先生は、発声と発音について研究なさっている方で、主に歌よりも、発音を治してもらってます。日本人はまず発音を注意されるんですね。私も完璧に近くした上で歌いたいので、それには注意しています。シンガー向けの発音のクラスがあって、音声学をやるのですが、1つ1つの単語を研究していくので、とても役に立ちました。
− やはり日本人だと「r」や「th」の発音とか言われるんですか?
そればっかりじゃなく、数限りなく注意されますね。私なんかは逆に子供のころからやっていたので、「r」がまき気味で、too muchと注意されました。けどアメリカ人でも歌った後に、この発音が〜とか注意されているし、ヨーロッパ人でもそう。標準が何なのか、ちょっとわからないんですけど、とにかく発音は大変ですね。
− クラスの人数は何人程度ですか?
シンガーのクラスは定員があって、8、9名ですね。他のクラスは20人ぐらいかな。定員のあるクラスは登録をした後にオーディションがあるので、ドキドキものです
− お勉強している上で、日本と違う点ってなにかありますか?
日本で音大に行ったことがないのでわからないんですが、個人レッスンを受けていて思ったのが、日本だと、イタリア語、フランス語の歌はとにかく丁寧に‘発音する’と言うのに重点が置かれますが、アメリカの場合は、英語はもちろん、他の言語の曲でも意味をすごく問われます。一つ一つの意味をわかった上で歌いなさい、って。それは違うなと思いますね。英語の歌でも、より深く、なぜこの単語、この表現がここで出ているのか、わかって歌っているのか?と聞かれます。分からないというと、その場で教えてくれたり、勉強してきなさいといわれたり、まちまちですが、そう考えてみると日本のジャズシンガーというのがどこまで理解して歌っているのかな〜と思いますね。日本にもジャズの研究の本だとかスラングの本はありますけど、実際にこっちに来てみないとわからないことがたくさんあって、日本ではわからない、勉強できない部分がありますよね。それは日々の生活習慣だったり、習しだったりするわけですけど。生活してみて、肌で感じられるというのは大きいですね。
− そこまで理解を深められると、歌も以前とは違った感じになるのではないですか?
そうですね。日本に帰ってきたときに感じますね。ライブをやるとお客さんの反応も変わっていますし、アメリカでの勉強がこういうところで役立っているんだ、と実感できます。
− ニューヨークでもいろいろライブとかなさっていますよね?

今は話があるとお受けしている程度ですね。今年からはもうちょっと余裕が出てくるだろうから、やってみたいとは思っているんですけど。
− ニューヨークのクワイヤにも参加なさっているとか?
学校の先生が指揮をしているので、それのお誘いを受けて毎週1回やっています。
− 学校でのお友達はどんな方が多いですか?
留学生同士が多いですかね。アメリカ人の友達ももちろん多いのですが、シティカレッジはイスラエル人と日本人が多いのかな?助け合いの精神がみんなあってとてもいい雰囲気です。いろいろな国の人同士なので、価値観が違って、変なところで怒らせちゃうと収集が着かなくて大変ですよね。ラテン系はハッピーなときはいいけど、トラブルがあると大変なので、怒らせないようにするとか(笑)。日本人以外は結構時間にルーズだったりするので、そういう点では日本人同士が一番信用できます。
− 1日のスケジュールはどんな感じですか?
学校がばっちりある日は9時から夜の7時までとかですね。平均して、3,4コマ入っているので、だいたい毎日6時間弱ぐらいですね。
− 治安についてハーレムということでしたが、気をつけていることなどありますか?
ハーレムと言えども昼間は全く安全です。でも夜は、公園など人の少ないところまた慣れない場所には絶対に行かないことです。現に友人も襲われました。が、必要以上に怖がらず、でも隙は見せない、ということに気を付けています。
− 生活面や、お勉強の面で苦労したことって特にありますか?
毎日が苦労の連続です。。。いろいろあるんですけど、最近はアパートのガスが止まってしまって、大家にいっても管理人にいっても相手にされなくて、いまだにどうにもなっていないんですよね。泣き寝入りをする羽目になるかも。あとはハーレムに住んでいるんですが、新鮮な野菜が食べれない、とか?大阪出身なので、納豆とは縁遠い生活をしていたんですが、こっちに着てからは食べれるようになっちゃいました。食文化はいろんな国の人が着ているから見ていても面白いですよね。電話とか光熱費とか申し込みをしていても手続がうまくいかなかったりとか、勝手にプランを変更されていたりだとか、いろいろ苦労はあります。ほんと、いかに戦って、信念を曲げないかというのが日々の課題ですね。言われちゃうとそうかな〜って納得しちゃうんですけど、おかしい、と思ったことに関しては、貫き通していかないとダメだと実感しています。1年が過ぎるまではあまり文句とか言わないようにしていたんですが、最近は積極的に何でも言うようにしています。面白いことに、アメリカは自分が発言することによって、新しい道が見えてきたりするので、言った者勝ちというのがありますね。何でも口に出していわないと損です。一番悪いのは、ウダウダ考えて、抑えてしまうことですね。一番損しちゃうので。大学は人数が多いので、事務処理にすごい手間がかかるんですね。ミスとか結構あるので、そんなときは声を大にして、一つ一つ言っていかないといけないですね。
− 自分が留学して成長したと感じる瞬間ってありますか?
小さい問題にあたふたしなくなったというのがありますね。価値観の違うところに住んでいるので、一人一人の考えも違うし、ある程度聞き流しして、対応したりだとか、自分をしかり持っていないと、って言うのがあります。アメリカに来たことによって、自分が日本人だということを強く意識したし、日本人の良さを発見したというのもあります。ただ、良さは持ちつつ、アグレッシブになるところもないと、大変なので、日本人の規則正しいところとか、はんなりしたところ、周り家の気遣いも持っていこうと思うようになりました。
− 留学してよかった点は?
英語の歌やジャズが常に身近にあるというのがとてもいいです。例えば歌詞でMy love とかdarling というのが合って、日本にいるときは使わないじゃないですか。でもアメリカでは友人同士で言い合ったりとか、彼氏彼女の間で使ったりだとか、そういうのを聞くと歌詞の一つ一つの理解度が詳しくなりますよね。こういうときに使うんだとか、分かると常に英語の生活に溶け込んで言ってると思いますね。
あとはニューヨークは世界中から一流といわれるものや人が集まっているので、一流を安く見れたりというのがすごくいいです。友人の友人が有名な人だったりとか、刺激があって、それでまた頑張ろうと思えます。いろんな意味で自分が強くなってるかな〜と思います。道を切り開いていく大変さとかあるけれど、ふと振り返ってみると、一人で頑張ってきたんだ、と達成感、充実感がありますよね。日々の生活はいっぱいいっぱいなんだけど、これだけやったんだなと振り返ったときに達成感とか、良かった、っていう、日本では味わうことができなかった感触があります。勉強も量が半端じゃなくあって、泣きそうになりながらですけど、終わったときの達成感があるし、みんな学生同士助け合ってやっていこうっていう姿勢があってそれも楽しいし頑張ろうっていう気になります。音楽論で分からないことがあったら、わかる人がリーダーシップをとってみんなで課題に取り組んだりだとか、学校生活の醍醐味を感じますね。社会人だと個人個人のことになってくると思うんですけど、学生はもちろん個人は個人なんだけど、助け合いというのがとても良いと思います。とにかく達成感の一言に尽きますよね。
− これから留学を考えている方に一言どうぞ。
学校側との書類上でのトラブル、ビザ関係でのトラブル等、なかなか事が思うように進まず、ストレスを感じることは多々あります。そういう時の為に、時間と心の余裕も持つことです。それから、明確な目標を持つつことです。これさえあれば、どんなに大変な時でも道は見えてくるだろうと私は信じています。
− 今日はありがとうございました。後2年間でまたどれだけ東さんが活躍なさるのかが本当に楽しみです。頑張ってください!
東かおるさんのHPでは、現在の彼女の様子がわかります。是非チェックを!
http://www.kaorumusic.com
花岡由裕さん/合唱指揮/マネス音楽院/アメリカ・ニューヨーク
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

長野県出身。幼少からピアノを始める。国際基督教大学卒業。国際基督教大学在学中よりグリークラブ指揮者。ニューヨーク・マネス音楽院合唱指揮科在学中。
(インタビュー2005年10月)
ー 花岡さんの今までの簡単な経歴をご紹介頂けますか?
花岡 高校までは普通に地元の長野の高校を出て東京の国際基督教大学に進学したんです。その国際基督教大学というのが、いろいろな分野を幅広く勉強するところでした。人文科学学科の音楽学専攻でしたが、パフォーマンスクラスが無く楽典や歴史の勉強をしました。それと共に大学のグリークラブの指揮者を2年間勤めたんですね。それがきっかけになって本格的に音楽の指揮を勉強したくなって留学を目指しまし た。留学の準備を1年くらいしてから挑戦したんですけど、英語力が足りなくてその年は駄目になってしまいました。
ー それはご卒業後に?
花岡 卒業後です。その後、1度実家の長野県に戻りまして、知的障害者授産施設の事務員を1年弱勤めました。その時は音楽だけに興味があったわけではなくて、いろんな事をやってみたいと思っていました。障害者施設でずっと働いていくのも選択肢として考えていましたが、やっぱり音楽をもっと勉強して仕事として音楽をやっていきたいという思いが強くありました。それでその年の12月直前に仕事を辞めてアメリカに来たんです。渡米前に色々と調べたんですが、ニューヨークで合唱指揮を専門にやっている学校が音楽大学だと今僕が通っているマネス音楽院にしかなかったんです。それで様子を見るために訪れて雰囲気が良かったので受験の手続きをしに来たのが12月の頭です。それでオーディションが2月の終わりだったんですね。その間に幸運にもマネス音楽院でエクステンションディビジョンという一般公開している授業をとることができました。そこで必要な授業を受けながら英会話学校に行って、英語力の向上をはかりました。その結果オーディションで合格することができました。
ー 今は何年生ですか?
花岡 今は大学院の1年ですね。僕はちょっと変わった受け方をしたんです。最初は大学の3年に編入という形で。というのもちょっと英語力に不安があったものですから。大学院だとより高度な英語力が必要でしょう?特に指揮科だと人前で話さなければいけないので。とりあえず受かることが先決と思い、そういった選択をしました。けれども一度国際基督教大学で学士課程は取っているものですから2年大学に通って卒業する必要は無いと判断し、1年後大学院のほうに編入しました。
ー というとマネスのほうで勉強なさっているのは2年目ということですか?
花岡 そうですね。二年目です。
ー 今お話伺っていてオーディションを受けられたということですけれども、マネス音楽院のオーディションって難しそうだなと思ったんですが、これはどういうことを具体的に行うのですか?
花岡 まずオーディション自体が二日間に分かれています。一日目は基礎的な音楽能力を試されるんです。聴音や譜読み初見能力、ピアノ技術、音楽理論など、基本的なことがどれくらい出来るかを1日目に試験します。
ー セオリーは筆記でやるんですか?
花岡 セオリーは筆記ですね。あと英語のテストも一日目にありましたね。音楽の基礎用語をどれくらい英語で理解できているか等、授業をしていく上で差し支えの無い英語力があるかどうかを試されるんですよ。一日目で問題がなければ二日目の実演オーディションに進むことができます。僕の専攻は合唱指揮ですので、学校の合唱団の指揮を振りました。課題曲が3曲と自由曲が1曲です。20分間の中でその四曲を振って練習させるわけです。どのような指導をするか、音楽をちゃんと理解できているのか、リハーサルで何を達成できたかを三人の審査員によって審査されます。それとは別に担当教授と1対1で面接を行います。彼には色々な質問と要求をされましたね(笑)。「どういうことを考えながら振ったのか」、「この場面で音楽はどうなっているか」とか、分析もさせられました。「実際に声部を歌ってくれ。」と言われたり、「4パートあるうちの3パートをピアノで弾いた上で残りの1パートを歌いなさい。」とか。
ー 難しそうですね。
花岡 そうですね。難しかったですね。 それで会議を何度も開いた後、二日間の総合的な評価によって、合格者が決まるそうです。後日聞いた話ですが。
ー 実際同じ科で何人位いらっしゃるんですか?
花岡 大学と大学院合わせて5人ですね。中には2つ以上の専攻の人もいます。例えば歌と合唱指揮や作曲と合唱指揮などですね。
ー 花岡さんは指揮だけですか?
花岡 そうですね。僕は合唱指揮のみですね。
ー なるほど。こんな難しそうな試験をどういうふうに対策していたのですか?
花岡 先ほどお話しましたが、受験する前にエクステンションプログラムで勉強していたので、担当教授の指揮のレッスンを受けることが出来ていました。それでオーディションの課題曲は既に発表されていたので、その曲をレッスンに持っていくことができました。そして学校にいることで友達が出来てきたというのが大きかったですね。指揮は演奏者達といかにつながるかが重要ですから。他の受験生はまるっきり初めて会った人たちを教えなければいけないわけですからね。僕は彼らよりもリラックスして振ることができたのではないかと思っています。
ー 同じように指揮科に行きたいという人がいた場合は、そういうエクステンションプログラムを必ず受けたほうがいいということですかね?
花岡 必ずしもそうとは言えないとは思いますが、緊張して自分の力が出せないというのはマイナスですからね。人によってはその場に行って、すぐ雰囲気をつくれる人もいると思うんです。けれども事前に先生が音楽のどういうところを重要視するかとか、それで合唱団のレベルもどれくらいかということを分かっていたほうが準備はしやすいですよね。『オーディションの時にどういうことを言おうか』等、要するにプランが立てやすいわけですから。そういうプログラムがあればとってみることはプラスだと思います。
ー それはだいたい2ヶ月前に行かれて受けたという感じだったんですか?
花岡 そうですね。大体2ヵ月半くらい前に行って準備しました。実は大学滞在中に一度日本から受験したこともあったんですが、アメリカと日本ですから書類の手続きや郵送にものすごく時間がかかるんですよね。それでその年一次試験は受かったけれど、二次試験が受けれないといったハプニングがありました。オーディションの課題曲が何かという連絡を受けられず、郵便で送ってくれたんですがそれが着いたのがオーディションの3日前くらいでした。楽譜が手に入っていないくて準備もできていないのにアメリカに行くわけにはいかないじゃないですか。その後も連絡して「何とか受験日を変えて欲しい」と頼みましたが無理でした。それからやっぱり日本で準備して3日前くらいに行ってオーディションというのは日程的に辛いし、土地感も分からないし、英語も慣れないしというので精神的に疲れ果ててしまうと思うんですね。前年の経験もあったし早めに来てその土地に慣れて、英語も多少しゃべる習慣をつけて、心の準備をすませてから受けたかったので早めに来ることに決めました。
ー なるほど。それでばっちり成功したわけですね。
花岡 そうですね。心の準備と音楽の準備のおかげで緊張せずにすみました。
ー 日本でもずっと合唱団の指揮なさっていたり、小さい時からピアノをなさっていたのですか?
花岡 ピアノは小さい時から習っていました。それから歌にも興味があって。中学、高校時代にも合唱をやっていたんですよ。その時は指揮は振っていませんでしたが歌うことが好きでした。大学になって初めて指揮者をやって、はまっちゃいましたね。
ー どの辺が指揮をやっていて楽しいところですか?
花岡 色々な楽しみや喜びがあると思うんです。例えば練習をやっていてみんなと一体になって音楽をしていると思える瞬間があるんですよ。合唱団の全体対指揮者の関係ではなくて、指揮者と歌い手一人一人の関係と、歌い手同士の1対1の関係を感じられるような。それぞれ一人一人が表現しあって音楽がぶつかりあって本当に大きな渦ができる。歌うことを彼らがとても楽しんでいるのが分かる。そうするとどんどん音楽がいい意味で変わっていくのが分かりますね。それから僕自身、指揮を振っていてかなり快感ですね。大学のグリークラブでは春と秋、毎年2回のペースでコンサートを行っていたんですが、秋のコンサートは有料 だったんですよ。たかだか400円か500円位の入場料でしたが、ホールが満員になった時があって。
ー すごいですね
花岡 600人くらいお客さんが入ってくれたことがあったんです。人数が入ってくれたことだけじゃなくて、その時のコンサートでは練習もたくさんしたおかげもあって、音楽を心から楽しめたんです。コンサートまで沢山練習をしていくと、どうしても『ここではこうしなきゃ。』というのが出てくると思うんですけど、そういう限られた音楽を作り出そうとするんじゃなくて、そこにいる観客の皆さんと歌い手たちと一緒に新しい音楽というかをつくりだせた気がしたんです。音楽というのはその場、その場、その時、その時でしか出来ないものなんだと深く感じました。それですべてのステージが終わってアンコールが終わったあとに、観客の皆さんがものすごい拍手をして下さいました。本当は2曲でアンコールをやめるはずだったんですけど、急遽もう一曲やろうということになって、予定を無視してやってしまいました(笑)そういったことを含めてみんなの気持ちが高まって、音楽を中心にホールが一体化した感覚を覚えました。それこそ快感としかいいようのないような。指揮者が主役というわけではないんだけれども、指揮者は歌い手と観客の間にいるじゃないですか。
ー そうですね。
花岡 だからその雰囲気に包まれているのが一番分かる場所だったと思うんですよね。歌い手たちの表情を見るのも楽しかったし。お客さんの顔を指揮が終わって振り向いてみたときに本当に喜んでくれているお客様とか、必死に拍手をしてくれているお客様とかを見て『これ以上の幸せはないな。』と思いました。『ああ、これはやめられないな。この感動を何度もというかもう一度味わいたい。』と思って。
ー 音楽の醍醐味を知ったのですね?
花岡 そうですね。コンサートを通じて、日本ではクラシック音楽というと壁があるというか敷居が高いといわれていて、僕もそう思っていたんですが、本当はとても近くにあるんじゃないかと思いなおすことができました。どんな人にも来てもらって楽しんでいってもらえるよう音楽をもっともっとしていきたいと思ったし、音楽の敷居を下げてもっともっといろんな人に音楽の喜びを知って欲しいなと。特に歌の場合はほとんど誰もが持っているじゃないですか、声って。だからよりたくさんの人に触れて、その喜びを伝えることが出来るかなと思って本格的に勉強しようと思ったわけです。
ー 実際に勉強なさって苦労する点とか、難しいなという事はやっぱりあるものですか?
花岡 そうですね。やっぱりアメリカで勉強しているので最初は言語の問題が難しくて。「音楽には言葉はいらない。」といったこともよく聞きますが、やはり指揮者として練習を進めなきゃいけなかったり、歌い手たちと良い関係性をつくりには言葉は必然なものですからね。そのコミュニケーションがうまくいかなくて歯がゆい思いをした時がありました。それから指揮を振りながら、どうしても指揮が音楽と隔離して数学のようなものになってしまうと感じることがあるんです。要するに機械的になってしまって、どうしても自分の感情と結びつかないというか。拍や各パートの入り、強弱ははっきり振れていて分かりやすくても、音楽的には全然表現出来ていなかったり。いかに自分の腕、顔、全身を使って音楽を表すか。もちろんそれだけじゃいけないんですけれども、それが出なかったら指揮を人間がやっている意味があまり無いじゃないですか。僕がやっている意味というか。ただの拍とりに終始するだけだとむしろ指揮者がいないほうがいいことも出てきますし。指揮者としていかに演奏者達に影響を与えて彼らから音楽を引き出すかというのは、ずっとこれからも試行錯誤していくのだろうなと思います。それから、授業について。普通の授業は英語が分かってくるにつれてだいぶ楽になってきたんですけれども、理論の授業で日本ではあまり勉強されていない対位法が必修なんですね。ルネサンス時代やバロックなどの音楽は主にこの対位法という理論をもとに書かれていたんですけども、この勉強を一から始めたので、周りの生徒に追いつくのが大変でしたね。僕は日本で音大を出ていないので基本的な能力が他の人より劣っていたと思うんです。その能力をまず上げていかなければと思い、最初の1年間は基礎能力の向上と英語力の向上を中心にやって、何とか授業についていけるという形でしね。でもやっぱり毎日続けていると効果は出てくるもので、だんだん最初は追いつこうとしていたものが、いつのまにか他の人よりうまく出来ていたりするんです。そうすると毎日続けることがすでに習慣になっているから、それからは余裕をもって授業にのぞむことができています。事実、プロの音楽家の方たちは毎日10 時間以上練習をしているそうですから、まだまだ僕なんて甘いのかもしれませんが。
ー 練習というのは具体的にはどういうことをなさるんですか?お家で鏡を見ながらとか?

花岡 指揮の練習はですね。まず振る音楽の分析をするんですけれども、その曲が例えば合唱曲だったら歌詞がついているじゃないですか。基本的にその歌詞の読み方と歌詞の意味を調べて理解して、それがどういうふうに音楽と結びついているかを楽譜から読み取る作業をします。作曲家の意図というか、彼らがどういうふうに歌詞を解釈して音楽に表現しているか。それから楽曲分析ですね。どんなハーモニーが使われているか、どういう和声進行になっているか、どの旋律が重要なのか、どこで場面転換が行われるか等々。そういう分析をして、それから各声部を良く知るためにそれぞれの声部を歌ったり、ある声部を歌いながら他のパートをピアノで弾く練習をします。だからまずコーラスの練習に持っていく前にもうすでに音楽を誰よりも知っていなければいけません。練習のときにはすでに頭の中で音楽が鳴っていて、間違っている部分を指摘したり、自分がどういう音楽をつくっていきたいのかを伝えていくわけです。あと担当教授との個人レッスンでは教授がピアノを弾いてくれて、それを指揮しますね。それで先生がアドバイスをくれるわけです。自分では気付けなかった音楽的な解釈を気付かせてくれたりします。僕の担当教授は生徒自身に良く考えさせる人で、よく「何を考えて振るのか」とか、「何を感じるのか」という指摘をうけます。そのおかげで合唱団の前で振る時には自分らしさ、自分の音楽を表現できるようになってきます。
ー 本当に下準備がすごく大事ということですね。合唱団の人と一緒にやる時というのは学校の方ですか?
花岡 毎年オーディションが行われて、学校の歌専攻の生徒たちで合唱団を形成しています。各パート4人程ですから全体で15人くらいですかね。合唱団の規模としては決して 大きくないんですが、各歌い手が1人1人プロになりたいと思ってやっているから、すぐにうまくなりますね。時間があまりないのですが、練習のつけ方しだいで、あっという間に曲ができたりもするので、そこは 指揮者の腕の見せ所といったところですかね。
ー 曲はご自分で選ぶのですか?
花岡 昨年は自分で選べたんですが、今年は教授が決めましたね。いくつか曲をピックアップして、その中で自分がこれを振りたいというのは一応希望はとったのですが、他の生徒とやりたい曲がかぶってしまって、希望通りにはいきませんでしたね。
ー 今はどんな歌を勉強していらっしゃるんですか?
花岡 今は“グリーンスリーヴス”で有名なイギリスの作曲家ヴォーン・ウィリアムスの曲や、ヴォルフという歌曲を沢山作曲したドイツの作曲家、モンテヴェルディというイタリアバロック時代の作曲家などの曲を勉強しています。時代がかたよらないように、言語がかたよらないように教授が選んだようです。
ー なるほど。時代が違うと指揮の仕方も変わってくるものなのですか?
花岡 そうですね。やっぱり音楽が違うし、何を重要視するかも変わってきますよね。時代によって、さまざまな演奏法のきまりもあるのでそれも勉強しなければいけません。
ー いろいろな言葉の曲をなさると、当然語学も勉強しなきゃいけないのでしょうね?
花岡 そうですね。合唱指揮者は当然必要になってきます。言語を知らないと指導できませんからね。ただ意味を知るだけでなくて、その国の言語独自の響きをしることも重要です。言葉と音が一致して曲が成り立っているわけだから、言語の響きを知らないと作曲家の意図が全然つかめなかったりするんですね。自分でしゃべって聞くからこそ深い意味があると思います。
ー 大変ですね。
花岡 そうですね。といっても何十もの言語を勉強するわけではないので。音楽を勉強する上で必須となっているのが、ラテン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、英語くらいですから。ドイツ語とイタリア語が読むのは比較的楽ですが、フランス語は見ただけでは読めませんからね。必死で勉強しなきゃません(笑)。それでも言語というのは決して暗号ではなくて、音楽や文化と結びついているわけですからそれを知ることが面白いですね。そういう意味ではそれほど負担に感じたりはしませんね。
ー 今ニューヨークにいらっしゃるわけですけども、マネスしか合唱指揮科はないということだったのですけれど、他の国は全く考えなかったんですか?
花岡 そうですね。ドイツとかフランスとかやっぱりヨーロッパが中心じゃないですか、クラッシック音楽は。そこへの留学も考えないことは無かったんですよ。学費はヨーロッパのほうが断然安いですしね。ただなぜアメリカを選んだかと言うと一つは言語の問題ですね。ヨーロッパに行くと英語が通じるとしても当然現地の言葉を勉強しなきゃいけないから、そうなると最初の1年間は言語を勉強することで手いっぱいになって音楽に身が入らないのではないかと思ったことがあります。そうすると留学滞在期間も長くなってしまい、その分負担がかかるのでは、と考えました。最近クラッシック音楽を勉強するのも中心、つまりはいい先生がヨーロッパからアメリカに移ってきている、という噂を聞いていたせいもあります。それからヨーロッパというとどうしても内的、国にもよると思うんですけど、その国の文化の伝統を重要にして古来のものをというようなイメージが強かったんですよ。けれどアメリカ、特にニューヨークはいろんな文化や民族が交わっている所ですし、いろんなものが入ってきているし。音楽で言ってもクラッシックだけではなくて、ジャズにしてもロックにしても沢山のものが集まっている。音楽の勉強をする事というのは、人間を勉強することに等しいというか、音楽は人間が作ったものだし、いろんな人達と触れ合うことで音楽を勉強し解釈していく上でここは自分の感性を磨くというか、人間性を磨くうえでもいい環境だと思ったんです。といってもクラシック音楽が決して軽んじていられているわけでもない。カーネギーホール、ジュリアード音楽院等、世界のトップの音楽ホールや音楽大学がニューヨークにあって、チャンスも十分この国では与えられているんです。学業的な面で言っても、アカデミックな勉学、つまり基本的な音楽を勉強するのはアメリカはしっかりしています。大学の体制がしっかりしている。ヨーロッパだと技術的で音楽的なことは学ぶけれども、基礎的な勉強がアメリカほど体系化されてはいないと思うんです。僕は音楽の基礎的な能力のレベルアップとより多くの知識を得ることが必要だと思ったので、全体的に考えてアメリカがベストかなと思いました。
ー 実際ベストだったということですか?
花岡 他の国に行った事がないので比べようがないですけども、そうですね。新しい音楽もここでは作られているし、数多くの素晴らしい演奏会に行くことも出来るし、いろんな人がいるし。そういった意味で本当に刺激になっていますね、ここにいることは。ニューヨークはみんながI,I,Iと言います。自分が出て行かないとどうにもならないというか。たくさんの人の中で自己主張をしていかないと埋もれてしまいますから。他人を思いやる気持ちも必要だけれども、この中でどう自分をアピールしていくかをよく考えさせられます。そうしないとすぐに他から遅れをとっていってしまう所ですから。自分の考え方や行動が、ここへ来て変わってきたなと感じます。
ー 最初に皆さんにお話を伺うと、最初の3ヶ月とか4ヶ月は苦しんだというふうに伺うんですけど、そういうのを乗り越えて成長したという感じがご自分の中でもありますか? それとも、そんなに最初から苦労してなかったですか?
花岡 最初ニューヨークに来た時に知り合いがほとんどいなかったんです。知り合いにこっちの人を紹介してもらったけれど言語は思うように聞き取れないし通じないし、でも自分で知り合いを作ってかなきゃいけなかったんです。それでも英語に慣れるために、日本語をしゃべらない環境をつくりました。アメリカ人のみの合唱団に参加したり。最初はまあ孤独に感じて寂しく感じることもありましたけれども。やっぱりそういった期間は必要だったと思いますね。それでも自分が好きなことをやっていたから辛さよりも楽しさや希望のほうが大きかった気がしますね。僕は日本にいたときは親にしろ友達にしろ頼りすぎていたきらいがあったから、良い機会にもなりましたね。自分ひとりで動いて生活して誰も頼る人がいない。自分の新しい一面を知れて、充実した毎日を過ごしているなと自覚できましたね。最初の3ヶ月間くらいは特に。
ー 今はすっかりそちらの生活にもなれて楽しくやっているのですね。
花岡 そうですね。コミュニケーションがだいぶ普通に出来るようになってきたので、日本での学生時代のように楽しんでいますね。それにアメリカの学生のほうがストレートに物を言うのでそれが心地よかったりします。建前がなく交流できることが嬉しかったですね。
ー 学校の授業はだいたい週に何回くらい行かれているのですか?
花岡 月曜日から金曜日までの五日間ですね。
ー 日本の学校みたいに朝から晩まで?
花岡 そんなことはなくて、日によっては2時間程で授業が終わる日もありますし、朝九時から五時まで立て続けに授業という日があったり。日本の大学と比べたら少ないかもしれません。人によってもちろん違うんですが僕の友達は1週間に3日間くらいしか来ないという人もいるし。
ー そうすると、宿題が結構あるのですか?

花岡 宿題は結構ありますね。こちらは日本とは比べ物にならないくらい(笑)。毎日の勉強の半分くらいが宿題。ピアノの練習や指揮の準備をもっと練習したいんだけれども、宿題で結構時間がたってしまったりするんですよ。本当毎日毎日宿題におわれているというのが正直なところです。
ー それはまったく譜読みなんかとは別な宿題が出ているのですよね?
花岡 そうですね。理論の宿題や分析など様々ですね。それから譜読みの授業自体もあるんですよ。オーケストラや弦楽四重奏等の楽譜を見てそれをピアノで弾くんですがそれもかなり準備に時間が必要ですね。
ー じゃ結構ピアノにむかっている時間が多い?
花岡 そうですね。多いです。ピアノと楽譜がほとんどですね。
ー それはご自宅ですか?
花岡 学校でやることが多いですね。学校にはピアノがおいてある練習室がかなりの数ありますしね。
ー 一日何時間くらいピアノを弾いているんですか?
花岡 それも日によるんですけど3時間から8時間くらいまで。
ー 8時間!
花岡 それも授業があるとやっぱりそんなに時間が取れないことがあるのですが、休日はお昼に学校に行って学校が閉まる9時半〜10時半までとか。
ー 好きじゃないと出来ないですね。
花岡 そうですね。でも、ずっとやっていると疲れるので、休憩を入れながらやっていますね。まあ基本的には 楽しいからやっているんですよ。
ー 今学校以外にどこか合唱団の指揮をなさったりしているのですか?
花岡 僕の指揮の先生が振っている合唱団があるんですけれども、そこで歌い手として参加していて、たまに練習の時に「振ってみろ」と言われることはあります。彼はNY州の隣のニュージャージー州でも、合唱団を一つ持っているんですが、そこでも振らせてくれるようです。ただし自動的にコンサートで歌わなければいけないんですが。
ー 交換条件が。
花岡 ギブアンドテイクですね。
ー 来年2年生ですよね。その後はどういうふうに考えていらっしゃるのですか?
花岡 そうですね。日本に戻ろうと思っています。日本にはアマチュア合唱団が沢山ありますしね。東京と地元の長野の合唱団のいくつかを振れたらいいなと考えています。僕が日本でお世話になっていた指揮の先生が、「日本には沢山の児童合唱団や大学の合唱団、アマチュア合唱団はあるけれども、その橋渡しがない。小さい時からずっと音楽を勉強していけるような学校をつくりたい。」とおっしゃっていて、それのお手伝いが出来たらいいなと思います。
ー 面白そうですね。
花岡 そうですね。すでに長野県では何人かの知り合いと合唱団を作る話をすすめています。スケジュールやボイストレーナーの依頼等着々と準備はすすんでいます。僕が帰ったらすぐに合唱団が始動できるようになっています。最初は合唱団を振る機会が少ないかもしれませんが、いろんな指揮者の先生や合唱団を訪ねて団員として歌いながら下振りを続けていきたいと思います。その下振りによって認められていけるためにも今頑張らなくてはと思ってます。
ー 遠い将来なんだけれども近い将来みたいにいろいろ決まっていらっしゃいますね。
花岡 そうですね。でも見えない部分の方が多いので不安もありますが。
ー これからニューヨークにいられる間に更にどういうことを勉強していきたいですか?
花岡 出来るだけ多くの音楽にふれたいですね。アメリカは作曲家も沢山いますし、現代の曲がかなり演奏されているんですよ。フランスも多いと聞きますが現代曲が世界で一番演奏されているのはアメリカだと思うので、沢山聴いたり歌ったりしていきたいですね。それをやがては日本にも取り入れていきたいという思いもあります。今の担当教授が現代曲もけっこう振るのでレッスンでも教わっていきたいですね。現代曲以外でも絶えず音楽に触れる機会を作って自分の基礎能力を上げなきゃいけないし、自分のスタイル、得意分野を確立してそれを日本に戻ったときに売りとしていけるくらいにはしたいですね。
ー 毎日学ぶことが多いですよね。
花岡 そうですね。音楽だけでなくてアメリカにいること自体も勉強になっていますよ。
ー 日本で振っているときとアメリカで振っているときとやっぱり感覚として違うものですか?
花岡 そうですね。アメリカの演奏者は個が強い印象をうけますね。だから最初はあまりまとまらないんですよ。ただそのほうが面白い音楽が最終的に出来るのではないかなという感覚がしますね。日本の合唱団は割と最初にパッとまとまるんですけど、そこからがなかなかうまくいかない。演奏者それぞれが表現するまでいってないというか。枠組みを最初に作っちゃう気がするんです。こっちは枠なんてなくて、お互いがぶつかりあいながら音楽を作っていくのが振っていて楽しいですね。苦労もしますけど。
ー どういう点で苦労しますか?
花岡 そうですね。個が強くてぶつかったままというのは困りますね。歩み寄りがない場合。それぞれが自分の声を出そうとするから、音色がまとまらなかったりするんですよね。もちろん一人一人個性がある声でいいんですけれども、それをどう合唱団として、音楽として一つの方向性に持っていくか。やっぱり合唱で歌うのはソロで歌うのとはまったく違いますからね。個を尊重してそれぞれの歌い手を納得させて、それでも全体としてはまとまるようにうまく持っていくテクニックがいるんですよね。
ー すごい大変ですね。
花岡 でもやりがいはありますね。
ー 逆に日本だったら没個性というか一人一人が出てこないわけじゃないですか。それをどうするかというのがあるのですか? 例えば、もっと小さくまとまらずに自由にやりなさい見たいな。
花岡 そういうことは直接的でなくても言っていかなければと思いますね。日本では合唱団という大きな団体にいるとどうしても自分の存在が埋もれてしまう風に考えがちなので。僕が日本の大学時代、指揮者の時によくやっていたのは、アンサンブルですね。各パート二人くらいの少人数で歌わせていたりしたんです。そうすると自分がどう歌いたい、表現したいという事もはっきりしてきます。そのあと合唱に戻ると全体がかわってくるんですね。合唱団が50人いたとして、合唱というのは50分の1の感覚じゃいけないと思うんですよね。むしろ1×50で1の可能性がいっぱいあって、いろんな表現があって、答えが100にも 200にもなるようなそういうものを作っていかなきゃいけないと思います。
ー 何か面白そうなんだけど大変そうっていうのが伺っていて思うんですけど。でもやりがいはありそうですね。
花岡 そうですね。それをやりとげてコンサートで指揮を振り終わった時とか、本当に興奮でもう心臓の鼓動が聞こえるんですよね。快感ですよ。
ー 凄い。楽しそう。
花岡 はい。やりますか(笑)
ー あがり症なんでちょっと難しいと思います。
花岡 それの克服にもなりますよ(笑)
ー 今後留学を考えている方に花岡さんの方からアドバイスや気をつけたほうがいいと思うことがあればお願いできますか?
花岡 そうですね。まず言いたいのは「やりたいなら、とりあえずやってみろ。」ということですね。物事って何でも実際にやってみないと本当にどうなるかは分からないですから。やらないで後悔するより、やって後悔したほうがずっと良いと僕は思います。僕もアメリカに来て、自分が何が足りないかが分かりました。それはまず動いた、アメリカに来たから見えてきた部分なんですよ。悩んでやらないで失敗しないよりやって失敗したほうが自分の糧になります。失敗したとしてもそれが次の成功につながります。僕も受験を失敗していますが、だからこそ学べたものが非常に大きかったです。最初は曖昧な道でも進んでみて、後でその道を進むためには何をどういうふうにやる必要があるか、その解決法を考察して作っていけばいい訳ですから。大きな目標、やりたいことに向かって恐がらずまずトライしていって欲しいということかな。英語にしてもやっぱり日本で勉強するのと、アメリカで勉強するのでは全然違いますからね。日々の生活の中で使わないと英語はなかなか身につかないですからね。日本のテストで高い点が取れても、こっちでは通用しないことばかりです。なぜなら日本の英語は日常では死んでいる英語だからです。最初が辛いとくじけてしまいそうになったりするかもしれないけれども,そういう時こそ、後になってあの時があったからと思えるはずです。死ぬほど勉強するとか死ぬほど辛いという時間こそ大切な時間だったと。だからもし本当に希望してやりたいと思うんだったら、ちょっとの事じゃ諦めないで欲しいですね。
ー なるほど。熱いですね(笑)
花岡 あと物事(手続き等)は何でも早め早めにやったほうがいいです。とってつけたようですが。
ー 今日は熱いお話をたくさんしていただいて、どうもありがとうございました。
柴田昌宜さん/指揮/モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミー/オーストリア・ザルツブルグ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

柴田昌宜さんプロフィール
大阪音楽大学卒業(トランペット専攻)同大学専攻科修了(指揮専攻)。2003年陸上自衛隊に一般幹部候補生(指揮者)として入隊。中央音楽隊に配属され全国音楽隊員に対する教育を担当する。2005年より東部方面音楽隊音楽班長を務め、国家的な式典や各種の演奏会を指揮する。この間モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミーに参加してディプロマを取得。2007年8月、第1混成団音楽隊隊長(那覇)に着任し、沖縄県下全域において演奏活動の任に当たっている。
― 現在までの略歴を教えて下さい。
柴田 大阪音大にトランペット専攻で入りました。その後、専攻科の指揮専攻に進み、卒業後、陸上自衛隊に指揮者として入隊しました。中央音楽隊から東部方面音楽隊を経て、ザルツブルグの講習会から帰国後の8月から沖縄の第一混成団音楽隊隊長として、沖縄に赴任しています。
― この講習会に参加されたきっかけを教えてください。
柴田 もともと、海外のマスタークラスに参加してみたいという希望がありまして、色々と探してはいたのです。以前から、モーツァルテウム音楽院夏期国際音楽アカデミーか、ウィーン国立音大の講習会に行ってみたかったのですが、今年8月に転勤することが決まりまして、7月中に参加できるものをと探したら、モーツァルテウムが時期的に合っていました。
― どのような理由で今回の講習会をお選びになったのですか?
柴田 やはりオーストリアということと、先生ですね。
― 先生は以前からご存知だったのですか?
柴田 ペーター・ギュルケという有名な指揮者で、ベートーベンのシンフォニーなどを校訂している人です。ペーター・ギュルケ版というのが出ているくらい、すごい権威者なので、是非にとは思っていました。

― レッスンの雰囲気はいかがでしたか?
柴田 かなり丁寧でした。日本人みたいでした。本当に基礎から細かく教えていただけました。
― 振り方に関することもありましたか?
柴田 そうですね、振り方に関することもありましたし、音楽的な作り方に関することもかなり緻密に指導されました。
― 特に印象に残っている事などありますか?
柴田 1番衝撃だったのは、「振りすぎだ」と言われたことでした。こちらからしたら、全部に指示を出して、丁寧に振っているつもりだったのですが、先生は、「これでは音楽の流れを止めてしまう」と言われました。
― それを受けて何か自分の中で変わられたことはあります?
柴田 そうですね、もちろん、音楽の流れを重視するようになりました。
― レッスンは何語で受講されましたか?
柴田 オーケストラがドイツ・カンマー・アカデミーというオケでしたので、先生はドイツ語と英語を使い分けてらっしゃいました。僕に対しては英語で指導してくださいました。
― 事前に語学の勉強はされていかれましたか?
柴田 いえ、まったくして行きませんでした。
― 英語がお得意なのですか?
柴田 得意というほどではありませんが、まったく分からないということもありません。

― 先生と言葉が噛み合わなくて不便に感じるところはありませんでしたか?
柴田 やはり伝わりにくいことはありました。これはたまたまなのですが、オーケストラのヴィオラ奏者に日本の方がいらっしゃったんですよ。それで、分かりにくい時はその方が間に入ってくれました。
― レッスンは何時くらいから始まりましたか?
柴田 だいたい朝の10時くらいから、休憩が途中1時間半から2時間くらいあって、5時くらいまで毎日やっていましたね。
― レッスンはどういう形ですか?
柴田 受講生は僕を含めて全部で6人でした。最初の1日はピアニストが2人入って先生とレッスンを行いました。2日目からは、オーケストラが3,40名くらい入って、あとは先生と受講生という感じでレッスンが行われました。
― その中で指導してもらう受講生が入れ替わるのですか?
柴田 人によって時間は多かったり、少なかったりしたのですが、僕はかなり多かったですね。午前と午後30分ずつくらいは振らせてもらいました。
― それは期待されていた、ということでしょうか?
柴田 どうでしょう(笑)。まぁ、何かあったかもしれないですけれど。課題曲にストラヴィンスキーの「ダンバートン・オクス」があって、僕はよく振らせてもらいましたが、受講生のなかにはまったく指揮をさせてもらえない人もいました。曲によって受講生を振り分けていたみたいです。簡単な曲しか、させてもらえない人もいました。
― 生徒さんのレベルによって曲を分けていたということでしょうか。
柴田 かもしれないですね。

― 受講生の中に日本人はいましたか?
柴田 いませんでした。僕の他は全部西洋人で、イタリアから2人と、オランダ、オーストリア、南アフリカから一人ずつ来ていました。
― 通訳はつけましたか?
柴田 手続きの時は通訳がいましたが、レッスンには入ってもらっていません。
― 手続きの時の通訳はいかがでしたか?
柴田 とてもよくしてもらいました。
― 練習はどのくらいできましたか?
柴田 指揮は練習というのがほとんどできないですから、宿泊先に帰って楽譜をずっと見ているような状況ですね。結構毎日のチェックが大変でした。復習ですね。次の日、今日教えてもらったことを踏まえてオーケストラを目の前にして振らないといけないので、勉強はかなりしました。
― それでは、レッスン以外の時間はほとんどを勉強に費やしていたのですか?
柴田 レッスンが終わったあとはオーケストラのメンバーや、ほかの受講者と食事に行ったりしましたので、勉強は朝5時に起きてやっていました。
― 交流を深められたのですね。
柴田 そうですね、他のコースと比べても交流はあったほうだと思います。

― 受講生によるコンサートは出演されましたか?
柴田 僕は一週間しかいなかったので最終日になったのですが、6人全員指揮をしました。ただ、曲の難易度だったり、長さはそれぞれ違っていて、だいたい順当な感じでした。
― 柴田さんは、どんな曲を振ったのですか?
柴田 僕はストラヴィンスキーをふらせてもらいました。
― 難しいストラヴィンスキーを!
柴田 はい、かなり難しかったのですけれど、頑張ってふりました。
― コンサートで指揮をされていかがでしたか?
柴田 オーケストラが来ている事もあって、かなりお客さんは来てくれていました。200人くらい入ったと思います。学校関係者もいたのですが、ザルツブルグの地元の人が多い感じでした。
― 地元に開かれたコンサートだったんですね。
柴田 そうですね。受講者コンサートの中でも目玉になっているようでした。プロのオーケストラと若い指揮者という関係で、ポスターにも出ていたくらいでした。
― 宿泊先の学生寮はいかがでしたか?
柴田 まぁまぁ、思ったよりは良かったです(笑)。1Kくらいで、バスタブはありませんでしたけど、シャワーが付いていました。新しくはありませんでしたが、普通に清潔でした。
― 建物は、オーストリアの伝統的な感じですか?
柴田 いえ、全然。四角い感じでした(笑)。

― 外食はされましたか?
柴田 はい、オーケストラのメンバー達とよく行きました。バーベキューをしてくれたんですよ。そういうのにも行ったりして面白かったですね。
― 外食はおいくらくらいでしたか?
柴田 旧市街の観光地の真ん中だと結構かかりましたね。食べて、ワインでも飲んだら、12,3ユーロくらい(約2,000円)。でも、ザルツブルグでも観光地じゃなく郊外に行けば、8,9ユーロくらい(約1,400円)ですみました。
― 近くにスーパーとかはありましたか?
柴田 モーツァルテウムは川を渡ったところにスーパーがありましたし、学生寮の近くにもかなり大きなスーパーがありました。ただ、平日の昼間しか開いてないので、僕はほとんど活用できませんでした。ほとんど外食でした。だから(渡航費用を)ぎりぎりで行ったら大変だと思います。
― 外食に結構かかりましたか?
柴田 そうですね、かかった方だと思います。
― 講習会と宿泊先はどういう風に行き来されましたか?
柴田 だいたいバスですね。
― どのくらいかかりましたか?
柴田 20分くらいだったと思います。
― バスが遅れたりとかはありましたか?
柴田 ほとんど定時だったと思います。
― スリなどの被害にあわれることはなかったですか?
柴田 何もありませんでした。ウィーンでも、ザルツブルグでも。

― 不審な人は見ましたか?
柴田 見る限りはなかったですね。
― 海外の人々とうまく付き合うコツは何かありますか?
柴田 自分の意見をはっきり言うことですね。色々と、「どう思う?」と聞かれることが多いんです。最初はちょっと少し下に見ているみたい
な感じがありましたね。でもそれが、僕が指揮をふって、音楽的な何かが伝わった時、なくなったように感じました。そういう意味では音楽で通じるというのは結構あるので、認め合うのが一番かな、と思いますね。
― 認め合えるものを持っていらっしゃるんですね(笑)。
柴田 それは分からないですけど(笑)。でも表現は結構できたかなというのはあります。音楽で何もなかったら、それからは相手にしない、という手もあると思います。
― 認め合うところは認め合うという方々がたくさんいらっしゃるんですね。
柴田 そうですね、やっぱり音楽で繋がっているなと思いますね。
― 今回講習会に参加して良かったと思われますか?
柴田 いやもう、かなり良かったですね。海外の方々とばかり話をして、日本語を話す機会がほとんどないくらいだったので、それぞれの国民性がよく分かりました。音楽をやる姿勢は一緒だな、自分がやっていることは間違っていないという再確認になりました。一週間はちょっと短いかな、とは思いました。しかし、仕事をしている関係で長期留学をするのは難しいため、休みを見つけてこうやって短期で講習会に行くしかないので、その分集中してできました。体力的にはきつかったですけれど、帰りは涙が止まりませんでしたね。参加できたことが嬉しくて。最後の日、受講者コンサートのあとに、70人、80人くらい集まった大宴会があったんですよ。とても楽しかったです。学校の先生とか、ミューレンバッハも来ました。オケのメンバーやヨーロッパの方々ともメールアドレス交換したりしました。人間的な付き合いが繋がって、本当に良かったですね。
― 講習会で自分が変わったとか、人間的に成長したな、と思うことはありますか?
柴田 音楽に対する自分の気持ち、取り組み方をまだ完璧に掴んだわけじゃなく、漠然とした感じではありますけれども、確立できたところはありますね。自分がやっていることが、本当に西洋でも同じようにやっているのか、日本でだけこうじゃないのか、と思っていたんです。指揮だったら、斉藤指揮法というのが日本ではあるんですが、それだけじゃ駄目だという事も分かりました。ひとつの僕の音楽性の指針にはなりました。
― 留学前にしっかりやっておけば良かった、ということはありますか?
柴田 曲ですね。もっとしっかりやっておけば良かったと思いました。留学する前は転勤前でばたばたしていて、なかなか楽譜を見る時間がなかったので。
― 日本とオーストリアで大きく違う点はありますか?
柴田 オーストリアはかなりルーズですね。サービスやテンポが。でも自分がそのテンポに入れば何のことはなかった。逆に気持ちにゆとりが出たりしました。

― 今後留学する人に何かアドバイスがありましたらお願いします。
柴田 悩んでいる人がいたら、無理してでも行った方がいいと思います。資金的にも無理してでも行った方が何かに繋がると思います。絶対に。二の足を踏んでいるとしたら、行った方がいい。でも、漠然とただ海外に行けば何かある、という人は行っても仕方がないと思います。ある程度、自分が悩んでいることや目標や目的がある人でないと参加する意味がないと思います。でも、きちんと目標がある人が行ったら、必ず何かがあると思います。
― 今後の活動の予定はいかがですか?
柴田 自衛隊での活動が基本にあります。吹奏楽の中でやることになるのですが、それはオーケストラから派生したものでもありますから、指揮というものは共通です。今回勉強したことを十分活かして、自衛隊の演奏を充実させていこうと思っています。自分のためだけではなく、自衛隊や地域のためにも、もっと人を感動させられるような音楽を作っていければと思います。
― 長い間ありがとうございました。
畑真由美さん/声楽/ロンバルディア声楽マスタークラス/イタリア・ミラノ近郊
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

畑真由美さんプロフィール
洗足学園音楽大学声楽卒業。2007年ロンバルディア声楽・ピアノマスタークラスにてルチアーナ・セッラ先生の講習会に参加。
― 現在までの略歴を教えて下さい。
畑 洗足学園音楽大学の声楽科卒業です。歌が大好きで小学生の頃、合唱部に入部。また作詞作曲した作品が採用されて、全校生徒に歌ってもらった事があります。高校の頃、イギリス研修でミュージカル鑑賞をしたのがきっかけで、歌を習いはじめました。最初は遊び心でしたが、指導を受けていたオペラ歌手の先生に憧れて、クラシックに興味を持ち、本格的に精進するようになりました。
― 大学を卒業されてからは、どのような活動をされていましたか?
畑 建築大学の音響学に於けるコンサートホール設計の実験に携わり、実験を兼ねてのクリスマスコンサートをしています。また、色々なオーディションを受けて公演に出演したり、小学校から依頼を受けてコンサートを企画・演奏しています。その他、自主的に門下生同士での演奏会や同期有志による歌とオーケストラにバレエをコラボレーションしたコンサートを手がけるなど、演奏の場を常に繰り広げています。
― 講習会に参加されたきっかけを教えてください。
畑 高音を美しく出す発声のテクニックやイタリア人が話しているかのように歌う発音のポイントをつかみたいと思いまして参加しました。特に本場イタリアのコロラトゥーラの先生のレッスンを受けてみたいというのが待望でした。
― ロンバルディアの講習会を選ばれた理由は何かありますか?
畑 ルチアーナ・セッラ先生のCDを持っていまして、先生の美声に近づきたかったからです(笑)。
― それは良い機会でしたね。
畑 はい、これほど有名な歌手の手ほどきが受けられるなんて、レッスンが始まるまで半信半疑でしたが、本物だったので、もう嬉しさ、隠し切れませんでした(笑)。
― 先生のレッスンの雰囲気はいかがでしたか?
畑 とっても良かったです。やはり先生お得意の高い声を目の前で出された時には、すごく感動しました。
― 教え方はいかがでしたか?
畑 実際に目の前で歌ってくださり、それを近くで見る事ができましたので、大変分かりやすかったです。常に口元の形やボディーチェックをしてくださいました。また、指導に熱心な先生で、お昼休みを短縮しても、夜遅くなっても、1人45分のレッスンは時間厳守されていました。

― 雰囲気は暖かいものでしたか?
畑 そうですね、すごく雰囲気を大事にされました。生徒それぞれの個性をちゃんと見抜いてくださる感じの先生でしたね。
― レッスンは何語で受けられましたか?
畑 イタリア語です。
― 通訳は付けられましたか?
畑 はい、付けました。
― 通訳の方はいかがでしたか?
畑 通訳の方は、もちろん、レッスンで先生がおっしゃることすべてのイタリア語を忠実に通訳してくれました。通訳の方にはレッスン以外でもお世話になりました。周りがとても田舎で、食べるところがあまりなく、英語も全然通じなくて、最初は困っていたんですね。それでいろいろ案内していただきました。レッスンで持参した以外の楽譜が必要になったときも、他の(イタリア人の)生徒に声をかけて借りて下さり、印刷屋さんを求めて一緒に歩き回って下さったことも。アフターサービスがよかったですね。そういった面では本当に助かりました。
― 語学の勉強はされていきましたか?
畑 大学で文法を学びました。その後は独学です。イタリア語は普段、歌で慣れているので、言葉は何となく聞き取れるのですが、会話となると本当に大変です。
特にイタリア人はおしゃべり好きで、しゃべるテンポも速いので、ついていかれませんでした。
― イタリアに行かれて語学が上達したという実感がありますか?
畑 たった一週間でしたが、結構覚えました。
― 会話などが中心ですか?
畑 そうですね、生徒のみなさんが休憩時間に話している時や、買い物に行った時など、最初は要望を伝えることも、聞くこともできなかったのですが、帰る時には片言は話せるようになりましたね。
― レッスンは何時から何時まででしたか?
畑 10時から20時まででした。
― その間、ほかの生徒さんのレッスンを聴講されたりしましたか?
畑 今回、日本から講習会に参加したのでは私だけでしたので、先生が「すべて聴講したほうがいい」と、前の方に席を用意されて、ほとんどつきっきりでした。
― 聴講では通訳がないと思うのですがいかがでしたか?
畑 1人、英語が話せる受講生の方がいました。先生が言われていることを英語になおしていただきました。
― 講習会ではどのくらい練習ができましたか?
畑 あまりプライベートの時間が取れなかったので、1時間くらいできればいい感じでしたね。
― どこで練習されたんですか?
畑 自分の部屋です。
― 宿泊先はどんなところでしたか?
畑 メディチ家のお屋敷(別荘)です。
― すごいですね、まるで昔の貴族のお屋敷という感じですか?
畑 そうですね。広大な美しい庭園がありました。部屋も一部屋一部屋が全部広くて貴族が使用していたお部屋をホテルの利便性を考慮して、少し改装したという感じです。シャンデリアだけでちょっと照明が暗く、古い建物なので、ゴーストバスターズが出てきそうです(編集注:ヨーロッパ人は強い光に弱く、弱い光で十分見えるため、日本などより照明は暗くなっています。)でも、一つ一つ見るととてもすばらしい!特にテーブルはすべて大理石です。ベッドはすべてダブルベッド。たまに天蓋付もあります。ソファーも上等です。絵画は必ず、飾られています。各部屋、各部屋、お姫様が泊まるようなゴージャス感がありました。別棟にはショパンが弾いたグランドピアノなどのピアノ博物館もありました。
― いいですね、女性なら1度は泊まってみたいような場所ですね。
畑 部屋には台所やキッチンも付いていました。私1人で泊まるには少し大きすぎて、初日は心細かったですね。
― 外食はされましたか?
畑 1度だけです。土日月をはさみましたので、ほとんどレストランが開いていなかったのです。また買うと量が多いいので、同じものを小出しに食べていました(笑)。
― 外食のお値段はどの程度でしたか?
畑 コースしかなかったので3,000円くらいでした。でも、とても美味しかったです。
― 講習会の会場と宿泊先はどのように行き来されましたか?
畑 講習会会場と宿泊先は同じ建物でした。私は2階の部屋だったのですが、講習会は1階でした。階段を下りればすぐ会場という感じでした。
― スリなどの被害にあわれることはなかったですか?
畑 ないですね。治安のいい場所でした。
― 講習会会場からはあまり出られなかったのですか?
畑 行く時間がなく、あまり行くところもありませんでした(笑)。スーパーマーケットに買出しに行ったりするくらいです。小さな町なので、近所のお店へ行っても15分もあればすべてを散策できるくらいです。
― 海外の方々がほとんどだったと思うのですが、周りの方とうまく付き合うコツはありますか?
畑 そうですね、自分から積極的に主張しないと、全然相手にされないと思います。それと、やはりイタリア語は話せた方がいいかな、とは思いましたね。1日いると、イタリア語しか聞こえてこないので、分からないとかなり自分が疲れてくるんですね。ですから、ある程度は、イタリア語ができた方がいいとは思います。
― 今回の講習会に参加して良かったと思える瞬間は、どんな時でしたか?
畑 日本にいらしたことのあるイタリア人の方が2,3人いらしたんです。その方々がすごくホスピタリティを重視してくださったんですね。というのも、日本に来た時にすごく日本人はおもてなしをしてくれると感じていたようでした。例えば、オペラの仕事で日本に来たそうなんですけれども、一生懸命日本語で話そうとしたら、公演が控えているのだから、公演で使う言葉、つまりイタリア語以外の言葉は使わなくていいんだよ、と言われて、何不自由なくイタリア語だけで過ごせる雰囲気にしてくださったということでした。そういう方々のお話を聞いて、自分も逆の立場の時があったらホスピタリティを重視したいなと思いました。
― 留学をされて、自分が変わったな、成長したなと思うことはありますか?
畑 多少の語学力と発声が変わりました、念願の「高い音域を発声するときのコツ」をつかんだような気がします。やはり外国人の先生はかなり広い舞台で歌われており、ご経験も豊富なので、効果を出すのがうまいのでしょうね。
― そういう先生に習ったというのは深い意味があったんですね。
畑 そうですね、たった一週間ですが、それでもかなり効果があったと思います。素晴らしい先生だと思いますね。
― 留学前にやっておいた方が良いことは語学のほかに何かありますか?
畑 選曲ですね。基本は歌曲と思い、歌曲をいくつか持参したのですが、それよりも、セッラ先生はオペラアリアを重視されます。自分で無理なく歌えるオペラアリアを何曲か用意して、一週間で完成できるような曲にした方がいいと思います。それと、鏡を見てレッスンを受けるので、ほとんどの方が暗譜でレッスンを受けていました。少し、楽譜から目を離せる程度に歌いこなしておいたほうがいいと思います。あとは、目的をはっきりさせることですね。先生に「何を習いたいのか」という自主性をすごく聞かれます。
― 前もって自分の中で計画を立てておくといいということですね。
畑 そうですね、曲を歌わなくてもいいんです。発声だけをやりたい人もいます。何がしたいかを決めておくのは、重要なポイントになってくるな、と私は思いました。
― 日本とイタリアで何が違うとお感じになりましたか?
畑 日本では10年くらいかけてやっとオペラアリアを歌えるようになりますが、イタリアではたった2.3ヶ月くらいですぐ難関のオペラアリアを歌うようです。ですから、10年以上の経験があると、相当あらゆる曲のレパートリーがあると周りから興味を持たれますね。ちょっと自負を感じることもありますね。
それから、イタリア人は母国語を大事にしているので、ほとんどイタリア語しか話さないですね(笑)。日本語を話そうとは、もちろんしないんですけれど、逆にイタリア語を話せない私に対して、「イタリア語を話せないのにどうして来たの?」とよく質問されました。そういう所は違うかな、と思いました。日本人はそんなことがあっても、わりと心を広く持って、頑張って向き合おうとすると思うのですが、イタリア人はイタリア語にプライドを持って、極力イタリア語以外は話さない、という雰囲気はありましたね。だから、こちらが積極的に話していかないと、と思います。イタリア人は待っていては来ない、というところは、日本とはギャップがあると思いました。
― 今後、留学する人にアドバイスしておきたいことはありますか?
畑 音楽用語というか、歌を歌う時に、「もうちょっと口を前に」とか、「目」「足」「息」とか、身体を使ってのアドバイスをされるので、身体の部位の言葉をイタリア語で覚えて行けば、レッスンの時にかなり役立つので良いと思います。
― ありがとうございました。
尾野文香さん/ピアノ/クールシュベール夏期国際音楽アカデミー/フランス・クールシュベール
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

尾野文香さんプロフィール
3才よりヤマハ音楽教室にてピアノとエレクトーンをはじめる。1996年PTNAピアノコンペティション全国決勝大会ベスト20位、1997年全日本学生音楽コンクール名古屋大会第2位、1998年ウィーン音楽コンクールインジャパン本選第1位。その後、ウィーンの講習会に招待され、ウィーンにて入賞者コンサートに出演し、ウィーン市長賞を授与。2002年、2003年ショパン国際ピアノコンクールin Asiaにて本選入賞など数多くのコンクールにて入賞。コンサート歴も多く、ピアチェーレ・コンサートシリーズ「あおい空」、アルマ21世紀コンサートなど出演。また2007年、アルマ室内管弦楽団と共演。これまでにピアノとエレクトーンを村田恵理子、エレクトーンを市川禎、ピアノを長谷川淳、宮脇恵子、弘中孝の各氏に師事。2007年クールシュベール夏期国際音楽アカデミーにて、パスカル・ドゥヴァイヨンに師事。2008年3月東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業後、4月より同大学大学院在学予定。
― 略歴を教えていただけますか?
尾野 最初はヤマハのグループレッスンに通ってエレクトーンとピアノを一緒にやっていました。その後、小学校2年生頃からピアノを本格的に習いはじめました。エレクトーンは小学校5年生までやっていました。現在は東京音楽大学の4年生です(注:インタビュー2007年8月)
― コンクールなどへの参加はありますか?
尾野 小学校6年生の時に、今はもうなくなってしまったコンクールなのですが、ウィーン音楽コンクールインジャパンで1位をいただいて、副賞としてウィーンの講習会を受けさせていただきました。
― 今回クールシュベールの講習会に参加したきっかけを教えていただけますか?
尾野 幼い頃から、留学したい気持ちは漠然とあったんですけれど、現実的に進路として考えた時に決めきれずにいたんです。そこで、やっぱり日本でいろいろ考えているよりも、実際に行っちゃった方が分かる事が多い、と思いました。行く前は、ずっと迷っていたんですよ。「留学したら必ずこうなれる」というのがあるわけじゃないですから。「大変なことも多いだろうし、お金もかかるし」って。でも、やっぱり今留学しなかったら、将来後悔するだろうなって思ったんです。20年、30年と時間が経った時に、「いやぁ、あの時留学しておけばよかったな」って思うのは嫌だったんです。それで、まずは、講習会で留学を体験してみたいと思ったのがきっかけです。
― いろいろなコースがある中で、クールシュベールを選ばれたのはどうしてですか?
尾野 私の場合、留学することや留学する国を完全に決めていたわけではなかったので、語学を全然やっていませんでした。それで、通訳さんがいるコースが条件だったんです。フランスか、ドイツか、オーストリアか、ポーランドに行きたかったんです。留学に対する知識が少なくて候補が多いのですが(笑)、その中で、いろいろと他の講習会をみて、レッスンの聴講がさせていただける事と、レッスンを聴講してみたいと思う先生方が多かったので、クールシュベールを選びました。
― パスカル・ドゥヴァイヨン先生を選ばれた理由はありますか?
尾野 はい、以前からパスカル・ドゥヴァイヨン先生のことを、一方的にですが本などで存じ上げていました。ドゥヴァイヨン先生にレッスンしていただくのを本当に楽しみに思い参加しました。
― レッスンの雰囲気はいかがでしたか?
尾野 すごく楽しかったですし、すごく素敵でした。あっという間に時間が過ぎてしまいました。ドゥヴァイヨン先生はとても丁寧に的確なことを分かりやすくご指導してくださいます。自分自身が曲の準備をちゃんとしていけばいく程、いろいろな事をより深く教えていただけると思います。
― 時間は1時間くらいですか?
尾野 そうですね、日によっては時間が押していたり、次の生徒さんがもう待っているので1時間ない時もあったかもしれません。曲によって日によってという感じです。
― 何回ドゥヴァイヨン先生からレッスンを受けたのですか?
尾野 私の場合は、ドゥヴァイヨン先生に4回、村田理夏子先生が2回でした。
― なるほど、村田先生はいかがでしたか?
尾野 ピアノ奏法や打鍵についてなど色々と教えていただきました。レッスン後には、留学などの相談にものってくださいました。
― ドゥヴァイヨン先生のクラスは何人くらいでしたか?
尾野 そうですね、多分20人くらいだったと思います。
― その中で日本人はどのくらいいましたか?
尾野 半分くらいは日本人だったと思います。外国ですでにドゥヴァイヨン先生に師事されている方もいらっしゃいました。
― レッスンは通訳を通じて受けられたということですが、通訳は分かりやすかったですか?
尾野 はい。ドゥヴァイヨン先生のアシスタントであり奥様でいらっしゃる、村田先生に通訳していただけたので、すごく分かりやすかったです。
― 語学の勉強は事前にされていかれたのですか?
尾野 いいえ、現地でも「ボンジュール」と「メルシー」くらいしか使っていないです(笑)。特にパリでは英語も結構通じます。大学ではドイツ語を選択していました。
― レッスンは何時からだったのですか?
尾野 私は夕方くらいのレッスンが多かったですね。
― 先生は丸1日レッスンしているのですか?
尾野 ドゥヴァイヨン先生はお昼前くらいからレッスンをされていたと思います。私は夕方からだったのではっきり覚えていません。先生によっては朝9時からレッスン、という先生もいらしたみたいです。
― レッスン時間以外は何をして過ごされましたか?
尾野 練習時間が結構制限されていたので、空き時間は聴講をしていました。あとは、友達と周辺を散策したり、ゆっくり食事をしたり、ビリヤード、スケート、卓球もしました(笑)。
― 練習時間は少なかったのですか?
尾野 1部屋を4人で割り振って使うようになっていました。使用時間が9時から21時だったので、1人平均3時間でした。その4人が全員日本人の場合は、わりときちんと割り振ってやっていたみたいですが、私の場合、2人韓国の方がいらっしゃいました。最初は割り振りをしていなくて、いつ練習できるか分からない状態だったので、割り振りをしたい、とお願いをしました。他の部屋で練習しようにも特に最初のうちはみんな気合いが入っていて空いている部屋はありませんでした。
― 韓国の方はルーズだったのですか?
尾野 そうかもしれません(笑)。というより、日本人が細かいと言った方が良いのかもしれません。多分、こちらから提案しなければ、ちゃんと練習時間が決まることはなかったと思います。
― 練習室以外では練習する場所はありましたか?
尾野 多分、なかったと思います。楽器の方は主にホテルの部屋で練習していたみたいです。
― 講習会でコンサートが行われたそうですね。
尾野 はい、講習会で指導されている先生方の出演されるコンサート(主に室内楽)が4回ありました。先生方全員が出演されるわけではないのですが、ドゥヴァイヨン先生は出演されて、すごく素敵でした。
― 生徒さんが出演されるコンサートはいかがでした?
尾野 終わりに2日間に渡って受講生のコンサートがありました。クールシュベールの講習会はとても参加人数が多く、たぶんピアノだけでも100人くらいはいます。ほかの楽器の人も入れると、多分200人を超すと思います。その中での選抜コンサートなので、たくさんの方が少しずつ演奏して、長い時間かかるような感じでした。

― 宿泊先はどんなところでしたか?
尾野 すごく綺麗なところでした。
― 食事はどうでしたか?
尾野 朝ご飯と晩ご飯は講習会の費用に含まれていて、朝は宿泊しているホテルで、夜はメイン会場のホテルでいただきました。お昼は近くのスーパーなどで買ったり、お金を払えばメイン会場のホテルでいただくこともできました。クロワッサンやフランスパン、乳製品はやはりおいしかったです(笑)。
― 宿泊先とレッスン会場は遠かったですか?
尾野 歩いて行ける距離でしたが、講習会会場のクールシュベールは標高1850mで冬はスキーができるリゾート地のためとても坂が多いんです。道といえば坂でした。クールシュベールに行かれる方は、運動靴など歩きやすい靴を持っていかれることをお勧めします。
― 尾野さんは持っていかれなかったのですか?
尾野 そうなんですよ。サンダルに後悔しました(笑)。しかも8月なのに、夏とは思えない涼しさでした。長袖なしでは過ごせない気候でしたが、湿度も低いし過ごしやすかったです。
― 日本とは違いますね。
尾野 そうですね。日本で言うと、秋の終わりくらいかも。雨の日なんか、はっきりと「寒い!」と言えるくらいでした。
― 暖房などはちゃんと入りましたか?
尾野 冷房も暖房も特に使った記憶がないので、冷暖房の必要はない気候だったんだと思います。

― クールシュベールの街として、治安はいかがでした?
尾野 すごく安全な印象でした。周りからも何かあったというような話は聞かなかったし、私自身も危険を感じるようなことは全くありませんでした。
― 海外の友達はできましたか?
尾野 私の場合、フランス語が話せないので、直接、仲良くたくさん話すことはできなかったのですが、フランス語が話せる日本の方に通訳してもらいながら海外の友達も混ざってお話したり遊んだりすることはありました。
― 日本人以外ではどちらの方が多かったですか?
尾野 フランスの方はもちろんフランス近隣、アメリカなど様々でしたが、韓国や中国などアジアの方が多くいらしゃいました。
― 講習会に参加して良かったと思える瞬間はどんな時でしたか?
尾野 さきほどお話しした、講習会の先生方が出演されるコンサートを観た時ですね。来てよかったと思いました。
― 留学されて、何か自分が変わったところ、成長したところはありますか?
尾野 講習会の期間が短かったので、大きな変化はあまりないのですけれど、今まで海外経験があまりなかったので、行く前の準備だけでも勉強になりました(笑)。思い切って講習会に参加してみて本当に良かった、と思っています。先ずは一歩という感じだったと思います。
― 留学前に準備しておいた方が良いと思うことはなんですか?
尾野 それはもう曲の準備ですね。講習会は素晴らしい先生方にみていただける貴重な機会だと思います。お金も時間もかけて参加するし、先生により深くたくさんの事を教えていただくためにも、しっかりと準備していくべきだと思います。現地では練習時間も限られます。
― 何曲みていただいたのですか?
尾野 ドゥヴァイヨン先生のレッスンは4回でしたが、1回目でショパンのエチュードを2曲みていただいて、2回目でベートーベンのソナタ第1楽章を、3回目はその続きで、4回目でまた別の曲をみていただきました。
― 日本とクールシュベールの違いはどんなところですか?
尾野 いろいろあると思いますが、例えば現地の方の人柄なんかは日本と比べてすごく明るかったですね。フランスに留学されている方は、「こっちに来てテンションが高くなって、リアクションが大きくなった」と言っていました(笑)。そんな雰囲気が、私はすごく好きでした。講習会は短い期間だったし、環境も保証されていたので、留学のいいところばかりを見たとは思いますが、本当に楽しかったです。良い思い出です。

― 今後留学される方にアドバイスしておきたいことは?
尾野 留学したい気持ちがあっていろいろ迷ったり悩んでいる方は、まず講習会に参加するなど現地に行ってみる事をお勧めします。日本で座って考えているよりも、実際に行動した方が分かる事も感じる事も断然多いと思います。講習会では同じ迷いを持っている人も多く参加していますし、すでに留学している人からいろいろお話を聞かせていただくチャンスもあります。
― 尾野さんは今後フランスに行かれる予定ですか?
尾野 そうですね、フランス以外の国にも興味はありますが、本当に楽しかったので、前よりももっと留学したくなりました。講習会の影響です。
― 今後の進路はどうされますか?
尾野 4月からは東京音大の大学院に進学しますが、長期留学も考えています。すごくしたいと思っています。
― コンサートのご予定などはありますか?
尾野 今度5月にピアチェーレ・ムジカ主催の「ひびき」というコンサートで地元の愛知県でメンデルスゾーンのピアノトリオ第1番を演奏させていただきます。大好きなトリオの曲ですし、しっかりとがんばりたいです。
― 頑張ってくださいね。長い間、ありがとうございました。
///////////////////////////////////////////
---尾野文香さんコンサート情報------
Musica Da Camera 2008
Concert the Piano Trio
2008年5月31日 開演17:30
知立リリオコンサートホール
問い合わせ:0562-84-0876
Program
ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第三番ハ短調Op.1-3
ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲第四番変ロ長調Op.11
メンデルスゾーン/ピアノ三重奏曲第一番ニ短調Op.49
出演;
ピアノ
岡田みずほ
三輪富美子
尾野文香
バイオリン
宗川諭理夫
チェロ
内田玲
行本康子さん/チェロ/ウィーン国際音楽ゼミナール/オーストリア・ウィーン
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

行本康子さんプロフィール
4歳よりピアノを始め、14歳のときにチェロに転向。桐朋学園大学音楽学部チェロ科に在籍中。現在、4年生。2008年ウィーン国際音楽ゼミナール参加。
- まず、簡単な自己紹介をお願いします。
行本 4歳の頃から10年くらいピアノを弾いていたのですが、少し嫌いになって辞めようと思っていたところに、たまたま小さな発表会を聴く機会があって、チェロの有名な曲「白鳥」を聴いて、チェロをやりたいと思ったんです。それで、14歳からチェロを始めて、桐朋学園大学に進学しました。現在、4年生です。
- これまで講習会に参加されたことはありますか?
行本 国内のでしたら、ついていた先生の個人的なものやその先生が講師としてよばれているものに2、3回参加したことがあります。
- では海外の講習会は初めてですか?
行本 はい、そうです。海外に行くこと自体、今回が初めてでした。
- では、どうしてこの講習会に参加されようと思ったのですか?
行本 去年くらいから、ドイツ語圏で知っている先生で、という条件で講習会を探していたのですが、去年は知っている先生がいなかったので参加しませんでした。今回はたまたま日本で2回見てもらったことのあるステファン先生の名前があったので、参加を決めました。
- なるほど。先生はステファン・クロプフィッチュ先生ですよね。前に教わったときからいい印象を持たれていたんですか?
行本 とても上手で、人柄がいいんです。教えることに専念している方ではないのですが、演奏する上で大切なことを細かく教えてくださる先生です。

- 講習会の参加者は何名くらいでしたか?
行本 全部で40人くらいだったと思います。チェロは4人でした。日本人が私の他にもう1人。韓国の中学生くらいの子、あとは、ドイツ語を話していたのでオーストリアの子だと思いますが、会場になっているウィーンの音大を受けたいと考えている子でした。
- 他の生徒さんの演奏を聴く機会はありましたか?
行本 韓国の子の演奏は聴けなかったのですが、あとの2人の演奏は聴きました。日本人の子はレッスンが前後だったので、必ず聴講していました。
- レッスンの雰囲気はいかがでしたか?
行本 多分、先生に見てもらうのが初めてであれば、どんな感じかな、と様子を見るののだとと思うのですが、私の場合、日本でも見てもらっていて先生も覚えてくださっていたので、初めからけっこう本格的なレッスンが始まりました。以前見ていただいたのは4、5年前なので私も変わっているとは思うんですが、年齢などを考慮して、真剣に見てくださったと思います。
- レッスンで印象に残っていることはありますか?
行本 一番ためになったなと思うのは、力の抜き方です。日本でも「力を抜きなさい」というのはよく言われることなんですが、具体的にどうしたらいいのかは教えてくれないので困っていたんです。ステファン先生は逆に「力を抜きなさい」という言葉は一言も言わずに、「こうしなさい」というのを2、3個具体的に言ってくれたんです。あとから考えると、その弾き方が結果的に力が抜けるのではないか、と思いました。
- 他には何かありましたか?
行本 レッスン中も弾きながら「ここはああしてこうして」と指示があるのですが、必ずレッスンの最後に「今日のレッスンで1番大切なことはね……」とその日の重要なポイントを1つか2つにまとめてお話をしてくださるんです。私のその日の様子を先生が絞って見てくださる形だったので、それがすごくよかったと思います。
- なるほど。
行本 今回、コンクールの課題曲に入っていることもあり、シューベルトを持っていったのですが、ウィーンの作曲家の曲で先生もウィーンの方なので「ウィーンの古典派はこう弾くんだよ」と他の曲よりも大切に見てくださった気がします。
- 何か参考になる具体的な言葉はありましたか?
行本 ホイリゲとよばれるバイオリンなどの演奏を聴きながらワインが飲める酒場に行って、陽気な人を見て来てごらんと言われました。曲の感じを掴むのに見て来た方がいいよ、と。実際に足を運んでみると、みなさん本当に楽しそうで、「あ、こういうことなんだ」というのが少し分かった気がしました。日本人の観光客ということで、向こうから話しかけてくれたり、“上を向いて歩こう”や童謡を歌いながら演奏してくれました。
- いい体験ですね。実際に演奏は変わりましたか?
行本 自分の中では変化はよく分からなかったのですが、参加者コンサートで演奏したときに、講師としてよばれていた日本人の先生が「ステファン先生の感じがすごく出ていて、よかったですよ」と言ってくださいました。ステファン先生のレッスンを受けて変わったのかなと思いました。

- レッスンのスケジュールを教えてください。
行本 月曜と木曜に先生に見ていただいて、月木月木でレッスンは計4回ありました。レッスンとレッスンの間に2、3日空くので、ちょうどよいペースでした。
- レッスンは1時間ですか?
行本 はい、ちょうど1時間です。
- 物足りなさは感じませんでしたか?
行本 感じませんでした。2週間あって、その中で4回のレッスンがあったので、私は十分かなと思いました。
- 講習会で組まれていたスケジュールについてお話を聞かせてください。
行本 初日に小さいホールのようなところでオープニングイベントがありました。まず、参加者の子たち3、4人のコンサートがあって、そのあと、講習会の大まかな説明を受けました。あとは最後に、サンドイッチと飲み物程度の軽いパーティーがありました。
- 他には全体で何かありましたか?
行本 13日(講習会3日目)には先生たちのコンサートがありました。先生たちの中からピアノ2人とビオラ、チェロの4人の先生が演奏してくださいました。チェロのステファン先生は1番最後にチャイコフスキーの「ロココ風の主題による変奏曲」を演奏をされたのですが、すごく評判がよくて、聴いていた他の楽器の受講生たちもステファン先生に教わりたい、と話していました。
- 13日だと、レッスンを1度受けたあとですよね?
行本 はい。11日初日に最初のレッスンがあったので。
- そうすると、これからのステファン先生のレッスンが楽しみになったのではないですか?
行本 そうですね(笑)。
- 他にもコンサートはありましたか?
行本 はい。会場が変更になって、ハイドン生誕の家ではなくて、隣ににシューベルト記念館がある小さなお城で開かれました。私はここで弾かせていただいたのですが、この会場はオープニングイベントのホールよりも学校よりも響いたので、音の響きはこの講習会中で1番よかったと思います。
- 日本だとなかなかないシチュエーションですよね。ウィーンのお城で演奏するというのは、どんな気分でしたか?
行本 すごくよかったです。他の受講生のみんなからも、私も弾くならここで弾きたいと羨ましがられました(笑)。
- お城でのコンサートでは何人が演奏したんですか?
行本 12人くらいです。
- 何曲演奏されたんですか?
行本 1人1曲で、私は先生と相談して演奏する曲を決めました。
- コンペティションも予定に組まれていたと思いますが、参加されましたか?
行本 いいえ、参加することはできませんでした。参加した人たちは、2曲を抜粋で演奏していました。そんなに堅苦しい雰囲気ではなくって、参加者コンサートとあまり変わらない雰囲気でした。
- そのあと、そのコンペティションで選ばれた人で受賞者コンサートがあったんですよね?
行本 そうです。コンペティションを12人くらいが受けて、10人が受賞していました。黒いパンツで弾いていた人がドレスで演奏していたりと、少しだけ雰囲気が変わっていました。
- その受賞者コンサートが講習会中、最後のイベントですか?
行本 はい、そうです。
- 練習はどこでしていましたか?
行本 ホテルで朝の9時〜夜の8時くらいまで音を出すことができたので、ホテルで練習しました。けっこう弾く時間はありましたね。
- 他の人の音は聞こえてきませんでしたか?
行本 窓を閉めて弾くというのが決まりだったんですが、おそらく窓を開けて弾いていた人の音は聞こえてくることもありました。ただ、私はそんなに気になりませんでした。
- レッスン以外の時間は何をしていましたか?
行本 外に出て、街を観光していました。
- ウィーンの街はいかがでしたか?
行本 すべてのものが大きいなぁというのが第一印象です。ガイドブックに載っているところやシェーンブルン宮殿、マリア・テレジア広場などに行きました。
- どこかお勧めのところはありますか?
行本 ホテルの近くにあったベルベデーレ宮殿です。私が滞在していたときは、中でクリムトの絵画展をしていました。次はゴッホ展になるようです。そこは楽しくて何時間でもいられる感じでした。
- 入場料はいくらくらいだったんですか?
行本 私は国際学生証を持っていなかったので、8〜9ユーロくらいでした。
- 宿泊先のホテルはどんなところでしたか?
行本 私は一人部屋を希望しました。部屋自体に不都合はなく、ドライヤーを借りたりすることもできて、そんなに困ることはありませんでした。日本のホテルより広かったです。
- 何か日本から持っていったほうがよいものはありましたか?
行本 歯ブラシは準備されていなかったので、持っていったほうがよいと思います。シャンプーやリンス、石けんも自分のものを使いたい人は準備しておくとよいと思います。
- ホテルのスタッフの対応はいかがでしたか?
行本 けっこうよかったと思います。行きたいところを伝えると、電車の時間を調べてくれたりしました。
- 他の参加者の方も同じホテルですか?
行本 はい。ほとんどの方が同じところに泊まっていました。レッスン時間などはバラバラでしたが、キッチンが共同なので、そこで会って話すのが楽しみでした。最初は外食をしていたのですが、毎日だと高くつくので、途中から自炊するようにしていました。
- 自炊していたんですね。食材はどうしていましたか?
行本 ホテルからすぐ近くのところにスーパーがあったので、そこで購入していました。
- 外食はいくらくらいだったんですか?
行本 中華料理など安いところは、5ユーロくらいでした。日本から来ている他の方と、ホテルの近くのレストランで食事をするときはだいたい8ユーロくらいでした。スープとメインとデザートが出て来る感じで、お腹はいっぱいになりました。高いといえば高いけど、こんなもんかな、という感じもしました。
- 参加者はどこの国の方が多かったですか?
行本 7割くらいが日本人でした。あとは、イタリア、韓国、ノルウェー人でした。
- 海外の方とうまく付き合うコツはありますか?
行本 日本人以外の参加者の方は、日本人が集団でいたので入りづらかったのか、特別な用事でもない限り、向こうから話しかけてくることはなかったです。なので、こちらから話しかけることのほうが多かったですね。話してみると、片言の適当な英語でもわかってくれたし、向こうもこちらがわかりやすいようにゆっくり話してくれたりと親切にしてくれました。
- 滞在中、何か困ったことはありましたか?
行本 困るという程でもありませんが、ホテルの朝ご飯が毎日一緒だったのが……(笑)。バイキングの内容が種類が少ないのにまったく同じだったんです。1週間くらいなら問題ないと思うのですが、2週間〜それ以上となると、少しきつかったです。パンが2種類とハムが2種類、チーズが2種類、スイカ、トマト、あとは飲み物が牛乳、ジュース、コーヒー、紅茶といった内容でした。
- ウィーンの交通はどうでしたか?
行本 電車に乗ってしまえばどこにでも行ける感じでした。日本のようにメトロの路線の数も多くないので、迷うこともありませんでした。チケットは乗り放題のものを購入しました。
- ウィーンの街は過ごしやすかったですか?
行本 日本と外国の違いだと思いますが、よく話しかけてくれました。お店の方だけでなく、そこに買い物に来ている現地のお客さんに話しかけられることもありました。ウサギの絵はがきをみていたら、そこにいた現地のお客さんが、その絵はがきと私の顔を見比べて「似てるわ」とおもしろおかしくいってきたり……。そういうことは日本ではないなぁ、と感じました。あとは、日本人で英語が話せる人というのは少ないと思いますが、ウィーンではほとんどの方がドイツ語以外に英語でも話してくれるので、助かりました。
- 初めての方でも行きやすい街ですね。
行本 はい。私が行けたくらいなんで……(笑)。

- 今回、留学をして成長したなと感じるところはありますか?
行本 周りの参加者を観察していて、やはり積極的な人が何かを掴めるのかな、ということがなんとなくわかりました。私も最初の1週間は様子を見ているところがあったのですが、後半は日本人はもちろん外国人にも話しかけてみようかなと思い、積極的にしていました。
- 講習会に参加してよかったなと思えることはありましたか?
行本 17日(講習会7日目)の参加者コンサートでお城で演奏したときに、イタリア人のクラリネットの男の子が私のチェロを気に入ってくれて、直前のピアノ合わせのときから「いいよ、いいよ」と言ってくれて、演奏が終わったあとも拍手で迎えてくれました。それで「室内楽をやらないか?」と彼が誘ってくれたんです。結局予定が合わなくて、合わせは出来ずに終わってしまったのですが、それでもそういうふうに言ってくれたことがすごくうれしかったです。日本に帰った後、彼とはメールをしています。
- 他に何かよい経験はできましたか?
行本 直接、講習会とは関係ないのですが、行きの飛行機で隣に座った女の人が乗り換えを手伝ってくれたり、帰りの飛行機でもスチュワーデスさんとチェロ分の座席のチケットのことで話が通じていないときに、日本人の女の人が間に入って通訳をしてくれて助けてくれました。最後のアムステルダムから成田の飛行機でも隣に座った男性が「趣味でコントラバスを弾くんですよー」と話しかけてくれました。その方は名刺もくださって「演奏会があるときは連絡してください」と言ってくれました。飛行機でもいろんな出会いがあって、楽しかったです(笑)。
- 楽器を持っていると話しかけやすいのかもしれないですね。
行本 それはそうかもしれないですね。そういえば、もう1人いた日本人のチェロの子は、楽器を現地で借りて、弓だけを持って来たと言っていました。その借りた楽器がすごくよい楽器で彼女にあっていて、気に入ってるみたいだったので、製作の年代や名前をメモさせました(笑)。
- 行本さんの楽器は向こうで音の鳴り具合はかわりましたか?
行本 日本に比べて向こうはよく乾燥しているから音の響きがよくなるということを聞いたりしますが、私の楽器はしけてるから響かないということはなくって、そんなに変わらないんじゃないかなと思いました。ただ、日本のほうが湿気は多いので、向こうに行って鳴らなくなるということはないと思います。
- 他に留学をして感じたことは何かありますか?
行本 やはり語学が大事だなと思いました。話したいという気持ちさえあればなんとかなるとは思うんですが、いろいろな言葉を知っていたほうが伝わりやすいかなと思いました。
- そうすると、留学する人へのアドバイスも「語学の勉強をしたほうがいい」ということになりますか?
行本 そうですね。ただ、そんなに前もって勉強していなくても、どんどん話しかけることが大事だと思います。あとアドバイスとしては、先生の選び方も大事だと思います。私は知っている先生に教わったので、レッスンが始まってからギャップを感じることはなかったのですが、感じてしまう人もいるようです。知っている先生に教わるのがベストですが、知らない先生でも少しでもいいので情報をキャッチしてから行ったほうが、向こうに行ってから驚いてしまうということもないと思います。
- 今後の活動の予定を教えてください。
行本 具体的にこれをというものはないんですが、卒業後はこの夏の経験を活かして何でも挑戦してみようと思うようになりました。今までは、表舞台に出ることを望んでいたのですが、そうではなくても、どこでも何でもいいから演奏が楽しくできれば、幸せなのかなと思うようになりました。だから、どんなに小さな仕事でも頼まれたら必ず演奏しようと思うようになりました。
- それはやはりウィーンで何か影響を受けたんですか?
行本 そうですね。外国の方は日本人とは違ってだいぶ楽しそうに弾いているし、街の人も楽器を持っていると興味を持ってくれたり、自然に音楽が流れている雰囲気が街にありました。
- これからも音楽を楽しんでいけるといいですね。今日は本当にありがとうございました。
新井田さゆりさん/声楽/カリアリ夏期国際音楽アカデミー/イタリア・カリアリ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

新井田さゆりさんプロフィール
高校3年で歌を始める。鹿野道男先生に師事。現在、東京音楽大学大学院声楽専攻オペラ研究領域在学中。2008年イタリア・カリアリ夏期国際音楽アカデミーでペギー・ブーヴレ氏に師事。2006年より三年連続特待給費生。2007年東京音楽大学卒業演奏会、同年第77回読売新人演奏会、同年埼玉新人演奏会に出演。また、JT主催アフタヌーンコンサートに2回出演。
-簡単な自己紹介をお願いします。
新井田 高校3年生の6月に声楽を習い始めて、それから東京音楽大学の声楽演奏科コースに入りました。現在は、大学院の2年生です。声楽専攻オペラ研究領域に在籍しています。
-高校3年生で歌を始めるまで、専門的に歌を学んだことはなかったんですか?
新井田 はい、なかったです。
-では、高校3年生のときに歌を始めたのはどうしてですか?
新井田 中学と高校が特別音楽に力を入れている学校で、合唱発表会があったんです。そのときに東京音大の先生が合唱指導にいらして、その先生が私の声を聞いて「音大に行ったらどうだろうか」と言ってくださり、その言葉を聞いて、私にもできるならやってみたいな、と思ったのが歌を始めたきっかけです。
-今もその先生に習っているんですか?
新井田 いえ、違います。そのときにその先生に東京音大の鹿野道男先生を紹介していただいて、高校3年生の6月にゼロから習い始めました。
-6月に始めて、それで声楽演奏科コースに合格したというのはすごいですよね。
新井田 もうとにかく必死で勉強しました。始める時期も遅かったので、2月の入学試験までの8ヶ月間は死に物狂いで、脇目も振らずに勉強しました。楽典などの基礎知識もなかったし、ピアノも弾けなかったんです。そうして必死でやっていると、自分でもみるみるうちに声が伸びていくのがわかりました。
-ええ、ええ。
新井田 もし声楽演奏科コースが無理でも声楽科コースで通るだろうと思えるくらいまでは成長していました。その頃は、人前で歌うということも全くしていなかったので、入学試験でも全然緊張しなかったんですよね。それがよかったのか、無事に合格しました。大学入学後の2年間はサボっていて、とても不真面目な生徒だったんです(笑)。でも、大学3年のときに釜洞祐子先生と出会い、先生の手ほどきで音楽の素晴らしさや楽しさを知り、自分で勉強していくことの大切さを知って、今では歌なしの人生は考えられないというぐらい歌を優先しています。
-今まで勉強は大学で主にされてきたんですよね?
新井田 はい、大学で全部やってきました。
-そうすると海外の講習会に参加されたことはありましたか?
新井田 いえ、ないですね。
-今回、海外の講習会に行きたいと思ったのはどうしてですか?
新井田 アンドビジョンに私の友人が勤めていまして、その友人に留学を考えていると相談したら、いろいろな情報をメールマガジンというかたちで定期的に送ってくれたんです。それで、海外に行きたいとのは思っていたんですが、具体的にどの講習会に参加したいということはなかったんです。そんなとき、たまたまメールマガジンで今回のカリアリの講習会が紹介されていて、講習会の内容うんぬんよりも「サルディニア島に行ける」、「世界遺産の素晴らしい地中海を望む美しい街で講習会ができます」という謳い文句に私は食いつきました。それが一番の動機ですね(笑)。
-海外に行かれたことはありましたか?
新井田 いえ、今回が初めてでした。
-興味があった国はありますか?
新井田 漠然と行くならヨーロッパ圏がいいなと思っていたので、特に国は決まっていなかったです。それから、今、学校で主に勉強している音楽がフランス音楽だったので、フランス語やフランスの文化を知りたいなと思いました。カリアリはイタリアですが、今回の講習会は講師人がフランス圏ということで、それにも興味を持ちました。

-ペギー先生のレッスンの雰囲気はいかがでしたか?
新井田 ペギー先生って見た目はすごい声を出すんだろうなって思うくらい立派な体格の方なので、私自身はわりと痩せ型なこともあって、ペギー先生との体格の差に度肝を抜かれてしまって、先生についていけるのかどうかすごく不安だったんです。でも、ガイダンスが終わって、先生に挨拶に行ったら、すごく優しい笑顔で迎えてくれたので、安心しました。レッスンもとっても丁寧に教えてくれましたね。もともと日本で勉強してきた声の技術を活かしながら、先生がそれに上乗せしてレッスンしてくれるという感じでした。あまり否定はされずに、褒めて伸ばすタイプの先生でした。
-レッスンで印象に残っていることはありますか?
新井田 ペギー先生が自分で歌って見せてくれるのがとても印象的でしたね。もしかしたら言葉の壁があったからかもしれませんが、理屈とかではなく、英語でもフランス語でも伝わらない部分があれば自分を見本にして見せてくれる、それを真似してみなさいという教え方がとっても印象的でした。
-先生の声はいかがでしたか?
新井田 とっても「ビューティフル」、美しい声でした。低いところから高いところまでムラなく出ていて、音楽に対する知識もすごく豊富で、オペラや室内楽、他の歌曲など、声楽と呼ばれるジャンルならどの曲を持っていっても、それこそミュージカルナンバーを持っていっても、ちゃんと教えてくれる人だと思います。
-新井田さんはどんな曲を持っていったんですか?
新井田 私はプーランクのオペラの声を全曲とリゴレットを持っていきました。
-今度の卒業試験の曲も教えてもらったんですよね。
新井田 教えてくれました。先生の持ち歌なのかわからないですが、私のやりたい曲の主人公の心情になって指導してくれて、素晴らしかったです。うまく説明できないのですが、苦しみの中で愛しているって言いながら死んでいくシーンがあるんです。それを先生がやってくれたんですけど、そのときに椅子の上からズルズルと体を落としていって、「愛してる」って言うのよ、って。そしたら、先生がずり落ちすぎて立ち上がれなくなっちゃって、みんなで助けて、「大丈夫ですか? 先生!」って、起こしたんです(笑)。すごく楽しかったんですが、それぐらい先生は真剣に教えてくれたんですよ。
-先生のレッスンを受けている人は何人くらいいましたか?

新井田 私を含めて9人ですね。日本人が私を含めて2人、中国人が1人、フランス人が3人、ギリシャ人が1人、ナイジェリア人が1人、韓国人が1人。歳はだいたい23歳か24歳でした。
-聴講はされましたか?
新井田 聴講するようにと先生が言ったので、常に部屋には9人生徒が揃った状態で、1人が歌っているのをみんなで聴いていました。
-聴講というスタイルはどうでしたか?
新井田 とっても刺激になりました。自分が教わっているときにわからないことでも、他の人のレッスンを聴講することで、客観的に見えてわかったり、あるいは自分がやっているときに、他の子たちが見て盛り上げてくれて、それによって自分の中で眠っていたテンションみたいなのが出てきたりしました。とても情熱のあるレッスンでしたね。毎回、朝からテンションアップで、先生が言ったことをきちんとできた子がいたり、望んでいる声が出たりすると拍手して盛り上がっていました。
-すごいですね。
新井田 はい。それをいろんな科の子が噂で聞きつけて、歌のレッスンはほとんど満員、日によってはレッスン室に入りきれないくらいギャラリーが増えたときもありました。それくらい明るいレッスンだったんですよ。本当に幸せな一時でした。みんながみんな音楽を楽しんでいる感じがうれしかったですね。
-そういうことって日本ではなかなかないですよね。

新井田 ないですね。多分、ペギー先生の人柄だと思います。さすがですよね。
-レッスンは何回くらいあったんですか?
新井田 1時間のレッスンが1人最低4回はありました。朝の10時に始まって、2〜3人受けて、みんなでお昼ご飯を食べに行って、2時くらいからまた2〜3人入って、5時くらいまであって、そのあとは解散か、それぞれ自主練をするという感じでした。
-レッスン以外の時間は練習したという感じですか?
新井田 そうなんですけど、ここだけの話、練習をせずに、みんなで遊びに行くこともありました(笑)。5時にレッスンが終わるので、6時くらいに待ち合わせをして、そのまんまバスで海に行ったりしました。
-他の受講生と仲良くなれたんですね。

新井田 本当にとても仲が良くて、みんなで朝ご飯を食べて、レッスンを受けて、海に行って、またみんなで夜ご飯を屋上で食べて……。寮に屋上があって、隣接してキッチンがあったので、そのそばでみんなでご飯を食べました。
-海外の人と仲良くなるコツは何かありますか?
新井田 基本の挨拶をちゃんとすることだと思います。会ったら「Ça va?」って、毎回挨拶していましたね。それから、リアクションをちゃんとするということです。少しでも相手の言っていることが分かれば、「あなたの言っていること、すごくわかるわ」というリアクションをすれば、あなたに対して理解を示しているのよ、あなたととても仲良くなりたいわ、という感じが伝わると思います。今回はみんなその空気を出していて、誰一人として人見知りする人もいなかったんです。とても幸せなことに、みんなと仲良くなりたいと思ってくれている人たちばかりだったので、みんなのおかげで仲良くなれた感じです。
-その人たちとは今も連絡を取っていますか?
新井田 はい。全員と連絡先を交換して、パソコンでメールを交換しています。
-あまり練習はされなかったですか?
新井田 いや、練習もちゃんとしましたよ。学校の中に練習室がいくつかあっって、先生は「聴講するように」と言っていたんですが、あまりにも声の質が違う人や、自分はソプラノなので、メゾの人がレッスンを受けているときはレッスン室を外れて、練習していました。
-どのくらい練習できましたか?
新井田 望めば望んだ分だけできましたね。
-部屋はけっこう空いていたんですか?
新井田 そうですね。歌なので、アップライトでも、あるいはピアノがなくても、発声だけできればいいので、空いている部屋があれば、スタッフの人に頼んで鍵をもらって練習することができました。
-環境はいかがでしたか?
新井田 環境は何の問題もなかったです。窓を開ければ涼しくなるし、窓を開けていても誰にも文句を言われませんでした。
-カリアリの街はどうでしたか?
新井田 坂道がすごく多くて、凸凹した街でした。あるときレストランにご飯を食べに行ったときに、お店が坂道の途中にあって、机と椅子が斜めっていたんですよ。それで、友達が「こんなに斜めっていたら、食べられない、まっすぐにしてほしい」って、お店の人に言ったんですよ。そしたら、お店の人が「いや、それがこの街だから」って。「斜めなのが、この街の特徴よ」と言われました(笑)。いい意味でそんなふうにおおらかで、みんなが街に沿った生き方をしていました。
-景色はいかがでしたか?
新井田 きれいでした。海外に行ったことがなかったので、他の国と比べられないのですが、建物がすごく美しい造りで、どこを撮っても絵になる街でした。
-移動はどうされていましたか?
新井田 バスです。一度故障で停まってしまったときがあって、その日は歩きました。坂道がすごいんですよ、途中に休み休み歩いたので、バスだと10分くらいのところが30分くらいかかりました。
-バスのチケットはどうされていましたか?
新井田 学生寮のすぐ目の前にキオスクがあったので、そこで7日間乗り放題で10ユーロのバスカードを買いました。一度バスに通してから7日間有効で、7日間は乗り放題なので、学校に行くのにももちろん使いましたし、他にもスーパーやレストラン、海にもバスで行きました。とても重宝しましたね。
-バスのダイヤの乱れはなかったんですか?
新井田 ありました。あったんですが、バスの本数がわりと多かったので、あまり困ることはなかったですね。全く時間通りには来ないんですけど、その分思わぬところで拾える感じです。電光掲示板にあと50分後にバス来るって書いてあるのに、すぐ来たりするんですよ。電光掲示板の意味が全くなかったです(笑)。
-バスはわかりやすかったですか?
新井田 はい。日本みたいに親切に停留所のアナウンスはないので、自分で風景を覚えてここで降りるんだなと覚えなければいけませんが、日本と同じようにボタンを押して、降りるという意思表示ができます。ただ、運転はすごく荒かったですね(笑)。でも、歩行者を大切にするんです。ちょっとでも道路を渡りたそうな人がいたら、どんなにスピードを出している車でも停まってくれるんですよ。それは日本と全然違いますよね。運転は荒いですけど、みんなマナーはよかったです。
-外食ではどんなものを食べたんですか?
新井田 イタリアン料理です。ピザやカプレーゼというイタリアのトマトのサラダ、あとはラザニアやフンギといったパスタ料理ばかりでした。
-おいしかったですか?
新井田 おいしかったです。特にチーズがとてもおいしかったです。ただ、サラダが日本と違って味がないんですよ。オイルで食べるんですよね。だから、ドレッシングを持っていったらよかったかなと思いました。
-いくらぐらいでしたか?
新井田 だいたい1人20ユーロいくかいかないかくらいで、結構高かったですね。なので、ほとんどスーパーで買って自炊しました。
-スーパーは寮の近くにあったんですか?
新井田 はい、徒歩圏内で行けるところにありました。とても大きいマーケットなので、ほとんどのものはそこで揃えることができました。寮はキッチンは付いていたんですが、フライパンなど一切の調理道具がなかったので、みんなで割り勘で買いました。
-仲が良い人がいてよかったですね。
新井田 本当にそうですよね。あとは、日本人がすごく多かったのも、他の科の子と仲良くなれたきっかけです。
-学生寮は安全でしたか?
新井田 それぞれの部屋に鍵が付いていて、外に出るときは鍵を受付に預けるシステムでした。帰って来て、鍵を受け取るときは、自分の鍵の番号を言わなければいけないので、それで棟のセキュリティーが守られていたんだと思います。
-生活面で困ることはありませんでしたか?
新井田 なかったですね。お湯がちゃんと出るシャワーもありましたし、お水も出るし、トイレも水洗トイレですし、冷蔵庫もあったし、電気も点くし、窓もあったし、すごくきれいな部屋でしたね。
-受講者はみんなそこに泊まっていたのですか?
新井田 はい、そうです。カリアリの講習会に参加していないバカンスで来ていた学生も泊まっていて、一般公開で宿泊施設として使っているようでした。話してみたら音楽と関係ないことをしていて、「何でここに泊まっているの?」と聞いたら、「ここはみんなに宿泊を開放しているんだよ」と教えてくれました。そんなふうに普通に観光に来ていた友達もできました。
-何語で話したんですか?
新井田 その人はアラブ系のイタリア人だったので、イタリア語でお話しました。
-イタリア語も話せるんですね。
新井田 学校が全部イタリア語だったので、イタリア語も使いました。寮の友達と話すときは、フランス語や英語だったんですが、お店やレストランやバス、あとスーパーでは全部イタリア語でしたね。
-語学はどのくらい勉強されたんですか?
新井田 フランス語は一応半年間、語学学校に通っていたんですが、それ以外の英語やイタリア語は、学校で文法を習う程度なので、自分でもよく話せたなと思います(笑)。
-英語はけっこう話せますか?

新井田 聞き取れはするんですけど、返せないこともありました。でも聞き取れたときはリアクションをするので、みんなと仲良くなれましたね。話が通じていると、みんな話しかけてくれるんです。私たち日本人でも、話しかけたときに向こうが“なんて言われたんだろう”って顔をしていると、ちょっとコミュニケーションがとりづらいなと思ってしまって、話しかけづらいと思うんです。“わかっているよ”っていうのをオーバーなくらい出せば、向こうも話しかけてくれますね。
-留学中に困ったことはありましたか?
新井田 特になかったです。バスが途中で停まってしまったときはかなり焦りましたけど、一人じゃなかったので、みんなで仲良く歩きましたし……。一人ではあまり行動しませんでした。なるべく現地のことをわかっている子や、言葉がわかっている子と一緒に行動するようにしていました。
-快適に過ごせたんですね。
新井田 困ったことと言えば、私の帰る日、7日の日曜日に、ちょうどローマ法王がサルディニア島に来まして、一切の交通機関が使えなくなっちゃったんです。ローマ法王を崇める人たちで道路が塞がってしまって、学校から寮に帰れなくなってしまったんです。警察に頼んだんですが、警察は対処してくれなくて、遠回りすれば寮に戻れる感じだったので、人だかりを避けて、こっちの方向だろうと感覚だけで帰りました。遅くなってしまうと、飛行機間に合わなくなってしまうので、必死で帰りました。街のみんながお祭り騒ぎで、いくら私が「寮に帰りたい」ってイタリア語で言っても、全然聞いてくれなくて、むしろ「一緒に盛り上がろう」みたいな……。結局、無事に寮に着いて、目の前の広場から空港行きのバスに乗ってなんとか間に合いました。
-カリアリの人たちはどんな人でしたか?
新井田 おおらかで、陽気でした。みんな笑っていましたね。日本人とかわかると、「ちょっと待ってください」とか「また来てください」とか、話しかけてくれました。
-治安はどうでしたか?
新井田 悪くなかったです。日本と同じような感じでした。悪い人も、ジプシーも、物売りもいなかったです。カリアリはリゾート地だからか、平和な街でした。
-日本と違う点を何か感じましたか?
新井田 大きいお札を嫌うことです。2ユーロくらいの買い物に10ユーロを出してしまうと、もうダメです。「両替してこい」って言われますね。面倒くさいみたいで、おつりをくれないんですよ。一度、43.75ユーロくらいの買い物をしたときに50ユーロで払おうとしたんです。でも、お店の人は0.25とか0.55といった細かいところを払ってほしかったみたいなんです。私はお札しか持っていなかったので、すごく嫌な顔をされて、おつりを小銭で渡されて「グラッチェ(ありがとう)」って言ったんですけど、「アリヴェデルチ(さようなら)」って言われました。普通、ありがとうって言ったら「プレーゴ(どういたしまして)」って返ってくるんですけど、さようならと返ってきて、寂しかったですね。
-他には何かありましたか?
新井田 参考になるかは分かりませんが、イタリアだからといって、コーヒーが特別おいしいということはなかったです。日本のほうが凝っているんじゃないかと思いました。
-向こうの方がこだわっているのは伝統料理なんでしょうか?
新井田 こだわっているというより、普通に味を付けたのが、めちゃめちゃおいしいんだと思います。隠し味っていう感じの味ではなくて、ただ素直にトマトの味がおいしいとかチーズがおいしいとかパンの生地がおいしいとかパスタの生地がおいしいとかそんな感じでした。
-日本食はありましたか?
新井田 中華料理とか日本料理とかどうやらあったらしいんですけど、私は行かなかったです。
-演奏会はありましたか?
新井田 先生たちの演奏会があって、すばらしかったです。ハープやフルートなど、歌以外のプロの演奏会になかなか行く機会がないので、すごくよかったです。
-どこで行われたんですか?
新井田 カリアリの学校のそばにある劇場でした。普通のホールで、真っ赤な絨毯でオペラ劇場のようなところでした。二階建てで、ほんとに広い劇場でした。先生たちの演奏会だけでなく、残っている学生はみんなそこで演奏会をしたようで、「すごくよかった」って後からメールで聞きました。
-留学して、成長したなと思えることはありますか?

新井田 世界の広さを肌で感じたのは、自分にとっていい経験になりました。自分が幸せな環境で暮らしているということも、日本にいるとわからなくて、世界にはいろんな人がいることを知りました。今回は、音楽の留学ということで集まっているので、それなりに裕福な方も多いのですが、その国その国で、国ごとに文化があって、歴史があって、そんななかでその子たちが育ってきて、生きていく術を学んでいるということが分かりました。
-なるほど。
新井田 一緒に話していても、日本では理解できないような言動や、おやって思うようなこともあったんですが、それはその子たち独自の国民性なのかなと思いました。例えば、日本人はとてもおとなしいと言われるじゃないですか? 私も言われたんですよ、「おとなしいね」、「なんでもかんでも『うんうん』って感じだね」って。それって、やっぱり国民性というか民族性ですよね。いろんな国の人たちと知り合えて、日本人ってそうなんだなって思いました。自分が意志の弱い人間なんだと、自分を知る機会になったと思います。
-参加してよかったと思う瞬間はありますか?
新井田 私が日本で勉強しているということをわかってくれた、ことですね。
-それはどういう意味ですか?
新井田 日本でもこういうふうに音楽を勉強している人がいる、ということを分かってもらえたことです。ヨーロッパの音楽をやっているわけじゃないですか? 日本人がイタリア語で歌って、フランス語で歌って、ドイツ語で歌って……。向こうの人は、言語に対するそういうストレスもなく歌っている。言葉も国も違うけれど、同じ楽譜を見て同じような勉強を日本でもしている女の子が一人いたのよ、と思ってくれる。自分の声で自分の歌を歌うことによって、友達ができたことがすごくうれしかったですね。言葉がわからなくても同じ曲を歌っていることで、心を通わせて音楽を楽しむことができたのがすごくうれしかったです。
-留学前にしておいたほうがいいてことはありますか?
新井田 語学ですね。もちろん全然わからなくても、困ることはないんですよ。なぜなら、結局は音楽で分かり合えるからです。不思議なんですけど、音楽は音を出すだけで、言葉が分からなくても分かり合えるんです。でも、自分の意思を伝えたり、相手の意思を全部わかりたいって思うときに、語学って必要なんです。どんなに大変でも時間とお金をかけて、語学は準備したほうがいいと思います。これははっきり言えます。付く先生にもよるんですが、付く先生が英語もOKなら、英語とイタリア語、カリアリに行くなら、できればフランス語、英語、イタリア語の3カ国ですね。
-今後留学を考えている人にアドバイスをお願いします。

新井田 勇気を持って、とにかく行くことですね。行くか行かないかって迷っている人に対するアドバイスというよりは、とにかく行けっていうアドバイスです。どんなに他の人が経験を細かく語ったとしても、行ってみないと、自分が経験してみないとわからないと思います。私もわかりませんでした。だから迷っているなら、行くべきだって思いました。
-短期の留学でしたが、身になることはありましたか?
新井田 ありました。私はたった1週間だったんですけど、自分の性格が変わるというか、すごく成長を実感しました。なぜなら、日本にいると刺激ももちろんあるけれど、それに慣れてしまっているんですよね。例えば、外国人が突然「ハロー」って声かけてくるわけじゃないし、誰か困っている人がいても声をかけるわけじゃない。でも、それが外国では当たり前なんですよね。ちょっとでも目が合えば「サヴァ?」と声をかけてくる。そのときに、自分一人で何かを思っていても仕方がないと思うんです。元気なら元気、元気がないなら元気がないと、どんどん自分を出していかないといけない。話しかけられたくなかったら、話しかけないで、という態度を出せばよくて、中途半端はよくないんです。でも、日本人ってどうしても中途半端にして、それが一つの礼儀みたいになってしまっていると思います。濁して、自分の意見をはっきり言わないほうがいい、そういう環境で育ってきている分、成長できることも、どうしてもそこでストップしてしまうんです。海外に一人でぽんと行くことで、そういうことに気がついて、全然違う自分が出てきちゃうんですよ。
-なるほど。
新井田 もちろん、成長するもさせないも自分次第なんですけどね。一緒に参加していた子も、「自分を出すことが恥ずかしくなくなって、分け隔てなく自分を出せるようになった」って言っていました。そういうふうに自己表現に対する考え方が1週間でだんだん変わってきて、「日本に帰ったら強くなっているかもね」なんて、笑って言っていました。
-へー。

新井田 でも、日本に帰ってくると、また日本に慣れてしまって、やっぱり日本の生き方になってしまうんですよね(笑)。でも、それはそれで、この国での生き方なんだな、と、そういう考えもできるようになりました。
-音楽に関してはいかがですか?
新井田 そうですね。本場の人に褒められるっていうのは、うれしいですよね。
-今後の活動の予定を教えてください。
新井田 この留学を活かしていこうと思っています。来年も海外で勉強したいなって思うくらい、海外が好きになっちゃいました。すごく楽しみです。自分もとにかく勉強しなくちゃな、と思うことができました。
-今日は本当にありがとうございました。
吉原未穂さん/ピアノ/モーツァルテウム音楽大学夏期国際音楽アカデミー/オーストリア・ザルツブルグ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

吉原未穂さんプロフィール
東京学芸大学G類芸術文化課程音楽科ピアノ専攻卒業。同大学大学院修士課程教育学研究科ピアノ専攻修了。修了時に、「特に優れた業績を挙げた奨学生」に認定され奨学金を授与される。大学院修了演奏会に出演。第7回日本ピアノ教育連盟オーディション入賞者演奏会出演、第45回・第46回全日本学生音楽コンクール東京大会入選。2008年日本シューマン協会設立35周年記念「ローベルト・シューマン音楽コンクール」ピアノ部門第2位(優秀賞)。2009年ザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学国際サマーアカデミーにてフランク・ウィバウト氏に師事。同講習会で、選抜者演奏会(アカデミーコンサート)、修了演奏会出演し、ディプロムを取得。
-まずはじめに、吉原さんの簡単なご経歴を教えてください。
吉原 東京学芸大学芸術文化課程ピアノ専攻を卒業後、同大学院修士課程を修了しました。
-今までに、海外の講習会に参加された事はありましたか?
吉原 いえ、今回が初めてです。
-今回、モーツァルテウムの講習会に参加してみようと思ったきっかけを教えてください。
吉原 フランク先生が日本にいらした時、マスタークラスを受講したのですが、とても素晴らしいレッスンを受けさせていただくことが出来たので。
-フランク・ヴィバウト先生とは、どうやって出会ったのですか?
吉原 鎌倉で、先生のマスタークラスを受講させていただいた事がきっかけです。
-日本で一度、レッスンを受けられたとのことですが、海外で講習会に参加されてみて、違いはありましたか?
吉原 ザルツブルクという自然に恵まれた素晴らしいモーツァルテウムの環境でしたので、いつも以上に音楽へ対して真剣に向き合うことができたと思います。

-今回の講習会は、だいたいどのくらいの人数が参加されていましたか?
吉原 ピアノだけではなく声楽や他の楽器の方もいらっしゃいますので、全体としては何千人という単位でしょうか。私が受けたクラスは15人でした。
-この講習会では初日にオーディションがあると思うのですが、15人中合格されたのは何人ですか?
吉原 先生のクラスは、今年は全員合格したようです。
-オーディションの様子はどんな感じでしたか?
吉原 先生のお部屋の前に全員集合して、呼ばれた人から一人ずつ中に入り、面接を受けつつ曲を弾くという形でした。
-オーディションは、どのくらいの時間でしたか?
吉原 人によっては、2曲弾いていた方もいらっしゃいましたが、だいたい1人10分程度でしょうか。
-1曲全部弾くという形ですか?
吉原 はい。先生から何を弾くか聞かれまして、その曲を最後まで弾かせていただきました。
-緊張しましたか?
吉原 そうですね。でも、先生が笑顔で迎えてくださったので、思っていたよりは、リラックスできました。
-オーディション合格後、レッスンのスケジュールはどんな感じでしたか?
吉原 まずオーディションが終了した直後に、レッスンスケジュールが貼りだされました。私は1番目だったので、心の準備も出来ないまま、オーディションが終了して1時間後にすぐレッスン開始でした(笑)。これが月曜日で、火曜日にアシスタントの先生のレッスンが入り、水曜日にもう一度先生のレッスンを受けました。そのときに、アカデミーコンサートに出てみないか、とお声をかけていただいたんです。そして、アカデミーコンサートのため、金曜日に特別レッスンを入れていただきました。
-では1週目から、先生のレッスンが3回もあったんですか!お忙しいスケジュールだったんですね。
吉原 そうですね。1週目でアシスタントの先生のレッスン1回も含めて計4回もあったので(笑)。次の週の月曜日が、アカデミーコンサートだったので、その午前中にも先生がレッスンをしてくださいました。そして、1日置いて水曜日にももう一回。
-レベルに応じて、アシスタントの先生のレッスンのほうが多くなることもあるんですか?
吉原 たぶんそうなると思います。
-レッスンの内容は、どんな感じでしたか?
吉原 先生が、今日は何をもってきたの?と聞いてくださるので、今日はこれですと、用意していった曲を1曲ずつ見ていただく形でした。だいたい、1回のレッスンで1曲1時間です。ソナタのときは半分ずつに分けて、今日は1楽章と2楽章を、という感じでしたね。
-レッスンの雰囲気はいかがでしたか?
吉原 先生は穏やかで、温かいアドヴァイスをくださいます。豊かなイマジネーションをお持ちの先生ですので、「こんな弾き方もあるよ」と、たくさん提案していただいた感じですね。その中から自分に合うものを取り入れていくという形でした。

-ピアノの弾き方など、基礎なことで指導を受けられたことはありましたか?
吉原 とにかく、「脱力」のことをおっしゃっていました。音楽に沿った体の使い方をしなさいということですね。音のイメージに合った響きを出すために、こういう体の使い方をしてみたら、とか。
-なるほど。先生は、どんな方ですか?
吉原 穏やかで温かく、すごく優しい方です。生徒想いの先生で、アカデミーコンサートに生徒が出る時には、必ず聴きにきてくださりアドヴァイスをくださいました。
-素敵な先生だったんですね。クラスは、どの国の方が多かったですか?
吉原 日本人は5人ですね。その中にはロンドンで先生に習っていらっしゃる方もいました。あとは、アシスタントの先生がスペインの方でしたので、スペイン人がすごく多かったです。
-スペイン人の方のレッスンは聴講はされましたか?
吉原 はい、皆すごく熱心でしっかり準備されていました。
-外国の方の演奏を聴くことは、刺激になりましたか?
吉原 はい、皆それぞれ素晴らしい個性を持っているので、それが音楽として伝わってきまして大変勉強になりました。
-先生のレッスンは、何語で受けられたんですか?
吉原 英語です。
-期間中は、皆さんどこで練習されるのですが?
吉原 モーツァルテウムの練習室を予約して使っていました。
-練習室は何室くらいあるんですか?
吉原 正確な数はわかりませんが、新校舎、旧校舎と、それ以外の場所にもそれぞれ練習室がありました。
-かなりたくさんあったんですね。では、予約が全く取れないということはなかったんですか?
吉原 それはなかったのですが、常に誰かが使っている状態でしたね。
-吉原さんは、1日どのくらい練習されましたか?
吉原 わたしは4時間確保しました。うまく調整して、レッスンの時間と重ならないように使っていました。
-練習時間は確保できたんですね。レッスン以外の時間は主に何をされましたか?
吉原 主に聴講ですね。
-ピアノ以外にも聴講されたりしましたか?
吉原 いえ、ピアノ以外は残念ながらできませんでした。自分の先生のレッスンの聴講がほとんどでした。ただ、他の先生のクラスの修了コンサートを聴きに行くことはできました。また、アカデミーコンサートも、何日か聴きに行きました。

-他には何をして過ごされましたか?
吉原 近隣の観光を少ししました。旧市街にお買い物に行ったり、学校のすぐ裏がミラベル庭園だったので、お昼ご飯を持って、ベンチに座って食べたり・・・。とにかく環境がすごく良かったですね。
-治安はどうでしたか?
吉原 悪くないと思います。怖い思いをしたことは、一度もありませんでした。
-街の人たちは、英語で話しても大丈夫でしたか?
吉原 はい。どこのお店に行っても大丈夫でした。日常生活で、困ることはほとんどなかったです。
-現地の食べ物はいかがでしたか?
吉原 基本的においしかったです。あと、スーパーでも何でも買えますし、マックも便利でした。
-マクドナルドですか。日本のものと味は違うのですか?
吉原 サイズが大きかったですね。でも、意外とリーズナブルに食べられたので良かったですよ。練習で遅く帰ってきたときには、スーパーが閉まっていることもあったので、便利でした。
-スーパーが早く閉まるということを、他の方からもよく聞きますが、実際いかがでしたか?
吉原 詳しくは分かりませんが、8時には完璧に閉まっていたと思います。
-日本とは違いますよね。生活面で何かびっくりしたことはありますか?
吉原 特にびっくりしたことはなかったですね。バスなども、遅れるものだと覚悟していたんですが、意外とちゃんと時間通りに来てくれましたし。
-では、日本人にとって住みやすい所なのかもしれませんね。
吉原 ええ、私にとっては、とても居心地がよかったです。
-宿泊先は、どういうところだったんですか?
吉原 わたしは学生寮に滞在していました。
-寮の中は、どんな雰囲気でしたか?
吉原 練習室もついていますから、モーツァルテウムに参加している生徒さんで、あふれているという感じでした。いろいろな国の方がたくさんいて、にぎやかでしたよ。
-お部屋はシングルルームですか?
吉原 はい、一人部屋で、お風呂もちゃんとお部屋の中にありました。驚いたのは、廊下をはさんで部屋のすぐ向かい側に、キッチンも一人ずつ完備されていたことです。まさに、ロッカーのような感じですね。ロッカーを開けると、冷蔵庫とコンロが出てくるという感じです。好きな時間に気兼ねなく料理が出来るので、とても便利だと思いました。

-それは便利ですね!では、ずっと自炊されていたんですか?
吉原 はい、少し・・・(笑)。なかなか忙しくて・・・。
-他の方とご飯を食べに行ったりはされましたか?
吉原 ええ、同じクラスの生徒全員で、先生と一緒にご飯を食べに行ったりもしました。
-他の国の方とも交流する機会があったと思うんですが、日本人以外の方とお友達になったりしましたか?
吉原 そうですね、話す機会はありました。同じクラスのスペイン人の子達と、英語でお話したりしました。
-外国の方と接してみていかがでしたか?
吉原 やはり、同じ目的を持って集まってきているので、親しくできました。でも、自分の英語力が不足していたと痛感しました・・・。
-語学力の必要性を感じた、ということですね。
吉原 はい、すごく感じました。勉強しよう!というきっかけになりました。
-頑張ってください!海外の方とコミュニケーションをとるにあたって、うまく付き合うコツなどはありますか?
吉原 やはり恥ずかしがらずに、自分から話しかけていくことでしょうか。
-他の国の方は、どんどん話しかけてこられましたか?
吉原 ええ。みんな温かい人たちで、良く話しかけてくれました。でも、何せ私が英語が少ししかできないので、うまく返せなかったりして・・・。もっと話したかったな、と思います。
-年齢層としては、若い方が多かったんですか?
吉原 そうですね。やはり大学生が多かったです。下は18歳くらいからですね。
-期間中は何か困ったことはありましたか?
吉原 特になかったんですが、一度熱を出してしまって・・・。2週目のアカデミーコンサートが終わった後、ホッとして気が緩んだのか、体調を崩してしまいました。その日が、ちょうどクラスの修了コンサートの日だったんです。でも、日本から持っていった薬を飲んで、いったん部屋に帰り横になっていたら、良くなりましたけど。やはり、薬は持っていってよかったな、と思いました。
-大事にいたらなくて良かったですね。
吉原 はい。海外で一人だと、いろいろ不安になりますからね。意外とハードな2週間でしたし(笑)。

-アカデミーコンサートに出演された感想は?
吉原 コンサート会場が、旧モーツァルテウムの校舎の中にある、「ヴィエナ・ザール」というホールでした。ここは、白が基調で金色で装飾されている、いかにもヨーロッパの宮殿という感じの、とても素敵なホールで、とても感動しました。そして、皆さんが本当に上手でしたし、すごく勉強になりました。
-クラスから何人くらい選抜されるのですか?
吉原 クラスによって全然違うんです。私のクラスは5人くらい選出されました。アカデミーコンサート総出演者数はピアノだけで20人くらいでしょうか。コンサートは、数回開かれました。たとえば1日目はピアノは何人、バイオリンは何人というようにプログラムされていました。私が出演した日は、ピアノばかりの日でしたけど。
-他の方の演奏を聞いて、どんなことをお感じになられましたか?
吉原 やはり皆さん、きちんと準備して来られているな、ということを感じました。皆さんすごく熱心でしたし、自分に合った先生をきちんと選ばれていましたね。
-やはり先生との相性は大事なんですね。
吉原 はい。2週間、その先生とのレッスンがメインになりますので、相性は本当に大事だと思います。
-吉原さんは、良い先生と出会えてよかったですね。今後、ヴィバウト先生に師事されたいという、ご希望はありますか?
吉原 そうですね。また先生の日本でのマスタークラスを受講させていただきたいです。またモーツァルテウムにも参加できたら、と思っています。
-今回初めて参加されてみて、ご自分が一番変わったと思うことは、どんなことですか?
吉原 まず、私は、日本では知らない人にはあまり積極的に話しかけたりしないタイプですが、いろんな人に話しかけるようになりました。やはり、わからないことが多いので、自然と積極的にならざるを得ませんよね。
-音楽面だけでなく人間的にということですね。
吉原 やはり、黙っていても何も進まないので、自分から、とにかく動かなきゃという感じになりました。
-なるほど。音楽面ではいかがですか?
吉原 自分の目指していく音楽の方向性が定まったということが大きいですね。あと、他の生徒さんが演奏していた曲を聴いて、自分もこの曲をレパートリーにしたいと思ったり、こういう演奏の仕方いいなって思ったりして、新たな目標もできました。

-今後、海外でレッスンを受けてみたいと希望されている方々に、準備しておいたほうがいいことや、アドバイスがあればお願いします。
吉原 まずは、しっかり語学の勉強をしておいたほうがよいです。あとは、事前につきたい先生の情報を、出来る限り集めておくことが必要です。音楽観が合わないと困るので、前の年に行かれた人がいたら、その方からお話を聞いて情報収集をしておくべきですね。どんな曲を持っていったらいいかなど、そこまで調べられたら、安心してレッスンを受けられると思います。
-では、生活面で、これは持っていったほうがいい!というお勧めグッズは?
吉原 やっぱり薬ですね。あと、簡単に食べられるレトルト食品や加工食品もあると便利です。私は一応、ある程度は日本から持って行ってたんですよ、いざというときのために。体調を崩して外に出られないときとか、レトルトものなどがあると安心でしたよ。あと、スーパーが早く閉まってしまって、何も買えなかったときなどに便利だと思います。
-周りにお店はありましたか?
吉原 寮の近くにはスーパーがありましたし、学校の近くにはパン屋さんがありました。あと、学校の中にも学食があるので、食べるのに困るということはありませんでした。
-では、最後になりますけど、吉原さんの今後の音楽活動の目標をお聞かせください。
吉原 やはり、たくさんレパートリーを増やして、演奏会などをしていけたらいいなと思います。実は、来年リサイタルをやるんです。今回教えていただいた曲を中心に、プログラムを組んで演奏していこうと思っています。今回の経験を生徒の指導にも生かせていかれたらと思っています。
-素敵ですね!ご活躍をお祈りしております。今日は本当にありがとうございました!
---------------------------------------------------------------------
今後のコンサート予定
2010年5月4日 千葉市美浜文化ホール・音楽ホールにて「吉原未穂ピアノリサイタル」
日本シューマン協会(ムジーク・ミルテ)主催を開催予定。
プログラム: シューマン 「森の情景」
シューマン ピアノソナタ第1番
シマノフスキ「マスク」よりドン・ファンのセレナード
ドビュッシー 前奏曲集第2集より 「花火」 他
原知恵子さん/イタリア語留学/イタリア・ペルージャ
音楽留学体験者でなくては分からないような、音楽大学、音楽専門学校、音楽教室のコースプログラム、夏期講習会、現地の生活情報などを伺ってみます。将来の自分の参考として活用してください。

原知恵子さんプロフィール
東京音楽大学音楽学部声楽演奏家コース卒業後、同大学大学院声楽専攻修了。第5回日本演奏家コンクール大学の部 奨励賞、第5回大阪国際コンクール大学の部第3位(1位・2位なし)、第23回江戸川区新人演奏会にオーディション合格し、演奏会出演。江戸川区主催「サロンコンサート」出演、婦人民主クラブ主催「クリスマスコンサート」「ジョイントコンサート」出演、その他様々なコンサートに出演。これまでに、中澤桂・大川隆子・釜洞祐子・吉田恭子・横山修司の各氏に師事。2009年4月よりイタリア・ペルージャにて語学留学中。
-まずは簡単なご経歴を教えてください。
原 東京音楽大学を卒業して、同大学院に進みました。その後アルバイトや派遣の仕事をしながら音楽活動をして、去年の4月にイタリアのペルージャに来ました。
-会社勤めをされていたんですね。
原 フリーターのような感じですけど。コンサートや音楽活動もしていましたので。
-どのようなお仕事をされていたんですか?
原 テレマーケティングなどもしましたし、ここに来る前の2年間は、発展途上国に鉄道や道路を作る建設コンサルタント会社の事務として働いていました。

-面白そうですね。
原 仕事も面白かったですし、とても良くしていただきました。
-声楽は、ずっとイタリアやドイツのものが中心ですか?
原 大学にいた頃は、ドイツ、日本、イタリアの曲などを歌っていました。大学院の修了演奏はドイツ歌曲でした。卒業してからは、イタリアものが多いですね。先生がイタリアの曲を中心に教えてくださる方なので。
-今はイタリアにいらっしゃると言うことですが、演奏活動などはされていますか?
原 全くの留学ですね。しかも、音楽留学ではなく語学留学です。
-そうなんですか!それはまたなぜ?
原 音楽活動だけでは生活していくのは難しいですよね。両親の理解もあって、20代のうちは、音楽を続けさせてもらっているんですけど、早く自立しなくてはと思っていて。なので、大学院を卒業してから、さらに音楽で留学するということは考えていなかったんです。そこで、音楽以外に自分に何ができるかを考えたときに、イタリア語に行き着いたんです。声楽をやる上で、イタリア語を理解することが重要になって来たのもきっかけですね。読んで意味を調べて歌うことは出来るんですけど、イタリア語の独特の響きや、リズムを勉強するほうがいいと思いまして。語学を勉強するのは好きでしたし、イタリア語も興味がありましたので。とにかく、これを仕事に活かせるものにしようと思いペルージャに来ました。
-大学院まで卒業されていると、その先も勉強を続けていくっていうのは難しいですか?
原 オペラ団体に入るっていう方法もあるんですけど、そこも結局、お金を払ってまた専門学校に行くような感じなんですね。そのお金があるなら、思い切って留学してみようかな、と。

-イタリア語を学ばれているということですけど、レッスンは週5日ですか?
原 はい。クラスのレベルによっても授業数は違いますけど基本は週5日です。レベルが6段階あって、私は、最初は上から3番目のクラスから始めたのですけど、こういう下のクラスは、文法中心にやっていくのでそんなに授業はないんです。文法が週に12時間、会話が4時間程度。ワンターム3ヶ月なんですが、一番上のクラスだけが6ヶ月なんです。今、私はそのクラスにいて、あと3ヶ月というところです。上の2つのクラスは、イタリアの文化や歴史という授業が入ってくるので、週に28時間くらいは授業があります。
-文化の授業などは、準備というか、調べものをしたりすることもあるんですよね?
原 はい。音楽は大丈夫なんですけど、歴史や文学などは大変です。ヨーロッパ圏の人は基礎知識がありますが、私はゼロからなので。インターネットを駆使して、いろいろ調べものはしています。
-将来、音楽活動をされる上でも刺激になりそうですね。
原 直接関わってこなくても、美術・音楽・文学は、常に関係していますからね。
-それにしても、中級クラスから始まったのはすごいですね。
原 いえいえ、こちらに来たばかりの時は全然ダメでしたよ。日本で勉強していたといっても話す機会はありませんでしたから。

-日本でも文法などは勉強されていたんですよね。
原 はい、学校でも授業がありましたし、卒業してからもイタリア語の学校に通っていました。
-やはりそういう準備をしておくべきですか?
原 そうですね、ゼロの状態で来てしまうと、まず生活するのが大変なので。旅行会話が出来るくらいには、語学は勉強してからの方がいいと思います。基礎の部分に時間をかけると、せっかくの時間が無駄になると思うので。
-なるほど。今はどういうところに住んでいるんですか。
原 学生アパートというか、共同アパートです。ここに来る前に、インターネットで不動産屋に頼んで決めました。私はイタリアに住む以上、イタリア人と暮らしたかったので、その希望を出しました。それで今の家を紹介してもらったんですけど、イタリア人の女の子3人と住んでいます。
-楽しそうですね!
原 はい。すごくラッキーでした。家もきれいだし、みんなすごくいい子たちなので。
-その方々は学生さんですか?
原 国立ペルージャ大学に通う子たちです。経済・生物などみんな専攻はバラバラなんですけど、ひとり語学系の勉強をしている子がいて、よく助けてもらっています。

-最初から意思の疎通はうまくいきましたか?
原 必要最低限のことは言えたんですけど、それ以外の日常的なおしゃべりになると、最初はなかなか入りにくかったですね。テンポもすごく速いし。でも、だんだんその人のしゃべり方に慣れてきて、向こうも慣れてくれたのもあって、一緒に買い物に行こうとか、誘ってくれるようになってきました。
-話す機会がないと覚えませんもんね。
原 語学留学で、イタリア人の友達を作るのは難しいじゃないですか。なので、家でもずっとイタリア語を話さなければいけない環境に自分を置けたのは、とても良かったと思います。学校で習っているだけじゃ、絶対にここまで来れなかったと思います。
-今の学校はどこの国の人の方が多いんですか?
原 この学校は、イタリアの国立大学が、外国人に向けて語学や文化を教えるために作った学校なので、世界中から学生が集まっています。EU圏の学生は、短期で来ている人が多いですね。あと、大学と中国の間で交換留学をさせるプログラムがあるみたいで、中国人専用のクラスがあります。
-ほかの学生さんと話す時もイタリア語ですか?
原 下のクラスだと、英語だったりします。あと、中国人は固まって中国語でしゃべってますね。日本人も同じです。今のクラスでは、日本人は私一人だけなので、私は必然的にイタリア語だけですね。
-語学留学するからには、その国の言語を話すべきですよね。その点、原さんはイタリア語漬けの生活を自ら選んだということですよね。素晴らしいです。
原 私も日本人が周りにいたら集まってしまうと思うし。やはり、この生活で良かったなって思いますね。
-細かい話ですけど、みんなでご飯を作ったりはしますか?
原 はい。基本は自分のものは自分で作るんですけど、みんな私よりもお料理が上手なので、よく作ってもらっています(笑)。ごくたまに私も日本の料理を作ってあげることがあるんですけど。イタリア人はトマトソース・サラミ・チーズ・ワインなど、なんでも自分の地元のものを一番と思って食べるんです。帰省したり彼女たちの両親が来る度に、食料をごっそり持って来るので、それをご馳走になったりします。
-本場の料理が楽しめるんですね!イタリアだと、やはりパスタですか?

原 パスタは多いですけど、一日に2回はないですよ。昼はパスタで夜は肉料理とかが普通です。
-日本食を作って食べたりしますか?
原 はい、材料を集めるのが難しいですけど。中国人が経営しているところで、おしょうゆやうどんを買ったりします。お好み焼きやカレー、焼うどんなどを作りました。
-やっぱり、日本の味が恋しくなりますよね。
原 恋しくなりますね。日本の食材は、来る時にたくさん持って来ましたし、先日も両親に送ってもらってたりして、けっこう充実してはいるんですけど(笑)。
-生活費は、月にどのくらいかかりますか?
原 家賃なども入れて、だいたい10万円くらいでしょうか。家賃がそんなに高くないので。光熱費はシェアですしね。
-シェアしたほうが安上がりですし、いい経験も出来て良いですよね。
原 こちらでは、ルームシェアが基本です。一人住まいもありますけど、料金が高いので、大抵みんなシェアしています。
-今、ペルージャにお住まいということですが、オペラを観に行ったりはしますか?
原 ここからだとフィレンツェまで電車で約2時間、ローマまでは3時間くらいで行けるんです。なので、そこに行った時は、オペラにも行きますね。泊りがけでヴェローナまで行って、野外オペラを観たりもしました。ペルージャでのオペラ公演は、年に一回しかないんですよ。それは残念なんですけど、オペラ以外のコンサートは頻繁にあります。
-声楽に触れる機会もあるんですね。ちなみに、生のオペラはいかがでしたか?
原 やっぱりすごく素敵でしたね。日本で観るのとは違うし、安い料金で気軽に観にいけるのが魅力ですね。あと、観ている人たちもノリが違うというか、心から楽しんでいて、その雰囲気も味わえるので、すごく楽しいです。
-劇場も大きいんですか?
原 基本的にイタリアの歌劇場は日本のように大きくはないです。馬蹄型の劇場で内装やシャンデリアもすごく素敵な劇場です。
-安く観られるんですか?
原 ペルージャで観た時は、10ユーロでした。普通料金は15ユーロなんですけど、学生料金があるので。
-それはいいですね!たまに歌いたくなったりしないんですか?

原 大学の授業で音楽史の授業があって、そこに教えに来ている先生がペルージャ音大のピアノの先生なんですよ。その先生が、学校のホールを使ってピアノを弾き、私たちに歌わせてくれるんです。そこで、たまたま先生が、私の声を気に入ってくださって。何度かコンサートを企画してくださったりしたんです。あと、学校の校舎が貴族の宮殿を使っているため、この建物の歴史に関する本が出版されたとき、セレモニーがあったんですが、そこで歌わせてもらったりもしました。なので、本当に私はラッキーだったんですが、歌う機会はあるんです。まだ帰国するまでに2回ほどコンサートの予定があります。
-それは素敵な縁ですね!
原 あとは、大学にある合唱団でソプラノが少ないから、ソプラノの声を厚くするために助けてくれないかって言われたりして(笑)。12月には合唱団の演奏旅行に付き添って南イタリアのバーリまで行ったりもしました。
-充実してますね!
原 本当に充実しています。
-今年の3月以降は、日本に帰国されるんですか?
原 3月の末日までテストがあって、バタバタ帰国するのはいやなので、滞在としては4月末までのつもりです。
-イタリアで音楽活動と言うわけではなく、とりあえず帰国なんですね。
原 音楽活動は考えていなくて、きちんとした仕事があれば、イタリアに残りたいと思っています。難しいことですが、今色々な人に話を聴いたりしていて可能性を模索している最中です。何もしないと後悔すると思うので、自分が納得できるところまで挑戦して帰るつもりです。
-イタリアは原さんに合っていましたか?
原 そうですね、生活のリズムや考え方とか、日本とは全然違うので、来たばかりのときは戸惑いましたけど、私の性格にはイタリアの方が合っているかなと思います。電車が遅れても待たされても別にいいやみたいな感じで(笑)。食べ物も好きですしね。

-それでも最初は戸惑ったんですね。
原 はい。イタリア人と一緒に生活していく上でけっこう戸惑いましたよ。最初に言ってたこととことが、いつも間にか変わってたりとか。キチンキチンとはしてないですからね。この前言ってたのと違う!っていちいち気にしてると、ストレスたまりますよ。
-手続きなどをしていても、適当だという話は良く聞きますよね。
原 学校の事務も警察なんかも、大体いいかげんですね。行くたびに言われることが違うし…。慣れるといつものことだって思えますけど。
-環境に自分を溶け込ませていくのは大事ですね。
原 イヤになってしまう人は1ヶ月でイヤになるみたいです。イタリアは好きだけど、生活は出来ないって。
-外国に住む場合は、うまく対応しないとストレスたまりますもんね。
原 そうですね。根底はしっかりとした考えを持って、細かいところは状況に対応出来るようにしていたほうがいいかもしれないですね。自分の中に一本柱がないと、いろんな方向に流されてしまうこともあるので・・・。麻薬とかも簡単に手に入りますから、自分ををしっかり持っていないと、流されてしまうと思います。
-信念は強く持つべきですね。イタリア語はもう問題なく話せるんですか?
原 日常会話は、だいたい大丈夫です。
-英語であれば、日本の学校での積み重ねがありますけど、イタリア語はなかなか基盤がないので、難しそうですけど。
原 響きだとか、イタリア語自体が好きだったというのもあるかもしれないですね。最初は私も英語が話したくて勉強していましたが、発音は英語のほうが難しいんです。ただイタリア語の文法は英語の何倍も大変です。
-自分に合う言語っていうのもあるのかもしれませんね。さて、そもそも原さんが声楽を勉強しようとしたきっかけは何だったんですか?
原 長くなりますが・・・。母親が音大卒だった関係もあり、私もピアノをやったりしていたんですが、興味はなかったんです。高校に入るときまでは、医学部に行こうと思っていましたし 。それが、中学卒業くらいの時に、テレビで宝塚を観て一気に魅了されてしまったんです。そこから、どんどんあの世界に入り込んでしまい、ついには宝塚歌劇団に入りたい!という所まで行ってしまったんです。親には大反対されたんですが、母の声楽の先生に、「やりたいようにやったらいい。でも本当にやりたいなら、明日からレッスンやり始めなさい」って言われたんです。そこで「じゃあ始めます」って宝塚の予備校に通い始めたんです(笑)。今までダンスなんかやったことなかったのに。

-最初は宝塚志望だったんですか!?
原 はい。ところが、その予備校の優秀な先輩たちが、全員試験に落ちちゃったのを見て、あんな優秀な人たちがだめなら、私にはとうてい無理だろうって、妙に納得しちゃったんです。そして、ちょうどそのとき、今度は劇団四季のミュージカルを観る機会があって。劇団四季は、ダンス部隊と歌部隊に分かれているんですよね。そして歌部隊には、音大出身の人も多いんです。ミュージカル自体が大好きだったので「こっちなら出来るかもしれない!それなら音大に行かなければ!」と思い、音大受験の勉強を始めました。
-ミュージカル歌手志望に変わったわけですね。
原 はい、ですから、東京音大に入った当初はクラシックに興味がなかったんです。私はミュージカルをやりたいんだからって。でも、大学3年のときに声楽演奏家コースのオーディションに受かり、本格的にオペラの勉強をしていくうちに、クラシックって面白いんだなって思うようになったんです。そして、実は4年生の時に、四季のオーディションに受かったんですけど、大学院に行くか四季に行くかすごく迷ったんです。そして、「今ここでミュージカルをやったら、クラシックの声にはもう戻れないだろうな」と思いまして。本当にやりたかったら大学院を出てからでも出来るだろうと。
-クラシック一本ではなく、変化して来ているんですね。だから視野が広いんですね。それにしても、宝塚にあこがれる気持ち、分かりますよ。
原 あれで大きく変わりましたね(笑)。
-きっかけって人それぞれですよね。今、ミュージカルに対する気持ちは?
原 コンサートなどで歌う機会があれば歌いたいですけど、ミュージカルはリズム感やセンスも必要なので難しいですよね。私もミュージカルはすごく好きですけど、心からミュージカルに惚れている人じゃないと続かないと思います。大変な世界ですからね。
-今後は、音楽を続けていかれるんですか?
原 はい、そうですね。音楽は音楽で続けていって、あとはどういう仕事をしていくかっていうのが問題ですね。イタリア語だけだと日本では活かすのは難しいので、やはり英語も使えるようにしないと・・・。どの仕事も英語があってこそと言う感じなので。
-次から次へと目標があって素晴らしいですね。
原 実際に活かしていかないといけないから、どうやってこの先につなげていこうかいつも迷っています。
-いろんな可能性を考えられるのは素晴らしいことですよ。
原 音楽だけでやっていくのはすごく大変なので、他に可能性を見つけていかないといけませんから。音楽をやっている多くの方は、おうちも裕福で、いつも親の援助が得られる感じですよね。私もそういう家庭で育ってきたので、甘えることは可能なんですが、私はそれがいつも重荷になっていて。ちゃんと自立するためにはどうしたらいいんだろうと悩んでいます。

-今やっていることは、将来を作ってくれると思いますよ。原さんの今の夢は何ですか?
原 イタリアで仕事をするか、いつもイタリアと関わっていけるような仕事が出来ればいいなと思っています。
-イタリアとの出会いは、大きかったんですね。応援しております。では、海外で勉強したい人にアドバイスをお願いします。
原 まずは思い切りが大切だと思います。行きたいなら思い切って挑戦してみるべきだと思います。あとは、きちんと下準備をしてから来ることも大切。自分でできることはなるべく自分の力でする、というのも大事だと思います。
-今日は本当にありがとうございました!